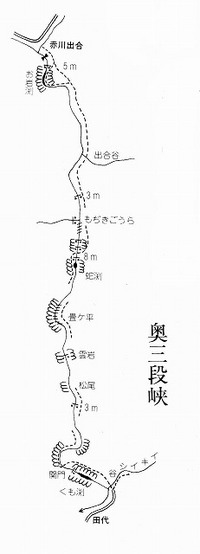2010年01月29日
官ノ倉山と石尊山(2010.1.24)
官ノ倉山と石尊山
2010年1月24日 埼玉県比企郡小川町 記録者 たか
24日(日)に低山ハイクに行ってきました。
今回も埼玉県比企郡小川町の山、官ノ倉山(344.7m)と石尊山(せきそんさん 344.2m)です。



車で登山口のある天王沼まで行き、そこから登りはじめます。
道は杉林の中を九十九折れで高度を稼ぎ、やがて官ノ倉峠に出ます。
ここは平らになっていて、臼入山から来るコースと外秩父七峰縦走コースとが交差するところ。
ここで道を間違えて縦走コースに入ってしまいました。正しいコースは左だったのです。
しばらく行くと庚申塚があり、そこに左に登っていく道がありました。標識を見ると官ノ倉山と出ています。ここで気が付いて正しい方向へ軌道修正。
良かった気が付いて(^_^;)



さて、そこからまた急な登りとなって、しばらく行くと官ノ倉山に着きました。
頂上には犬連れのハイカーがいました。
空は青く、冬の澄み切った空気で遠くまで見通せます。山に詳しくないので山の名前は分かりませんが、赤城山は分かりました。
しばらく休んで次の目的地、石尊山に向かいます。
石尊山へは一度坂を下って、また登り返します。登り返すといってもたいしたことはありません。ちょっと息が切れるくらいです。
石尊山は官ノ倉山より、もっと見晴らしが良いところでした。
360度とまでは行きませんが、ぐるっと見渡せます。
山頂には祠が祀られていたので、手を合わせて無病息災を祈ります。



昼飯も持ってきたのですが、まだ早すぎるのでここでは食べず、ゆっくり休んだ後に下山しました。
帰り道でも数組のハイカーとすれ違ったので、けっこう人気のコースのようです。
今回もお手軽登山でしたが、楽しい時間を過ごせました。
コースタイム
天王沼(9:35)-官ノ倉峠(9:52)-庚申塚(9:57)-官ノ倉山(10:06)
-石尊山(10:21)-天王沼(11:06)
2010年1月24日 埼玉県比企郡小川町 記録者 たか
24日(日)に低山ハイクに行ってきました。
今回も埼玉県比企郡小川町の山、官ノ倉山(344.7m)と石尊山(せきそんさん 344.2m)です。



車で登山口のある天王沼まで行き、そこから登りはじめます。
道は杉林の中を九十九折れで高度を稼ぎ、やがて官ノ倉峠に出ます。
ここは平らになっていて、臼入山から来るコースと外秩父七峰縦走コースとが交差するところ。
ここで道を間違えて縦走コースに入ってしまいました。正しいコースは左だったのです。
しばらく行くと庚申塚があり、そこに左に登っていく道がありました。標識を見ると官ノ倉山と出ています。ここで気が付いて正しい方向へ軌道修正。
良かった気が付いて(^_^;)



さて、そこからまた急な登りとなって、しばらく行くと官ノ倉山に着きました。
頂上には犬連れのハイカーがいました。
空は青く、冬の澄み切った空気で遠くまで見通せます。山に詳しくないので山の名前は分かりませんが、赤城山は分かりました。
しばらく休んで次の目的地、石尊山に向かいます。
石尊山へは一度坂を下って、また登り返します。登り返すといってもたいしたことはありません。ちょっと息が切れるくらいです。
石尊山は官ノ倉山より、もっと見晴らしが良いところでした。
360度とまでは行きませんが、ぐるっと見渡せます。
山頂には祠が祀られていたので、手を合わせて無病息災を祈ります。



昼飯も持ってきたのですが、まだ早すぎるのでここでは食べず、ゆっくり休んだ後に下山しました。
帰り道でも数組のハイカーとすれ違ったので、けっこう人気のコースのようです。
今回もお手軽登山でしたが、楽しい時間を過ごせました。
コースタイム
天王沼(9:35)-官ノ倉峠(9:52)-庚申塚(9:57)-官ノ倉山(10:06)
-石尊山(10:21)-天王沼(11:06)
タグ :埼玉
2010年01月28日
鶏鳴山(2010.1.24)
鶏鳴山
2010年1月24日(日) 栃木県日光市今市 記録者 やませみ
今日は栃木100名山、60座の鶏鳴山に登ってきました。
栃木県日光市(旧今市市)長畑地内に位置し標高961mの山です。
天気は快晴! 一路林道中井線を車止めへとしかし既に満車でした。
仕方なく少し戻り林道脇に車を止め、おにぎり・水をリュックに放り込み準備完了。 いざ、出発です。 時間は10時5分。



登山口の看板に『ご自由にお登りください。』の文字が? よく読んで見ると大手土木会社の名前が書いてありました。 納得です。私有地なんですね。少し行くと立派なログハウスが山の中に突如出現。たぶん会社の保養所なのでしょう。
程なく進むと登山道入口の小さな標識をみつけました。この標識のおかげでいつも迷わずに登ることができます。 設置している方に感謝!感謝!!です。 いつも思うのですがどんな方が設置してるんですかなね?
登りだしてしばらくは、手入れの行き届いた桧の林の中をすすみます。樹齢50~60年くらいはたつでしょうか? 登山道に差し込む木漏れ日がなんとも好い感じでした。
桧木立ををすぎたあたりから段々と急なガレ場が続きます。チョット気を抜くとズルズルと滑り落ちてしましそうな感じでした。
確か私の記憶だと2004年に女性の登山者が滑落し動けなくなってしまい防災へりに救助されたのがこの山だったような気がします。 登ってみて納得しました。
ガレ場(岩場)をぬけどんどん進んで行くと程なく頂上に。急に視界が開け西に日光連山、南に関東平野、筑波山ととてもすばらしい眺めでありました。 残念ながら霞が多く「富士山」は見えませんでした。
でも、チョットまてよ『 ここ、頂上??』
良く見ると山名板とみかげが見当たりません。そんなこんなで山頂探し! さらに2~3分程進んだところに961mのピークがありました。 あったー! あったー!! (笑) ご年配の方が山頂だと思い先程の眺めの良いところでお昼を食べていたので帰りがけに教えてあげました。
私もおにぎりをほうばり少しやすんでから、来た道を滑り落ちないように下山しました。



帰り道にすれ違った登山者12名、登山犬1匹(ノーリードでした。) 結構人気あるのですね。
程よく汗をかき車止めに到着! 帰り道に鹿沼温泉(旧ウエルサンピア)により疲れを癒して帰路につきました
2010年1月24日(日) 栃木県日光市今市 記録者 やませみ
今日は栃木100名山、60座の鶏鳴山に登ってきました。
栃木県日光市(旧今市市)長畑地内に位置し標高961mの山です。
天気は快晴! 一路林道中井線を車止めへとしかし既に満車でした。
仕方なく少し戻り林道脇に車を止め、おにぎり・水をリュックに放り込み準備完了。 いざ、出発です。 時間は10時5分。



登山口の看板に『ご自由にお登りください。』の文字が? よく読んで見ると大手土木会社の名前が書いてありました。 納得です。私有地なんですね。少し行くと立派なログハウスが山の中に突如出現。たぶん会社の保養所なのでしょう。
程なく進むと登山道入口の小さな標識をみつけました。この標識のおかげでいつも迷わずに登ることができます。 設置している方に感謝!感謝!!です。 いつも思うのですがどんな方が設置してるんですかなね?
登りだしてしばらくは、手入れの行き届いた桧の林の中をすすみます。樹齢50~60年くらいはたつでしょうか? 登山道に差し込む木漏れ日がなんとも好い感じでした。
桧木立ををすぎたあたりから段々と急なガレ場が続きます。チョット気を抜くとズルズルと滑り落ちてしましそうな感じでした。
確か私の記憶だと2004年に女性の登山者が滑落し動けなくなってしまい防災へりに救助されたのがこの山だったような気がします。 登ってみて納得しました。
ガレ場(岩場)をぬけどんどん進んで行くと程なく頂上に。急に視界が開け西に日光連山、南に関東平野、筑波山ととてもすばらしい眺めでありました。 残念ながら霞が多く「富士山」は見えませんでした。
でも、チョットまてよ『 ここ、頂上??』
良く見ると山名板とみかげが見当たりません。そんなこんなで山頂探し! さらに2~3分程進んだところに961mのピークがありました。 あったー! あったー!! (笑) ご年配の方が山頂だと思い先程の眺めの良いところでお昼を食べていたので帰りがけに教えてあげました。
私もおにぎりをほうばり少しやすんでから、来た道を滑り落ちないように下山しました。



帰り道にすれ違った登山者12名、登山犬1匹(ノーリードでした。) 結構人気あるのですね。
程よく汗をかき車止めに到着! 帰り道に鹿沼温泉(旧ウエルサンピア)により疲れを癒して帰路につきました
タグ :栃木
2010年01月27日
宮島弥山(2010.01.26)
今年初は、神の山、弥山で…
2010年1月26日 広島県 弥山 記録者:あーちゃん
今日は、神の島宮島の弥山(みせん)に登ってきました。
今年初の登山です。
あまり、登り初めとか意識する方ではないのですが、
なんとなく、今年は、初めて登るのなら弥山かな?なんて思っていました。

まずは、宮島のシンボル、大鳥居が迎えてくれました。
弥山には、何コースか登山コースがあります。
以前、紅葉谷コースから登って、大元コースから下ったので、
今回は、まだ歩いたことのない大聖院コースから登って、多宝塔コースを下りました。
今回の大聖院コースは、登山道がほとんど…、いや全部石段の道。
土がありません…

前に歩いた大元コースも、石段ばかりだったのですが、
そのときは、ここは、参道なんだなって思った記憶があります。
ここも、参道なのかな…??
どんどん歩いて、1時間弱で、仁王門跡に到着。
ここから、弥山の山頂方面に向かいます。

頂上~♪
で、頂上では、かなりの展望が望めます!!!!
瀬戸の美しい海と、島々…、それに青空♪♪


弥山の山頂には、広場があって、その広場を囲んで、岩がごつごつ!
頂上で景色を楽しんだ後、元の仁王門跡まで戻り、
今度は、大元コース方面の途中にある駒ヶ林へ向かいました。
駒ヶ林は、厳島合戦の古戦場跡だそうです。
そこには、大きな岩があって、その上で、お昼ご飯♪
向かいに、弥山の頂上の展望台が見えました。


駒ヶ林から、多宝塔コースを下ります。
ここは、あまり登山道が整備されていなくて、
道標もなく、時々、倒木が道を遮ったりしています。
途中、この道であっているのかなって不安になったりしましたが、
まぁ、人の足跡はしっかりあるし、道は、絶えず続いているし、
本当に迷いそうな所には、赤いテープがあったし、まぁ、大丈夫。
でも、一箇所だけ、分岐で違う道を行ってしまって…
足跡があったから、つい、明るい方に向かってしまったら、道がなくなってしまって…
なんとなくいけそうだったけど、明らかに、登山道でないって感じになってしまったので、
引き返して、分岐で、もう一つのほうに向かいました。
そしたら、明快な道が続いていて、ホッ(^^;
迷いそうになったけど、景色も良く、明るくって(石段でない)土の道だったので、
結構、この道、楽しんで下りました。

随分下りて来て、厳島神社を上から見る。箱庭のようです(^^

帰りのフェリーの中から。
結局、登って下りて、約3時間。
見事な青空の中、楽しい初登山でした♪
2010年1月26日 広島県 弥山 記録者:あーちゃん
今日は、神の島宮島の弥山(みせん)に登ってきました。
今年初の登山です。
あまり、登り初めとか意識する方ではないのですが、
なんとなく、今年は、初めて登るのなら弥山かな?なんて思っていました。
まずは、宮島のシンボル、大鳥居が迎えてくれました。
弥山には、何コースか登山コースがあります。
以前、紅葉谷コースから登って、大元コースから下ったので、
今回は、まだ歩いたことのない大聖院コースから登って、多宝塔コースを下りました。
今回の大聖院コースは、登山道がほとんど…、いや全部石段の道。
土がありません…
前に歩いた大元コースも、石段ばかりだったのですが、
そのときは、ここは、参道なんだなって思った記憶があります。
ここも、参道なのかな…??
どんどん歩いて、1時間弱で、仁王門跡に到着。
ここから、弥山の山頂方面に向かいます。
頂上~♪
で、頂上では、かなりの展望が望めます!!!!
瀬戸の美しい海と、島々…、それに青空♪♪
弥山の山頂には、広場があって、その広場を囲んで、岩がごつごつ!
頂上で景色を楽しんだ後、元の仁王門跡まで戻り、
今度は、大元コース方面の途中にある駒ヶ林へ向かいました。
駒ヶ林は、厳島合戦の古戦場跡だそうです。
そこには、大きな岩があって、その上で、お昼ご飯♪
向かいに、弥山の頂上の展望台が見えました。
駒ヶ林から、多宝塔コースを下ります。
ここは、あまり登山道が整備されていなくて、
道標もなく、時々、倒木が道を遮ったりしています。
途中、この道であっているのかなって不安になったりしましたが、
まぁ、人の足跡はしっかりあるし、道は、絶えず続いているし、
本当に迷いそうな所には、赤いテープがあったし、まぁ、大丈夫。
でも、一箇所だけ、分岐で違う道を行ってしまって…
足跡があったから、つい、明るい方に向かってしまったら、道がなくなってしまって…
なんとなくいけそうだったけど、明らかに、登山道でないって感じになってしまったので、
引き返して、分岐で、もう一つのほうに向かいました。
そしたら、明快な道が続いていて、ホッ(^^;
迷いそうになったけど、景色も良く、明るくって(石段でない)土の道だったので、
結構、この道、楽しんで下りました。
随分下りて来て、厳島神社を上から見る。箱庭のようです(^^
帰りのフェリーの中から。
結局、登って下りて、約3時間。
見事な青空の中、楽しい初登山でした♪
2010年01月26日
小田代ヶ原スノーシュートレッキング
小田代ヶ原スノーシュートレッキング
2010年1月11日 栃木県奥日光 記録者 じっちゃん
正月明け初めての3連休。
正月はどこも行かなかったからどこかで体を動かそう(そう言えば初詣もして居なかった。笑)と副隊長にメールを入れると副隊長も連休は隊長に振られたらしく日光へ行こうとなった次第であります。
話が変わりますが昨年から隊長や副隊長達と冬の雪山遊びをし始めたのには訳があるのです。
毎年晩秋まできのこきのこと山を駆け回っていて秋に体が最高潮になるのですがその後がいけません。
冬の間は近くの山に月一でハイキングに行く程度であとの休みは炬燵の番人になる始末、そんなある年に・・・・・・。
渓のシーズン始まりの7月、念願叶って憧れの早出川へ渓の翁こと瀬畑雄三氏との釣行が決まり先発隊として1日早く入渓したは良いが私の体調不良と言うか体力不足から皆と1夜を共に出来ず撤退をした苦い経験がありました。
やはり年とともに体力の衰えは激しく春の山菜からでは渓シーズン始まりまでに取り戻せなくなって来たのです。
そこで冬の間のトレーニングとして雪山遊びをする事にしたのでありました。
そんな訳で今年最初の雪山登山を日光の高山に白羽の矢を立ていざ出発しましたが情報不足で建てたいい加減な計画のだったため当日問題が発生。
急遽小田代ヶ原に変更と相成った訳でありました。
今回は湯川に沿って小田代を目指し1週して戻る事に。
川沿いの樹林帯は昨日新雪のお陰で動物たちの足跡がくっきり残りとてもいい足跡観察会になりました。
その後は昨日の雪と風のお陰で人の足跡がすべて消えた雪原を2人で小田代の貴婦人を撮るベストスポットまで今日初めてのトレースを付けて歩けました。
帰りは小田城を1週するように別ルートでもどり湯川沿いを登り返して車まで戻り本日のスノーシュートレッキング終了。
シーズン最初にしてはとても楽しくいい足慣らしになったトレッキングでありました。
副隊長ありがとう。またよろしく。



2010年1月11日 栃木県奥日光 記録者 じっちゃん
正月明け初めての3連休。
正月はどこも行かなかったからどこかで体を動かそう(そう言えば初詣もして居なかった。笑)と副隊長にメールを入れると副隊長も連休は隊長に振られたらしく日光へ行こうとなった次第であります。
話が変わりますが昨年から隊長や副隊長達と冬の雪山遊びをし始めたのには訳があるのです。
毎年晩秋まできのこきのこと山を駆け回っていて秋に体が最高潮になるのですがその後がいけません。
冬の間は近くの山に月一でハイキングに行く程度であとの休みは炬燵の番人になる始末、そんなある年に・・・・・・。
渓のシーズン始まりの7月、念願叶って憧れの早出川へ渓の翁こと瀬畑雄三氏との釣行が決まり先発隊として1日早く入渓したは良いが私の体調不良と言うか体力不足から皆と1夜を共に出来ず撤退をした苦い経験がありました。
やはり年とともに体力の衰えは激しく春の山菜からでは渓シーズン始まりまでに取り戻せなくなって来たのです。
そこで冬の間のトレーニングとして雪山遊びをする事にしたのでありました。
そんな訳で今年最初の雪山登山を日光の高山に白羽の矢を立ていざ出発しましたが情報不足で建てたいい加減な計画のだったため当日問題が発生。
急遽小田代ヶ原に変更と相成った訳でありました。
今回は湯川に沿って小田代を目指し1週して戻る事に。
川沿いの樹林帯は昨日新雪のお陰で動物たちの足跡がくっきり残りとてもいい足跡観察会になりました。
その後は昨日の雪と風のお陰で人の足跡がすべて消えた雪原を2人で小田代の貴婦人を撮るベストスポットまで今日初めてのトレースを付けて歩けました。
帰りは小田城を1週するように別ルートでもどり湯川沿いを登り返して車まで戻り本日のスノーシュートレッキング終了。
シーズン最初にしてはとても楽しくいい足慣らしになったトレッキングでありました。
副隊長ありがとう。またよろしく。



タグ :栃木
2010年01月25日
仙元山(2010.1.20)
仙元山リハビリ登山
2010年1月20日(水)晴 埼玉県比企郡小川町 仙元山(298.9m) 記録者 たか
ギックリ腰もだいぶ良くなって、痛みはほとんど無くなりました。
今日は代休だったのですが、家でゴロゴロしてるのも退屈です。かといって腰のことも考えると無理も出来ませんし。
なのでかねてから考えていた低山ハイクに行くことにしました。
今日の山は埼玉県比企郡小川町の仙元山です。
この山、なんと標高298.9m(^_^;) 東京タワー(333m)より低いです。それに登山口の標高が100mほどありますから、実質約200mの登山です。でもリハビリにはちょうどよいコースでしょう。
家を10時半に出発(笑) 登山口には1時間ほどで着きました。
林道バリケード手前のスペースに車を止めて、バリケードをすり抜けしばらく歩くと右手に遊歩道がありました。
そう、登山道じゃなく遊歩道って書いてあります(^_^;)



道は植林された杉木立の中を登っていきます。木漏れ日が優しい日差しを投げかけます。
今日は久しぶりに穏やかな陽気になると天気予報が言っていました。
現在の気温は10度ほどでしょうか。だんだんと汗が吹き出してきたので、立ち止まってウインドブレイカーを脱ぎました。
登山道は杉が多いですが、ところどころ植林が切れて雑木林となります。クヌギやコナラといった木々は落葉樹ですから、この時期は葉が落ちて青空が見えます。杉の薄暗い森よりもずっと気持ちがいいですね
やがて道は尾根へと出ます。合流地点を左に行くと青山城址ですが、それは帰りに寄るとして山頂を目指します。
なんか開けてきたような・・・
え~、マジ! もう着いたの!?
あっというまに山頂でした(爆)
ここまで写真撮りながらで30分
散歩ですね(^_^;)
山頂からは小川町が良く見えます。
遠くには群馬の山が見えています。
どれがどれだか私には分かりませんけど、方角的には浅間山、榛名山、赤城山が見えるはず。



頂上でお昼を食べて全然見晴らしのきかない展望台に寄り、そのあと百庚申に立ち寄りました。
百庚申とは庚申塚がたくさんあるところ。その庚申塚が静寂に包まれてずらーっと建ってました。今から150年ほど前のものだそうです。
さて、一通り見て帰路に着きました。
帰り道には「青山城址」に寄ってみましょう。
この城は500年ほど前にあったようで、砦のようなものだったのでしょうね。
500年程前というと織田信長の時代・・・。戦国時代ですね。
その時代だったら、のんびり山登りなんてしてられませんね。
500年前のものが一つだけ残ってました。それは岩を切り抜いたノミの跡です。
そんな歴史のロマンを感じながら下るとあっという間に車に着いちゃいました。
500年の時の流れと比べ物にならないほどの短さですね(^_^;)
でも、近所を散歩するよりずっと気持ちがいいし、楽しい時間でした。
2010年1月20日(水)晴 埼玉県比企郡小川町 仙元山(298.9m) 記録者 たか
ギックリ腰もだいぶ良くなって、痛みはほとんど無くなりました。
今日は代休だったのですが、家でゴロゴロしてるのも退屈です。かといって腰のことも考えると無理も出来ませんし。
なのでかねてから考えていた低山ハイクに行くことにしました。
今日の山は埼玉県比企郡小川町の仙元山です。
この山、なんと標高298.9m(^_^;) 東京タワー(333m)より低いです。それに登山口の標高が100mほどありますから、実質約200mの登山です。でもリハビリにはちょうどよいコースでしょう。
家を10時半に出発(笑) 登山口には1時間ほどで着きました。
林道バリケード手前のスペースに車を止めて、バリケードをすり抜けしばらく歩くと右手に遊歩道がありました。
そう、登山道じゃなく遊歩道って書いてあります(^_^;)



道は植林された杉木立の中を登っていきます。木漏れ日が優しい日差しを投げかけます。
今日は久しぶりに穏やかな陽気になると天気予報が言っていました。
現在の気温は10度ほどでしょうか。だんだんと汗が吹き出してきたので、立ち止まってウインドブレイカーを脱ぎました。
登山道は杉が多いですが、ところどころ植林が切れて雑木林となります。クヌギやコナラといった木々は落葉樹ですから、この時期は葉が落ちて青空が見えます。杉の薄暗い森よりもずっと気持ちがいいですね
やがて道は尾根へと出ます。合流地点を左に行くと青山城址ですが、それは帰りに寄るとして山頂を目指します。
なんか開けてきたような・・・
え~、マジ! もう着いたの!?
あっというまに山頂でした(爆)
ここまで写真撮りながらで30分
散歩ですね(^_^;)
山頂からは小川町が良く見えます。
遠くには群馬の山が見えています。
どれがどれだか私には分かりませんけど、方角的には浅間山、榛名山、赤城山が見えるはず。



頂上でお昼を食べて全然見晴らしのきかない展望台に寄り、そのあと百庚申に立ち寄りました。
百庚申とは庚申塚がたくさんあるところ。その庚申塚が静寂に包まれてずらーっと建ってました。今から150年ほど前のものだそうです。
さて、一通り見て帰路に着きました。
帰り道には「青山城址」に寄ってみましょう。
この城は500年ほど前にあったようで、砦のようなものだったのでしょうね。
500年程前というと織田信長の時代・・・。戦国時代ですね。
その時代だったら、のんびり山登りなんてしてられませんね。
500年前のものが一つだけ残ってました。それは岩を切り抜いたノミの跡です。
そんな歴史のロマンを感じながら下るとあっという間に車に着いちゃいました。
500年の時の流れと比べ物にならないほどの短さですね(^_^;)
でも、近所を散歩するよりずっと気持ちがいいし、楽しい時間でした。
タグ :埼玉
2010年01月20日
上田市・太郎山~虚空蔵山縦走・後
太郎山~虚空蔵山縦走・後
10年1月17日(日) 参加者:じゅんちゃ&木偶野呂馬 記録:木偶野呂馬


北ア蓮華・北葛・唐沢岳方面/雪道を行く
太郎山方虚空蔵山へ
11:00発,階段を登り神社の裏側をすり抜けて太郎山に向かい、5~6分で山頂(1164m)に着くとそこからは雪山だった。神社からの展望に加えて北側の山々,根子岳や四阿山,烏帽子岳,浅間山等が望まれるようになり、また北アルプスの蓮華岳以北の山々もよく見えるようになる。


西峠にて/マップ
大勢の登山者もほとんどが太郎山止まりで、そこから虚空蔵山に向けて縦走する者はいないが踏み跡はある。11:25発,西に向かって伸びる稜線をそのまま下ると程なく境内の展望広場からの道を合わせ、5分ほどで西峠に着く(11:32)。北側からわずかに風があるが陽射しは暖かくルンルンの稜線漫歩となる。


ここでお昼/虚空蔵山かと思った
11:52,1069mのピーク付近で南向きの暖かな草地に腰を下ろして昼食を摂り、12:15出発。しばらく後に木の間越しにそれらしいピークが見え、その間の大きな弛みを下るとその鞍部辺りが大覗きである。そこから市街地に下る道があり虚空蔵山登頂後はそこまで戻って下る予定で12 :20に通過。


最後の登りかと思ったが・・/向こうのピークだった
直下から見上げる件のピークはちょっとした岩峰で、アイゼンのないプラブーツは滑りやすくやや手間取る。12:44にそのピーク(1073m)に到達,だそれは目指す山ではなく、虚空蔵山は目の前の小ピークを越えたさらに先で行くか止めるかちょっとためらう距離にあった。そこに一団の登山者の姿が見えているのを見て前進する。jun1さんはここで軽アイゼンを装着。


虚空蔵山にて/烏帽子岳を望む
13:02,最後のロープ場を登り切って虚空蔵山に着くと、入れ違いに一団のパーティーが太郎山に向けて出発し山頂一帯は急に静かになる。13:12,どこまでも晴れ渡る山々を目に納めて下山開始。ロープ場のすぐ下からの踏み跡を辿って直下降する。


兎峰分岐/ロープ場あり
前世紀の遺物とも言えるプラブーツでの雪のない岩場の下りには最悪である。この靴はくるぶしをスッポリ覆っているので岩場の凹凸を足首で吸収して柔軟に対応することが出来ない。なので思い切って次のステップを踏み出せず歩きのリズムがつくれない。スキー靴を履いて歩くほどではないが、靴によって動きを支配されてしまいおっかなびっくりの腰の引けた歩きになってしまう上に上半身の揺れが大きくなり疲れる。フラットな雪面にフィットしてこそのプラブーツであることがよく分かった。


座摩神社/縁起
13:24,兎峰と言う岩峰に向かう道と、それを迂回する道の分岐で北側をトラバースする峰を選んで滑りやすいロープ場をさらに下り、ようやく緩やかになった辺りで10分の休憩。14:00,送電線鉄塔(№23)を通過,14:06,座摩神社着。そこからは車道があり、大休止の後人家のある平地に下りる(14:34)。


兎峰に登山者が見える/登山口着
14:45,市街地から上田バイパスに出て見上げるとそそり立つ兎峰の岩峰に登山者の姿が認められた。4km歩いて15:40,登山口へ戻り終了。


鹿教温泉文殊堂/氷の灯篭
帰途、久々に鹿教湯温泉に浸かる。文殊堂に向かう道が氷の灯篭でライトアップされて幻想的な雰囲気を醸していた。


付 時代の終焉
90年頃に買ったプラブーツが壊れた。10年間の空白のおかげでかさしたる劣化も見られず未だ使い続けていたのだが、遂に終焉の時は来た。
プラブーツの利点はインナーブーツがあり、それが足に柔らかくフィットして履き心地がよく、また雪山の幕営時、テントから外に出る際にいちいち靴を履かず、インナーだけで出られるので非常に重宝することだ。
一方で突然破壊と言う問題があって90年代には国会でも取り上げられたことがあり、常に不安がつきまとう靴でもあった。実際、壊れたブーツからそのインナーブーツを取り出してみると、プラの本体は底の部分を除くと極めて薄っぺらで決して頑丈とは言えないつくりだったことが分かり、壊れてもおかしくない気がした。
破損部は上部のフックがついた部分が本体から引きちぎれそうになったもので、突然破壊とは言えないが引きちぎれるのは時間の問題となっているので今後の使用には耐えられそうにない。
時代はすでにプラブーツを越えて今では顧みられなくなっている遺物であるが、自分にとっては重宝なだけでなく数々の恩恵を与えてくれた大切な存在だった。


革靴も駄目になって今現在登山靴がないのでたちまちの山行にも支障が出てしまい困ったことになった。リスクの高い稜線では論外だが、単なる雪道ならシュリンゲでぐるぐる巻きにしてでももう1~2回使うつもりではある。
10年1月17日(日) 参加者:じゅんちゃ&木偶野呂馬 記録:木偶野呂馬


北ア蓮華・北葛・唐沢岳方面/雪道を行く
太郎山方虚空蔵山へ
11:00発,階段を登り神社の裏側をすり抜けて太郎山に向かい、5~6分で山頂(1164m)に着くとそこからは雪山だった。神社からの展望に加えて北側の山々,根子岳や四阿山,烏帽子岳,浅間山等が望まれるようになり、また北アルプスの蓮華岳以北の山々もよく見えるようになる。


西峠にて/マップ
大勢の登山者もほとんどが太郎山止まりで、そこから虚空蔵山に向けて縦走する者はいないが踏み跡はある。11:25発,西に向かって伸びる稜線をそのまま下ると程なく境内の展望広場からの道を合わせ、5分ほどで西峠に着く(11:32)。北側からわずかに風があるが陽射しは暖かくルンルンの稜線漫歩となる。


ここでお昼/虚空蔵山かと思った
11:52,1069mのピーク付近で南向きの暖かな草地に腰を下ろして昼食を摂り、12:15出発。しばらく後に木の間越しにそれらしいピークが見え、その間の大きな弛みを下るとその鞍部辺りが大覗きである。そこから市街地に下る道があり虚空蔵山登頂後はそこまで戻って下る予定で12 :20に通過。


最後の登りかと思ったが・・/向こうのピークだった
直下から見上げる件のピークはちょっとした岩峰で、アイゼンのないプラブーツは滑りやすくやや手間取る。12:44にそのピーク(1073m)に到達,だそれは目指す山ではなく、虚空蔵山は目の前の小ピークを越えたさらに先で行くか止めるかちょっとためらう距離にあった。そこに一団の登山者の姿が見えているのを見て前進する。jun1さんはここで軽アイゼンを装着。


虚空蔵山にて/烏帽子岳を望む
13:02,最後のロープ場を登り切って虚空蔵山に着くと、入れ違いに一団のパーティーが太郎山に向けて出発し山頂一帯は急に静かになる。13:12,どこまでも晴れ渡る山々を目に納めて下山開始。ロープ場のすぐ下からの踏み跡を辿って直下降する。


兎峰分岐/ロープ場あり
前世紀の遺物とも言えるプラブーツでの雪のない岩場の下りには最悪である。この靴はくるぶしをスッポリ覆っているので岩場の凹凸を足首で吸収して柔軟に対応することが出来ない。なので思い切って次のステップを踏み出せず歩きのリズムがつくれない。スキー靴を履いて歩くほどではないが、靴によって動きを支配されてしまいおっかなびっくりの腰の引けた歩きになってしまう上に上半身の揺れが大きくなり疲れる。フラットな雪面にフィットしてこそのプラブーツであることがよく分かった。


座摩神社/縁起
13:24,兎峰と言う岩峰に向かう道と、それを迂回する道の分岐で北側をトラバースする峰を選んで滑りやすいロープ場をさらに下り、ようやく緩やかになった辺りで10分の休憩。14:00,送電線鉄塔(№23)を通過,14:06,座摩神社着。そこからは車道があり、大休止の後人家のある平地に下りる(14:34)。


兎峰に登山者が見える/登山口着
14:45,市街地から上田バイパスに出て見上げるとそそり立つ兎峰の岩峰に登山者の姿が認められた。4km歩いて15:40,登山口へ戻り終了。


鹿教温泉文殊堂/氷の灯篭
帰途、久々に鹿教湯温泉に浸かる。文殊堂に向かう道が氷の灯篭でライトアップされて幻想的な雰囲気を醸していた。


付 時代の終焉
90年頃に買ったプラブーツが壊れた。10年間の空白のおかげでかさしたる劣化も見られず未だ使い続けていたのだが、遂に終焉の時は来た。
プラブーツの利点はインナーブーツがあり、それが足に柔らかくフィットして履き心地がよく、また雪山の幕営時、テントから外に出る際にいちいち靴を履かず、インナーだけで出られるので非常に重宝することだ。
一方で突然破壊と言う問題があって90年代には国会でも取り上げられたことがあり、常に不安がつきまとう靴でもあった。実際、壊れたブーツからそのインナーブーツを取り出してみると、プラの本体は底の部分を除くと極めて薄っぺらで決して頑丈とは言えないつくりだったことが分かり、壊れてもおかしくない気がした。
破損部は上部のフックがついた部分が本体から引きちぎれそうになったもので、突然破壊とは言えないが引きちぎれるのは時間の問題となっているので今後の使用には耐えられそうにない。
時代はすでにプラブーツを越えて今では顧みられなくなっている遺物であるが、自分にとっては重宝なだけでなく数々の恩恵を与えてくれた大切な存在だった。


革靴も駄目になって今現在登山靴がないのでたちまちの山行にも支障が出てしまい困ったことになった。リスクの高い稜線では論外だが、単なる雪道ならシュリンゲでぐるぐる巻きにしてでももう1~2回使うつもりではある。
2010年01月19日
上田市・太郎山~虚空蔵山縦走
太郎山~虚空蔵山縦走・前
10年1月17日(日) 参加者:じゅんちゃ&木偶 記録者:木偶野呂馬


左:縦走路からの太郎山 右:上田市街を見下ろす
jnu1さんにお任せで上田市と坂城町の境にある太郎山,虚空蔵山を縦走する。上田近辺の山はまったく未知であるし、当初は近場で雪山ハイキング出来る山を~と言うことだったので完全装備で現地に着いてみたら何と半袖の山だった。
太郎山はこの地方では人気の山で登山口付近の道路には車がズラリと並んでおり、老若男女沢山の登山者がハイキングシューズで次々と登って行く。またすでに下りて来る人もあり、jun1さんは『安曇野で言えば光城山みたいな山らしい』と言う。そんな中での雪山対応のプラブーツはいささか奇異に見えたかもしれないがそれしかなかったのでいたしかたなし。


左:登山口 右:祠あり
9:22発。快晴で陽射しのある所は暖かく地面が緩み始めているが、南東稜を登る登山道は殆どがコナラなどの樹林帯の中で雪が残っており、それが凍って滑りやすく意外と歩きにくい。雪山のつもりだったので軽アイゼンは持っていないし、10本爪を履くわけにもいかないので恐るおそる登る羽目になる。長袖シャツを着て歩き始めたが、直に暑くなり半袖になる。


左:赤門 右:太郎神社
この地方特有の祠や里程標を見ながらゆっくり登って40分で『太郎山神社』と書かれた鳥居を通り、さらに40分で赤い鳥居のある山門の先の石段を登って10:46太郎神社に着く。


左:関東富士見100選碑 右:北ア蓮華岳方面
神社はまったくの日陰で冷蔵庫のような寒さだが、山門に戻って南側に廻るとそこは東~南~西に向けて開けた明るい展望広場で、東の烏帽子岳から浅間の外輪山,秩父山塊,八ヶ岳・蓼科山,南アルプス,霧が峰,美ヶ原,を隔てて西の北アルプスに至る山々が望まれ、また眼下に上田市や青木村の街並みを見下ろすことが出来た。よく晴れていて富士山もスッキリ見えており『関東富士見100選』の1つである。


左:八ヶ岳の裾野と富士 右:蓼科山・八ヶ岳
太郎神社からの展望でアルプスや八ヶ岳,秩父山塊等の遠景の山々以上に興味深かいのは、南南西方向に端正なたたずまいを見せる夫神岳とそれをそのまま持ち上げて南に大きく傾けたような子檀嶺(こまゆみ)岳,そこから始まって十観山,御鷹山,入山,二ツ石峰,保福寺峠,三才山,戸谷峰と連なる山なみや女神岳,独鈷山等,青木村を取り巻く山々である。


左:境界線ラインの右端に子檀嶺(こまゆみ)岳,ラインの左にある端正な山が夫神岳
右:十観山~御鷹山~入山~二ツ石峰~三才山~戸谷峰の境界線ライン
特に保福寺峠から十観山に至る旧四賀村と青木村の境界線の山なみは、これまで冬期縦走を目論みながらも保福寺峠への道が通行不能になるために手を拱いていたのだが、それを逆方向から見ると十観山から保福寺峠まで縦走してピストンするか鹿教湯温泉に下るというコース取りもあり得ると言うことに気づかされ、大いに参考になった。いつもとは違う方向から山を見るのも時に必要なことだと言うことを教えられた気がする。
10年1月17日(日) 参加者:じゅんちゃ&木偶 記録者:木偶野呂馬


左:縦走路からの太郎山 右:上田市街を見下ろす
jnu1さんにお任せで上田市と坂城町の境にある太郎山,虚空蔵山を縦走する。上田近辺の山はまったく未知であるし、当初は近場で雪山ハイキング出来る山を~と言うことだったので完全装備で現地に着いてみたら何と半袖の山だった。
太郎山はこの地方では人気の山で登山口付近の道路には車がズラリと並んでおり、老若男女沢山の登山者がハイキングシューズで次々と登って行く。またすでに下りて来る人もあり、jun1さんは『安曇野で言えば光城山みたいな山らしい』と言う。そんな中での雪山対応のプラブーツはいささか奇異に見えたかもしれないがそれしかなかったのでいたしかたなし。


左:登山口 右:祠あり
9:22発。快晴で陽射しのある所は暖かく地面が緩み始めているが、南東稜を登る登山道は殆どがコナラなどの樹林帯の中で雪が残っており、それが凍って滑りやすく意外と歩きにくい。雪山のつもりだったので軽アイゼンは持っていないし、10本爪を履くわけにもいかないので恐るおそる登る羽目になる。長袖シャツを着て歩き始めたが、直に暑くなり半袖になる。


左:赤門 右:太郎神社
この地方特有の祠や里程標を見ながらゆっくり登って40分で『太郎山神社』と書かれた鳥居を通り、さらに40分で赤い鳥居のある山門の先の石段を登って10:46太郎神社に着く。


左:関東富士見100選碑 右:北ア蓮華岳方面
神社はまったくの日陰で冷蔵庫のような寒さだが、山門に戻って南側に廻るとそこは東~南~西に向けて開けた明るい展望広場で、東の烏帽子岳から浅間の外輪山,秩父山塊,八ヶ岳・蓼科山,南アルプス,霧が峰,美ヶ原,を隔てて西の北アルプスに至る山々が望まれ、また眼下に上田市や青木村の街並みを見下ろすことが出来た。よく晴れていて富士山もスッキリ見えており『関東富士見100選』の1つである。


左:八ヶ岳の裾野と富士 右:蓼科山・八ヶ岳
太郎神社からの展望でアルプスや八ヶ岳,秩父山塊等の遠景の山々以上に興味深かいのは、南南西方向に端正なたたずまいを見せる夫神岳とそれをそのまま持ち上げて南に大きく傾けたような子檀嶺(こまゆみ)岳,そこから始まって十観山,御鷹山,入山,二ツ石峰,保福寺峠,三才山,戸谷峰と連なる山なみや女神岳,独鈷山等,青木村を取り巻く山々である。


左:境界線ラインの右端に子檀嶺(こまゆみ)岳,ラインの左にある端正な山が夫神岳
右:十観山~御鷹山~入山~二ツ石峰~三才山~戸谷峰の境界線ライン
特に保福寺峠から十観山に至る旧四賀村と青木村の境界線の山なみは、これまで冬期縦走を目論みながらも保福寺峠への道が通行不能になるために手を拱いていたのだが、それを逆方向から見ると十観山から保福寺峠まで縦走してピストンするか鹿教湯温泉に下るというコース取りもあり得ると言うことに気づかされ、大いに参考になった。いつもとは違う方向から山を見るのも時に必要なことだと言うことを教えられた気がする。
2010年01月19日
山スキー、西吾妻山・若女平コース
山スキー、西吾妻山・若女平コース
2010年1月11日 福島県西吾妻山 記録者 哲ちゃん
ここに来るのはこれが二回目。前回はロープウェイとリフトを乗り継ぎスキー場のトップまで行ったものの、容赦なく降り続いてくれる雪のために断念しスキー場をそのまま滑り降りる事になってしまった。今日はうってかわっての青空が広がり、絶好の山スキー日和に恵まれる。スキー場のトップまで行き辺りを偵察するがトレースは無かった。入山地点がよく解らなかったが適当に歩きやすいところから中大嶺を目指す。樹氷が立ち並ぶ中を、GPSを頼りに高い方を目指しながら歩いていく。樹氷原は中大嶺の山頂付近まで続いていて、そこまで行きようやく視界が広がり西吾妻山を見ることが出来た。ここから西吾妻山までは青空の下の爽快な歩きとなった。



飯豊山、蔵王山などが遠くに見え山形の平野部までもがよく見えた。平たい山容の西吾妻山の山頂は何処だかわからなかったが、一応一番高いと思われる付近に行ってから西吾妻小屋に降った。ここでシールを剥がし若女平に向けて滑り降りる。樹氷原の中に突入すると激パウが待っていてくれた。沢筋に滑るがまだやや雪は少なめだった。あと2~3m積もれば快適にロングランが楽しめそうだったが、ボトムに入ると板は止まってしまう。沢筋とツリーランを繰り返しながら若女平付近に到着。



ルートが若干左にずれていたようでトラバース気味に2、3の支尾根を越えてからルートの痩せ尾根に乗る。この尾根を降り手持ちの資料での下降点に着いたが、滑り降りられそうな斜面が無い。どうやらここでもまだ雪不足で滑降に適した斜面になっていなかったようだった。しかたがないので引き返し適当な所からトラバース気味に沢筋まで降りる。あとは沢の横を滑って道路にでた。



2010年1月11日 福島県西吾妻山 記録者 哲ちゃん
ここに来るのはこれが二回目。前回はロープウェイとリフトを乗り継ぎスキー場のトップまで行ったものの、容赦なく降り続いてくれる雪のために断念しスキー場をそのまま滑り降りる事になってしまった。今日はうってかわっての青空が広がり、絶好の山スキー日和に恵まれる。スキー場のトップまで行き辺りを偵察するがトレースは無かった。入山地点がよく解らなかったが適当に歩きやすいところから中大嶺を目指す。樹氷が立ち並ぶ中を、GPSを頼りに高い方を目指しながら歩いていく。樹氷原は中大嶺の山頂付近まで続いていて、そこまで行きようやく視界が広がり西吾妻山を見ることが出来た。ここから西吾妻山までは青空の下の爽快な歩きとなった。



飯豊山、蔵王山などが遠くに見え山形の平野部までもがよく見えた。平たい山容の西吾妻山の山頂は何処だかわからなかったが、一応一番高いと思われる付近に行ってから西吾妻小屋に降った。ここでシールを剥がし若女平に向けて滑り降りる。樹氷原の中に突入すると激パウが待っていてくれた。沢筋に滑るがまだやや雪は少なめだった。あと2~3m積もれば快適にロングランが楽しめそうだったが、ボトムに入ると板は止まってしまう。沢筋とツリーランを繰り返しながら若女平付近に到着。



ルートが若干左にずれていたようでトラバース気味に2、3の支尾根を越えてからルートの痩せ尾根に乗る。この尾根を降り手持ちの資料での下降点に着いたが、滑り降りられそうな斜面が無い。どうやらここでもまだ雪不足で滑降に適した斜面になっていなかったようだった。しかたがないので引き返し適当な所からトラバース気味に沢筋まで降りる。あとは沢の横を滑って道路にでた。



タグ :福島
2010年01月18日
山王帽子山
山王帽子山
2010年1月17日 栃木県日光市 山王帽子山 記録者 あっちゃん
 今回は山王帽子山に行ってきました。
今回は山王帽子山に行ってきました。
ハイシーズンは観光客で賑わう光徳牧場もさすがにこの季節は人も疎らで
気温マイナス8度の雪景色!
クロスカントリーのコースもあり
やや明るめの樹林帯を縫うように登山道をひた歩きます。
適当に締まってサラッとした雪の感触がスノーシューから伝わって
何とも言えない気持ちの高揚感がたまりません!!
暫くトレースを辿って登山口まで来ると
なんと美味しい風景でしょう!
まっさらな雪だけで誰のトレースもありません。
ラッセルマニアの自分としては最高のシチュエーションであります。


あまり展望の開けたポイントは少ないのですが
時折見える戦場ヶ原や男体山を眺めながら快調に歩を進め
深い雪に汗をかきながら約3時間半ほどで山頂へたどり着き小休止
軽く山頂ラーメンとオニギリを食べ下山しました。
静寂な雪山の自然と仲間との楽しい会話
豪勢じゃないけど旨い飯
なんて、楽しい遊びなんでしょうか!!
改めて思いました!
今度はどこに行こうかな!
2010年1月17日 栃木県日光市 山王帽子山 記録者 あっちゃん
 今回は山王帽子山に行ってきました。
今回は山王帽子山に行ってきました。ハイシーズンは観光客で賑わう光徳牧場もさすがにこの季節は人も疎らで
気温マイナス8度の雪景色!
クロスカントリーのコースもあり
やや明るめの樹林帯を縫うように登山道をひた歩きます。
適当に締まってサラッとした雪の感触がスノーシューから伝わって
何とも言えない気持ちの高揚感がたまりません!!
暫くトレースを辿って登山口まで来ると
なんと美味しい風景でしょう!
まっさらな雪だけで誰のトレースもありません。
ラッセルマニアの自分としては最高のシチュエーションであります。


あまり展望の開けたポイントは少ないのですが
時折見える戦場ヶ原や男体山を眺めながら快調に歩を進め
深い雪に汗をかきながら約3時間半ほどで山頂へたどり着き小休止
軽く山頂ラーメンとオニギリを食べ下山しました。
静寂な雪山の自然と仲間との楽しい会話
豪勢じゃないけど旨い飯
なんて、楽しい遊びなんでしょうか!!
改めて思いました!
今度はどこに行こうかな!
タグ :栃木
2010年01月11日
ちょいと本沢へ~雪中往復12時間の日帰り入浴
ちょいと本沢へ~雪中往復12時間の日帰り入浴
1月10日(日) 八ヶ岳・渋の湯~本沢温泉往復 参加者2名 記録:木偶野呂馬


前々から本沢温泉に行こう行こうと言いながらなかなか実現しなかったのは、縦走の途中で立ち寄って稲子か松原湖方面に下るのでなければ態々温泉狙いで行ってまた戻ってこなければならないからである。
今回はシーズン最初の足慣らしを兼ねてそれをやろうと言うことになり、天狗岳方面には目もくれずひたすら本沢温泉だけを目指し、また汗をかいて戻ることにした。


中山峠からルートは夏沢峠経由でぐるっと廻るかあるいはその逆かであるが、峠まで来て見ると天狗岳方面の風が強そうなので、あまり深く考えずに行け行けドンドンで峠を越えてみどり池・しらびそ小屋方面に下る。
2人ともそのルートを知らないままに、いきなりの鎖場からほぼ真下に向けて一気に谷底まで下ろされ、さらに急な下りが続くのにびっくりする。200mは下ったかと思う辺りに『中山峠まで40分 みどり池まで40分』と書かれた看板があり、時計を見ると峠から20分かかっていた。その時点では『こんな壁のような急登なんてとても登れたものじゃない~』等と思っていたルートだが、結果的には帰路そこを登る羽目になる。


看板から幾分ゆるくなった道を下る途中で10人あまりのパーティーと数人のパーティー、2人ずれの2組のパーティーを交わし、30分あまりで『みどり池⇔中山峠』の標識を通過,その少し先でみどり池・しらびそ小屋方面と本沢温泉方面の分岐点に到達し、右折して尾根越えの道に入る。中山峠から55分。


道は天狗岳から東に張り出す大きな尾根を越える道で、はじめはほぼ等高線に沿った揺るやかな登りがだらだらと続き、最後にややきつめの登りがあって尾根を乗越す辺りに『本沢温泉へ30分』の標識があり、そこから登った分だけ下るとまもなく稲子小屋方面からの道に合流する。そこで4人のパーティーを追い越して20分弱で本沢温泉に着く。中山峠から2時間17分,渋の湯からは5時間17分。


本館の少し下にある外風呂は本館とは別料金(600円)で男女別になっておらず、混浴もしくは混浴を避けたければ先客優先で空くのを待つ,あるいは待ってもらうと言う仕組みになっている。浴槽が2つあり木の板で覆われているのではじめはかなり熱いが、蓋を取って浸かっているとすぐに丁度いい湯加減になる。蓋を全部取らずに首だけ出していればそれ以上は冷めないのでゆったりと長湯できる。
4~5人は入れるが脱衣場が狭く登山スタイルでの靴や衣類の着脱に手間取るのが難点。野天風呂は登山道を少し登って先の沢にあるが、まったくの野天なので雪の中で入るには脱衣,着衣が大変そう。


しっかり温まり弁当を食べて帰途に就く。予定では夏沢峠から箕冠山,根石岳,東天狗岳と廻ることになるのだが、ナイフリッジで吹雪かれるのは避けたいと言うことで来た道を引き返すことにする。
中山峠直下の登りを考えると気が重いが、お湯に浸かって緩んだ気分での稜線歩きはよろしくないだろう。『逆コースにすればよかった』とjun1さんが悔やむことしきりだが事前研究不足で致し方なし。


中山峠まで3.5時間,渋の湯まで6時間を見込んで11:40に出発。アイゼンをつけたので蹴り足が流れない分だけ歩きやすくなり、みどり池分岐まで1時間半,峠下の看板まで2時間半と順調に来る。途中で女性1名を含む4人の若者のパーティーに先を譲って後を追うも、22~23kgを担いでぐいぐい登って行く若さには追いつきようもなかった。


峠下からの登りでは木の間越しに見えたと思った空が実はその上の雪の壁で、その壁では久々に両手でピッケルを思いっきり打ち込んで体を引き上げる場面もあったが、下った時に思ったほどのしんどさはなく35分で壁を登りきって中山峠に14:45,見込みより30分早く着く。


黒百合ヒュッテ着15:00,気温-9.5℃。朝よりも増えたテントを尻目にすぐに下山。その頃になって日が照り始め、林間がパッと明るくなる。
16:30渋の湯着。本沢温泉から峠まで3時間05分,渋の湯までは5時間50分。


ちょっと温泉へ・・,雪中往復12時間の日帰り入浴やよし!
標高2100mの本沢温泉は本邦最高所温泉とある。昔は白馬鑓温泉が本邦最高所温泉と言われていたが最近はそう言われなくなったし地図にもそうは書いてない。
2.5万図で見ると本沢は2110mの等高線の下,白馬槍はその上に書かれていて白馬鑓の方が高いように見える。ただ野天風呂は2150mと書いてあるので、それを以って最高所としているのかも知れない。
ウイキペディアによると白馬鑓温泉は「以前は『日本最高所の温泉』を名乗っていた時期もあったが、立山のみくりが池温泉や八ヶ岳の本沢温泉などのほうが標高が高く、最近はそのような表示はしていない」とあった。
どちらであろうと大したことではない。※みくりが池温泉は2410m
1月10日(日) 八ヶ岳・渋の湯~本沢温泉往復 参加者2名 記録:木偶野呂馬


前々から本沢温泉に行こう行こうと言いながらなかなか実現しなかったのは、縦走の途中で立ち寄って稲子か松原湖方面に下るのでなければ態々温泉狙いで行ってまた戻ってこなければならないからである。
今回はシーズン最初の足慣らしを兼ねてそれをやろうと言うことになり、天狗岳方面には目もくれずひたすら本沢温泉だけを目指し、また汗をかいて戻ることにした。


中山峠からルートは夏沢峠経由でぐるっと廻るかあるいはその逆かであるが、峠まで来て見ると天狗岳方面の風が強そうなので、あまり深く考えずに行け行けドンドンで峠を越えてみどり池・しらびそ小屋方面に下る。
2人ともそのルートを知らないままに、いきなりの鎖場からほぼ真下に向けて一気に谷底まで下ろされ、さらに急な下りが続くのにびっくりする。200mは下ったかと思う辺りに『中山峠まで40分 みどり池まで40分』と書かれた看板があり、時計を見ると峠から20分かかっていた。その時点では『こんな壁のような急登なんてとても登れたものじゃない~』等と思っていたルートだが、結果的には帰路そこを登る羽目になる。


看板から幾分ゆるくなった道を下る途中で10人あまりのパーティーと数人のパーティー、2人ずれの2組のパーティーを交わし、30分あまりで『みどり池⇔中山峠』の標識を通過,その少し先でみどり池・しらびそ小屋方面と本沢温泉方面の分岐点に到達し、右折して尾根越えの道に入る。中山峠から55分。


道は天狗岳から東に張り出す大きな尾根を越える道で、はじめはほぼ等高線に沿った揺るやかな登りがだらだらと続き、最後にややきつめの登りがあって尾根を乗越す辺りに『本沢温泉へ30分』の標識があり、そこから登った分だけ下るとまもなく稲子小屋方面からの道に合流する。そこで4人のパーティーを追い越して20分弱で本沢温泉に着く。中山峠から2時間17分,渋の湯からは5時間17分。


本館の少し下にある外風呂は本館とは別料金(600円)で男女別になっておらず、混浴もしくは混浴を避けたければ先客優先で空くのを待つ,あるいは待ってもらうと言う仕組みになっている。浴槽が2つあり木の板で覆われているのではじめはかなり熱いが、蓋を取って浸かっているとすぐに丁度いい湯加減になる。蓋を全部取らずに首だけ出していればそれ以上は冷めないのでゆったりと長湯できる。
4~5人は入れるが脱衣場が狭く登山スタイルでの靴や衣類の着脱に手間取るのが難点。野天風呂は登山道を少し登って先の沢にあるが、まったくの野天なので雪の中で入るには脱衣,着衣が大変そう。


しっかり温まり弁当を食べて帰途に就く。予定では夏沢峠から箕冠山,根石岳,東天狗岳と廻ることになるのだが、ナイフリッジで吹雪かれるのは避けたいと言うことで来た道を引き返すことにする。
中山峠直下の登りを考えると気が重いが、お湯に浸かって緩んだ気分での稜線歩きはよろしくないだろう。『逆コースにすればよかった』とjun1さんが悔やむことしきりだが事前研究不足で致し方なし。


中山峠まで3.5時間,渋の湯まで6時間を見込んで11:40に出発。アイゼンをつけたので蹴り足が流れない分だけ歩きやすくなり、みどり池分岐まで1時間半,峠下の看板まで2時間半と順調に来る。途中で女性1名を含む4人の若者のパーティーに先を譲って後を追うも、22~23kgを担いでぐいぐい登って行く若さには追いつきようもなかった。


峠下からの登りでは木の間越しに見えたと思った空が実はその上の雪の壁で、その壁では久々に両手でピッケルを思いっきり打ち込んで体を引き上げる場面もあったが、下った時に思ったほどのしんどさはなく35分で壁を登りきって中山峠に14:45,見込みより30分早く着く。


黒百合ヒュッテ着15:00,気温-9.5℃。朝よりも増えたテントを尻目にすぐに下山。その頃になって日が照り始め、林間がパッと明るくなる。
16:30渋の湯着。本沢温泉から峠まで3時間05分,渋の湯までは5時間50分。


ちょっと温泉へ・・,雪中往復12時間の日帰り入浴やよし!
標高2100mの本沢温泉は本邦最高所温泉とある。昔は白馬鑓温泉が本邦最高所温泉と言われていたが最近はそう言われなくなったし地図にもそうは書いてない。
2.5万図で見ると本沢は2110mの等高線の下,白馬槍はその上に書かれていて白馬鑓の方が高いように見える。ただ野天風呂は2150mと書いてあるので、それを以って最高所としているのかも知れない。
ウイキペディアによると白馬鑓温泉は「以前は『日本最高所の温泉』を名乗っていた時期もあったが、立山のみくりが池温泉や八ヶ岳の本沢温泉などのほうが標高が高く、最近はそのような表示はしていない」とあった。
どちらであろうと大したことではない。※みくりが池温泉は2410m
2010年01月05日
鶏頂山(2010.1.3)
あけおめことよろで初ラッセル
2010年1月3日 栃木県 鶏頂山 記録者 あっちゃん
皆様 明けましておめでとうございます。
年末から年始に掛けての強い冬型の気圧配置により全国各地で大荒れの天気となり
たぶんにもれず栃木の山々も大分白く雪化粧をして朝日に輝いております。
また、今年も待望のラッセルの季節がやってまいりました!
てなわけで、いそいそと鶏頂山へ今年の初ラッセルをしに出かけてきました。
今年は自分達が初登山者のようで
目の前にはまっさらな雪の斜面が広がり
気分は盛り上がります。


♪愉快なラッセル
楽しいラッセル
ラッセル ラッセル♪
途中目印が積雪のため見つからず登山道からはずれ
股下ぐらいのラッセルを交代しながら尾根に向かい
いい汗を流しながら長いアルバイトをしてしまいましたが
なんとか山頂に到着。


曇り勝ちの天気でしたが
山頂付近に差し掛かるころには回復し
素晴らしい景色を堪能して下山しました。
今回は新しい仲間も加わりとても充実した山となりました。
これから、雪山のベストシーズンです。
安全に楽しく山行する為にも日々のトレーニングを怠らずに
励みたいと思います。
さて、次はどこに行こうかな~!!


2010年1月3日 栃木県 鶏頂山 記録者 あっちゃん
皆様 明けましておめでとうございます。
年末から年始に掛けての強い冬型の気圧配置により全国各地で大荒れの天気となり
たぶんにもれず栃木の山々も大分白く雪化粧をして朝日に輝いております。
また、今年も待望のラッセルの季節がやってまいりました!
てなわけで、いそいそと鶏頂山へ今年の初ラッセルをしに出かけてきました。
今年は自分達が初登山者のようで
目の前にはまっさらな雪の斜面が広がり
気分は盛り上がります。


♪愉快なラッセル
楽しいラッセル
ラッセル ラッセル♪
途中目印が積雪のため見つからず登山道からはずれ
股下ぐらいのラッセルを交代しながら尾根に向かい
いい汗を流しながら長いアルバイトをしてしまいましたが
なんとか山頂に到着。


曇り勝ちの天気でしたが
山頂付近に差し掛かるころには回復し
素晴らしい景色を堪能して下山しました。
今回は新しい仲間も加わりとても充実した山となりました。
これから、雪山のベストシーズンです。
安全に楽しく山行する為にも日々のトレーニングを怠らずに
励みたいと思います。
さて、次はどこに行こうかな~!!


タグ :栃木
2010年01月04日
初日の出
みなさま、明けましておめでとうございます。
さて、今年の山遊びは元旦早朝に始まりました。
数日前から元日の天気は良さそうとの予報だったので、子どもたちを焚き付けました。
「(大晦日の晩に)明日は何月何日?」
「一年の最初の日って、何月何日?」
「一年の最初に見る太陽ってスゴクキレイだぞ!」
「その太陽のことを初日の出って言うんだぞ!」
「初日の出に向かって、自分が一番やりたいことをお願いすんだぞ!」
と言いながら、元旦早朝6:00に隊長と副隊長を起こました。事務局長はさすがに無理です(笑)

オイラも20年以上ぶりに行く、地元の山(丘)の初日の出ポイント。
子どもと一緒に行く初の“初日の出”はとってもキレイで、希望に満ちていました。
※年末の寒波のため、藤枝市の低山でも山頂は雪が舞っていました。
さて、今年の山遊びは元旦早朝に始まりました。
数日前から元日の天気は良さそうとの予報だったので、子どもたちを焚き付けました。
「(大晦日の晩に)明日は何月何日?」
「一年の最初の日って、何月何日?」
「一年の最初に見る太陽ってスゴクキレイだぞ!」
「その太陽のことを初日の出って言うんだぞ!」
「初日の出に向かって、自分が一番やりたいことをお願いすんだぞ!」
と言いながら、元旦早朝6:00に隊長と副隊長を起こました。事務局長はさすがに無理です(笑)

オイラも20年以上ぶりに行く、地元の山(丘)の初日の出ポイント。
子どもと一緒に行く初の“初日の出”はとってもキレイで、希望に満ちていました。
※年末の寒波のため、藤枝市の低山でも山頂は雪が舞っていました。
2010年01月04日
石尊山(2010.1.1)
綺麗尽くしの初登山
2010年1月1日 埼玉県小川町 石尊山 記録者 はら坊
昨年より副隊長に習い初日の出登山を始めて今年で二年目になる。
はじめは寒いし暗いし心細いし気が引けたが、一発遣っちまったら病みつきになった。
まぁ~登山と言っても344,2mの山で登山と言えるほどの物では無い。
埼玉の小川町に在る石尊山と言う山である。ここに上がるルートは幾つか在るが、我々はガイドブック通りの菅ノ倉山344mのピ-クを越えて、少し下って再び上がると言うルートである。
暗闇の中ヘッデン頼りでは結構スリリングである。
ここからの初日の出の眺めは中々で、晴れていれば都心のビル街、筑波山、男体山、日光白根山、足尾の山々、赤城に榛名、浅間山と素晴しいパノラマが広がる。今回は、赤城~日光方面は雪雲の中だった。
と簡単に説明はした物の、やはり実際に登って見ないと分からないであろう。
朝5:00時に家を出て5:30登山口に到着、今年は一台の車も止まっていないが、即歩き出す。
初日の出を見るだけならこんな早く歩き出す事もあるまいが、もう一つ早く出ての楽しみが私には有った。それは、夜景。
これがまた綺麗である。息子とよりも・・・と見たい(爆)
そんな洒落た人が居る訳も無く息子と楽しむ。いや息子は楽しんではいない、『何でこんなに早く出るんだよ~。寒いよ~。』と私に愚痴の矢を飛ばしてくる。


漸く東の空が紅く燃え上がってくる。東の赤から濃紺の空何処から替わるか分からないが何とも言えない色の変化である。とても綺麗だ。
西の空に眼を移すと、真丸のお月様が2010年を満面の笑みを浮かべて迎えている、のか2009年を名残惜しんでいるのか・・・これもとても綺麗だ。
そうこうしてる内に辺りが薄明るくなり、一組また一組とあっと言う間に山頂は満員御礼になる、昨年もそうであったが何故か安心する。
お天道様が頭を出すとものの数分で上がり切ってしまう。
その数分の間に今年一年の無事を祈り今年の初日の出登山も無事完結となった。


2010年1月1日 埼玉県小川町 石尊山 記録者 はら坊
昨年より副隊長に習い初日の出登山を始めて今年で二年目になる。
はじめは寒いし暗いし心細いし気が引けたが、一発遣っちまったら病みつきになった。
まぁ~登山と言っても344,2mの山で登山と言えるほどの物では無い。
埼玉の小川町に在る石尊山と言う山である。ここに上がるルートは幾つか在るが、我々はガイドブック通りの菅ノ倉山344mのピ-クを越えて、少し下って再び上がると言うルートである。
暗闇の中ヘッデン頼りでは結構スリリングである。
ここからの初日の出の眺めは中々で、晴れていれば都心のビル街、筑波山、男体山、日光白根山、足尾の山々、赤城に榛名、浅間山と素晴しいパノラマが広がる。今回は、赤城~日光方面は雪雲の中だった。
と簡単に説明はした物の、やはり実際に登って見ないと分からないであろう。
朝5:00時に家を出て5:30登山口に到着、今年は一台の車も止まっていないが、即歩き出す。
初日の出を見るだけならこんな早く歩き出す事もあるまいが、もう一つ早く出ての楽しみが私には有った。それは、夜景。
これがまた綺麗である。息子とよりも・・・と見たい(爆)
そんな洒落た人が居る訳も無く息子と楽しむ。いや息子は楽しんではいない、『何でこんなに早く出るんだよ~。寒いよ~。』と私に愚痴の矢を飛ばしてくる。


漸く東の空が紅く燃え上がってくる。東の赤から濃紺の空何処から替わるか分からないが何とも言えない色の変化である。とても綺麗だ。
西の空に眼を移すと、真丸のお月様が2010年を満面の笑みを浮かべて迎えている、のか2009年を名残惜しんでいるのか・・・これもとても綺麗だ。
そうこうしてる内に辺りが薄明るくなり、一組また一組とあっと言う間に山頂は満員御礼になる、昨年もそうであったが何故か安心する。
お天道様が頭を出すとものの数分で上がり切ってしまう。
その数分の間に今年一年の無事を祈り今年の初日の出登山も無事完結となった。


タグ :埼玉
2010年01月02日
八紘嶺・山伏(2009.12.22~23)
忘年登山(静岡編)その②
2009年12月22日~23日 静岡県と山梨県の県境 八紘嶺・山伏 記録者 あーちゃん
忘年登山、続きです。
12月23日。
7時半過ぎに民宿を出て、近くの登山口に向かいます。
準備をして、登りだしたのが、8時過ぎ。
この日は、扇の要から、日本三大崩れの一つと言われる大谷(おおや)崩を登って、
山伏(やんぶし)に向かいます。

登り始めは、明るい登山道。

こんなに明るいのに、周辺の木や石にコケがあります。
と言うことは、水が多いってことだけど、登山道には水の気配はなし。
近くに小さな川があったけど…
しばらく、緩い傾斜の道を歩いて、扇の要へ。
大谷崩が、扇を広げたような形をしているから、その中心、扇の要。
この辺りを過ぎると、傾斜が段々ときつくなっていきました。

真ん中のくぼんだ所が、新窪乗越。
そこまで、この斜面にあるジグザグの道を進んで行きます。
時々、横からの落石にも注意しつつ、この大きな大谷崩を登っていきました。

登山道右側を見上げる!
この大谷崩は、300年ほど昔にあった地震で崩れて出来たものだそうです。
すごい崩れようだったのでしょうねぇ…
この日も、見事な青空♪
大谷崩を登りきったら、新窪乗越で、ここから、山伏まで尾根移動。
今まで、山の南側を登っていたから、雪も風も少なかったけど、
ここは、北側からの風も吹いてきて、かなり寒い。
そして、雪ががっちり凍っているので、軽アイゼンを付けて登ることにしました。
アイゼンは、その昔…
白馬岳の大雪渓を歩いた時に使って以来…
最初は、その性能が信じられずに、恐る恐る…
そのうち、慣れて、どんどん進んでいきました。
登山道は、雪、雪、雪…
深いところでは50cmくらいありました。
でも、山の南側の日のよく当たる所には、地面が見えていたりと、いろいろです。
でも、全体的には、雪の登山道。

しかし…、雪が積もった後、最初にこの踏み跡をつけた人って…
雪の中、ちゃんと見事に登山道に沿って踏み跡を作っているのだから、
よく知っている人が道を作っているのでしょうか??

雪の中をひたすら歩いて、11時半前に、山伏頂上到着です。

ここからも、美しい富士山が!!!
前日の、八紘嶺に比べてかなり展望がよく、美しい富士山が目の前にその姿を現していました。


この白骨樹と富士山の姿は、よくNHKとかの富士山の映像とかで紹介されるそうです。
同行者さん、『一度、この雪をかぶったここからの富士山が見てみたかった』と言われていました。
何度か登ったことがあるのですが、こんな富士山を見たことがなかったとか…
この日は、頂上に雲が現れたり消えたりしていたので、富士山もかなり風が強いんだろうなって思いました。
でも、相変わらずの見事なその姿!!
絶景です!!!
で、3人で、かわるがわる写真を撮ったり、それぞれ富士山に見入ったり…
素晴らしい光景でした。
思えば、今年、この富士山に登ったんですよね。
夏の出来事なのに、もう随分昔のことのような気がします(^^;
ちなみに、ネットは、ヤナギランを鹿の被害から守るために張ってあるそうです。
ここの頂上は、ヤナギランの群生があるとか…、それも見てみたいなって思いました。
それにしても、どこも鹿の被害、大変そうだな…
さて、富士山を堪能した後、山頂は寒いので、下って食事と言うことになり、
少し食べ物でお腹を満たした後、もと来た道を下ります。

下りの道の途中で。
雪がきらきら♪
その上に、木立の細い影がきれいです♪♪
どんどんと下って行って、13時過ぎに、新窪乗越に到着。
小休止を取って、再び大谷崩を下ります。
下りは、ずるずるとして、歩きにくい。
足元に集中しないといけないのに、ついつい辺りの景色に目を奪われて…
途中で、ずるっとこけちゃいましたσ(^_^;

大谷崩の上のほうを振り返って…

下っていく方の山並み♪
足ががくがくとなりながら、ひたすら下って、14時15分。
最初の登山口に到着です。
車を停めた辺りで、遅い昼食。
暖かいスープを飲んで一息(^^
その後、梅ヶ島温泉の温泉施設の黄金の湯(だったかな?)によって、汗を流してから、
静岡駅まで連れて行ってもらいました。
今回ご一緒したおじさん方と再会を約束して、夕方6時過ぎの新幹線に乗って、広島へ…
2日間の忘年登山はこれで終わりです。
忘年登山の名にふさわしく、いい締めくくりの山行になりました。
新たな山友も出来たし、美しい富士山を2日間とも見れたし♪
やっぱり、2009年も晴れ女だったし(^^v
さて、2010年、どんな一年になるでしょうか??
いっぱい山に登って、いっぱい川に行って、きれいなもの素敵なものを見てみたい♪
で、いっぱいいろんな人に出会いたいって思います。
ということで、
今年も、よろしくお願いします(^^
2009年12月22日~23日 静岡県と山梨県の県境 八紘嶺・山伏 記録者 あーちゃん
忘年登山、続きです。
12月23日。
7時半過ぎに民宿を出て、近くの登山口に向かいます。
準備をして、登りだしたのが、8時過ぎ。
この日は、扇の要から、日本三大崩れの一つと言われる大谷(おおや)崩を登って、
山伏(やんぶし)に向かいます。
登り始めは、明るい登山道。
こんなに明るいのに、周辺の木や石にコケがあります。
と言うことは、水が多いってことだけど、登山道には水の気配はなし。
近くに小さな川があったけど…
しばらく、緩い傾斜の道を歩いて、扇の要へ。
大谷崩が、扇を広げたような形をしているから、その中心、扇の要。
この辺りを過ぎると、傾斜が段々ときつくなっていきました。
真ん中のくぼんだ所が、新窪乗越。
そこまで、この斜面にあるジグザグの道を進んで行きます。
時々、横からの落石にも注意しつつ、この大きな大谷崩を登っていきました。
登山道右側を見上げる!
この大谷崩は、300年ほど昔にあった地震で崩れて出来たものだそうです。
すごい崩れようだったのでしょうねぇ…
この日も、見事な青空♪
大谷崩を登りきったら、新窪乗越で、ここから、山伏まで尾根移動。
今まで、山の南側を登っていたから、雪も風も少なかったけど、
ここは、北側からの風も吹いてきて、かなり寒い。
そして、雪ががっちり凍っているので、軽アイゼンを付けて登ることにしました。
アイゼンは、その昔…
白馬岳の大雪渓を歩いた時に使って以来…
最初は、その性能が信じられずに、恐る恐る…
そのうち、慣れて、どんどん進んでいきました。
登山道は、雪、雪、雪…
深いところでは50cmくらいありました。
でも、山の南側の日のよく当たる所には、地面が見えていたりと、いろいろです。
でも、全体的には、雪の登山道。
しかし…、雪が積もった後、最初にこの踏み跡をつけた人って…
雪の中、ちゃんと見事に登山道に沿って踏み跡を作っているのだから、
よく知っている人が道を作っているのでしょうか??
雪の中をひたすら歩いて、11時半前に、山伏頂上到着です。
ここからも、美しい富士山が!!!
前日の、八紘嶺に比べてかなり展望がよく、美しい富士山が目の前にその姿を現していました。
この白骨樹と富士山の姿は、よくNHKとかの富士山の映像とかで紹介されるそうです。
同行者さん、『一度、この雪をかぶったここからの富士山が見てみたかった』と言われていました。
何度か登ったことがあるのですが、こんな富士山を見たことがなかったとか…
この日は、頂上に雲が現れたり消えたりしていたので、富士山もかなり風が強いんだろうなって思いました。
でも、相変わらずの見事なその姿!!
絶景です!!!
で、3人で、かわるがわる写真を撮ったり、それぞれ富士山に見入ったり…
素晴らしい光景でした。
思えば、今年、この富士山に登ったんですよね。
夏の出来事なのに、もう随分昔のことのような気がします(^^;
ちなみに、ネットは、ヤナギランを鹿の被害から守るために張ってあるそうです。
ここの頂上は、ヤナギランの群生があるとか…、それも見てみたいなって思いました。
それにしても、どこも鹿の被害、大変そうだな…
さて、富士山を堪能した後、山頂は寒いので、下って食事と言うことになり、
少し食べ物でお腹を満たした後、もと来た道を下ります。
下りの道の途中で。
雪がきらきら♪
その上に、木立の細い影がきれいです♪♪
どんどんと下って行って、13時過ぎに、新窪乗越に到着。
小休止を取って、再び大谷崩を下ります。
下りは、ずるずるとして、歩きにくい。
足元に集中しないといけないのに、ついつい辺りの景色に目を奪われて…
途中で、ずるっとこけちゃいましたσ(^_^;
大谷崩の上のほうを振り返って…
下っていく方の山並み♪
足ががくがくとなりながら、ひたすら下って、14時15分。
最初の登山口に到着です。
車を停めた辺りで、遅い昼食。
暖かいスープを飲んで一息(^^
その後、梅ヶ島温泉の温泉施設の黄金の湯(だったかな?)によって、汗を流してから、
静岡駅まで連れて行ってもらいました。
今回ご一緒したおじさん方と再会を約束して、夕方6時過ぎの新幹線に乗って、広島へ…
2日間の忘年登山はこれで終わりです。
忘年登山の名にふさわしく、いい締めくくりの山行になりました。
新たな山友も出来たし、美しい富士山を2日間とも見れたし♪
やっぱり、2009年も晴れ女だったし(^^v
さて、2010年、どんな一年になるでしょうか??
いっぱい山に登って、いっぱい川に行って、きれいなもの素敵なものを見てみたい♪
で、いっぱいいろんな人に出会いたいって思います。
ということで、
今年も、よろしくお願いします(^^
2010年01月01日
男抱山(2010.01.01)
恒例・ご来光
2010年1月1日 栃木県宇都宮市 男抱山 記録者 副隊長
今年で4回目になる新年ご来光登山。
息子佑次郎が3年生の時に「元旦に初日の出を見に行こう!」と計画したものの
年明けの天気が悪く中止となり1年延期となった。当初の登山は古賀志山だった
のだが、考えてみたらかなり込み合いそうな山ではあった。
一年の延期の間に低山ハイキングを繰り返したぺんぎん隊は転んでも只は起きない。
山頂からの展望に東が開けている山、そして手軽に登れる山をちゃんと記憶に残して
いたのである。
念願叶って小学校4年から今年で連続4回目のご来光登山となる男抱山。
ご来光の瞬間は筆舌に尽くし難いものがあり、ここにいくら書いたところで
伝わるものでは無いのだが、登山記には成り得ない超低山ハイキングのこの
山ではご来光を表現するしかないわけで、拙い表現と画像でお伝え致します。(笑)
この山からは遥か東に八溝の山々までズ~ッと平野続き、それ故に眺めが良い。
海無し栃木県としては水平線からの日の出は望むべくも無く、遥か八溝のてっ辺から
顔を覗かすご来光が最上と言っても良い。
さて、朝6時過ぎに登山口に到着したぺんぎん隊、ヘッ電を点けて登山道に進む。
急登に喘ぎながらも空が白みだし八溝の空がオレンジグラデーションに彩られる。
登山口から山頂まで30分行程の山、この時期の日の出時刻は6:52頃であるから
山頂に急いだところで30分近くの待機時間があるのだが、日の出まで刻々と変わる
東の空の模様は飽きる事が無い。


八溝の山々の縁取りがオレンジ色に燃え始める。その中の一か所だけが一層明る
く輝き始め天に向かって後光が射し始めるといよいよご来光だ。
チョンと破れた一点から強烈な光が射したかと思うとズンズンズンズンと休むことなく
太陽が昇り、凡そ1分間の豪華なショーが始まる。
ご来光を拝んだ瞬間に「あれを祈ろう!」「これをお願いしよう!」と考えていた事も
全く忘れて只々その光景に魅了されてしまう。
強烈な光に眩んだ瞳を西へと転じれば霊峰富士の真っ白な姿が目に飛び込んで来る。
「こいつは春から縁起がいいわい!」と喜ぶ親子は純日本人か・・・(笑)


 郊外の低山から我が町越しにご来光を拝む元日の朝
郊外の低山から我が町越しにご来光を拝む元日の朝
この光景が思い出として息子の記憶に残ってくれたら・・・私が初日の出に祈り損ねた
願いもこれで4年目、来年こそは忘れずにお願いしなくちゃね。
2010年1月1日 栃木県宇都宮市 男抱山 記録者 副隊長
今年で4回目になる新年ご来光登山。
息子佑次郎が3年生の時に「元旦に初日の出を見に行こう!」と計画したものの
年明けの天気が悪く中止となり1年延期となった。当初の登山は古賀志山だった
のだが、考えてみたらかなり込み合いそうな山ではあった。
一年の延期の間に低山ハイキングを繰り返したぺんぎん隊は転んでも只は起きない。
山頂からの展望に東が開けている山、そして手軽に登れる山をちゃんと記憶に残して
いたのである。
念願叶って小学校4年から今年で連続4回目のご来光登山となる男抱山。
ご来光の瞬間は筆舌に尽くし難いものがあり、ここにいくら書いたところで
伝わるものでは無いのだが、登山記には成り得ない超低山ハイキングのこの
山ではご来光を表現するしかないわけで、拙い表現と画像でお伝え致します。(笑)
この山からは遥か東に八溝の山々までズ~ッと平野続き、それ故に眺めが良い。
海無し栃木県としては水平線からの日の出は望むべくも無く、遥か八溝のてっ辺から
顔を覗かすご来光が最上と言っても良い。
さて、朝6時過ぎに登山口に到着したぺんぎん隊、ヘッ電を点けて登山道に進む。
急登に喘ぎながらも空が白みだし八溝の空がオレンジグラデーションに彩られる。
登山口から山頂まで30分行程の山、この時期の日の出時刻は6:52頃であるから
山頂に急いだところで30分近くの待機時間があるのだが、日の出まで刻々と変わる
東の空の模様は飽きる事が無い。


八溝の山々の縁取りがオレンジ色に燃え始める。その中の一か所だけが一層明る
く輝き始め天に向かって後光が射し始めるといよいよご来光だ。
チョンと破れた一点から強烈な光が射したかと思うとズンズンズンズンと休むことなく
太陽が昇り、凡そ1分間の豪華なショーが始まる。
ご来光を拝んだ瞬間に「あれを祈ろう!」「これをお願いしよう!」と考えていた事も
全く忘れて只々その光景に魅了されてしまう。
強烈な光に眩んだ瞳を西へと転じれば霊峰富士の真っ白な姿が目に飛び込んで来る。
「こいつは春から縁起がいいわい!」と喜ぶ親子は純日本人か・・・(笑)


 郊外の低山から我が町越しにご来光を拝む元日の朝
郊外の低山から我が町越しにご来光を拝む元日の朝この光景が思い出として息子の記憶に残ってくれたら・・・私が初日の出に祈り損ねた
願いもこれで4年目、来年こそは忘れずにお願いしなくちゃね。
タグ :栃木