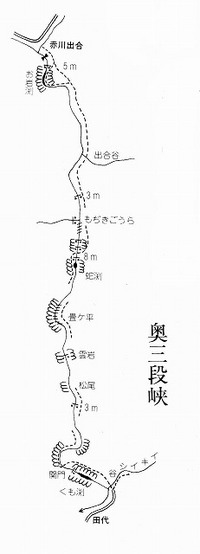2010年10月15日
温泉ケ岳・金精山(2010.10.06)
温泉ケ岳・金精山
2010年10月6日 栃木県奥日光 記録者 副隊長
一人で山に行くのだが、「さて何処にしよう・・・」
宇都宮からでも漸く男体山が見える季節になって来た。ここは一つ、いろは坂でも駆け上がり奥日光の山にでも行こうか・・・。ある程度は自分の希望で休暇日を選べる立場を逆手に紅葉のメッカ「秋の日光の平日」を満喫しようと考えた。
早朝の空いている時刻に龍頭ノ滝や戦場ヶ原を覗き見しながら奥日光湯元方面に向かう。「龍頭はまだ早い・・・」「戦場は綺麗な草紅葉だ・・・」戦場ヶ原から小田代ケ原の散策というお手軽プランに誘惑されるが「いやいや、今日は山なのだ!」とクルマに乗り込む。一人旅は気楽なものだ。奥日光湯元から金精道路へ入る。いくつかのカーブを切って金精トンネル手前の小広い駐車場に滑り込む。今日の起点は此処だ。
金精トンネルからの登山口から金精峠へと登る。この峠を右に進めば金精山を経て日光白根山、左に道をとれば温泉ケ岳を経て奥鬼怒川根名草山へと続く。真っすぐなら群馬県側の菅沼へ・・・三方の道筋がつけられている。今日の私の目的は右、展望豊かな温泉ケ岳への道だ。
 赤い扉に閉ざされた金精神社を背に温泉ケ岳への登山道を進む。ツガの林にウルシやモミジ、ナナカマドが色を添えてくれている。ほとんど茶色だけれど時折赤や黄色が混ざる絨毯を踏みしめる。ここまで来て漸く登山靴にリズムが生まれて来た。
赤い扉に閉ざされた金精神社を背に温泉ケ岳への登山道を進む。ツガの林にウルシやモミジ、ナナカマドが色を添えてくれている。ほとんど茶色だけれど時折赤や黄色が混ざる絨毯を踏みしめる。ここまで来て漸く登山靴にリズムが生まれて来た。
峠に登り切るまで死にそうだった・・・急登の連続に心臓バクバク、怠け過ぎである。認めたくはないものの現実として50を過ぎると落ちぶれるのは早いものである。一回りも若い連中に遊んで貰う身としては勝道上人には遠く及ばずとも自らに修行を課せなければ彼らに着いて行く体力は到底維持出来ない。そう、悲しいかな「維持」が精一杯であって「進歩」は無い・・・。
九十九折れの登山道を歩く。後ろを振り返ると樹林越しに断崖切り立った金精山が聳えている。いつの間にか金精山を越える高さまで登ると次は白根山が顔を出す。東斜面には朝日に霞む男体山や湯ノ湖から戦場ケ原、中禅寺湖が一望出来る、いい歩きだ。
温泉ケ岳山頂への分岐に到着。このまま登山道は温泉ケ岳の中腹をトラバースして根名草山へと続いているので左に道をとり温泉ケ岳山頂へと向かう。笹が被さる道筋にいつの間にかズボンがびしょ濡れになる。
徐々に傾斜を増す笹道を登り詰めると青空が目に飛び込んで来る。周囲にこれ以上高い場所は空だけ・・・私はバカでも煙でも無い、だけど気分は良い。
 温泉ケ岳山頂に到着。
温泉ケ岳山頂に到着。
生憎と雲が張り出して来て期待していた展望は得られなかったが北に念仏小屋から根名草山手前の大きくガレを刻んだ懐かしいピーク(オロオソロシ沢源頭)が見える。東の男体山も
は雲に隠れてしまっているが、手前足元には昨春スノーシューで訪ねた「切り込」「刈り込」の二つの湖が見下ろせる。コーヒーを飲みながら小休止。
9時を20分回り下山開始。
下りながら樹林越しに見えるお向かいの金精山が気になりだした。思ったよりも時間が早い事も手伝ってちょっと色気を出す事にした。
金精峠まで下ると金精神社の脇をすり抜けて意気揚々と真っすぐに金精山への登山道に進む。この際やっつけて帰る。
しかし意気揚々とした気分も5分と持たなかった。登山道は傾斜を増しロープや梯子が出て来た。登って来たのを半ば後悔もしたが、この機会を逃すとまた金精峠までの急登も振り出しになってしまう、峠の上に居るうちに登った方が利口なのだと尻を叩く。色々考えている内に登山道が傾斜を緩め山頂に到着出来た。
展望は更に悪くなっていたがまあ良し。山頂で一人の登山者が美味しそうにタバコを吸っている。思わず「美味しいでしょう!?」と声を掛ける。タバコをやめて久しくなるが、こうした空気の良い場所で吸う一服というのが格別美味しかった記憶が有る。彼が一本吸い終えるのを見届けて下山。途中、峠の神社でご神体を拝んで駐車場まで下った。
私の場合、アフター登山を3~4日間楽しめる。多い時など一週間も楽しませてくれる。今日も寝起きから始まり仕事中も身体を動かす度に今回の登山を思い起こしているのだから良い趣味に恵まれたものである。
2010年10月6日 栃木県奥日光 記録者 副隊長
一人で山に行くのだが、「さて何処にしよう・・・」
宇都宮からでも漸く男体山が見える季節になって来た。ここは一つ、いろは坂でも駆け上がり奥日光の山にでも行こうか・・・。ある程度は自分の希望で休暇日を選べる立場を逆手に紅葉のメッカ「秋の日光の平日」を満喫しようと考えた。
早朝の空いている時刻に龍頭ノ滝や戦場ヶ原を覗き見しながら奥日光湯元方面に向かう。「龍頭はまだ早い・・・」「戦場は綺麗な草紅葉だ・・・」戦場ヶ原から小田代ケ原の散策というお手軽プランに誘惑されるが「いやいや、今日は山なのだ!」とクルマに乗り込む。一人旅は気楽なものだ。奥日光湯元から金精道路へ入る。いくつかのカーブを切って金精トンネル手前の小広い駐車場に滑り込む。今日の起点は此処だ。
金精トンネルからの登山口から金精峠へと登る。この峠を右に進めば金精山を経て日光白根山、左に道をとれば温泉ケ岳を経て奥鬼怒川根名草山へと続く。真っすぐなら群馬県側の菅沼へ・・・三方の道筋がつけられている。今日の私の目的は右、展望豊かな温泉ケ岳への道だ。
 赤い扉に閉ざされた金精神社を背に温泉ケ岳への登山道を進む。ツガの林にウルシやモミジ、ナナカマドが色を添えてくれている。ほとんど茶色だけれど時折赤や黄色が混ざる絨毯を踏みしめる。ここまで来て漸く登山靴にリズムが生まれて来た。
赤い扉に閉ざされた金精神社を背に温泉ケ岳への登山道を進む。ツガの林にウルシやモミジ、ナナカマドが色を添えてくれている。ほとんど茶色だけれど時折赤や黄色が混ざる絨毯を踏みしめる。ここまで来て漸く登山靴にリズムが生まれて来た。峠に登り切るまで死にそうだった・・・急登の連続に心臓バクバク、怠け過ぎである。認めたくはないものの現実として50を過ぎると落ちぶれるのは早いものである。一回りも若い連中に遊んで貰う身としては勝道上人には遠く及ばずとも自らに修行を課せなければ彼らに着いて行く体力は到底維持出来ない。そう、悲しいかな「維持」が精一杯であって「進歩」は無い・・・。
九十九折れの登山道を歩く。後ろを振り返ると樹林越しに断崖切り立った金精山が聳えている。いつの間にか金精山を越える高さまで登ると次は白根山が顔を出す。東斜面には朝日に霞む男体山や湯ノ湖から戦場ケ原、中禅寺湖が一望出来る、いい歩きだ。
温泉ケ岳山頂への分岐に到着。このまま登山道は温泉ケ岳の中腹をトラバースして根名草山へと続いているので左に道をとり温泉ケ岳山頂へと向かう。笹が被さる道筋にいつの間にかズボンがびしょ濡れになる。
徐々に傾斜を増す笹道を登り詰めると青空が目に飛び込んで来る。周囲にこれ以上高い場所は空だけ・・・私はバカでも煙でも無い、だけど気分は良い。
 温泉ケ岳山頂に到着。
温泉ケ岳山頂に到着。生憎と雲が張り出して来て期待していた展望は得られなかったが北に念仏小屋から根名草山手前の大きくガレを刻んだ懐かしいピーク(オロオソロシ沢源頭)が見える。東の男体山も
は雲に隠れてしまっているが、手前足元には昨春スノーシューで訪ねた「切り込」「刈り込」の二つの湖が見下ろせる。コーヒーを飲みながら小休止。
9時を20分回り下山開始。
下りながら樹林越しに見えるお向かいの金精山が気になりだした。思ったよりも時間が早い事も手伝ってちょっと色気を出す事にした。
金精峠まで下ると金精神社の脇をすり抜けて意気揚々と真っすぐに金精山への登山道に進む。この際やっつけて帰る。
しかし意気揚々とした気分も5分と持たなかった。登山道は傾斜を増しロープや梯子が出て来た。登って来たのを半ば後悔もしたが、この機会を逃すとまた金精峠までの急登も振り出しになってしまう、峠の上に居るうちに登った方が利口なのだと尻を叩く。色々考えている内に登山道が傾斜を緩め山頂に到着出来た。
展望は更に悪くなっていたがまあ良し。山頂で一人の登山者が美味しそうにタバコを吸っている。思わず「美味しいでしょう!?」と声を掛ける。タバコをやめて久しくなるが、こうした空気の良い場所で吸う一服というのが格別美味しかった記憶が有る。彼が一本吸い終えるのを見届けて下山。途中、峠の神社でご神体を拝んで駐車場まで下った。
私の場合、アフター登山を3~4日間楽しめる。多い時など一週間も楽しませてくれる。今日も寝起きから始まり仕事中も身体を動かす度に今回の登山を思い起こしているのだから良い趣味に恵まれたものである。
タグ :栃木
2010年09月01日
ミツモチ山
ミツモチ山 2010年8月30日 記録者 副隊長
朝6時に目覚めた私は物ぐさに足で障子を開けて空の様子を窺う。灰色の雲が広がる空を寝ぼけながらも確認して本を読み始めた。
7時になり佑次郎が起き出して学校に行く仕度を始めた。その気配にも目を移す事なく本を読み続けていると階下で朝食を終わらせた佑次郎が寝室に上がって来て「山は?」と声を掛けて来た。「曇ってるし雨も降りそうだから止めた。」と答えると「はあ?晴れてるよ!」と言って笑っている。「そんな筈は・・・」と再度障子を開けてみると確かに青空が見えている。慌てて起き出して朝食をとりながら佑次郎を学校へと送り出す。朝食を済ませて手っ取り早く身支度をしてクルマを乗り出す。
佑次郎に言われて青空を眺めたものの、実際には青空は西の空であって北の空には灰色の雲が湧いていた。正に行こうと思っている方向が曇りであるのは承知でアクセルを踏む。歩くのが目的とも言える今日の登山は雨が降らなければ良しとするまでだ。
 宇都宮を出外れて鬼怒川を渡り矢板へとクルマを進める。矢板市泉の交差点から大間々へと左折して標高を稼ぐ。学校平から更に左折し八方が原を抜け1278mの大間々台駐車場に滑り込む。駐車場にはクルマが二台、さすが平日である。
宇都宮を出外れて鬼怒川を渡り矢板へとクルマを進める。矢板市泉の交差点から大間々へと左折して標高を稼ぐ。学校平から更に左折し八方が原を抜け1278mの大間々台駐車場に滑り込む。駐車場にはクルマが二台、さすが平日である。
手っ取り早く身支度を済ませて登山道を歩き始める。釈迦ケ岳へ向かう登山道を50m程歩くと左に分かれる登山道がある。今回訪ねるミツモチ山(1248m)への分岐だ。帰路は真っすぐこの先の道から帰って来る予定で分岐を左に入る。
ブナやミズナラの森を楽しみながら下る。いくつかの涸れ沢を整備された板橋で渡り順調に下る。
笹原が目立つようになると徐々に登り返して雑木からヤシオツツジの森に出る。「大丸」という標識から直角に曲がり雑木林の明るい登山道をしばらく気分良く進むと三等三角点標石を通過してミツモチ山山頂に辿り着く。
予想した通りに展望は雲に遮られてしまっていたが、久しぶりの山歩きに満足して山頂展望台でひと時を過ごした。友人たちに今の景色をと思い携帯を取り出したが圏外であり思いは果たせず帰路につく。帰路は青空コースと名付けられた砂利道の林道散歩。ほとんど水平移動で小一時間で大間々台に到着し今回の山歩きは終了。



ここまで読んでピンと来た方は多いだろう。下りから始まる登山と水平移動に近い帰路。そう、今回の登山は目的とする山頂よりもクルマを止めた場所の方が標高が高いという不思議な登山。帰路に使った道を往復に使えば殆ど登らずに登山が出来る。(笑)
しかし往路に歩いた登山道の森は良かった。ブナやミズナラの中をのんびり歩くのは気分が良いものだ。あくせく登るばかりが登山ではないと教えてくれた様な気がする。
朝6時に目覚めた私は物ぐさに足で障子を開けて空の様子を窺う。灰色の雲が広がる空を寝ぼけながらも確認して本を読み始めた。
7時になり佑次郎が起き出して学校に行く仕度を始めた。その気配にも目を移す事なく本を読み続けていると階下で朝食を終わらせた佑次郎が寝室に上がって来て「山は?」と声を掛けて来た。「曇ってるし雨も降りそうだから止めた。」と答えると「はあ?晴れてるよ!」と言って笑っている。「そんな筈は・・・」と再度障子を開けてみると確かに青空が見えている。慌てて起き出して朝食をとりながら佑次郎を学校へと送り出す。朝食を済ませて手っ取り早く身支度をしてクルマを乗り出す。
佑次郎に言われて青空を眺めたものの、実際には青空は西の空であって北の空には灰色の雲が湧いていた。正に行こうと思っている方向が曇りであるのは承知でアクセルを踏む。歩くのが目的とも言える今日の登山は雨が降らなければ良しとするまでだ。
手っ取り早く身支度を済ませて登山道を歩き始める。釈迦ケ岳へ向かう登山道を50m程歩くと左に分かれる登山道がある。今回訪ねるミツモチ山(1248m)への分岐だ。帰路は真っすぐこの先の道から帰って来る予定で分岐を左に入る。
ブナやミズナラの森を楽しみながら下る。いくつかの涸れ沢を整備された板橋で渡り順調に下る。
笹原が目立つようになると徐々に登り返して雑木からヤシオツツジの森に出る。「大丸」という標識から直角に曲がり雑木林の明るい登山道をしばらく気分良く進むと三等三角点標石を通過してミツモチ山山頂に辿り着く。
予想した通りに展望は雲に遮られてしまっていたが、久しぶりの山歩きに満足して山頂展望台でひと時を過ごした。友人たちに今の景色をと思い携帯を取り出したが圏外であり思いは果たせず帰路につく。帰路は青空コースと名付けられた砂利道の林道散歩。ほとんど水平移動で小一時間で大間々台に到着し今回の山歩きは終了。
ここまで読んでピンと来た方は多いだろう。下りから始まる登山と水平移動に近い帰路。そう、今回の登山は目的とする山頂よりもクルマを止めた場所の方が標高が高いという不思議な登山。帰路に使った道を往復に使えば殆ど登らずに登山が出来る。(笑)
しかし往路に歩いた登山道の森は良かった。ブナやミズナラの中をのんびり歩くのは気分が良いものだ。あくせく登るばかりが登山ではないと教えてくれた様な気がする。
タグ :栃木
2010年08月07日
男体山登拝祭 2010.7/31~8/1
男体山登拝祭
2010年7月31日~8月1日 栃木県 日光男体山 記録者 やませみ
登拝祭は、1200年の以上の歴史をもつ、奥日光の霊場と言われる二荒山神社中宮祠の最大の祭りで、男体山の神様を称えまつり諸願成就を祈願する祭典です。 毎年8月1日の午前0時に同神社の登拝門が開けられ7日までの期間中は夜間の男体山登山が解禁となり、山頂で御来光を仰ぐことができます。
 今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。
今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。
7月31日(土) 二荒山神社中宮祠に11時20分に到着。 いつもは社務所で受付けを済ませるのだが、今日はお祭りどうやら勝手が違うみたいだ、入口近くに特設のテントが、ここで登拝料1000円(えっ、通常は500円なのに・・・)を奉納、「御守り」と「登拝之証」をいただき境内へ。溢れんばかりの人混み。初めての夜間登山に一同、自然とテンションが上がる。
 8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。
8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。
登拝者は50~60人ほどの集団に分けられ神主さんの御祓いを受け順次、標高2486mの山頂奥に宮を目指す。しばらくして我々の順番、漆黒の山道へと歩き出す。
山道にはもちろん外灯などなく、真っ暗な道をヘッドランプの明かりを頼りに進む。
だが、しばらく山道を進むとそこは大渋滞。普段なら数分で歩ける道も、人また人で進みようがない。
日頃の運動不足がたたっているのか、息も絶え絶えの登拝者がちらほら。
先ほどまでの厳粛なムードも一掃。山中は一年に一度のお祭りに賑わいを見せ始める。
しばらくして人の波も動き始め、ようやく3合目に時計は既に1時25分をまわっていた。ここからアスファルトの林道を歩くことに。道幅が広がったためか先程までの渋滞に痺れをきらした登拝者が一揆に抜き去って行く。4合目に着く。そこにはいくつもの売店があり飲み物や豚汁を買い求める人たちで賑わっていた。美味しそうな食べ物の香りに誘われついつい覗いてしまう。が、見るだけで何も買わない。
この場所には自衛隊の救護班の方々が待機していた。臨時の仮設トイレも設置してあり女性陣は大助かりである。
一息いれて、石造の鳥居をくぐる。ここから道は少しずつ険しさを増してくる。
がしかし、ここも人・人・人で大渋滞。 暗闇の山道にヘッドランプの明かりが延々と何処までも続いているのが見える。ふと空を見上げれば満天の星空。「こんな綺麗な星をみるの久しぶりだなぁ~」と思いながら滑りやすい山道を慎重に登る。いや、立ち止まっている。
7合目を過ぎ、徐々に気温が下がってくるのが分かる。夜明けが近いのか空が少しずつ白み始めてきた。
 「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。
「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。
ほどなくして夜明けを迎える。なんとまだ7.5合目にいる。なんてことだ・・・
ようやく8合目。前を見ると先を行く3人組が視界から消える。ずいぶんと離されてしまった様だ。東の空をよくみると霧に霞む岩陰にぼんやりとした太陽がすでに昇っていた。
この辺りから女性陣2名のペースが極端に遅くなる。きけば久々の山歩きらしく足が思うように上がらないみたいだ。ひとりの女性がよほど辛かったのか、
「私、ここで待ってる・・・」と言い出す始末。
おいおい、「あとすこしだから頑張ろうよ・・・」
「せっかくここまで登ったんだから・・・」
「山頂まで行こうよ・・・」と宥める私。
その後9合目を過ぎて傾斜は緩やかに、岩場から徐々に崩れやすい砂地状の道に変わってくる。
バテバテ気味の彼女。しばらくの間ペースを合わせ一緒に歩いていたが、気を使わせてしまったのかどうかは解からないが「先に行って・・・」の一言が。(もしかして、もう限界か・・・?)
そこから私は滑りやすい斜面を最後の力を振り絞り、よろけながらも山頂に。
先頭の3人が鳥居の横で私らが登ってくるのを待っていてくれた。先に5人で奥の宮に参拝を済ませ彼女が来るのを待つ。遅れること10分全員が揃い5時40分頂上にようやく辿り着く。「あぁ、疲れた~・・・」
 残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」
残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」
大剣でそれぞれに記念撮影を済ませ、空いてる場所に100均で買ったシートを広げ遅い?朝食にする。
くる途中バナナしか口にしていなかったのでお腹ぺこぺこであった。
おにぎり2個とカップラーメンをぺろりと平らげ残っていたバナナをまた頬張る。冷えた体が徐々に温まりだすのが良くわかる。お腹も満たされじっとして居ると猛烈な睡魔が襲ってくる。
登った山は下りなければならない。当たり前のことだが、意外と忘れなれがちなのが登山は下りの方がきつ いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。
いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。
途中、あの有名な1000回おじさんこと、「田名網忠吉」さんとお会いできメンバー全員が快く握手をしていただく。とても85歳とは思えない握力の強さに一同、驚きであった。
たしかこの日が1175回?目の登頂だったと思う・・・
強烈な下り坂は徐々に我々の足、膝を壊し始める。先を行く彼女が「膝がいた~い!」と言う。
歩くたびにどんどん痛くなってくる。それでも下らなければ帰れない。それが登山なのだ。
「あとどくらいですか・・・?」
ん~「あとすこしかなぁ・・・」
「あとすこしって・・・?」
「だからあともうすこし・・・」
「いま何合目あたりですか・・・?」
「3合目あたりかなぁ・・・」
「ほんとは何合目なの・・・?」
「だから、3合目・・・」 (ほんとうは、まだ6合目あたりであった。(笑))
そんな会話をし、互いを励まし合いながらやっとの想いで登拝門をくぐり抜け、無事下山となった。
時計はあと数分で11時ちょうどになろうとしていた。
帰路、疲れた体を「奥日光湯本温泉」の源泉にゆっくりと浸かり前日来の汗と汚れを洗い流し今回の夜通し2日間に及ぶ山遊びも終わりとなった。「ああ~。ほんまにづがれだ~!」
2010年7月31日~8月1日 栃木県 日光男体山 記録者 やませみ
登拝祭は、1200年の以上の歴史をもつ、奥日光の霊場と言われる二荒山神社中宮祠の最大の祭りで、男体山の神様を称えまつり諸願成就を祈願する祭典です。 毎年8月1日の午前0時に同神社の登拝門が開けられ7日までの期間中は夜間の男体山登山が解禁となり、山頂で御来光を仰ぐことができます。
 今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。
今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。 7月31日(土) 二荒山神社中宮祠に11時20分に到着。 いつもは社務所で受付けを済ませるのだが、今日はお祭りどうやら勝手が違うみたいだ、入口近くに特設のテントが、ここで登拝料1000円(えっ、通常は500円なのに・・・)を奉納、「御守り」と「登拝之証」をいただき境内へ。溢れんばかりの人混み。初めての夜間登山に一同、自然とテンションが上がる。
 8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。
8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。登拝者は50~60人ほどの集団に分けられ神主さんの御祓いを受け順次、標高2486mの山頂奥に宮を目指す。しばらくして我々の順番、漆黒の山道へと歩き出す。
山道にはもちろん外灯などなく、真っ暗な道をヘッドランプの明かりを頼りに進む。
だが、しばらく山道を進むとそこは大渋滞。普段なら数分で歩ける道も、人また人で進みようがない。
日頃の運動不足がたたっているのか、息も絶え絶えの登拝者がちらほら。
先ほどまでの厳粛なムードも一掃。山中は一年に一度のお祭りに賑わいを見せ始める。
しばらくして人の波も動き始め、ようやく3合目に時計は既に1時25分をまわっていた。ここからアスファルトの林道を歩くことに。道幅が広がったためか先程までの渋滞に痺れをきらした登拝者が一揆に抜き去って行く。4合目に着く。そこにはいくつもの売店があり飲み物や豚汁を買い求める人たちで賑わっていた。美味しそうな食べ物の香りに誘われついつい覗いてしまう。が、見るだけで何も買わない。
この場所には自衛隊の救護班の方々が待機していた。臨時の仮設トイレも設置してあり女性陣は大助かりである。
一息いれて、石造の鳥居をくぐる。ここから道は少しずつ険しさを増してくる。
がしかし、ここも人・人・人で大渋滞。 暗闇の山道にヘッドランプの明かりが延々と何処までも続いているのが見える。ふと空を見上げれば満天の星空。「こんな綺麗な星をみるの久しぶりだなぁ~」と思いながら滑りやすい山道を慎重に登る。いや、立ち止まっている。
7合目を過ぎ、徐々に気温が下がってくるのが分かる。夜明けが近いのか空が少しずつ白み始めてきた。
 「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。
「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。ほどなくして夜明けを迎える。なんとまだ7.5合目にいる。なんてことだ・・・
ようやく8合目。前を見ると先を行く3人組が視界から消える。ずいぶんと離されてしまった様だ。東の空をよくみると霧に霞む岩陰にぼんやりとした太陽がすでに昇っていた。
この辺りから女性陣2名のペースが極端に遅くなる。きけば久々の山歩きらしく足が思うように上がらないみたいだ。ひとりの女性がよほど辛かったのか、
「私、ここで待ってる・・・」と言い出す始末。
おいおい、「あとすこしだから頑張ろうよ・・・」
「せっかくここまで登ったんだから・・・」
「山頂まで行こうよ・・・」と宥める私。
その後9合目を過ぎて傾斜は緩やかに、岩場から徐々に崩れやすい砂地状の道に変わってくる。
バテバテ気味の彼女。しばらくの間ペースを合わせ一緒に歩いていたが、気を使わせてしまったのかどうかは解からないが「先に行って・・・」の一言が。(もしかして、もう限界か・・・?)
そこから私は滑りやすい斜面を最後の力を振り絞り、よろけながらも山頂に。
先頭の3人が鳥居の横で私らが登ってくるのを待っていてくれた。先に5人で奥の宮に参拝を済ませ彼女が来るのを待つ。遅れること10分全員が揃い5時40分頂上にようやく辿り着く。「あぁ、疲れた~・・・」
 残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」
残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」大剣でそれぞれに記念撮影を済ませ、空いてる場所に100均で買ったシートを広げ遅い?朝食にする。
くる途中バナナしか口にしていなかったのでお腹ぺこぺこであった。
おにぎり2個とカップラーメンをぺろりと平らげ残っていたバナナをまた頬張る。冷えた体が徐々に温まりだすのが良くわかる。お腹も満たされじっとして居ると猛烈な睡魔が襲ってくる。
登った山は下りなければならない。当たり前のことだが、意外と忘れなれがちなのが登山は下りの方がきつ
 いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。
いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。途中、あの有名な1000回おじさんこと、「田名網忠吉」さんとお会いできメンバー全員が快く握手をしていただく。とても85歳とは思えない握力の強さに一同、驚きであった。
たしかこの日が1175回?目の登頂だったと思う・・・
強烈な下り坂は徐々に我々の足、膝を壊し始める。先を行く彼女が「膝がいた~い!」と言う。
歩くたびにどんどん痛くなってくる。それでも下らなければ帰れない。それが登山なのだ。
「あとどくらいですか・・・?」
ん~「あとすこしかなぁ・・・」
「あとすこしって・・・?」
「だからあともうすこし・・・」
「いま何合目あたりですか・・・?」
「3合目あたりかなぁ・・・」
「ほんとは何合目なの・・・?」
「だから、3合目・・・」 (ほんとうは、まだ6合目あたりであった。(笑))
そんな会話をし、互いを励まし合いながらやっとの想いで登拝門をくぐり抜け、無事下山となった。
時計はあと数分で11時ちょうどになろうとしていた。
帰路、疲れた体を「奥日光湯本温泉」の源泉にゆっくりと浸かり前日来の汗と汚れを洗い流し今回の夜通し2日間に及ぶ山遊びも終わりとなった。「ああ~。ほんまにづがれだ~!」
タグ :栃木
2010年06月11日
日光社山(2010.6.6)
新緑の社山
2010年6月6日 栃木県日光 社山1827m 記録者 やませみ
そろそろ梅雨入りの気配。そんな6月の初め先々週に続き今回もまた急遽日曜日がお休みに。
正直、このところの不定期な休みは何の予定も立たず困っているのが本音であった。とは言っても今の私にとっては貴重な休みなのである。明日の天気予報はどうやら晴れらしい。となれば家に居るのは勿体無い話。
この時点で頭の中は「晴れ=山遊び」の答えしか無かった。
だからと言って特に行き先にあてがある訳ではなかった。早速行き先を探し始めた。日光近郊のマップを広げ「何処がいかんべ・・・?」などと、つぶやきながら見入っているとシャグナゲの文字が目に止まる。
「あぁ~そうか、もしかしたら満開のアズマシャクナゲ見られっかなぁ・・・。」と思い「社山」に登って見ることにした。
5時起床。外は予報通り晴れ、いや快晴である。否応なしに高ぶるテンションを抑えながらの準備、6時10分に自宅を出る。R119を日光に向け快適に車を走らせる。ところが徳次郎の交差点の少し手前でレインウェアを乗せ忘れたのに気付き車を止める、代わりになるジャケットも忘れてる。慌ててUターンすることに、自宅に戻り忘れ物をのせ仕切り直しとなる。こんな時ひとりは結構お気楽なものである。
いろは坂の上り口へ差し掛かる、見るからに普段より車が多い。「あれかなぁ~、きっとこの車列も梅雨入り前の晴天に誘われて出かけてきたのかな・・・?」ふと、そんなこと考えながら九十九折の道を中禅寺湖畔へとのんびり車を走らせる。
歌ヶ浜駐車場に8時に到着。奥の駐車場には大型・中型バスが7~8台、手前の小型車スペースもほとんど満車の状態、空いてる場所を見つけどうにか車を止めた。
 清々しい空気のなか身支度を済ませ中禅寺湖畔沿いの道を阿世潟方面に歩き出す。朝の中禅寺湖、周りの山々が湖面に映りこんで静かなたたずまいを見せている。
清々しい空気のなか身支度を済ませ中禅寺湖畔沿いの道を阿世潟方面に歩き出す。朝の中禅寺湖、周りの山々が湖面に映りこんで静かなたたずまいを見せている。
滅多にお目に掛かれないシルエット、先を急ぐ訳でもないのでしばらくこの風景を味わうことにする。岸辺には大勢の釣り人の姿が、釣りもする私はロッドが弧を描いていないか気になって、気になって右だけを見ながらの歩行となり足元が少し覚束無い。(これも釣屋の宿命なのでしょうか・・・。)
程なくしてイタリア大使館別荘記念館公園前に帰りに寄ることにし先に進む。この辺りから暫らくは萌える様な新緑の樹林層 が美しい森の中、初夏を告げる「エゾハルゼミ」の大合唱をBGMに快適な歩行が続く。これだけでも「今日はほんと来て良かったなぁ」と思える自分がいる瞬間でもあった。心地よい森林浴を楽しみながら進むと阿世潟峠の入り口に着く。
が美しい森の中、初夏を告げる「エゾハルゼミ」の大合唱をBGMに快適な歩行が続く。これだけでも「今日はほんと来て良かったなぁ」と思える自分がいる瞬間でもあった。心地よい森林浴を楽しみながら進むと阿世潟峠の入り口に着く。
ここからはダケカンバの森の中を緩やかに登って行く。10分ほどで峠の分岐に達し右折して社山方面へ、ちょうど身頃の山ツツジが迎えてくれる。
 小笹の尾根道を上って行くとやがて樹林帯の急登が始まり山道は小刻みにジグザグと登って行く。高度が上がるにつれ、どんどん見晴らしも良くなってくる。樹林帯を抜け無人の雨量観測所の横を過ぎると山道一眺望が利くピークへ。右手に男体山、大真名子山、小真名子山、太郎山、前方には奥白根山また眼下には中禅寺湖に竜頭の滝とほぼ360度が一望できる場所でもある。痩せ尾根には満開のシロヤシオが標高が上がってきたせいかこの辺りのツツジはまだ蕾である。
小笹の尾根道を上って行くとやがて樹林帯の急登が始まり山道は小刻みにジグザグと登って行く。高度が上がるにつれ、どんどん見晴らしも良くなってくる。樹林帯を抜け無人の雨量観測所の横を過ぎると山道一眺望が利くピークへ。右手に男体山、大真名子山、小真名子山、太郎山、前方には奥白根山また眼下には中禅寺湖に竜頭の滝とほぼ360度が一望できる場所でもある。痩せ尾根には満開のシロヤシオが標高が上がってきたせいかこの辺りのツツジはまだ蕾である。
この後見晴らしの良い急勾配の尾根道を一気に駆け上がり(ちょっと大袈裟?でも本人はそのつもりです。)山頂に着く。山頂には5~6人のパーティーが食事中であった。そのままその場を通り過ぎその先の展望の良い斜面へと足を伸ばすことに。そこにはアズマシャクナゲの群生地がある。早々ザックを放り投げ(いいえ、そ~っと置いて。)日光側の斜面へとあわよくば「満開!満開!・・・??」 その期待も虚しく3分咲きって感~じ・・・今年はまだ少し早かった様であった。やはり春先の寒さの影響なのだろうか?
 少し時間が早いのだがお昼にすることにした。周りを見渡すとこの場所、展望よ~し、座り心地よ~しで30人いや40人近い方が休んでいた。松木渓谷が正面に見えるお気に入りの席に陣取ります。私が渓流釣りを始めた18歳の頃、松木、久蔵沢によく足を運んだものだ、きっとその思い出が自然と自分をこの席に導くのかも知れません。今、こうして見下ろしているほとんどの斜面は嘗ての足尾の煙害によって木々が立ち枯れ無残な姿を未だに残している。ただ山肌を笹だけが覆う異様な風景に不気味ささえ感じるのは自分だけなのだろうか。
少し時間が早いのだがお昼にすることにした。周りを見渡すとこの場所、展望よ~し、座り心地よ~しで30人いや40人近い方が休んでいた。松木渓谷が正面に見えるお気に入りの席に陣取ります。私が渓流釣りを始めた18歳の頃、松木、久蔵沢によく足を運んだものだ、きっとその思い出が自然と自分をこの席に導くのかも知れません。今、こうして見下ろしているほとんどの斜面は嘗ての足尾の煙害によって木々が立ち枯れ無残な姿を未だに残している。ただ山肌を笹だけが覆う異様な風景に不気味ささえ感じるのは自分だけなのだろうか。
 あまりの天気の良さと程よい暖かさが否が応に眠気を誘う。お腹も心も満たされ来た道を戻ることにする。しかし腰を上げるのが少々遅かった様である。休憩してた場所の人混みのなかに20人弱のパーティーが居たのをすっかり忘れてしまい先に行かれてしまったのです。もうこうなると急で狭い登山道、その団体を抜くに抜けず恰もパーティーの最後尾を金魚の糞のごとく下りる嵌めに。でもこれが女性の後ろ姿を眺めながらの下山となり結構楽しかったりもする。(笑)下り始めて間もなく今度は上りの団体が次から次に、そのうちの一行は見た目50人は居る感じだ、遥か下の方までその列が繋がっている。「ありゃ~、こりゃ~もうダメだは~・・・。」山道は一方通行状態です。まるでGWの高速道路のよう大渋滞でさっきから止まったまま全然動きましぇん。(泣)あとは流れに任せるがままであった。
あまりの天気の良さと程よい暖かさが否が応に眠気を誘う。お腹も心も満たされ来た道を戻ることにする。しかし腰を上げるのが少々遅かった様である。休憩してた場所の人混みのなかに20人弱のパーティーが居たのをすっかり忘れてしまい先に行かれてしまったのです。もうこうなると急で狭い登山道、その団体を抜くに抜けず恰もパーティーの最後尾を金魚の糞のごとく下りる嵌めに。でもこれが女性の後ろ姿を眺めながらの下山となり結構楽しかったりもする。(笑)下り始めて間もなく今度は上りの団体が次から次に、そのうちの一行は見た目50人は居る感じだ、遥か下の方までその列が繋がっている。「ありゃ~、こりゃ~もうダメだは~・・・。」山道は一方通行状態です。まるでGWの高速道路のよう大渋滞でさっきから止まったまま全然動きましぇん。(泣)あとは流れに任せるがままであった。
今回、下りだけでも100人超えの登山者とすれ違い「社山」の人気の高さに改めて驚きました。渋滞が解消しようやく阿世潟峠の分岐に辿り着く。時計を見ると思いのほか時間が早かったので往路には戻らず「半月峠」回りで帰ることにする。上り始めて間もなく初老のカップルにお会いする。そのときの会話
「こんにちは、良いお天気ですね~。」
「ほんと、そうですね。 おひとりなんですか・・・?」
「はい、そうですよ。」
すると男性の方が私が向かう方を指差し
「あの辺りでさっき熊出たそうだから気を付けたのがいいよ。」
「え~、熊でだんすか・・・遭いたくねえな~」
話をよく聞くと私の直前を行く方が5、6分前に昼食をしてる時に目撃したらしいのです。「ご心配ありがとうございます。」
お礼を言ってその場を立ち去ることに、こんな時単独行は心細いものである。少し緊張の面持ちのまま熊さんに遭わないことを願いつつ、いつもより足早に歩く自分であった。気が付けばいつの間にか湖畔沿いの「狸窪」まで下りこれで一安心である。
帰り道、イタリア大使館別荘記念館をゆっくり見学し歌ヶ浜駐車場に3時に到着、怪我も無く熊にも遭わず今日の登山の終わりとなる。仕事を離れこの雄大で豊かな自然の中でこんなに楽しい時間を過ごせた私はきっと幸せ者であるに違いない。次は秋の紅葉の時期にでもまた訪れて見ようと思う。帰路、霧降にある入浴料、大人400円の天然温泉で今日の疲れを洗い流し今回の山遊びも終わりとなった。
2010年6月6日 栃木県日光 社山1827m 記録者 やませみ
そろそろ梅雨入りの気配。そんな6月の初め先々週に続き今回もまた急遽日曜日がお休みに。
正直、このところの不定期な休みは何の予定も立たず困っているのが本音であった。とは言っても今の私にとっては貴重な休みなのである。明日の天気予報はどうやら晴れらしい。となれば家に居るのは勿体無い話。
この時点で頭の中は「晴れ=山遊び」の答えしか無かった。
だからと言って特に行き先にあてがある訳ではなかった。早速行き先を探し始めた。日光近郊のマップを広げ「何処がいかんべ・・・?」などと、つぶやきながら見入っているとシャグナゲの文字が目に止まる。
「あぁ~そうか、もしかしたら満開のアズマシャクナゲ見られっかなぁ・・・。」と思い「社山」に登って見ることにした。
5時起床。外は予報通り晴れ、いや快晴である。否応なしに高ぶるテンションを抑えながらの準備、6時10分に自宅を出る。R119を日光に向け快適に車を走らせる。ところが徳次郎の交差点の少し手前でレインウェアを乗せ忘れたのに気付き車を止める、代わりになるジャケットも忘れてる。慌ててUターンすることに、自宅に戻り忘れ物をのせ仕切り直しとなる。こんな時ひとりは結構お気楽なものである。
いろは坂の上り口へ差し掛かる、見るからに普段より車が多い。「あれかなぁ~、きっとこの車列も梅雨入り前の晴天に誘われて出かけてきたのかな・・・?」ふと、そんなこと考えながら九十九折の道を中禅寺湖畔へとのんびり車を走らせる。
歌ヶ浜駐車場に8時に到着。奥の駐車場には大型・中型バスが7~8台、手前の小型車スペースもほとんど満車の状態、空いてる場所を見つけどうにか車を止めた。
 清々しい空気のなか身支度を済ませ中禅寺湖畔沿いの道を阿世潟方面に歩き出す。朝の中禅寺湖、周りの山々が湖面に映りこんで静かなたたずまいを見せている。
清々しい空気のなか身支度を済ませ中禅寺湖畔沿いの道を阿世潟方面に歩き出す。朝の中禅寺湖、周りの山々が湖面に映りこんで静かなたたずまいを見せている。滅多にお目に掛かれないシルエット、先を急ぐ訳でもないのでしばらくこの風景を味わうことにする。岸辺には大勢の釣り人の姿が、釣りもする私はロッドが弧を描いていないか気になって、気になって右だけを見ながらの歩行となり足元が少し覚束無い。(これも釣屋の宿命なのでしょうか・・・。)
程なくしてイタリア大使館別荘記念館公園前に帰りに寄ることにし先に進む。この辺りから暫らくは萌える様な新緑の樹林層
 が美しい森の中、初夏を告げる「エゾハルゼミ」の大合唱をBGMに快適な歩行が続く。これだけでも「今日はほんと来て良かったなぁ」と思える自分がいる瞬間でもあった。心地よい森林浴を楽しみながら進むと阿世潟峠の入り口に着く。
が美しい森の中、初夏を告げる「エゾハルゼミ」の大合唱をBGMに快適な歩行が続く。これだけでも「今日はほんと来て良かったなぁ」と思える自分がいる瞬間でもあった。心地よい森林浴を楽しみながら進むと阿世潟峠の入り口に着く。ここからはダケカンバの森の中を緩やかに登って行く。10分ほどで峠の分岐に達し右折して社山方面へ、ちょうど身頃の山ツツジが迎えてくれる。
 小笹の尾根道を上って行くとやがて樹林帯の急登が始まり山道は小刻みにジグザグと登って行く。高度が上がるにつれ、どんどん見晴らしも良くなってくる。樹林帯を抜け無人の雨量観測所の横を過ぎると山道一眺望が利くピークへ。右手に男体山、大真名子山、小真名子山、太郎山、前方には奥白根山また眼下には中禅寺湖に竜頭の滝とほぼ360度が一望できる場所でもある。痩せ尾根には満開のシロヤシオが標高が上がってきたせいかこの辺りのツツジはまだ蕾である。
小笹の尾根道を上って行くとやがて樹林帯の急登が始まり山道は小刻みにジグザグと登って行く。高度が上がるにつれ、どんどん見晴らしも良くなってくる。樹林帯を抜け無人の雨量観測所の横を過ぎると山道一眺望が利くピークへ。右手に男体山、大真名子山、小真名子山、太郎山、前方には奥白根山また眼下には中禅寺湖に竜頭の滝とほぼ360度が一望できる場所でもある。痩せ尾根には満開のシロヤシオが標高が上がってきたせいかこの辺りのツツジはまだ蕾である。この後見晴らしの良い急勾配の尾根道を一気に駆け上がり(ちょっと大袈裟?でも本人はそのつもりです。)山頂に着く。山頂には5~6人のパーティーが食事中であった。そのままその場を通り過ぎその先の展望の良い斜面へと足を伸ばすことに。そこにはアズマシャクナゲの群生地がある。早々ザックを放り投げ(いいえ、そ~っと置いて。)日光側の斜面へとあわよくば「満開!満開!・・・??」 その期待も虚しく3分咲きって感~じ・・・今年はまだ少し早かった様であった。やはり春先の寒さの影響なのだろうか?
 少し時間が早いのだがお昼にすることにした。周りを見渡すとこの場所、展望よ~し、座り心地よ~しで30人いや40人近い方が休んでいた。松木渓谷が正面に見えるお気に入りの席に陣取ります。私が渓流釣りを始めた18歳の頃、松木、久蔵沢によく足を運んだものだ、きっとその思い出が自然と自分をこの席に導くのかも知れません。今、こうして見下ろしているほとんどの斜面は嘗ての足尾の煙害によって木々が立ち枯れ無残な姿を未だに残している。ただ山肌を笹だけが覆う異様な風景に不気味ささえ感じるのは自分だけなのだろうか。
少し時間が早いのだがお昼にすることにした。周りを見渡すとこの場所、展望よ~し、座り心地よ~しで30人いや40人近い方が休んでいた。松木渓谷が正面に見えるお気に入りの席に陣取ります。私が渓流釣りを始めた18歳の頃、松木、久蔵沢によく足を運んだものだ、きっとその思い出が自然と自分をこの席に導くのかも知れません。今、こうして見下ろしているほとんどの斜面は嘗ての足尾の煙害によって木々が立ち枯れ無残な姿を未だに残している。ただ山肌を笹だけが覆う異様な風景に不気味ささえ感じるのは自分だけなのだろうか。 あまりの天気の良さと程よい暖かさが否が応に眠気を誘う。お腹も心も満たされ来た道を戻ることにする。しかし腰を上げるのが少々遅かった様である。休憩してた場所の人混みのなかに20人弱のパーティーが居たのをすっかり忘れてしまい先に行かれてしまったのです。もうこうなると急で狭い登山道、その団体を抜くに抜けず恰もパーティーの最後尾を金魚の糞のごとく下りる嵌めに。でもこれが女性の後ろ姿を眺めながらの下山となり結構楽しかったりもする。(笑)下り始めて間もなく今度は上りの団体が次から次に、そのうちの一行は見た目50人は居る感じだ、遥か下の方までその列が繋がっている。「ありゃ~、こりゃ~もうダメだは~・・・。」山道は一方通行状態です。まるでGWの高速道路のよう大渋滞でさっきから止まったまま全然動きましぇん。(泣)あとは流れに任せるがままであった。
あまりの天気の良さと程よい暖かさが否が応に眠気を誘う。お腹も心も満たされ来た道を戻ることにする。しかし腰を上げるのが少々遅かった様である。休憩してた場所の人混みのなかに20人弱のパーティーが居たのをすっかり忘れてしまい先に行かれてしまったのです。もうこうなると急で狭い登山道、その団体を抜くに抜けず恰もパーティーの最後尾を金魚の糞のごとく下りる嵌めに。でもこれが女性の後ろ姿を眺めながらの下山となり結構楽しかったりもする。(笑)下り始めて間もなく今度は上りの団体が次から次に、そのうちの一行は見た目50人は居る感じだ、遥か下の方までその列が繋がっている。「ありゃ~、こりゃ~もうダメだは~・・・。」山道は一方通行状態です。まるでGWの高速道路のよう大渋滞でさっきから止まったまま全然動きましぇん。(泣)あとは流れに任せるがままであった。今回、下りだけでも100人超えの登山者とすれ違い「社山」の人気の高さに改めて驚きました。渋滞が解消しようやく阿世潟峠の分岐に辿り着く。時計を見ると思いのほか時間が早かったので往路には戻らず「半月峠」回りで帰ることにする。上り始めて間もなく初老のカップルにお会いする。そのときの会話
「こんにちは、良いお天気ですね~。」
「ほんと、そうですね。 おひとりなんですか・・・?」
「はい、そうですよ。」
すると男性の方が私が向かう方を指差し
「あの辺りでさっき熊出たそうだから気を付けたのがいいよ。」
「え~、熊でだんすか・・・遭いたくねえな~」
話をよく聞くと私の直前を行く方が5、6分前に昼食をしてる時に目撃したらしいのです。「ご心配ありがとうございます。」
お礼を言ってその場を立ち去ることに、こんな時単独行は心細いものである。少し緊張の面持ちのまま熊さんに遭わないことを願いつつ、いつもより足早に歩く自分であった。気が付けばいつの間にか湖畔沿いの「狸窪」まで下りこれで一安心である。
帰り道、イタリア大使館別荘記念館をゆっくり見学し歌ヶ浜駐車場に3時に到着、怪我も無く熊にも遭わず今日の登山の終わりとなる。仕事を離れこの雄大で豊かな自然の中でこんなに楽しい時間を過ごせた私はきっと幸せ者であるに違いない。次は秋の紅葉の時期にでもまた訪れて見ようと思う。帰路、霧降にある入浴料、大人400円の天然温泉で今日の疲れを洗い流し今回の山遊びも終わりとなった。
タグ :栃木
2010年06月03日
石裂山(2010.06.01)
石裂山
2010年6月1日 栃木県 石裂山 記録者 副隊長
サラリーマンにとって休日は貴重な一日だとつくづく思う。少し前までは半自営業的な生活だったので自由な時間は自分で作り出せたが、サラリーマンともなると無駄な時間でさえ賃金で拘束され自由が利かない身となるのを10数年ぶりに体感している。
そんな身であるが数年来の山渓遊びを通じて休日の配分にも結構利口になった私である。身体を休める休日と心を休める休日を上手く使い分ける事が出来るようになったのも趣味と言う範疇ではあるけれど自然と触れ合う楽しさを教えて貰えた貴重な体験の積み重ねがあったからこそである。
朝、目を覚ますとまだ隣で佑次郎が寝息を立てている。今日は火曜日、平日の朝だから佑次郎は起き出すと共にそそくさと中学校へと行ってしまう。布団の中から佑次郎を送り出した後しばらく本を読んでいた私だがトイレに立った際に自室に差し込む明るい陽射しが妙に心を捉えて落ち着かなくなった。
「う~ん、今日は天気が良いんだなぁ、山でも歩いて来ようかなぁ・・・。」
こんな考えが浮かんだ途端にもう壁に掛かっていたザックを引き下ろしていた。
 特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。
特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。
荒井川沿いの道を登山口に続く林道を探しながら走ったが、何処をどうしたものか登山口が見つからないままに加蘇山神社の社務所前まで来てしまった。加蘇山神社と言えば石裂山(おざくさん)の登山口に当たる場所である。「これも何かの縁か・・・」と急きょ石裂山登山に切り替える事にした。
社務所に在る石裂山回遊コース案内を眺めると大体4時間くらいの様子だ。現在9:30であるから13:30下山でも14:00過ぎには帰宅出来る目算である。
荒井川源流部に当たる沢沿いの登山道を軽い気分で歩き出す。沢音を聞きながらの登山は釣り屋の私にとって何よりも快適である。あちらこちらに「禁漁区」と赤字で書かれた札を目にするが沢の流れを覗き込んでみても一向に魚影は無い。登山道が横を走る里川の延長でしかない川だから最初から期待はしていないが、ついつい魚影を求めては儚い夢を追いかけてしまう。あざ笑う様に大きなヒキガエルが泳いでいるのが見えて苦笑してしまう。
 周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。
周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。
東屋がある中ノ宮に登り付く。「奥の宮・東剣ノ峰」の標識の先の岩場に長い鎖が下ろされているのが見える。
「そう言えば石裂山は鎖場と梯子の山だった・・・」
 気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。
気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。
この鎖場、「行者返しの岩場」と呼ばれている。私は行者では無いので帰らずに済んだ。でも雨後や雨天時なら無理は禁物と思わされる岩場である。登ってしまったら降りるのに首を傾げる程度の岩場と表現しておく。
さらに脇道にステンレス製の階段が伸びる「奥の宮」を参拝してから登山道に戻り尾根に取り付く。岩場を木の根を掴みながら登る。「一部にはハイキングコースと案内されていますが、ここは登山道です。」と書かれていた案内板の注意文を思い浮かべる。
鎖場・階段を越え「東剣ノ峰」に到着。樹木に遮られて大した展望も無い。「西剣ノ峰」へと進む鞍部に下る。これが長いステンレス製の階段の下り。何の気なしに降り始めたが、その長さに途中で「そう言えば俺って高所恐怖症じゃなかった?!」と気が付いてそれからの長かった事・・・。
鞍部に辿り着くもすぐに西剣ノ峰への登り返し。九十九折れの急登と途中で振り返ると、東剣ノ峰から下る崖に取り付けられた階段が見える。「あんなとこ降りて来たの・・・?!」と改めて驚く。
西剣ノ峰に登り付くと生い茂る樹木の間から鋭い岩肌を見せる石裂山が目の前に見える。正直「あそこに登るの・・・?」と思ったものだが、実際に登ってみるともう核心部は越えていた様で呆気ない思いで山頂に立つ。
山頂から見える展望は地理不案内にてコメント無し。(笑)
 本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。
本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。
月山からの下りも時折鎖場や梯子を介して結構急な下りで一気に標高を下げて来る。スギ林に入る頃には次第に沢音も大きくなって来る。「音はすれども水が見えないなぁ・・・。」と思っていたら突然岩の間から水が流れ出して沢を作り始める。伏流水が顔を出した瞬間である。この流れも荒井川の源流域の一筋となっていくわけである。
もう充分に沢と呼べる流れを渡ると登路と合流して周回を終える。ここからは往路を逆に辿るだけである。緊張の中にも心を癒された一人旅が無事に終わった。
 釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。
釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。
家に帰り御帰還ビールで一杯やっていると佑次郎が帰って来た。「今日ねぇ、山に行って来たんだ。」こう話し掛けると「何処の?」と御愛想が返って来た。それでも山の様子を写真を見せながら詳しく話してやる。「お父さんが“山に行った”って聞くとお前も行きたくなるだろ?」こう問い掛けた私にニヤリと笑いを返して来る。満更でもない表情に安心しながら残りのビールを美味しく飲んだ。「佑、今度は一緒に行こうな・・・」
2010年6月1日 栃木県 石裂山 記録者 副隊長
サラリーマンにとって休日は貴重な一日だとつくづく思う。少し前までは半自営業的な生活だったので自由な時間は自分で作り出せたが、サラリーマンともなると無駄な時間でさえ賃金で拘束され自由が利かない身となるのを10数年ぶりに体感している。
そんな身であるが数年来の山渓遊びを通じて休日の配分にも結構利口になった私である。身体を休める休日と心を休める休日を上手く使い分ける事が出来るようになったのも趣味と言う範疇ではあるけれど自然と触れ合う楽しさを教えて貰えた貴重な体験の積み重ねがあったからこそである。
朝、目を覚ますとまだ隣で佑次郎が寝息を立てている。今日は火曜日、平日の朝だから佑次郎は起き出すと共にそそくさと中学校へと行ってしまう。布団の中から佑次郎を送り出した後しばらく本を読んでいた私だがトイレに立った際に自室に差し込む明るい陽射しが妙に心を捉えて落ち着かなくなった。
「う~ん、今日は天気が良いんだなぁ、山でも歩いて来ようかなぁ・・・。」
こんな考えが浮かんだ途端にもう壁に掛かっていたザックを引き下ろしていた。
 特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。
特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。荒井川沿いの道を登山口に続く林道を探しながら走ったが、何処をどうしたものか登山口が見つからないままに加蘇山神社の社務所前まで来てしまった。加蘇山神社と言えば石裂山(おざくさん)の登山口に当たる場所である。「これも何かの縁か・・・」と急きょ石裂山登山に切り替える事にした。
社務所に在る石裂山回遊コース案内を眺めると大体4時間くらいの様子だ。現在9:30であるから13:30下山でも14:00過ぎには帰宅出来る目算である。
荒井川源流部に当たる沢沿いの登山道を軽い気分で歩き出す。沢音を聞きながらの登山は釣り屋の私にとって何よりも快適である。あちらこちらに「禁漁区」と赤字で書かれた札を目にするが沢の流れを覗き込んでみても一向に魚影は無い。登山道が横を走る里川の延長でしかない川だから最初から期待はしていないが、ついつい魚影を求めては儚い夢を追いかけてしまう。あざ笑う様に大きなヒキガエルが泳いでいるのが見えて苦笑してしまう。
 周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。
周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。東屋がある中ノ宮に登り付く。「奥の宮・東剣ノ峰」の標識の先の岩場に長い鎖が下ろされているのが見える。
「そう言えば石裂山は鎖場と梯子の山だった・・・」
 気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。
気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。この鎖場、「行者返しの岩場」と呼ばれている。私は行者では無いので帰らずに済んだ。でも雨後や雨天時なら無理は禁物と思わされる岩場である。登ってしまったら降りるのに首を傾げる程度の岩場と表現しておく。
さらに脇道にステンレス製の階段が伸びる「奥の宮」を参拝してから登山道に戻り尾根に取り付く。岩場を木の根を掴みながら登る。「一部にはハイキングコースと案内されていますが、ここは登山道です。」と書かれていた案内板の注意文を思い浮かべる。
鎖場・階段を越え「東剣ノ峰」に到着。樹木に遮られて大した展望も無い。「西剣ノ峰」へと進む鞍部に下る。これが長いステンレス製の階段の下り。何の気なしに降り始めたが、その長さに途中で「そう言えば俺って高所恐怖症じゃなかった?!」と気が付いてそれからの長かった事・・・。
鞍部に辿り着くもすぐに西剣ノ峰への登り返し。九十九折れの急登と途中で振り返ると、東剣ノ峰から下る崖に取り付けられた階段が見える。「あんなとこ降りて来たの・・・?!」と改めて驚く。
西剣ノ峰に登り付くと生い茂る樹木の間から鋭い岩肌を見せる石裂山が目の前に見える。正直「あそこに登るの・・・?」と思ったものだが、実際に登ってみるともう核心部は越えていた様で呆気ない思いで山頂に立つ。
山頂から見える展望は地理不案内にてコメント無し。(笑)
 本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。
本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。月山からの下りも時折鎖場や梯子を介して結構急な下りで一気に標高を下げて来る。スギ林に入る頃には次第に沢音も大きくなって来る。「音はすれども水が見えないなぁ・・・。」と思っていたら突然岩の間から水が流れ出して沢を作り始める。伏流水が顔を出した瞬間である。この流れも荒井川の源流域の一筋となっていくわけである。
もう充分に沢と呼べる流れを渡ると登路と合流して周回を終える。ここからは往路を逆に辿るだけである。緊張の中にも心を癒された一人旅が無事に終わった。
 釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。
釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。家に帰り御帰還ビールで一杯やっていると佑次郎が帰って来た。「今日ねぇ、山に行って来たんだ。」こう話し掛けると「何処の?」と御愛想が返って来た。それでも山の様子を写真を見せながら詳しく話してやる。「お父さんが“山に行った”って聞くとお前も行きたくなるだろ?」こう問い掛けた私にニヤリと笑いを返して来る。満更でもない表情に安心しながら残りのビールを美味しく飲んだ。「佑、今度は一緒に行こうな・・・」
タグ :栃木
2010年05月11日
日光男体山
今度は表から
2010年5月9日 栃木県日光市 男体山 記録者 はら坊
「副隊長が休みだから何所か釣りに行きませんか?」
そんな感じで始った今回の遊びだったのだが、最終的に副隊長と私の二人での登山になった。
行先も、榛名山等と言う話も出たが隊長が居ないという事で県外遠征はNG、副隊長も夜中から仕事と言う事で栃木県内霊峰男体山に決めた。
3年程前、裏から登った事があったので、今回は表から登る事にした。
いろは坂登り口のトイレのある駐車場で待ち合わせ、合流して一台で登山口へ向う。
二荒山神社の門が6時開門と言う事で時間が来るのを支度を済まし、朝食を摂りながら待つ。
時間になると開門を待ちわびた登山者達が一斉に流れ込む。
登拝届けを済まし\500を納めいざ登山道へ・・・
いきなり急な階段、登りかけて直ぐ白根葵の群生を覗きに脇道に入るもその姿は無かった。
という事で、山頂へと歩みを進めるが衰えた体に急登が容赦なく圧し掛かる。
そう言えば最近休みとなると疲れて一日寝てしまっている事が多い。
これでは筋力体力とも鈍ってしまって当然である。
そんな衰えた体にムチを打ち山頂を目指す。
途中年配のパーティーを追い越し林道に飛び出る。
「この林道何処まで行ってるのかな?」
「山頂まで道付いてたりして・・・」
「山開きの時の神主は、この道を車で行くんじゃない・・・(笑)」
などと話しながら林道をしばし歩く。
その頃には体も温まり副隊長の歩みも軽やかになってきた様でペースも上がる。
後ろから追いかけるのもキツイ位だ。
 ほとんど直登の登山道は大きなガレ場が現れると何処がルートか分からなくなり、歩幅がバラつきとても疲れる。
ほとんど直登の登山道は大きなガレ場が現れると何処がルートか分からなくなり、歩幅がバラつきとても疲れる。
ガレ場が過ぎると直ぐに残雪が現れた。何だかやけに滑る・・・
足腰が弱くなった事を実感する。
来週の安達太良が心配になって来る。
残雪をクリアーすると漸く間近の火山灰帯になり歩き易くなって山頂へのペースも上がり直ぐ登頂達成。
3年前と何も変わらず私達を出迎えてくれた。剣の前で記念撮影を撮り、
少し早い昼食、山頂ラーメンを食べいざ下山・・・
と思った所に途中パスしてきたご老人が到着、御歳85歳!!男体山登頂1000回越えと言う方と記念撮影を撮らせて頂き頭を温泉に切替え下山。
下山も終盤になりかけて今朝覗き込んだ白根葵の群生地を覗き込むと、何と薄紫色の花を付け私達の無事を祝してくれている様だった。


一日副隊長の背中を追った登山・・・キツかったけど、心地の良い時間だった。
きっと副隊長もあの人の背中をこんな気持ちで見ていたのかな・・・
そんな事を考えちょっとセンチメンタルな気持ちになり臭い温泉に浸かった。
2010年5月9日 栃木県日光市 男体山 記録者 はら坊
「副隊長が休みだから何所か釣りに行きませんか?」
そんな感じで始った今回の遊びだったのだが、最終的に副隊長と私の二人での登山になった。
行先も、榛名山等と言う話も出たが隊長が居ないという事で県外遠征はNG、副隊長も夜中から仕事と言う事で栃木県内霊峰男体山に決めた。
3年程前、裏から登った事があったので、今回は表から登る事にした。
いろは坂登り口のトイレのある駐車場で待ち合わせ、合流して一台で登山口へ向う。
二荒山神社の門が6時開門と言う事で時間が来るのを支度を済まし、朝食を摂りながら待つ。
時間になると開門を待ちわびた登山者達が一斉に流れ込む。
登拝届けを済まし\500を納めいざ登山道へ・・・
いきなり急な階段、登りかけて直ぐ白根葵の群生を覗きに脇道に入るもその姿は無かった。
という事で、山頂へと歩みを進めるが衰えた体に急登が容赦なく圧し掛かる。
そう言えば最近休みとなると疲れて一日寝てしまっている事が多い。
これでは筋力体力とも鈍ってしまって当然である。
そんな衰えた体にムチを打ち山頂を目指す。
途中年配のパーティーを追い越し林道に飛び出る。
「この林道何処まで行ってるのかな?」
「山頂まで道付いてたりして・・・」
「山開きの時の神主は、この道を車で行くんじゃない・・・(笑)」
などと話しながら林道をしばし歩く。
その頃には体も温まり副隊長の歩みも軽やかになってきた様でペースも上がる。
後ろから追いかけるのもキツイ位だ。
 ほとんど直登の登山道は大きなガレ場が現れると何処がルートか分からなくなり、歩幅がバラつきとても疲れる。
ほとんど直登の登山道は大きなガレ場が現れると何処がルートか分からなくなり、歩幅がバラつきとても疲れる。ガレ場が過ぎると直ぐに残雪が現れた。何だかやけに滑る・・・
足腰が弱くなった事を実感する。
来週の安達太良が心配になって来る。
残雪をクリアーすると漸く間近の火山灰帯になり歩き易くなって山頂へのペースも上がり直ぐ登頂達成。
3年前と何も変わらず私達を出迎えてくれた。剣の前で記念撮影を撮り、
少し早い昼食、山頂ラーメンを食べいざ下山・・・
と思った所に途中パスしてきたご老人が到着、御歳85歳!!男体山登頂1000回越えと言う方と記念撮影を撮らせて頂き頭を温泉に切替え下山。
下山も終盤になりかけて今朝覗き込んだ白根葵の群生地を覗き込むと、何と薄紫色の花を付け私達の無事を祝してくれている様だった。


一日副隊長の背中を追った登山・・・キツかったけど、心地の良い時間だった。
きっと副隊長もあの人の背中をこんな気持ちで見ていたのかな・・・
そんな事を考えちょっとセンチメンタルな気持ちになり臭い温泉に浸かった。
タグ :栃木
2010年03月08日
冬季 前白根山~奥白根山
冬季 前白根山~奥白根山ピストン
2010年3月7日 栃木県日光市 白根山 記録者 あっちゃん
今回は、前から考えていた女峰山に続き奥白根山に登頂してきました。
結構ハードな行程なので深夜2時30分に起床
いつもの如く愛車に乗り込み、日光湯元温泉へ・・・
天気予報は雪でしたが、生憎の雨模様・・・・
テンションがた落ちです。
駐車場の車の中でいろいろ考えを巡らし夜明けまで待って雨なら撤退、雪に変われば決行と決め仮眠します。
薄明るく成り始めたころみぞれになり路面もやや白くなり始め、あまり気分が乗らないのですが出発の準備を始めます。
5時50分
みぞれの中を歩き始めます。
スキー場の雪質はザラメ状で隅っこを歩くと時々膝までもぐって、あまり良い状態ではありません。
ゴアの合羽を羽織っていたのですが登山口付近では異様に暑く感じられ脱ぎました。
6時34分
ここから外山尾根までの急登が第一関門
天気は良くないし、暑いし、疲れるし、時々落とし穴に嵌るし、汗が目に入って痛いし
何度も戻ろうかなどと考えつつも体は上へと動き出すのでした。
ナンヤカンヤで8時09分外山尾根に到着
ここまでくれば前白根山までは一息です。
でも、急登はまだ続きます。
喘ぎながら殆どトレースの消えた雪の急斜面を登り何度も最中雪の落とし穴に掴まり、そのたびに体力が奪われていき、またここでも「ヤッパ戻るかな~」などと思いつつも歩き続け前白根山山頂に9時24分到着



この先はまだ歩いたことが無い未知の世界です。
相変わらずガス濃く、湿った雪が降り続いています。
白錫尾根を少し歩いて避難小屋へ
ここでも落とし穴が沢山あり、腿が攣りそうです・・・・。
10時00分避難小屋到着
始めて見る避難小屋の外観は比較的きれいで驚きました。
雪で閉ざされ中の様子は伺うことが出来ず残念でしたが
とりあえず先を急ぐことに
暫く谷を登ると奥白根山の表示があり今回はここにザックをデポして頂きを目指すことにします。
GPS、デジコン、三脚、携帯電話をポケットに入れて山頂に向かって最短ルートで直登します。
上部の急斜面では10m登っては深呼吸をするようなペースでなかなかきついです。
11時09分待望の奥白根山山頂に到達しました。



ガスと雪は相変わらずで展望は殆ど無く以前に登った菅沼ルートが少しだけ見えて感慨深いです。
どんどんガスが濃くなるようなので長居は無用、とっとと下山です。
登りでは辛かった斜面もシリセードで楽チン!
1時間近く掛かった所が立ったの15分!
デポしたザックに戻り腹ごしらえして帰路に着きました。
13時54分車に到着。
悪天とこのところの天候不順で思うようにトレーニング出来ていなかったため正直辛い山行でした。
でも、時間的には女峰山の時より早かったんですよね・・。
なんか、不思議な感じです。
まっ、いっか~!!
今度はどこに行くべかな~!
2010年3月7日 栃木県日光市 白根山 記録者 あっちゃん
今回は、前から考えていた女峰山に続き奥白根山に登頂してきました。
結構ハードな行程なので深夜2時30分に起床
いつもの如く愛車に乗り込み、日光湯元温泉へ・・・
天気予報は雪でしたが、生憎の雨模様・・・・
テンションがた落ちです。
駐車場の車の中でいろいろ考えを巡らし夜明けまで待って雨なら撤退、雪に変われば決行と決め仮眠します。
薄明るく成り始めたころみぞれになり路面もやや白くなり始め、あまり気分が乗らないのですが出発の準備を始めます。
5時50分
みぞれの中を歩き始めます。
スキー場の雪質はザラメ状で隅っこを歩くと時々膝までもぐって、あまり良い状態ではありません。
ゴアの合羽を羽織っていたのですが登山口付近では異様に暑く感じられ脱ぎました。
6時34分
ここから外山尾根までの急登が第一関門
天気は良くないし、暑いし、疲れるし、時々落とし穴に嵌るし、汗が目に入って痛いし
何度も戻ろうかなどと考えつつも体は上へと動き出すのでした。
ナンヤカンヤで8時09分外山尾根に到着
ここまでくれば前白根山までは一息です。
でも、急登はまだ続きます。
喘ぎながら殆どトレースの消えた雪の急斜面を登り何度も最中雪の落とし穴に掴まり、そのたびに体力が奪われていき、またここでも「ヤッパ戻るかな~」などと思いつつも歩き続け前白根山山頂に9時24分到着



この先はまだ歩いたことが無い未知の世界です。
相変わらずガス濃く、湿った雪が降り続いています。
白錫尾根を少し歩いて避難小屋へ
ここでも落とし穴が沢山あり、腿が攣りそうです・・・・。
10時00分避難小屋到着
始めて見る避難小屋の外観は比較的きれいで驚きました。
雪で閉ざされ中の様子は伺うことが出来ず残念でしたが
とりあえず先を急ぐことに
暫く谷を登ると奥白根山の表示があり今回はここにザックをデポして頂きを目指すことにします。
GPS、デジコン、三脚、携帯電話をポケットに入れて山頂に向かって最短ルートで直登します。
上部の急斜面では10m登っては深呼吸をするようなペースでなかなかきついです。
11時09分待望の奥白根山山頂に到達しました。



ガスと雪は相変わらずで展望は殆ど無く以前に登った菅沼ルートが少しだけ見えて感慨深いです。
どんどんガスが濃くなるようなので長居は無用、とっとと下山です。
登りでは辛かった斜面もシリセードで楽チン!
1時間近く掛かった所が立ったの15分!
デポしたザックに戻り腹ごしらえして帰路に着きました。
13時54分車に到着。
悪天とこのところの天候不順で思うようにトレーニング出来ていなかったため正直辛い山行でした。
でも、時間的には女峰山の時より早かったんですよね・・。
なんか、不思議な感じです。
まっ、いっか~!!
今度はどこに行くべかな~!
タグ :栃木
2010年02月26日
古賀志山(2010.2.21)
息子と登山♪
2010年2月21日 栃木県宇都宮市 古賀志山 記録者 やませみ
千葉の大学に行ってる次男から20日の朝、突然帰ってくるとのメールが届いたのである。
夕方、いつものように駅まで迎えにその帰り道の車中で私は息子とのある約束を思い出した。
それは一月くらい前にメールで 「●さと、今度お父さんと山、一緒に行くかぁ!」と送ったのです。まぁたぶん返事は「行かないー」だろうと予想してたのですが結果は意外にも「いいよー!!」の快諾でした。
これは息子と山行のチャンス到来!!
うっしーしー。と思う自分がいたのであった。
ほどなくして自宅へ到着、早々母親の歓迎を受け夕食のテーブルへと。 いつになく食卓が賑やかである。明らかに次男が家にいない時と料理の品数が・・・多くねぇ・・。それを見た次男は当然ご満悦であった。
一人でのアパート暮らし普段あまり碌な物は食ってないはずである。
正月以来の一家団欒の時間が始まる。何時になく女房の顔が綻んでいた。未熟児で生まれ人一倍手のかかった次男は特に可愛いみたいである。
ここからは私と次男のやり取り・・
父 「●●と、この間のメールのこと憶えてる?」
次男 「うん。 おぼえてるよぉ」
父 「お父さん明日急きょ休みになったんだよねぇ」
次男 「ふーん。 ・・・んで」
父 「山、いくか?あした」
父 「山頂で食べるラーメンうまいんだよねー」
次男 「何山?いくのぉ」
父 「何処にする?」
次男 「月山、火山なら良いよー」
父 「・・・・・???」
父 「それって山は山でも食物家・・?」 (なんだよぉ、もぉ。)って感じでした。
息子はどうやら山よりも食べ物家の方が好いみたいで、結局その夜は折合いが付かず寝ることに。正直この時点で山行きは半ば諦めていました。
替わって翌朝、朝食を済ませ炬燵でテレビを見ヌクヌクしていると2階から勢いよく次男が私のとなりに繰るなり
「今日、山いくの・・?」・・・しばし無言の私。
すると、「お父さん着るもの貸して。靴はどれ履けばいいのぉ」の声が。
こうなれば話しは早い。速攻出かける準備をする。
近くのコンビニで食料を買い込み家から車で15分で行ける古賀志山へと向かう。赤川ダム下の駐車場に到着。 時間はすでに11時ちょうど。
いつになく車が多く三段下の駐車場にようやく空きスペースを見つけて車を止めやっと出発である。
今日のコースは急だったので特に決めてなく、なんとなく足の向くまま北登山口へ。でもこのまま登るのもつまらいし・・
・・て、ことで東稜の見晴台へ南側から登りはじめることに。
最初は一緒のペースで歩いていたのだが、だんだんと私が遅れをとるようになる。 いやはやなんとも10代の若さが羨ましい。
直登に近い鎖場をなんなく越え見晴し台に着く、案の定昼どきで満杯である。仕方なくそのまま古賀志山頂へと向う。
するとどうでしょう。こちらはがらがらです。 ラッキー!!!
一番南側のテーブルに場所をとりお楽しみの昼食です♪
おにぎりとお気に入りのカップラーメンを頬張りしばしまったりとした親子の時間を過ごしました。おなかも満たされこのまま降るのも芸がないので
御岳山まで足をのばすことになり午後の部開始である。
親子での登山の証しにカメラのシャッターをお願いすべく5人組のご年配の方のひとりに頼み記念撮影。するとメンバーの一人の女性が僕が2人分の荷物を背負ってることに気付き冷かされる始末に。そうなのです、息子はノーザックだったのです。お父さんは甘いのひと言が・・・
でも、もう一人の女性の方が家にも大学生の息子がいるので何となく気持ちは解かりますよとの優しいお声がけ。 そうですか、ありがとうございます。そんな他愛もない会話をしつつメンバー達に別れを告げ登山道へとすすむ。
ところがこの先がほとんど日陰の為、アイスバーン状態ですべるのなんのって。いつもは10分で行ける距離を30分ほどかかりやっとの思いで御岳山頂に着いたのである。ここでも記念の証しを取りそうそうに来た道を恐る恐る戻ったのである。
帰路は残雪のない南登山道を下りることに50分ほどで駐車場に帰ってきました。 この日は天気が良かったのもあり森林公園は家族連れでとても賑わっていました。駐車場が一杯だったのは登山客だけじゃ無かったみたいです。
と言うことで、久々に親子の時間を過ごせた一日でした。
こういう時が「近いうちにまたあれば好いなーと!」・・と願う父である。



2010年2月21日 栃木県宇都宮市 古賀志山 記録者 やませみ
千葉の大学に行ってる次男から20日の朝、突然帰ってくるとのメールが届いたのである。
夕方、いつものように駅まで迎えにその帰り道の車中で私は息子とのある約束を思い出した。
それは一月くらい前にメールで 「●さと、今度お父さんと山、一緒に行くかぁ!」と送ったのです。まぁたぶん返事は「行かないー」だろうと予想してたのですが結果は意外にも「いいよー!!」の快諾でした。
これは息子と山行のチャンス到来!!
うっしーしー。と思う自分がいたのであった。
ほどなくして自宅へ到着、早々母親の歓迎を受け夕食のテーブルへと。 いつになく食卓が賑やかである。明らかに次男が家にいない時と料理の品数が・・・多くねぇ・・。それを見た次男は当然ご満悦であった。
一人でのアパート暮らし普段あまり碌な物は食ってないはずである。
正月以来の一家団欒の時間が始まる。何時になく女房の顔が綻んでいた。未熟児で生まれ人一倍手のかかった次男は特に可愛いみたいである。
ここからは私と次男のやり取り・・
父 「●●と、この間のメールのこと憶えてる?」
次男 「うん。 おぼえてるよぉ」
父 「お父さん明日急きょ休みになったんだよねぇ」
次男 「ふーん。 ・・・んで」
父 「山、いくか?あした」
父 「山頂で食べるラーメンうまいんだよねー」
次男 「何山?いくのぉ」
父 「何処にする?」
次男 「月山、火山なら良いよー」
父 「・・・・・???」
父 「それって山は山でも食物家・・?」 (なんだよぉ、もぉ。)って感じでした。
息子はどうやら山よりも食べ物家の方が好いみたいで、結局その夜は折合いが付かず寝ることに。正直この時点で山行きは半ば諦めていました。
替わって翌朝、朝食を済ませ炬燵でテレビを見ヌクヌクしていると2階から勢いよく次男が私のとなりに繰るなり
「今日、山いくの・・?」・・・しばし無言の私。
すると、「お父さん着るもの貸して。靴はどれ履けばいいのぉ」の声が。
こうなれば話しは早い。速攻出かける準備をする。
近くのコンビニで食料を買い込み家から車で15分で行ける古賀志山へと向かう。赤川ダム下の駐車場に到着。 時間はすでに11時ちょうど。
いつになく車が多く三段下の駐車場にようやく空きスペースを見つけて車を止めやっと出発である。
今日のコースは急だったので特に決めてなく、なんとなく足の向くまま北登山口へ。でもこのまま登るのもつまらいし・・
・・て、ことで東稜の見晴台へ南側から登りはじめることに。
最初は一緒のペースで歩いていたのだが、だんだんと私が遅れをとるようになる。 いやはやなんとも10代の若さが羨ましい。
直登に近い鎖場をなんなく越え見晴し台に着く、案の定昼どきで満杯である。仕方なくそのまま古賀志山頂へと向う。
するとどうでしょう。こちらはがらがらです。 ラッキー!!!
一番南側のテーブルに場所をとりお楽しみの昼食です♪
おにぎりとお気に入りのカップラーメンを頬張りしばしまったりとした親子の時間を過ごしました。おなかも満たされこのまま降るのも芸がないので
御岳山まで足をのばすことになり午後の部開始である。
親子での登山の証しにカメラのシャッターをお願いすべく5人組のご年配の方のひとりに頼み記念撮影。するとメンバーの一人の女性が僕が2人分の荷物を背負ってることに気付き冷かされる始末に。そうなのです、息子はノーザックだったのです。お父さんは甘いのひと言が・・・
でも、もう一人の女性の方が家にも大学生の息子がいるので何となく気持ちは解かりますよとの優しいお声がけ。 そうですか、ありがとうございます。そんな他愛もない会話をしつつメンバー達に別れを告げ登山道へとすすむ。
ところがこの先がほとんど日陰の為、アイスバーン状態ですべるのなんのって。いつもは10分で行ける距離を30分ほどかかりやっとの思いで御岳山頂に着いたのである。ここでも記念の証しを取りそうそうに来た道を恐る恐る戻ったのである。
帰路は残雪のない南登山道を下りることに50分ほどで駐車場に帰ってきました。 この日は天気が良かったのもあり森林公園は家族連れでとても賑わっていました。駐車場が一杯だったのは登山客だけじゃ無かったみたいです。
と言うことで、久々に親子の時間を過ごせた一日でした。
こういう時が「近いうちにまたあれば好いなーと!」・・と願う父である。



タグ :栃木
2010年02月23日
女峰山(2010.2.21)
祝 冬期赤薙山~女峰山ピストン
2010年2月21日 栃木県日光市 赤薙山~女峰山 記録者 あっちゃん
先週の辛い体験と苦い経験の記憶がまだ新しい金曜日
来週は家族に付き合ってお買い物と決めていたのですが、
不意にかみさんから「今回は買い物に行かないから山に行ってくれば~。」と言われ
敗退の悔しさから毎夜自分の体を苛める様に厳しくトレーニングしていたのですが、(当初の目標は28日にトライする予定でした。)その一言でいきなり心に火が灯り心も体も戦闘モードに。
ネットで天候をチッェクしたところ今度の日曜日は気候が安定して絶好の登山日和みたいです。
当日深夜2時に起床
前回同様に総ての支度を前日に夜に済ませ身支度を整え愛車に乗り込みひた走ります。
15分ほど走ったところでメールのチェックと思い携帯電話を探すのですが見当たらず良く良く考えてみたら自分の枕元に忘れてきたようです。
非常時の連絡や下山メールなどに必ず使うし不要な心配を掛けないためにもわざわざ取りに引き返しました。
自宅に着いたとき室内から物音がしてカミサンが携帯を手にして裏口に立って「気を付けてね~。」と一言。
何と無く勇気付けられ「何だか 行けそうな気がする~」と呟きながら最近お気に入りのエルレ ガーデンのCDをガンガンかけて再び車を一路霧降高原へ・・・。
今回は少し早めに歩き出す予定で早起きしたのですが結局前回とあまり変わらない時間に到着。
AM4時15分に駐車場を出発、赤薙山に向けてひた歩きます。
前回の様な疲労感は感じられずとても快調です。
今回はスノーシュウは履かずに初めからアイゼンにしたのが正解だったようでとても歩きやすく
スピードも早いようです。
沢山のトレースがありとても楽チン!!
さすがに人気の山です。
赤薙山到着5時51分
小休止のあとさきを目指します。
ここから先は前回歩いた自分のトレースが所々にあるだけでかなり新鮮味があります。
ラッセルマニアの心を満たすには十分の積雪と不意にはまり込む落とし穴があり息も上がります。



空は白み始め東の方が明るくなりかけたころ急に風が吹き
風速15~20メーターはあろうかと思われる突風が右へ左へ吹き荒れ
足場の危うい尾根や岩場では何度かヒヤリとさせられたのですが1時間ほどで穏やかになり一安心!
奥社跡到着6時45分
オニギリを一つ食べ水分を補給して先を急ぎます。
気持ち良い陽射しの中足取りは快調です。
しかし、長い登りと分かりにくいトレースに少しペースを乱され歩きやすい硬い雪面を探しながら辿り一里ヶ曽根がとても遠く感じられ、なかなか辛いところです。
 一里ヶ曽根到着8時00分
一里ヶ曽根到着8時00分
前回より2時間30分も早い到着どぇっす。
時計を見た時自分もビックリでした。
事前に休憩する場所を決め、その間はゆっくりでも歩き続けることを心がけたのが良かったようです。
ここでまたエネルギーを補給して目の前に聳える女峰山を目指します。
樹林帯を過ぎ山頂が見渡せる尾根に取り付いた時、事前に予定していた通りにザックをデポして空身で山頂へ向かいます。
とは言っても連絡用の携帯、記録用のGPS、コンデジ、ミニ三脚はポケットに詰め込み、片手にはグリベルのピッケルを握り締め今回山行の最大の難所に気合を入れ挑みます。
2箇所、急な岩場の斜面がありおそらくガリガリに凍り付いてかなり危険で在ろうと想像していたのですが、やはりアイゼンのケッツアがやっと食い込むぐらいにカチカチで殆どアイスクライミングに近い登りが30メーターほど滑ったら間違いなく150メーター滑落してしまうであろう急斜面を一気に駆け上がりました。
正に『行きはよいよい帰りは怖い・・」の心境でしたがまずは憧れた女峰山山頂へ
 女峰山登頂10時15分
女峰山登頂10時15分
ついに到着しました。
快晴無風、紺碧の空
轟音を遥か後方に響かせながら通り過ぎるいつもより一回り大きなジェット旅客機
いつもと違うアングルから見渡せる山々
誰もいない山頂はこの一時だけは自分だけのものです。
心地よい疲労感と達成感が心と体に染み渡り何とも言えない満足感が体を包み込み最高の気分です!!
暫く休んで景色を眺め、また来ることを心に誓い山頂を後にしました。
 気持ちよい尾根を下りながらさっき越えてきた岩場の下りが気になります。
気持ちよい尾根を下りながらさっき越えてきた岩場の下りが気になります。
登りより下りの方が恐怖感がありそうで『慎重に行こう!!」と呟きながら暫く下ると程なく切れ落ちた岩場です。
後ろ向きになり足場を確認しながら下るのですが、あまり手がかりも無くピッケルだけが頼りです。
一歩一歩慎重に下り何とか安心できる所まで降りた時「あぁ~、やっと帰れる」と思えたのでした。
後はひたすら歩くのみ、殆ど休まず下山です。
駐車場到着14時29分
思ったよりずいぶん早く下山出来ました。
今回の山行では、丈夫に生んでくれた両親に感謝すると共に、日頃のトレーニングの成果とその内容の見直しが必要かな。
あと、道具も2~3欲しいものが・・・・
あと背中を押してくれたカミサンに感謝です!!
さて、次はどこに行こうかな~。
2010年2月21日 栃木県日光市 赤薙山~女峰山 記録者 あっちゃん
先週の辛い体験と苦い経験の記憶がまだ新しい金曜日
来週は家族に付き合ってお買い物と決めていたのですが、
不意にかみさんから「今回は買い物に行かないから山に行ってくれば~。」と言われ
敗退の悔しさから毎夜自分の体を苛める様に厳しくトレーニングしていたのですが、(当初の目標は28日にトライする予定でした。)その一言でいきなり心に火が灯り心も体も戦闘モードに。
ネットで天候をチッェクしたところ今度の日曜日は気候が安定して絶好の登山日和みたいです。
当日深夜2時に起床
前回同様に総ての支度を前日に夜に済ませ身支度を整え愛車に乗り込みひた走ります。
15分ほど走ったところでメールのチェックと思い携帯電話を探すのですが見当たらず良く良く考えてみたら自分の枕元に忘れてきたようです。
非常時の連絡や下山メールなどに必ず使うし不要な心配を掛けないためにもわざわざ取りに引き返しました。
自宅に着いたとき室内から物音がしてカミサンが携帯を手にして裏口に立って「気を付けてね~。」と一言。
何と無く勇気付けられ「何だか 行けそうな気がする~」と呟きながら最近お気に入りのエルレ ガーデンのCDをガンガンかけて再び車を一路霧降高原へ・・・。
今回は少し早めに歩き出す予定で早起きしたのですが結局前回とあまり変わらない時間に到着。
AM4時15分に駐車場を出発、赤薙山に向けてひた歩きます。
前回の様な疲労感は感じられずとても快調です。
今回はスノーシュウは履かずに初めからアイゼンにしたのが正解だったようでとても歩きやすく
スピードも早いようです。
沢山のトレースがありとても楽チン!!
さすがに人気の山です。
赤薙山到着5時51分
小休止のあとさきを目指します。
ここから先は前回歩いた自分のトレースが所々にあるだけでかなり新鮮味があります。
ラッセルマニアの心を満たすには十分の積雪と不意にはまり込む落とし穴があり息も上がります。



空は白み始め東の方が明るくなりかけたころ急に風が吹き
風速15~20メーターはあろうかと思われる突風が右へ左へ吹き荒れ
足場の危うい尾根や岩場では何度かヒヤリとさせられたのですが1時間ほどで穏やかになり一安心!
奥社跡到着6時45分
オニギリを一つ食べ水分を補給して先を急ぎます。
気持ち良い陽射しの中足取りは快調です。
しかし、長い登りと分かりにくいトレースに少しペースを乱され歩きやすい硬い雪面を探しながら辿り一里ヶ曽根がとても遠く感じられ、なかなか辛いところです。
 一里ヶ曽根到着8時00分
一里ヶ曽根到着8時00分前回より2時間30分も早い到着どぇっす。
時計を見た時自分もビックリでした。
事前に休憩する場所を決め、その間はゆっくりでも歩き続けることを心がけたのが良かったようです。
ここでまたエネルギーを補給して目の前に聳える女峰山を目指します。
樹林帯を過ぎ山頂が見渡せる尾根に取り付いた時、事前に予定していた通りにザックをデポして空身で山頂へ向かいます。
とは言っても連絡用の携帯、記録用のGPS、コンデジ、ミニ三脚はポケットに詰め込み、片手にはグリベルのピッケルを握り締め今回山行の最大の難所に気合を入れ挑みます。
2箇所、急な岩場の斜面がありおそらくガリガリに凍り付いてかなり危険で在ろうと想像していたのですが、やはりアイゼンのケッツアがやっと食い込むぐらいにカチカチで殆どアイスクライミングに近い登りが30メーターほど滑ったら間違いなく150メーター滑落してしまうであろう急斜面を一気に駆け上がりました。
正に『行きはよいよい帰りは怖い・・」の心境でしたがまずは憧れた女峰山山頂へ
 女峰山登頂10時15分
女峰山登頂10時15分ついに到着しました。
快晴無風、紺碧の空
轟音を遥か後方に響かせながら通り過ぎるいつもより一回り大きなジェット旅客機
いつもと違うアングルから見渡せる山々
誰もいない山頂はこの一時だけは自分だけのものです。
心地よい疲労感と達成感が心と体に染み渡り何とも言えない満足感が体を包み込み最高の気分です!!
暫く休んで景色を眺め、また来ることを心に誓い山頂を後にしました。
 気持ちよい尾根を下りながらさっき越えてきた岩場の下りが気になります。
気持ちよい尾根を下りながらさっき越えてきた岩場の下りが気になります。登りより下りの方が恐怖感がありそうで『慎重に行こう!!」と呟きながら暫く下ると程なく切れ落ちた岩場です。
後ろ向きになり足場を確認しながら下るのですが、あまり手がかりも無くピッケルだけが頼りです。
一歩一歩慎重に下り何とか安心できる所まで降りた時「あぁ~、やっと帰れる」と思えたのでした。
後はひたすら歩くのみ、殆ど休まず下山です。
駐車場到着14時29分
思ったよりずいぶん早く下山出来ました。
今回の山行では、丈夫に生んでくれた両親に感謝すると共に、日頃のトレーニングの成果とその内容の見直しが必要かな。
あと、道具も2~3欲しいものが・・・・
あと背中を押してくれたカミサンに感謝です!!
さて、次はどこに行こうかな~。
タグ :栃木
2010年02月17日
女峰山 改 一里ヶ曽根(2010.2.14)
赤薙山~一里ヶ曽根
2010年2月14日 栃木県日光 赤薙山~一里ヶ曽根 記録者 あっちゃん
今回は、霧降高原の駐車場から赤薙山~奥社跡~ヤハズ~一里ヶ曽根~女峰山を日帰りで踏破するべく
深夜3時に起床、
前夜から登山の準備を済ませ、装備を詰め込んだ愛車に乗り込み一路日光へ・・・・。
4時15分駐車場に到着。
まだ真っ暗な中ただ一人黙々と準備を済ませ
ヘッデンの明かりを頼りに歩き始めます。
ゲレンデ跡の急な斜面に息が上がり結構辛く
何と無く今日の体調はあまり良く無い様な気がして少し不安になり
下界の夜景の美しさに勝手に哀愁を感じ感動しつつも
この先の雪の状態が気になります。
ここ数日天気は荒れ模様で今日だけつかの間の晴れ間が期待出来そうとのこと、
予想では、適当な硬さの雪とその上にふんわりと乗っかった新雪の斜面を想像していたのですが
以外に最中状態の雪質で
この後大変な苦労が待って居ようとは思いもせず歩を進めます。
東の空が段々と赤く染まり空の雲の状態が目視出来始めたころ
町の夜景が色あせ、山の形がハッキリしてきます。
直感で「今日の天気が持つのはお昼までだな~。」と感じ行動時間を逆算して
早くも「今回は無理かもな~」と頭の中で自分と違う誰かが囁き
「そうかもね~。」と一人呟く自分がいました。(この時点でまだ赤薙山頂のずいぶん手前でした。)


6時50分赤薙山到着
下からスノーシュウを履いてきたのですがクラストした急斜面では歯が立たず
ズルズルと滑りかなり体力を消耗してしまい結構バテましたが
今年の西暦と同じ標高の2010メートル
今年は登ろうと考えていたので、誰もいない山頂で一人ニヤニヤしながら鳥居をパチリと一枚
小休止の後再び気合を入れ先を目指します。
この先は誰のトレースも無くルートの確認や不安定な足元に悩まされ遅々として距離が伸びず時間ばかりが過ぎて行きかなりテンションが下がります。
アイゼンに履き替えかなり危うい尾根筋を辿り樹林帯を潜り行くと
日向になる部分は表面が硬く比較的歩きやすいのですが
日陰の部分になるとたちまち脆くなり、場所によっては下腹部までもぐり
今まで経験したことの無いラッセルが始まります。
まるで、落とし穴様な雪の斜面はやる気と体力をどんどん自分の体から奪い取ってゆくのでした。
何度落ちたか忘れたころアクシデントが・・・・。
右足が取られた瞬間バランスを崩し、左足のケッツァの部分で自分の右足のフクラハギを蹴り飛ばしてしまい、右足に激痛が・・・。
ここは冷静にと自分に言い聞かせ暫く休んで様子を見たところ外傷も無く段々痛みも和らいできたので
先を目指すことに決め再び歩き始めます。


奥社跡で小休止してヤハズの痩せ尾根を通過
再び樹林帯に入り不規則で予測不能な落とし穴が何度も襲ってきます。
そしてまた同じところを蹴っ飛ばしてしまい思わず「ガッデム!!」「サノバビッチッ!!」と叫ぶ自分でした。
正直この時点でやる気0パーセント
せめて切のよい所で一里ヶ曽根までは行こうと思い
半ば気力だけで何とか辿り着きました。
時間は10時20分
目の前に女峰山が見えるのですが
夏道で約1時間
この状態だと良くて片道2時間半は掛かるだろうと思った時
今回は諦めることにしました。
暫く女峰山を眺めデッカイ声でリベンジを誓い帰路に着きました。


予想はしていたのですが雪山の女峰山は厳しかった!!
帰りは自分のトレースがあるので安心でしたが落とし穴はいたる所にあり
かなり苦労させられました。
次回天候次第でもう一度チャレンジしたいと思います。
今回の山行で実感が掴めたのと、女峰山の頂になんとしても立ってみたい気持ちがさらに高まったのです。
気持ちと体の調子を上げて、来るべき日のためにトレーニングに励みたいと思います。
さ~てと!
頑張るべ~てか~!!
2010年2月14日 栃木県日光 赤薙山~一里ヶ曽根 記録者 あっちゃん
今回は、霧降高原の駐車場から赤薙山~奥社跡~ヤハズ~一里ヶ曽根~女峰山を日帰りで踏破するべく
深夜3時に起床、
前夜から登山の準備を済ませ、装備を詰め込んだ愛車に乗り込み一路日光へ・・・・。
4時15分駐車場に到着。
まだ真っ暗な中ただ一人黙々と準備を済ませ
ヘッデンの明かりを頼りに歩き始めます。
ゲレンデ跡の急な斜面に息が上がり結構辛く
何と無く今日の体調はあまり良く無い様な気がして少し不安になり
下界の夜景の美しさに勝手に哀愁を感じ感動しつつも
この先の雪の状態が気になります。
ここ数日天気は荒れ模様で今日だけつかの間の晴れ間が期待出来そうとのこと、
予想では、適当な硬さの雪とその上にふんわりと乗っかった新雪の斜面を想像していたのですが
以外に最中状態の雪質で
この後大変な苦労が待って居ようとは思いもせず歩を進めます。
東の空が段々と赤く染まり空の雲の状態が目視出来始めたころ
町の夜景が色あせ、山の形がハッキリしてきます。
直感で「今日の天気が持つのはお昼までだな~。」と感じ行動時間を逆算して
早くも「今回は無理かもな~」と頭の中で自分と違う誰かが囁き
「そうかもね~。」と一人呟く自分がいました。(この時点でまだ赤薙山頂のずいぶん手前でした。)


6時50分赤薙山到着
下からスノーシュウを履いてきたのですがクラストした急斜面では歯が立たず
ズルズルと滑りかなり体力を消耗してしまい結構バテましたが
今年の西暦と同じ標高の2010メートル
今年は登ろうと考えていたので、誰もいない山頂で一人ニヤニヤしながら鳥居をパチリと一枚
小休止の後再び気合を入れ先を目指します。
この先は誰のトレースも無くルートの確認や不安定な足元に悩まされ遅々として距離が伸びず時間ばかりが過ぎて行きかなりテンションが下がります。
アイゼンに履き替えかなり危うい尾根筋を辿り樹林帯を潜り行くと
日向になる部分は表面が硬く比較的歩きやすいのですが
日陰の部分になるとたちまち脆くなり、場所によっては下腹部までもぐり
今まで経験したことの無いラッセルが始まります。
まるで、落とし穴様な雪の斜面はやる気と体力をどんどん自分の体から奪い取ってゆくのでした。
何度落ちたか忘れたころアクシデントが・・・・。
右足が取られた瞬間バランスを崩し、左足のケッツァの部分で自分の右足のフクラハギを蹴り飛ばしてしまい、右足に激痛が・・・。
ここは冷静にと自分に言い聞かせ暫く休んで様子を見たところ外傷も無く段々痛みも和らいできたので
先を目指すことに決め再び歩き始めます。


奥社跡で小休止してヤハズの痩せ尾根を通過
再び樹林帯に入り不規則で予測不能な落とし穴が何度も襲ってきます。
そしてまた同じところを蹴っ飛ばしてしまい思わず「ガッデム!!」「サノバビッチッ!!」と叫ぶ自分でした。
正直この時点でやる気0パーセント
せめて切のよい所で一里ヶ曽根までは行こうと思い
半ば気力だけで何とか辿り着きました。
時間は10時20分
目の前に女峰山が見えるのですが
夏道で約1時間
この状態だと良くて片道2時間半は掛かるだろうと思った時
今回は諦めることにしました。
暫く女峰山を眺めデッカイ声でリベンジを誓い帰路に着きました。


予想はしていたのですが雪山の女峰山は厳しかった!!
帰りは自分のトレースがあるので安心でしたが落とし穴はいたる所にあり
かなり苦労させられました。
次回天候次第でもう一度チャレンジしたいと思います。
今回の山行で実感が掴めたのと、女峰山の頂になんとしても立ってみたい気持ちがさらに高まったのです。
気持ちと体の調子を上げて、来るべき日のためにトレーニングに励みたいと思います。
さ~てと!
頑張るべ~てか~!!
タグ :栃木
2010年02月04日
那須縦走 プチ遭難
那須縦走
2010年1月31日 栃木県那須 茶臼岳~南月山~黒尾谷岳 記録者 あっちゃん
今回はクロヤスさんと二人で茶臼岳~南月山~黒尾谷岳と縦走してきました。
大丸温泉駐車場で支度をし、山を眺めながら検討したところ一般の登山道には先行者が多数居る様なので誰も歩いていないスキー場側の斜面を登り茶臼岳方面に登ることに決め真新しいトレースを刻みながら快調に高度を上げていきます。
下から眺めたときは山頂まで近いような気がしていたのですが急登を過ぎた先がだらだらの斜面で結構疲れました。


牛が首付近から茶臼岳を眺めるとなんとそこにはヨーロッパの山並みを思わせるような岩峰が青空に聳え立っており、暫し目を奪われるのでした。
那須にしてはこの時期に珍しい程の快晴美風で何とも心地よいお天気!
気分は最高です!


色んな話をしながら快調に歩を進め
程なく南月山頂へたどり着き木製ベンチに腰掛この後起こる非常事態も予期せぬまま美味しく山頂ラーメンを頂ながら談笑する二人でした。
食事も済んだころ俄かに靄が濃くなりどんどん視界がなくなっていきます。
そそくさと身支度を済ませ先を急ぐことに・・・・・・。
ここに一つの油断がありました。
南月山から黒尾谷岳までのルートを二人とも良く把握しておらず安直に尾根を辿れば辿り着けると思い込み斜面を降りたのですが当てにしていた目印も殆ど無く登山道は雪に埋もれどこなのかハッキリ確認できません。
しかも、靄が段々濃くなり展望が利かなくなり地図も良く確認しないままどんどん下って行ったのが運の尽き完全にロストしてしまい5回6回と行ったり来たりを繰り返し段々ドツボに嵌っていき、何とか黒尾谷岳山頂に辿りついた時はもう辺りは薄暗くなり
ヘッデンを点けての下山となりました。
しかし、ここからも苦難の下山!
まったく登山者がいないようでトレースは見当たらず頼りの目印も殆ど見当たらず何度も登山道からはずれトラバースを何度も繰り返しヘッデンの明かりを頼りに必死の下山を続けやっと、住宅街の明かりがちらほら見え少し安心しつつも苦難は続きます!
下山開始から約2時間半なんとか下山することが出来ました。
事前に良くルートを把握していなかったことが最大の敗因ですがもっと慎重に、そして小まめに現在位置と進むべき方向を確認して行動すべきだったと反省仕切りです!
急な斜面を下るときついつい楽な方へ降りてしまい勝ちですが一つ間違うと命とりになってしまう事もあるのだな~と今回のプチ遭難で思い知らされました。
これからは気持ちを入れ替えより慎重にルートファインデングをして行くように心掛けたいと思いました。
緊急ビバーク用の装備も良く検討していかないと万が一の時運命を左右することも身に染みて感じられ今回は良い反省材料になりました!
次回からはこんなことが無いように気を引き締めて楽しい山行を続けたいと思います!
クロヤスさん辛かったけど良い経験でしたね~!
また、よろぴく!!
さて、次はどこに行こうかな~!


2010年1月31日 栃木県那須 茶臼岳~南月山~黒尾谷岳 記録者 あっちゃん
今回はクロヤスさんと二人で茶臼岳~南月山~黒尾谷岳と縦走してきました。
大丸温泉駐車場で支度をし、山を眺めながら検討したところ一般の登山道には先行者が多数居る様なので誰も歩いていないスキー場側の斜面を登り茶臼岳方面に登ることに決め真新しいトレースを刻みながら快調に高度を上げていきます。
下から眺めたときは山頂まで近いような気がしていたのですが急登を過ぎた先がだらだらの斜面で結構疲れました。


牛が首付近から茶臼岳を眺めるとなんとそこにはヨーロッパの山並みを思わせるような岩峰が青空に聳え立っており、暫し目を奪われるのでした。
那須にしてはこの時期に珍しい程の快晴美風で何とも心地よいお天気!
気分は最高です!


色んな話をしながら快調に歩を進め
程なく南月山頂へたどり着き木製ベンチに腰掛この後起こる非常事態も予期せぬまま美味しく山頂ラーメンを頂ながら談笑する二人でした。
食事も済んだころ俄かに靄が濃くなりどんどん視界がなくなっていきます。
そそくさと身支度を済ませ先を急ぐことに・・・・・・。
ここに一つの油断がありました。
南月山から黒尾谷岳までのルートを二人とも良く把握しておらず安直に尾根を辿れば辿り着けると思い込み斜面を降りたのですが当てにしていた目印も殆ど無く登山道は雪に埋もれどこなのかハッキリ確認できません。
しかも、靄が段々濃くなり展望が利かなくなり地図も良く確認しないままどんどん下って行ったのが運の尽き完全にロストしてしまい5回6回と行ったり来たりを繰り返し段々ドツボに嵌っていき、何とか黒尾谷岳山頂に辿りついた時はもう辺りは薄暗くなり
ヘッデンを点けての下山となりました。
しかし、ここからも苦難の下山!
まったく登山者がいないようでトレースは見当たらず頼りの目印も殆ど見当たらず何度も登山道からはずれトラバースを何度も繰り返しヘッデンの明かりを頼りに必死の下山を続けやっと、住宅街の明かりがちらほら見え少し安心しつつも苦難は続きます!
下山開始から約2時間半なんとか下山することが出来ました。
事前に良くルートを把握していなかったことが最大の敗因ですがもっと慎重に、そして小まめに現在位置と進むべき方向を確認して行動すべきだったと反省仕切りです!
急な斜面を下るときついつい楽な方へ降りてしまい勝ちですが一つ間違うと命とりになってしまう事もあるのだな~と今回のプチ遭難で思い知らされました。
これからは気持ちを入れ替えより慎重にルートファインデングをして行くように心掛けたいと思いました。
緊急ビバーク用の装備も良く検討していかないと万が一の時運命を左右することも身に染みて感じられ今回は良い反省材料になりました!
次回からはこんなことが無いように気を引き締めて楽しい山行を続けたいと思います!
クロヤスさん辛かったけど良い経験でしたね~!
また、よろぴく!!
さて、次はどこに行こうかな~!


タグ :栃木
2010年01月28日
鶏鳴山(2010.1.24)
鶏鳴山
2010年1月24日(日) 栃木県日光市今市 記録者 やませみ
今日は栃木100名山、60座の鶏鳴山に登ってきました。
栃木県日光市(旧今市市)長畑地内に位置し標高961mの山です。
天気は快晴! 一路林道中井線を車止めへとしかし既に満車でした。
仕方なく少し戻り林道脇に車を止め、おにぎり・水をリュックに放り込み準備完了。 いざ、出発です。 時間は10時5分。



登山口の看板に『ご自由にお登りください。』の文字が? よく読んで見ると大手土木会社の名前が書いてありました。 納得です。私有地なんですね。少し行くと立派なログハウスが山の中に突如出現。たぶん会社の保養所なのでしょう。
程なく進むと登山道入口の小さな標識をみつけました。この標識のおかげでいつも迷わずに登ることができます。 設置している方に感謝!感謝!!です。 いつも思うのですがどんな方が設置してるんですかなね?
登りだしてしばらくは、手入れの行き届いた桧の林の中をすすみます。樹齢50~60年くらいはたつでしょうか? 登山道に差し込む木漏れ日がなんとも好い感じでした。
桧木立ををすぎたあたりから段々と急なガレ場が続きます。チョット気を抜くとズルズルと滑り落ちてしましそうな感じでした。
確か私の記憶だと2004年に女性の登山者が滑落し動けなくなってしまい防災へりに救助されたのがこの山だったような気がします。 登ってみて納得しました。
ガレ場(岩場)をぬけどんどん進んで行くと程なく頂上に。急に視界が開け西に日光連山、南に関東平野、筑波山ととてもすばらしい眺めでありました。 残念ながら霞が多く「富士山」は見えませんでした。
でも、チョットまてよ『 ここ、頂上??』
良く見ると山名板とみかげが見当たりません。そんなこんなで山頂探し! さらに2~3分程進んだところに961mのピークがありました。 あったー! あったー!! (笑) ご年配の方が山頂だと思い先程の眺めの良いところでお昼を食べていたので帰りがけに教えてあげました。
私もおにぎりをほうばり少しやすんでから、来た道を滑り落ちないように下山しました。



帰り道にすれ違った登山者12名、登山犬1匹(ノーリードでした。) 結構人気あるのですね。
程よく汗をかき車止めに到着! 帰り道に鹿沼温泉(旧ウエルサンピア)により疲れを癒して帰路につきました
2010年1月24日(日) 栃木県日光市今市 記録者 やませみ
今日は栃木100名山、60座の鶏鳴山に登ってきました。
栃木県日光市(旧今市市)長畑地内に位置し標高961mの山です。
天気は快晴! 一路林道中井線を車止めへとしかし既に満車でした。
仕方なく少し戻り林道脇に車を止め、おにぎり・水をリュックに放り込み準備完了。 いざ、出発です。 時間は10時5分。



登山口の看板に『ご自由にお登りください。』の文字が? よく読んで見ると大手土木会社の名前が書いてありました。 納得です。私有地なんですね。少し行くと立派なログハウスが山の中に突如出現。たぶん会社の保養所なのでしょう。
程なく進むと登山道入口の小さな標識をみつけました。この標識のおかげでいつも迷わずに登ることができます。 設置している方に感謝!感謝!!です。 いつも思うのですがどんな方が設置してるんですかなね?
登りだしてしばらくは、手入れの行き届いた桧の林の中をすすみます。樹齢50~60年くらいはたつでしょうか? 登山道に差し込む木漏れ日がなんとも好い感じでした。
桧木立ををすぎたあたりから段々と急なガレ場が続きます。チョット気を抜くとズルズルと滑り落ちてしましそうな感じでした。
確か私の記憶だと2004年に女性の登山者が滑落し動けなくなってしまい防災へりに救助されたのがこの山だったような気がします。 登ってみて納得しました。
ガレ場(岩場)をぬけどんどん進んで行くと程なく頂上に。急に視界が開け西に日光連山、南に関東平野、筑波山ととてもすばらしい眺めでありました。 残念ながら霞が多く「富士山」は見えませんでした。
でも、チョットまてよ『 ここ、頂上??』
良く見ると山名板とみかげが見当たりません。そんなこんなで山頂探し! さらに2~3分程進んだところに961mのピークがありました。 あったー! あったー!! (笑) ご年配の方が山頂だと思い先程の眺めの良いところでお昼を食べていたので帰りがけに教えてあげました。
私もおにぎりをほうばり少しやすんでから、来た道を滑り落ちないように下山しました。



帰り道にすれ違った登山者12名、登山犬1匹(ノーリードでした。) 結構人気あるのですね。
程よく汗をかき車止めに到着! 帰り道に鹿沼温泉(旧ウエルサンピア)により疲れを癒して帰路につきました
タグ :栃木
2010年01月26日
小田代ヶ原スノーシュートレッキング
小田代ヶ原スノーシュートレッキング
2010年1月11日 栃木県奥日光 記録者 じっちゃん
正月明け初めての3連休。
正月はどこも行かなかったからどこかで体を動かそう(そう言えば初詣もして居なかった。笑)と副隊長にメールを入れると副隊長も連休は隊長に振られたらしく日光へ行こうとなった次第であります。
話が変わりますが昨年から隊長や副隊長達と冬の雪山遊びをし始めたのには訳があるのです。
毎年晩秋まできのこきのこと山を駆け回っていて秋に体が最高潮になるのですがその後がいけません。
冬の間は近くの山に月一でハイキングに行く程度であとの休みは炬燵の番人になる始末、そんなある年に・・・・・・。
渓のシーズン始まりの7月、念願叶って憧れの早出川へ渓の翁こと瀬畑雄三氏との釣行が決まり先発隊として1日早く入渓したは良いが私の体調不良と言うか体力不足から皆と1夜を共に出来ず撤退をした苦い経験がありました。
やはり年とともに体力の衰えは激しく春の山菜からでは渓シーズン始まりまでに取り戻せなくなって来たのです。
そこで冬の間のトレーニングとして雪山遊びをする事にしたのでありました。
そんな訳で今年最初の雪山登山を日光の高山に白羽の矢を立ていざ出発しましたが情報不足で建てたいい加減な計画のだったため当日問題が発生。
急遽小田代ヶ原に変更と相成った訳でありました。
今回は湯川に沿って小田代を目指し1週して戻る事に。
川沿いの樹林帯は昨日新雪のお陰で動物たちの足跡がくっきり残りとてもいい足跡観察会になりました。
その後は昨日の雪と風のお陰で人の足跡がすべて消えた雪原を2人で小田代の貴婦人を撮るベストスポットまで今日初めてのトレースを付けて歩けました。
帰りは小田城を1週するように別ルートでもどり湯川沿いを登り返して車まで戻り本日のスノーシュートレッキング終了。
シーズン最初にしてはとても楽しくいい足慣らしになったトレッキングでありました。
副隊長ありがとう。またよろしく。



2010年1月11日 栃木県奥日光 記録者 じっちゃん
正月明け初めての3連休。
正月はどこも行かなかったからどこかで体を動かそう(そう言えば初詣もして居なかった。笑)と副隊長にメールを入れると副隊長も連休は隊長に振られたらしく日光へ行こうとなった次第であります。
話が変わりますが昨年から隊長や副隊長達と冬の雪山遊びをし始めたのには訳があるのです。
毎年晩秋まできのこきのこと山を駆け回っていて秋に体が最高潮になるのですがその後がいけません。
冬の間は近くの山に月一でハイキングに行く程度であとの休みは炬燵の番人になる始末、そんなある年に・・・・・・。
渓のシーズン始まりの7月、念願叶って憧れの早出川へ渓の翁こと瀬畑雄三氏との釣行が決まり先発隊として1日早く入渓したは良いが私の体調不良と言うか体力不足から皆と1夜を共に出来ず撤退をした苦い経験がありました。
やはり年とともに体力の衰えは激しく春の山菜からでは渓シーズン始まりまでに取り戻せなくなって来たのです。
そこで冬の間のトレーニングとして雪山遊びをする事にしたのでありました。
そんな訳で今年最初の雪山登山を日光の高山に白羽の矢を立ていざ出発しましたが情報不足で建てたいい加減な計画のだったため当日問題が発生。
急遽小田代ヶ原に変更と相成った訳でありました。
今回は湯川に沿って小田代を目指し1週して戻る事に。
川沿いの樹林帯は昨日新雪のお陰で動物たちの足跡がくっきり残りとてもいい足跡観察会になりました。
その後は昨日の雪と風のお陰で人の足跡がすべて消えた雪原を2人で小田代の貴婦人を撮るベストスポットまで今日初めてのトレースを付けて歩けました。
帰りは小田城を1週するように別ルートでもどり湯川沿いを登り返して車まで戻り本日のスノーシュートレッキング終了。
シーズン最初にしてはとても楽しくいい足慣らしになったトレッキングでありました。
副隊長ありがとう。またよろしく。



タグ :栃木
2010年01月18日
山王帽子山
山王帽子山
2010年1月17日 栃木県日光市 山王帽子山 記録者 あっちゃん
 今回は山王帽子山に行ってきました。
今回は山王帽子山に行ってきました。
ハイシーズンは観光客で賑わう光徳牧場もさすがにこの季節は人も疎らで
気温マイナス8度の雪景色!
クロスカントリーのコースもあり
やや明るめの樹林帯を縫うように登山道をひた歩きます。
適当に締まってサラッとした雪の感触がスノーシューから伝わって
何とも言えない気持ちの高揚感がたまりません!!
暫くトレースを辿って登山口まで来ると
なんと美味しい風景でしょう!
まっさらな雪だけで誰のトレースもありません。
ラッセルマニアの自分としては最高のシチュエーションであります。


あまり展望の開けたポイントは少ないのですが
時折見える戦場ヶ原や男体山を眺めながら快調に歩を進め
深い雪に汗をかきながら約3時間半ほどで山頂へたどり着き小休止
軽く山頂ラーメンとオニギリを食べ下山しました。
静寂な雪山の自然と仲間との楽しい会話
豪勢じゃないけど旨い飯
なんて、楽しい遊びなんでしょうか!!
改めて思いました!
今度はどこに行こうかな!
2010年1月17日 栃木県日光市 山王帽子山 記録者 あっちゃん
 今回は山王帽子山に行ってきました。
今回は山王帽子山に行ってきました。ハイシーズンは観光客で賑わう光徳牧場もさすがにこの季節は人も疎らで
気温マイナス8度の雪景色!
クロスカントリーのコースもあり
やや明るめの樹林帯を縫うように登山道をひた歩きます。
適当に締まってサラッとした雪の感触がスノーシューから伝わって
何とも言えない気持ちの高揚感がたまりません!!
暫くトレースを辿って登山口まで来ると
なんと美味しい風景でしょう!
まっさらな雪だけで誰のトレースもありません。
ラッセルマニアの自分としては最高のシチュエーションであります。


あまり展望の開けたポイントは少ないのですが
時折見える戦場ヶ原や男体山を眺めながら快調に歩を進め
深い雪に汗をかきながら約3時間半ほどで山頂へたどり着き小休止
軽く山頂ラーメンとオニギリを食べ下山しました。
静寂な雪山の自然と仲間との楽しい会話
豪勢じゃないけど旨い飯
なんて、楽しい遊びなんでしょうか!!
改めて思いました!
今度はどこに行こうかな!
タグ :栃木
2010年01月05日
鶏頂山(2010.1.3)
あけおめことよろで初ラッセル
2010年1月3日 栃木県 鶏頂山 記録者 あっちゃん
皆様 明けましておめでとうございます。
年末から年始に掛けての強い冬型の気圧配置により全国各地で大荒れの天気となり
たぶんにもれず栃木の山々も大分白く雪化粧をして朝日に輝いております。
また、今年も待望のラッセルの季節がやってまいりました!
てなわけで、いそいそと鶏頂山へ今年の初ラッセルをしに出かけてきました。
今年は自分達が初登山者のようで
目の前にはまっさらな雪の斜面が広がり
気分は盛り上がります。


♪愉快なラッセル
楽しいラッセル
ラッセル ラッセル♪
途中目印が積雪のため見つからず登山道からはずれ
股下ぐらいのラッセルを交代しながら尾根に向かい
いい汗を流しながら長いアルバイトをしてしまいましたが
なんとか山頂に到着。


曇り勝ちの天気でしたが
山頂付近に差し掛かるころには回復し
素晴らしい景色を堪能して下山しました。
今回は新しい仲間も加わりとても充実した山となりました。
これから、雪山のベストシーズンです。
安全に楽しく山行する為にも日々のトレーニングを怠らずに
励みたいと思います。
さて、次はどこに行こうかな~!!


2010年1月3日 栃木県 鶏頂山 記録者 あっちゃん
皆様 明けましておめでとうございます。
年末から年始に掛けての強い冬型の気圧配置により全国各地で大荒れの天気となり
たぶんにもれず栃木の山々も大分白く雪化粧をして朝日に輝いております。
また、今年も待望のラッセルの季節がやってまいりました!
てなわけで、いそいそと鶏頂山へ今年の初ラッセルをしに出かけてきました。
今年は自分達が初登山者のようで
目の前にはまっさらな雪の斜面が広がり
気分は盛り上がります。


♪愉快なラッセル
楽しいラッセル
ラッセル ラッセル♪
途中目印が積雪のため見つからず登山道からはずれ
股下ぐらいのラッセルを交代しながら尾根に向かい
いい汗を流しながら長いアルバイトをしてしまいましたが
なんとか山頂に到着。


曇り勝ちの天気でしたが
山頂付近に差し掛かるころには回復し
素晴らしい景色を堪能して下山しました。
今回は新しい仲間も加わりとても充実した山となりました。
これから、雪山のベストシーズンです。
安全に楽しく山行する為にも日々のトレーニングを怠らずに
励みたいと思います。
さて、次はどこに行こうかな~!!


タグ :栃木
2010年01月01日
男抱山(2010.01.01)
恒例・ご来光
2010年1月1日 栃木県宇都宮市 男抱山 記録者 副隊長
今年で4回目になる新年ご来光登山。
息子佑次郎が3年生の時に「元旦に初日の出を見に行こう!」と計画したものの
年明けの天気が悪く中止となり1年延期となった。当初の登山は古賀志山だった
のだが、考えてみたらかなり込み合いそうな山ではあった。
一年の延期の間に低山ハイキングを繰り返したぺんぎん隊は転んでも只は起きない。
山頂からの展望に東が開けている山、そして手軽に登れる山をちゃんと記憶に残して
いたのである。
念願叶って小学校4年から今年で連続4回目のご来光登山となる男抱山。
ご来光の瞬間は筆舌に尽くし難いものがあり、ここにいくら書いたところで
伝わるものでは無いのだが、登山記には成り得ない超低山ハイキングのこの
山ではご来光を表現するしかないわけで、拙い表現と画像でお伝え致します。(笑)
この山からは遥か東に八溝の山々までズ~ッと平野続き、それ故に眺めが良い。
海無し栃木県としては水平線からの日の出は望むべくも無く、遥か八溝のてっ辺から
顔を覗かすご来光が最上と言っても良い。
さて、朝6時過ぎに登山口に到着したぺんぎん隊、ヘッ電を点けて登山道に進む。
急登に喘ぎながらも空が白みだし八溝の空がオレンジグラデーションに彩られる。
登山口から山頂まで30分行程の山、この時期の日の出時刻は6:52頃であるから
山頂に急いだところで30分近くの待機時間があるのだが、日の出まで刻々と変わる
東の空の模様は飽きる事が無い。


八溝の山々の縁取りがオレンジ色に燃え始める。その中の一か所だけが一層明る
く輝き始め天に向かって後光が射し始めるといよいよご来光だ。
チョンと破れた一点から強烈な光が射したかと思うとズンズンズンズンと休むことなく
太陽が昇り、凡そ1分間の豪華なショーが始まる。
ご来光を拝んだ瞬間に「あれを祈ろう!」「これをお願いしよう!」と考えていた事も
全く忘れて只々その光景に魅了されてしまう。
強烈な光に眩んだ瞳を西へと転じれば霊峰富士の真っ白な姿が目に飛び込んで来る。
「こいつは春から縁起がいいわい!」と喜ぶ親子は純日本人か・・・(笑)


 郊外の低山から我が町越しにご来光を拝む元日の朝
郊外の低山から我が町越しにご来光を拝む元日の朝
この光景が思い出として息子の記憶に残ってくれたら・・・私が初日の出に祈り損ねた
願いもこれで4年目、来年こそは忘れずにお願いしなくちゃね。
2010年1月1日 栃木県宇都宮市 男抱山 記録者 副隊長
今年で4回目になる新年ご来光登山。
息子佑次郎が3年生の時に「元旦に初日の出を見に行こう!」と計画したものの
年明けの天気が悪く中止となり1年延期となった。当初の登山は古賀志山だった
のだが、考えてみたらかなり込み合いそうな山ではあった。
一年の延期の間に低山ハイキングを繰り返したぺんぎん隊は転んでも只は起きない。
山頂からの展望に東が開けている山、そして手軽に登れる山をちゃんと記憶に残して
いたのである。
念願叶って小学校4年から今年で連続4回目のご来光登山となる男抱山。
ご来光の瞬間は筆舌に尽くし難いものがあり、ここにいくら書いたところで
伝わるものでは無いのだが、登山記には成り得ない超低山ハイキングのこの
山ではご来光を表現するしかないわけで、拙い表現と画像でお伝え致します。(笑)
この山からは遥か東に八溝の山々までズ~ッと平野続き、それ故に眺めが良い。
海無し栃木県としては水平線からの日の出は望むべくも無く、遥か八溝のてっ辺から
顔を覗かすご来光が最上と言っても良い。
さて、朝6時過ぎに登山口に到着したぺんぎん隊、ヘッ電を点けて登山道に進む。
急登に喘ぎながらも空が白みだし八溝の空がオレンジグラデーションに彩られる。
登山口から山頂まで30分行程の山、この時期の日の出時刻は6:52頃であるから
山頂に急いだところで30分近くの待機時間があるのだが、日の出まで刻々と変わる
東の空の模様は飽きる事が無い。


八溝の山々の縁取りがオレンジ色に燃え始める。その中の一か所だけが一層明る
く輝き始め天に向かって後光が射し始めるといよいよご来光だ。
チョンと破れた一点から強烈な光が射したかと思うとズンズンズンズンと休むことなく
太陽が昇り、凡そ1分間の豪華なショーが始まる。
ご来光を拝んだ瞬間に「あれを祈ろう!」「これをお願いしよう!」と考えていた事も
全く忘れて只々その光景に魅了されてしまう。
強烈な光に眩んだ瞳を西へと転じれば霊峰富士の真っ白な姿が目に飛び込んで来る。
「こいつは春から縁起がいいわい!」と喜ぶ親子は純日本人か・・・(笑)


 郊外の低山から我が町越しにご来光を拝む元日の朝
郊外の低山から我が町越しにご来光を拝む元日の朝この光景が思い出として息子の記憶に残ってくれたら・・・私が初日の出に祈り損ねた
願いもこれで4年目、来年こそは忘れずにお願いしなくちゃね。
タグ :栃木
2009年12月23日
前白根山(2009.12.20)
前白根山
2009年12月20日 栃木県日光市 前白根山 記録者 あっちゃん
今期初雪山登山してきました。
予定は菅沼から奥白根でしたが
ここ2~3日の大雪で駐車場が埋まってしまい駐車スペースがありません。
入り口に3台止めてあったので奥をのぞいて見ると
テント泊の方が2人いたのでお話を伺って見たところ
前日にきて駐車スペースを確保するのにほぼ一日スコップで雪かきをして疲れたので
一晩ゆっくりして今から登山開始とのこと
良く周りを見渡すと40センチ~60センチぐらい積もっていて
スコップも持参していない自分達はとても太刀打ちできません。
仕方ないので来た道を引き返し日光湯元温泉へ
前白根山を目指すことにしました。
湯元スキー場駐車場には14~5名に団体登山隊が出発の準備をしており
時間的に遅れてきた自分達はその後を追う様に出発


スキー場の脇を歩き暫くして登山道へ
大雪のためほとんど踏跡はなくなりいきなりのハードなラッセル!!
体はキツイのですがなんだか楽しい気持ちになり今季初ラッセルを楽しめました。
団体さんは途中で下山したため
その後はトレース無しの雪道を辛くも楽しいラッセルで踏破し
前白根山のピークに立つことができ
大満足の今期初雪山山行になりました。


天候が荒れ気味でとても寒かったのですが
山頂付近は見事に晴れ渡り360度の素晴らしい眺めを堪能することができました!
今度はどこに行こうかな~


片山さんの富士山での事故はとても残念に思います。
あれだけ場数を踏んできた人たちでさへ自然の猛威に対処し切れないのですから。
「人の振り見て我が振り直せ」
じゃ無いですけど
素人の自分なりに十分に気をつけて今後の山行に臨みたいと思います。
2009年12月20日 栃木県日光市 前白根山 記録者 あっちゃん
今期初雪山登山してきました。
予定は菅沼から奥白根でしたが
ここ2~3日の大雪で駐車場が埋まってしまい駐車スペースがありません。
入り口に3台止めてあったので奥をのぞいて見ると
テント泊の方が2人いたのでお話を伺って見たところ
前日にきて駐車スペースを確保するのにほぼ一日スコップで雪かきをして疲れたので
一晩ゆっくりして今から登山開始とのこと
良く周りを見渡すと40センチ~60センチぐらい積もっていて
スコップも持参していない自分達はとても太刀打ちできません。
仕方ないので来た道を引き返し日光湯元温泉へ
前白根山を目指すことにしました。
湯元スキー場駐車場には14~5名に団体登山隊が出発の準備をしており
時間的に遅れてきた自分達はその後を追う様に出発


スキー場の脇を歩き暫くして登山道へ
大雪のためほとんど踏跡はなくなりいきなりのハードなラッセル!!
体はキツイのですがなんだか楽しい気持ちになり今季初ラッセルを楽しめました。
団体さんは途中で下山したため
その後はトレース無しの雪道を辛くも楽しいラッセルで踏破し
前白根山のピークに立つことができ
大満足の今期初雪山山行になりました。


天候が荒れ気味でとても寒かったのですが
山頂付近は見事に晴れ渡り360度の素晴らしい眺めを堪能することができました!
今度はどこに行こうかな~


片山さんの富士山での事故はとても残念に思います。
あれだけ場数を踏んできた人たちでさへ自然の猛威に対処し切れないのですから。
「人の振り見て我が振り直せ」
じゃ無いですけど
素人の自分なりに十分に気をつけて今後の山行に臨みたいと思います。
タグ :栃木
2009年12月20日
猪倉山・多気山(2009.12.20)
城山巡り
2009年12月20日 栃木県日光宇都宮 小倉山・猪倉山・多気山 記録者 副隊長
今日も家に居るのことに気が引けるくらい天気が良い。隊長は折悪しく部活、それも午前10時から午後3時という誠に中途半端な時間。午前なら午前、午後なら午後とはっきり区切った指導は出来ないものかと顧問の先生に一言申したい気分である。
まあそんな愚痴を言ったところで事態は好転しないので一人で外出の仕度を始める。図書館に本を返しがてら年末年始に読む本を何かを見つくろって来よう。そんな気持ちで車を走らせたのは良いが余りにも山が綺麗に見えて思わずハンドルを切り車は自然と郊外に向かっていた。
特に何処とも決めたわけでもなかったが、ふと先日登った板橋城址城山を思い出し、あの時に目にした猪倉城址というのを見てみようと決めた。もう一つの小倉城址の方はこの間仕事の合間に登って来ていたのでこの場を借りて合わせてご紹介しよう。
小倉城址の城山は例弊紙街道JR日光線文挟駅前から左折し車窓左手に見える城山を目指して車を走らせ5分ほどで案内板が立つ登山口に着く。
植林されたスギ林を登り途中丸太で組んだ階段を上り切ると本丸跡の山頂に着く。スギ林に囲まれ展望は無く、木々の間から板橋城址城山が見えるくらい。
本丸跡の周辺にはお堀の跡らしき溝や見張り用の台地らしきものが見えるが詳しくは分からず周辺を散歩して下山して来た。


さて続いて猪倉城址城山。こちらは県道宇都宮大沢線を走り猪倉山泉福寺の看板をお寺目掛けて進む。登山口はお寺の本堂前左にある階段を上ったところから始まる。うっそうとしたスギ林の中を黙々と登る。九十九折れに登って行く登山道の途中のあちらこちらに小広い平坦な場所が有る。山城の見張り場の様な所なのかも知れず、そこの一つに立ってみたら登って来た登山道は一目瞭然。城山を攻めて来る敵を迎え撃つには格好の構造になっている気がする。まあ、その辺は全然「城山」というものに詳しく無いので勝手な推測。
お寺の境内からものの30分もかからずに「此処に猪倉城ありき」という石碑に到着。その上のピークが猪倉山の山頂である。


この二つを同じ日に回るとして移動時間も含めて2時間もあれば足りそう。先日の板橋城址城山がこの二つの山の中間にあるので3つを合わせて登って半日といったところか・・・。
今日の場合は猪倉山の45分ほどの散歩しか無いのでついでと言ったら申し訳ないが帰りがけに宇都宮大沢線を国道293号で右折して栃木100名山の一つでもある多気山に寄って来た。
多気山も戦国時代の山城として知られ山全体あちらこちらに土塁や空堀の遺構が散見出来ると言われている。まあ私の場合「城山つながり」といった具合で立ち寄ったまでで、その詳細などには全然詳しく無い。
多気不動尊の赤い鳥居をくぐり山道を車で上がる。ものの1~2分でお茶屋前の大きな駐車場に着くのでそこから登山を始める。
スギ林とヒノキ林のだらだらの山道を登る。ところどころにやはり見張り場であろうか平坦な部分が登山道を挟んで設けられている。途中、崩れかけた石段を登り雑木林が見えて来ると山頂も近い。
山頂は本丸跡であろう大きな平坦地になっていて日当たりが良い。平たん部を抜けて雑木林の中を進むと多気山三角点のあるピークに出る。終始展望は余り良く無い。


こんな具合に「城山つながり」で山を歩いてみたが、展望が良いのは以前に紹介した板橋城址のみで他の3つは展望が無い。ただ山城の城址として興味が有る方にはかなり探検心を掻き立てる山だとは思う。登山道をちょっと脇に入ると空堀や石垣・土塁などが見つかるので面白い。
城址を詳しく調べるのは別として紹介した4つの山を登るのは車があれば1日で全部回れる。
2009年12月20日 栃木県日光宇都宮 小倉山・猪倉山・多気山 記録者 副隊長
今日も家に居るのことに気が引けるくらい天気が良い。隊長は折悪しく部活、それも午前10時から午後3時という誠に中途半端な時間。午前なら午前、午後なら午後とはっきり区切った指導は出来ないものかと顧問の先生に一言申したい気分である。
まあそんな愚痴を言ったところで事態は好転しないので一人で外出の仕度を始める。図書館に本を返しがてら年末年始に読む本を何かを見つくろって来よう。そんな気持ちで車を走らせたのは良いが余りにも山が綺麗に見えて思わずハンドルを切り車は自然と郊外に向かっていた。
特に何処とも決めたわけでもなかったが、ふと先日登った板橋城址城山を思い出し、あの時に目にした猪倉城址というのを見てみようと決めた。もう一つの小倉城址の方はこの間仕事の合間に登って来ていたのでこの場を借りて合わせてご紹介しよう。
小倉城址の城山は例弊紙街道JR日光線文挟駅前から左折し車窓左手に見える城山を目指して車を走らせ5分ほどで案内板が立つ登山口に着く。
植林されたスギ林を登り途中丸太で組んだ階段を上り切ると本丸跡の山頂に着く。スギ林に囲まれ展望は無く、木々の間から板橋城址城山が見えるくらい。
本丸跡の周辺にはお堀の跡らしき溝や見張り用の台地らしきものが見えるが詳しくは分からず周辺を散歩して下山して来た。


さて続いて猪倉城址城山。こちらは県道宇都宮大沢線を走り猪倉山泉福寺の看板をお寺目掛けて進む。登山口はお寺の本堂前左にある階段を上ったところから始まる。うっそうとしたスギ林の中を黙々と登る。九十九折れに登って行く登山道の途中のあちらこちらに小広い平坦な場所が有る。山城の見張り場の様な所なのかも知れず、そこの一つに立ってみたら登って来た登山道は一目瞭然。城山を攻めて来る敵を迎え撃つには格好の構造になっている気がする。まあ、その辺は全然「城山」というものに詳しく無いので勝手な推測。
お寺の境内からものの30分もかからずに「此処に猪倉城ありき」という石碑に到着。その上のピークが猪倉山の山頂である。


この二つを同じ日に回るとして移動時間も含めて2時間もあれば足りそう。先日の板橋城址城山がこの二つの山の中間にあるので3つを合わせて登って半日といったところか・・・。
今日の場合は猪倉山の45分ほどの散歩しか無いのでついでと言ったら申し訳ないが帰りがけに宇都宮大沢線を国道293号で右折して栃木100名山の一つでもある多気山に寄って来た。
多気山も戦国時代の山城として知られ山全体あちらこちらに土塁や空堀の遺構が散見出来ると言われている。まあ私の場合「城山つながり」といった具合で立ち寄ったまでで、その詳細などには全然詳しく無い。
多気不動尊の赤い鳥居をくぐり山道を車で上がる。ものの1~2分でお茶屋前の大きな駐車場に着くのでそこから登山を始める。
スギ林とヒノキ林のだらだらの山道を登る。ところどころにやはり見張り場であろうか平坦な部分が登山道を挟んで設けられている。途中、崩れかけた石段を登り雑木林が見えて来ると山頂も近い。
山頂は本丸跡であろう大きな平坦地になっていて日当たりが良い。平たん部を抜けて雑木林の中を進むと多気山三角点のあるピークに出る。終始展望は余り良く無い。


こんな具合に「城山つながり」で山を歩いてみたが、展望が良いのは以前に紹介した板橋城址のみで他の3つは展望が無い。ただ山城の城址として興味が有る方にはかなり探検心を掻き立てる山だとは思う。登山道をちょっと脇に入ると空堀や石垣・土塁などが見つかるので面白い。
城址を詳しく調べるのは別として紹介した4つの山を登るのは車があれば1日で全部回れる。
タグ :栃木
2009年12月16日
社山(2009.12.13)
社山
2009年12月13日 栃木県日光 社山 記録者 はら坊
一週間の疲れが溜まりに溜まって一日中ゴロゴロ寝ていた土曜日の夕方、副隊長からメールが入った。
『明日空いてる?』
『空いてます。』
『近場で何処か行く?』
ってな感じで日光中禅寺湖の畔に在る社山に行く事になった。
その後の会話も色々あったが、長くなるので省略する事にする。
社山{しゃざん}と言うらしい『随分と神々しい名前だな~。シャザンオールスターズ』などとボケてみるものの反応は中禅寺湖の水くらい冷たい。寒さも余計に身にしみる。
神々しい名前に胸が高鳴る・・・じゃなく湖畔の遊歩道でもう心臓がバクバクで高鳴るのは心拍数だ。
 遊歩道から見える社山の頂は、勿論雪。
遊歩道から見える社山の頂は、勿論雪。
尾根ずたいの登山である事は、下から見ても分かる。
何処と無く赤城山の黒檜山を思わせる佇まいである。
途中男体山が湖に映り込み逆さ冨士ならぬ逆さ男体山を見せてくれた。
副隊長も言っていたが、~富士という名が付いていないのが不思議なくらいだ。
やっと登山道入り口に到着。って先週も言っていたが、標高差が無いので全然楽な筈だが疲れが溜まった体には結構こたえる。


第一のピークに立つと榛名山の掃部ヶ岳からの眺めに似ている。
と言っても此方は、かなりのラージ版である。
 尾根ずたいを歩いていると、足尾側には木が無く、中禅寺湖側には木が生えている。副隊長が言うには、銅山の鉛害の傷跡らしい。
尾根ずたいを歩いていると、足尾側には木が無く、中禅寺湖側には木が生えている。副隊長が言うには、銅山の鉛害の傷跡らしい。
この尾根を挟んで足尾側では、鉱夫たちが身を削り働いて居たのであろう。その北側の中禅寺湖側では、名だたるヨーロッパの貴族たちが余暇を満喫していたのであろう。何だか複雑な気分であったが、展望はと言うともう最高であった。関東平野は雲の中だった物の中禅寺湖側は男体山~白根までくっきりと見える。
が、まだ山頂には到着はしていないのだ。
あそこが山頂だ・・・っと三回くらい言った所でやっと山頂に到着した。
神々しい名前とは裏腹に祠も何も無い山頂だった。
山頂から少し先に行くと視界が開けてとても綺麗だった。副隊長と『あれが皇海山で、鋸山、んじゃあれが庚申山かな』などと先週行った山の位置を確認たりして見る。とても楽しいひと時である。
昼食には久し振りの山頂ラーメンとおむすびをたいらげ下山。
隊長と雪合戦をしながら下山したが、隊長の足取りは今年の両神山の雪の下山の時とは比べもんにならない位軽かった。


下山する時は登りとは別の景色が見えるから不思議だ。それを楽しみながら無事に下山し、イタリア大使館別荘を覗き込んで今回の山行も無事フィナーレとなった。
副隊長の日記は【続きを読む】へ
続きを読む
2009年12月13日 栃木県日光 社山 記録者 はら坊
一週間の疲れが溜まりに溜まって一日中ゴロゴロ寝ていた土曜日の夕方、副隊長からメールが入った。
『明日空いてる?』
『空いてます。』
『近場で何処か行く?』
ってな感じで日光中禅寺湖の畔に在る社山に行く事になった。
その後の会話も色々あったが、長くなるので省略する事にする。
社山{しゃざん}と言うらしい『随分と神々しい名前だな~。シャザンオールスターズ』などとボケてみるものの反応は中禅寺湖の水くらい冷たい。寒さも余計に身にしみる。
神々しい名前に胸が高鳴る・・・じゃなく湖畔の遊歩道でもう心臓がバクバクで高鳴るのは心拍数だ。
尾根ずたいの登山である事は、下から見ても分かる。
何処と無く赤城山の黒檜山を思わせる佇まいである。
途中男体山が湖に映り込み逆さ冨士ならぬ逆さ男体山を見せてくれた。
副隊長も言っていたが、~富士という名が付いていないのが不思議なくらいだ。
やっと登山道入り口に到着。って先週も言っていたが、標高差が無いので全然楽な筈だが疲れが溜まった体には結構こたえる。
第一のピークに立つと榛名山の掃部ヶ岳からの眺めに似ている。
と言っても此方は、かなりのラージ版である。
この尾根を挟んで足尾側では、鉱夫たちが身を削り働いて居たのであろう。その北側の中禅寺湖側では、名だたるヨーロッパの貴族たちが余暇を満喫していたのであろう。何だか複雑な気分であったが、展望はと言うともう最高であった。関東平野は雲の中だった物の中禅寺湖側は男体山~白根までくっきりと見える。
が、まだ山頂には到着はしていないのだ。
あそこが山頂だ・・・っと三回くらい言った所でやっと山頂に到着した。
神々しい名前とは裏腹に祠も何も無い山頂だった。
山頂から少し先に行くと視界が開けてとても綺麗だった。副隊長と『あれが皇海山で、鋸山、んじゃあれが庚申山かな』などと先週行った山の位置を確認たりして見る。とても楽しいひと時である。
昼食には久し振りの山頂ラーメンとおむすびをたいらげ下山。
隊長と雪合戦をしながら下山したが、隊長の足取りは今年の両神山の雪の下山の時とは比べもんにならない位軽かった。
下山する時は登りとは別の景色が見えるから不思議だ。それを楽しみながら無事に下山し、イタリア大使館別荘を覗き込んで今回の山行も無事フィナーレとなった。
副隊長の日記は【続きを読む】へ
続きを読む
タグ :栃木
2009年12月10日
城山(2009.11.29)
板橋城址「城山」
2009年11月29日 栃木県日光市板橋 城山 記録者 副隊長
思わぬ良い天気に誘われてて一人で里山を歩いている。里山の場所は日光市(旧今市市)の板橋地区。
確か二年ほど前の新聞で地元が登山道整備に力を入れて登山道が開かれたという記事を読んだ。その時に「ああ、山を切り開いてわざわざ登山道を新しく作るのかぁ、そのままじゃだめなのかなぁ・・・」と漠然とながらその功罪を考えたのがこの里山である。
 名前は「城山」(443m)で山頂には「板橋城跡」がある。宇都宮市そのものが城下町であるからなのか、いにしえの武将がこの辺りを戦略上で重要な地形と見定めたのか、宇都宮市近郊には山を城に見立てて砦の建築を施した「山城」というものが数か所ある。ここ「板橋城」もその一つで1504年から1520年にかけて宇都宮氏一族が築城し、小田原北条氏家臣の板橋氏の手を経て徳川一族へと城主が変遷して行ったという記録がある。時は戦国時代という古い歴史だ。(お城だから当たり前か・・・笑)
名前は「城山」(443m)で山頂には「板橋城跡」がある。宇都宮市そのものが城下町であるからなのか、いにしえの武将がこの辺りを戦略上で重要な地形と見定めたのか、宇都宮市近郊には山を城に見立てて砦の建築を施した「山城」というものが数か所ある。ここ「板橋城」もその一つで1504年から1520年にかけて宇都宮氏一族が築城し、小田原北条氏家臣の板橋氏の手を経て徳川一族へと城主が変遷して行ったという記録がある。時は戦国時代という古い歴史だ。(お城だから当たり前か・・・笑)
さて、現在に時間を戻して登山口から歩いて行く。等幅で綺麗に敷き詰められた砕石の小道を進むといきなり轍の跡がある幅広い林道に飛び出す。「???」と首を傾げながらも道標が指す「板橋城跡」を目指して進む。5分も歩くと小広い車止めに到着して本格的な登山道が始まる。
脇に小沢が流れる登山道はスギ林の奥に向かい緩やかな傾斜で一直線に進んで行く。突き当りから右に折れて丸太で組んだ階段が斜面をズンズン登って行く。私の場合この階段というのが登山で一番疲れる。何の事は無い休むタイミングが取りにくいというだけである。(笑)
約150mの標高差を階段8割で登り詰めると山頂直下の「天狗岩」との分岐に出る。山頂を優先に右に折れ斜面を登る。視線の先は青空が大きく開け東屋の屋根がちょこんと見えている。如何にも展望の良さを想像させる景色である。
 頂上に登り詰めると東屋の中に女性が二人座っていて外で男性が威勢よく両手を振り体操をしながら周囲の説明をしている。脇を通りながら軽く挨拶をすると小声で「あっちから登って来たんだねぇ・・・」という声が聞こえる。山頂は広く小さな窪みを挟んで全長50mほどの平坦な地形である。東屋を背に平たん部の先まで行ってみるとそちらにも登山道が有る事がわかった。どうやら彼女たちはこちらから登って来たらしい。
頂上に登り詰めると東屋の中に女性が二人座っていて外で男性が威勢よく両手を振り体操をしながら周囲の説明をしている。脇を通りながら軽く挨拶をすると小声で「あっちから登って来たんだねぇ・・・」という声が聞こえる。山頂は広く小さな窪みを挟んで全長50mほどの平坦な地形である。東屋を背に平たん部の先まで行ってみるとそちらにも登山道が有る事がわかった。どうやら彼女たちはこちらから登って来たらしい。
この山頂、周囲の眺めは良い。開けていないのは北東方面くらいで東に鞍掛山から古賀志山、鹿沼市街の展望を挟んで二股山などの鹿沼市近郊の山々から遠くは県南の山々、転じて男体山から大真名子・小真名子、女峰、赤薙と並び最後は鶏頂山や釈迦ケ岳・高原山が見える。
山頂にある「城山」の案内板には冒頭の歴史説明がもう少し詳細に記されていてその歴史を振り返りながら城主の如く周囲を見渡すのも面白い。
伐採新しい切り株に腰掛けてスケッチブックを開いてお絵かきを始める。隊長が居ない時の暇つぶしに始めたスケッチである。現地で下書きだけ済ませて帰宅後に暇を見て彩色しているが、本当なら現地で全て仕上げてしまえる腕になりたい願望はある。
 そうこうするうちに東屋脇に白杭が立っている事に気が付いた。「あれ?」と思うが早いか「これは三角点表示杭だよなぁ・・・」と気が付き寄り添うように頭だけ出している御影石に気が付く。「おお、これは三角点様、気が付くのが遅れて申し訳ありません!」と頭こそ下げないけれど敬礼をする。
そうこうするうちに東屋脇に白杭が立っている事に気が付いた。「あれ?」と思うが早いか「これは三角点表示杭だよなぁ・・・」と気が付き寄り添うように頭だけ出している御影石に気が付く。「おお、これは三角点様、気が付くのが遅れて申し訳ありません!」と頭こそ下げないけれど敬礼をする。
油断というのかそれこそ鼻から期待もしていなかった三角点の所在に嬉しさ倍増でカメラを構える。帰宅後に「点の記」を調べたら明治34年に選点されている三等三角点だった。
山頂で30分ほどあれこれと動き回り下山にかかる。帰路「天狗岩」なる物に一応興味を抱いて下山路を通り過ぎて南に進む。途中「畳石」という奇岩?を越えて「天狗岩」まで5分ほど。「天狗岩」はいにしえの物語曰く、「城山の危機に日光山の天狗が降り立った岩」との事でありました。(笑)
分岐まで引き返し往路を一気に下山。車止めを過ぎて林道を歩いている時に往路では気付かなかった異様な洞窟を目にして好奇心旺盛な中年オヤジは左手の斜面に取り付く。近くまで行くとその規則正しい四角形の洞穴から「ああ、大谷石の切り出し場かぁ・・・」と察しが付く。しかし大谷石の採石が盛んだった大谷町は古賀志山をは挟んだ向こう側であるから「こんなところまで・・・」と結構意外な思いではあった。
帰宅後、「城山」から「板橋城」というキーワードを得て少し調べてみたら「猪倉城」「小倉城」というのが近くに在る事がわかった。どちらも「板橋城」に並び当時は威勢を誇った様子が垣間見られる。突っ込んだ興味とまでは行かないが、機会が有ればこの二つの城址である里山を歩いてみたいと思う今回の登山だった。


2009年11月29日 栃木県日光市板橋 城山 記録者 副隊長
思わぬ良い天気に誘われてて一人で里山を歩いている。里山の場所は日光市(旧今市市)の板橋地区。
確か二年ほど前の新聞で地元が登山道整備に力を入れて登山道が開かれたという記事を読んだ。その時に「ああ、山を切り開いてわざわざ登山道を新しく作るのかぁ、そのままじゃだめなのかなぁ・・・」と漠然とながらその功罪を考えたのがこの里山である。
さて、現在に時間を戻して登山口から歩いて行く。等幅で綺麗に敷き詰められた砕石の小道を進むといきなり轍の跡がある幅広い林道に飛び出す。「???」と首を傾げながらも道標が指す「板橋城跡」を目指して進む。5分も歩くと小広い車止めに到着して本格的な登山道が始まる。
脇に小沢が流れる登山道はスギ林の奥に向かい緩やかな傾斜で一直線に進んで行く。突き当りから右に折れて丸太で組んだ階段が斜面をズンズン登って行く。私の場合この階段というのが登山で一番疲れる。何の事は無い休むタイミングが取りにくいというだけである。(笑)
約150mの標高差を階段8割で登り詰めると山頂直下の「天狗岩」との分岐に出る。山頂を優先に右に折れ斜面を登る。視線の先は青空が大きく開け東屋の屋根がちょこんと見えている。如何にも展望の良さを想像させる景色である。
この山頂、周囲の眺めは良い。開けていないのは北東方面くらいで東に鞍掛山から古賀志山、鹿沼市街の展望を挟んで二股山などの鹿沼市近郊の山々から遠くは県南の山々、転じて男体山から大真名子・小真名子、女峰、赤薙と並び最後は鶏頂山や釈迦ケ岳・高原山が見える。
山頂にある「城山」の案内板には冒頭の歴史説明がもう少し詳細に記されていてその歴史を振り返りながら城主の如く周囲を見渡すのも面白い。
伐採新しい切り株に腰掛けてスケッチブックを開いてお絵かきを始める。隊長が居ない時の暇つぶしに始めたスケッチである。現地で下書きだけ済ませて帰宅後に暇を見て彩色しているが、本当なら現地で全て仕上げてしまえる腕になりたい願望はある。
油断というのかそれこそ鼻から期待もしていなかった三角点の所在に嬉しさ倍増でカメラを構える。帰宅後に「点の記」を調べたら明治34年に選点されている三等三角点だった。
山頂で30分ほどあれこれと動き回り下山にかかる。帰路「天狗岩」なる物に一応興味を抱いて下山路を通り過ぎて南に進む。途中「畳石」という奇岩?を越えて「天狗岩」まで5分ほど。「天狗岩」はいにしえの物語曰く、「城山の危機に日光山の天狗が降り立った岩」との事でありました。(笑)
分岐まで引き返し往路を一気に下山。車止めを過ぎて林道を歩いている時に往路では気付かなかった異様な洞窟を目にして好奇心旺盛な中年オヤジは左手の斜面に取り付く。近くまで行くとその規則正しい四角形の洞穴から「ああ、大谷石の切り出し場かぁ・・・」と察しが付く。しかし大谷石の採石が盛んだった大谷町は古賀志山をは挟んだ向こう側であるから「こんなところまで・・・」と結構意外な思いではあった。
帰宅後、「城山」から「板橋城」というキーワードを得て少し調べてみたら「猪倉城」「小倉城」というのが近くに在る事がわかった。どちらも「板橋城」に並び当時は威勢を誇った様子が垣間見られる。突っ込んだ興味とまでは行かないが、機会が有ればこの二つの城址である里山を歩いてみたいと思う今回の登山だった。

タグ :栃木