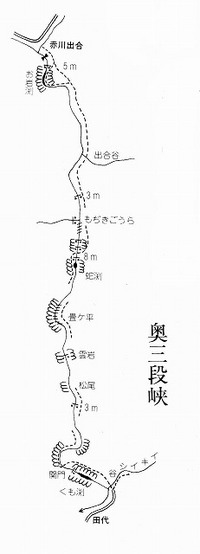2010年05月19日
安達太良山 山開き
山≦生ビール?
2010年5月16日 福島県 安達太良山 記録者 はら坊
山登りには色々な色々なスタンスが有ると思う。
本格的に高山を行く人や、低山ハイキングの延長線の人、最近流行のトレイルランナー、どれも山を愛し、登頂を目的としていると思う。
装備も技術もそれぞれだと思う。
だが我々釣屋の登山とは、山は愛しているが、登頂を目的としない。
目的はあくまで釣りであり、沢であり、岩魚である。
そんな我々が、最近山にはまり込んで来ている。
山とは言っても、低山から日帰りで行ける山である。
今回そんな釣屋3人が安達太良山の山開きにトライしてきた。
この話が来たのは1月の半ば、そんな先の予定など分かるはずも無い面々であった。
待ち遠しい気持ちを抑え、仕事が入らないことを祈り続けてきた。
皆そうであった筈だ。
私はどうしても登りたかった。
行かなければならない山であった。
そうそれは、故斉藤信之さんの故郷であり、何しろこの山を愛し毎日眺めていたに違いない場所であったから、どうしても登りたかった。
先週の男体山から少々風邪気味で、毎晩風邪薬を腹いっぱいに成るほど飲むも喉の痛みが直らず、体はダルイまま決行日前日になってしまった。
決行日前日には急な仕事が入ってしまっていたが、それも半日で片付けて準備に入る。
 はやる気持ちを抑えきれず、予定より早く副隊長と合流。
はやる気持ちを抑えきれず、予定より早く副隊長と合流。
しみたかさんとの待ち合わせ場所に向う。
こちらも早めの合流をして、安達太良山登山口を目指す。
二本松インターチェンジを目前にしみたかさんの口から
『そう言えば、アサヒビールの工場で生ビールが飲めるアサヒビール園が
あるんだ。ジンギスカンが美味しいかったんだ。』
と何気に餌をまく、それに源流の岩魚のごとく食いついたのが、副隊長である。
『うぉぉぉ~~~何時から?いくら?登るの止めてそっちに行く?』
そんな中チャッカリ携帯で情報を入手している私であった・・・
そんな話で盛り上がっていると、あっと言う間に登山口に到着、準備を早々にしていざ出発。だがこの早目の出発が後々後悔の種になる。
我々は普段から子供を連れ出して遊んでいる為、時間に相当な余裕を持つようになってしまっている。
まぁ~そのうち子供達に
『年寄り連れてるから、時間に余裕を持って・・・』
何て言われてしまうんだろうが・・・
登り始めて直ぐに沢を渡る。橋の上から沢を覗き込み、
『魚居るかな?』
『居そうだよね・・・』
『竿は・・・?』
『有るけど・・・餌は無いよ・・・』
沢水を見るとやはり釣屋の血が騒いでしまう・・・
山屋にはなりきれて居ない山屋モドキであった。
 登山道まで硫黄の香りが漂ってくる・・・
登山道まで硫黄の香りが漂ってくる・・・
臭いの方が良いのかな・・・?
副隊長が
『あれっ・・・隊長の臭いがする。』
などと冗談を飛ばす。
これは隊長と登った事のある人でないと分からない事で・・・
香りがお届けできないのが残念です。
さほど高度も稼がずに硫黄の香り漂う中くろがね小屋に到着。
到着目前に宿泊客のお見送りの歓声が上がる。
ここでしばし休憩・・・
この大自然のスケールはやはり写真では伝えきれない・・・
ここから急登に入り一気に高度を稼ぐ。
空の青さと岩の黒、雪渓の白と火山灰の赤茶色、それとなんと言っても硫黄の香り・・・
そんな大自然、地球の息吹が伝わって来る中あっと言う間に山頂に立った。
安達太良山山頂の文字が刻まれた柱より高い所に三角点がある最高地点があり、まずはそこに立った。
そこから私は、
 『斎藤さん見える?斎藤さんの故郷の山に立ったよ。』
『斎藤さん見える?斎藤さんの故郷の山に立ったよ。』
心の中で叫んでは見たもののきっとこの強風にかき消されてしまったかな。
でもきっと斎藤さんは、
『何でそんな所に居るんだ、そこは山スキーに行くとこだぞ。八久和に来い。八久和で岩魚たちと遊ばなくちゃ。今年は来いよ。』
そんな事を言われた気がした。
山頂では開山祝いの為、徐々に沢山の人達が集まって来た。
自衛隊の姿までもがあった。
ここで雪渓を駆け上がってくる冷たい強風の中1時間以上待つ事になった。
今朝の早出を始めて後悔したが後の祭り。安達太良開山祭りってな事で、岩陰で身を潜め風をかわすも山頂の風はアッチコッチから吹き付けてきて余り意味が無いが、時間まで我慢我慢・・・
漸く目的の一つ記念品のペナントを入手する。
目的の二つ目副隊長の知り合いの方々と記念撮影をして、最大の目的であるアサヒビール園に頭を切替える。
さ~て下山だ~・・・
車に付くや否や今度は、
 『温泉はどっちでもいいや・・・生・生・・・』
『温泉はどっちでもいいや・・・生・生・・・』
と言うまるでK上さんの様な副隊長を説得して温泉で汗を流し、生ビールへと向った一行であった。
しみたかさん運転ありがとう御座いました。
またお願いします。
2010年5月16日 福島県 安達太良山 記録者 はら坊
山登りには色々な色々なスタンスが有ると思う。
本格的に高山を行く人や、低山ハイキングの延長線の人、最近流行のトレイルランナー、どれも山を愛し、登頂を目的としていると思う。
装備も技術もそれぞれだと思う。
だが我々釣屋の登山とは、山は愛しているが、登頂を目的としない。
目的はあくまで釣りであり、沢であり、岩魚である。
そんな我々が、最近山にはまり込んで来ている。
山とは言っても、低山から日帰りで行ける山である。
今回そんな釣屋3人が安達太良山の山開きにトライしてきた。
この話が来たのは1月の半ば、そんな先の予定など分かるはずも無い面々であった。
待ち遠しい気持ちを抑え、仕事が入らないことを祈り続けてきた。
皆そうであった筈だ。
私はどうしても登りたかった。
行かなければならない山であった。
そうそれは、故斉藤信之さんの故郷であり、何しろこの山を愛し毎日眺めていたに違いない場所であったから、どうしても登りたかった。
先週の男体山から少々風邪気味で、毎晩風邪薬を腹いっぱいに成るほど飲むも喉の痛みが直らず、体はダルイまま決行日前日になってしまった。
決行日前日には急な仕事が入ってしまっていたが、それも半日で片付けて準備に入る。
 はやる気持ちを抑えきれず、予定より早く副隊長と合流。
はやる気持ちを抑えきれず、予定より早く副隊長と合流。しみたかさんとの待ち合わせ場所に向う。
こちらも早めの合流をして、安達太良山登山口を目指す。
二本松インターチェンジを目前にしみたかさんの口から
『そう言えば、アサヒビールの工場で生ビールが飲めるアサヒビール園が
あるんだ。ジンギスカンが美味しいかったんだ。』
と何気に餌をまく、それに源流の岩魚のごとく食いついたのが、副隊長である。
『うぉぉぉ~~~何時から?いくら?登るの止めてそっちに行く?』
そんな中チャッカリ携帯で情報を入手している私であった・・・
そんな話で盛り上がっていると、あっと言う間に登山口に到着、準備を早々にしていざ出発。だがこの早目の出発が後々後悔の種になる。
我々は普段から子供を連れ出して遊んでいる為、時間に相当な余裕を持つようになってしまっている。
まぁ~そのうち子供達に
『年寄り連れてるから、時間に余裕を持って・・・』
何て言われてしまうんだろうが・・・
登り始めて直ぐに沢を渡る。橋の上から沢を覗き込み、
『魚居るかな?』
『居そうだよね・・・』
『竿は・・・?』
『有るけど・・・餌は無いよ・・・』
沢水を見るとやはり釣屋の血が騒いでしまう・・・
山屋にはなりきれて居ない山屋モドキであった。
 登山道まで硫黄の香りが漂ってくる・・・
登山道まで硫黄の香りが漂ってくる・・・臭いの方が良いのかな・・・?
副隊長が
『あれっ・・・隊長の臭いがする。』
などと冗談を飛ばす。
これは隊長と登った事のある人でないと分からない事で・・・
香りがお届けできないのが残念です。
さほど高度も稼がずに硫黄の香り漂う中くろがね小屋に到着。
到着目前に宿泊客のお見送りの歓声が上がる。
ここでしばし休憩・・・
この大自然のスケールはやはり写真では伝えきれない・・・
ここから急登に入り一気に高度を稼ぐ。
空の青さと岩の黒、雪渓の白と火山灰の赤茶色、それとなんと言っても硫黄の香り・・・
そんな大自然、地球の息吹が伝わって来る中あっと言う間に山頂に立った。
安達太良山山頂の文字が刻まれた柱より高い所に三角点がある最高地点があり、まずはそこに立った。
そこから私は、
 『斎藤さん見える?斎藤さんの故郷の山に立ったよ。』
『斎藤さん見える?斎藤さんの故郷の山に立ったよ。』心の中で叫んでは見たもののきっとこの強風にかき消されてしまったかな。
でもきっと斎藤さんは、
『何でそんな所に居るんだ、そこは山スキーに行くとこだぞ。八久和に来い。八久和で岩魚たちと遊ばなくちゃ。今年は来いよ。』
そんな事を言われた気がした。
山頂では開山祝いの為、徐々に沢山の人達が集まって来た。
自衛隊の姿までもがあった。
ここで雪渓を駆け上がってくる冷たい強風の中1時間以上待つ事になった。
今朝の早出を始めて後悔したが後の祭り。安達太良開山祭りってな事で、岩陰で身を潜め風をかわすも山頂の風はアッチコッチから吹き付けてきて余り意味が無いが、時間まで我慢我慢・・・
漸く目的の一つ記念品のペナントを入手する。
目的の二つ目副隊長の知り合いの方々と記念撮影をして、最大の目的であるアサヒビール園に頭を切替える。
さ~て下山だ~・・・
車に付くや否や今度は、
 『温泉はどっちでもいいや・・・生・生・・・』
『温泉はどっちでもいいや・・・生・生・・・』と言うまるでK上さんの様な副隊長を説得して温泉で汗を流し、生ビールへと向った一行であった。
しみたかさん運転ありがとう御座いました。
またお願いします。
タグ :福島
2010年01月19日
山スキー、西吾妻山・若女平コース
山スキー、西吾妻山・若女平コース
2010年1月11日 福島県西吾妻山 記録者 哲ちゃん
ここに来るのはこれが二回目。前回はロープウェイとリフトを乗り継ぎスキー場のトップまで行ったものの、容赦なく降り続いてくれる雪のために断念しスキー場をそのまま滑り降りる事になってしまった。今日はうってかわっての青空が広がり、絶好の山スキー日和に恵まれる。スキー場のトップまで行き辺りを偵察するがトレースは無かった。入山地点がよく解らなかったが適当に歩きやすいところから中大嶺を目指す。樹氷が立ち並ぶ中を、GPSを頼りに高い方を目指しながら歩いていく。樹氷原は中大嶺の山頂付近まで続いていて、そこまで行きようやく視界が広がり西吾妻山を見ることが出来た。ここから西吾妻山までは青空の下の爽快な歩きとなった。



飯豊山、蔵王山などが遠くに見え山形の平野部までもがよく見えた。平たい山容の西吾妻山の山頂は何処だかわからなかったが、一応一番高いと思われる付近に行ってから西吾妻小屋に降った。ここでシールを剥がし若女平に向けて滑り降りる。樹氷原の中に突入すると激パウが待っていてくれた。沢筋に滑るがまだやや雪は少なめだった。あと2~3m積もれば快適にロングランが楽しめそうだったが、ボトムに入ると板は止まってしまう。沢筋とツリーランを繰り返しながら若女平付近に到着。



ルートが若干左にずれていたようでトラバース気味に2、3の支尾根を越えてからルートの痩せ尾根に乗る。この尾根を降り手持ちの資料での下降点に着いたが、滑り降りられそうな斜面が無い。どうやらここでもまだ雪不足で滑降に適した斜面になっていなかったようだった。しかたがないので引き返し適当な所からトラバース気味に沢筋まで降りる。あとは沢の横を滑って道路にでた。



2010年1月11日 福島県西吾妻山 記録者 哲ちゃん
ここに来るのはこれが二回目。前回はロープウェイとリフトを乗り継ぎスキー場のトップまで行ったものの、容赦なく降り続いてくれる雪のために断念しスキー場をそのまま滑り降りる事になってしまった。今日はうってかわっての青空が広がり、絶好の山スキー日和に恵まれる。スキー場のトップまで行き辺りを偵察するがトレースは無かった。入山地点がよく解らなかったが適当に歩きやすいところから中大嶺を目指す。樹氷が立ち並ぶ中を、GPSを頼りに高い方を目指しながら歩いていく。樹氷原は中大嶺の山頂付近まで続いていて、そこまで行きようやく視界が広がり西吾妻山を見ることが出来た。ここから西吾妻山までは青空の下の爽快な歩きとなった。



飯豊山、蔵王山などが遠くに見え山形の平野部までもがよく見えた。平たい山容の西吾妻山の山頂は何処だかわからなかったが、一応一番高いと思われる付近に行ってから西吾妻小屋に降った。ここでシールを剥がし若女平に向けて滑り降りる。樹氷原の中に突入すると激パウが待っていてくれた。沢筋に滑るがまだやや雪は少なめだった。あと2~3m積もれば快適にロングランが楽しめそうだったが、ボトムに入ると板は止まってしまう。沢筋とツリーランを繰り返しながら若女平付近に到着。



ルートが若干左にずれていたようでトラバース気味に2、3の支尾根を越えてからルートの痩せ尾根に乗る。この尾根を降り手持ちの資料での下降点に着いたが、滑り降りられそうな斜面が無い。どうやらここでもまだ雪不足で滑降に適した斜面になっていなかったようだった。しかたがないので引き返し適当な所からトラバース気味に沢筋まで降りる。あとは沢の横を滑って道路にでた。



タグ :福島
2009年12月04日
会津駒ケ岳(2009.9.21~22)
やあ、会えたね!
2009年9月21日~22日 福島県会津駒ケ岳 記録者 副隊長
 会津駒ケ岳は福島県南会津郡桧枝岐村にある標高2133mの山で日本百名山の一つ。残雪期に駒の形に見える雪形が現れることが「駒ケ岳」という山名の由来とされている。江戸時代の文献「新編会津風土記」では「駒嶽夏秋ノ間残雪駒ノ形ヲナス処アリ、故に此名アリ」とある。頂上とその稜線は草原になっていて木道が敷設されている。山頂から北北西の中門岳方面への稜線には池塘が多く、高山植物が多い。
会津駒ケ岳は福島県南会津郡桧枝岐村にある標高2133mの山で日本百名山の一つ。残雪期に駒の形に見える雪形が現れることが「駒ケ岳」という山名の由来とされている。江戸時代の文献「新編会津風土記」では「駒嶽夏秋ノ間残雪駒ノ形ヲナス処アリ、故に此名アリ」とある。頂上とその稜線は草原になっていて木道が敷設されている。山頂から北北西の中門岳方面への稜線には池塘が多く、高山植物が多い。
まあ、前知識としてはこんなもんで出発。
まだ暗い登山口に到着したが駐車している車の多さにびっくり。私の車は最後の空きスペースに駐車出来たがその後に来た車は林道の下の方までUターンして行った。帰路に知ったのだが登山口まで20分くらい歩くのでは?と思うくらいな場所まで駐車してあった。そしてこれもまた驚きなのだが車の中で夜明けを待つ間に大型のバスが2台やって来て沢山の登山者を下ろして行った。百名山恐るべし!
標準登山時間は滝沢登山口から3時間半とされている。しかし我々ぺんぎん隊には標準などというものは関係無く、ぺんぎん隊時間が適用される。今回は登山以外の目的もあるのでデカザックを背負っている。団体さんのいる登山道は何とも行動しずらくて、抜くのも抜かれるのも時間が掛かる。ぺんぎん隊時間もそっちのけの団体さん時間に翻弄される。
会津駒名物の急登を凌いで何とか水場に到着。
「駒の小屋はまだか?」
「まだだ・・」
これが合言葉のように繰り返される。
森林限界を超えて漸く駒の小屋の姿が望める。木道が延びる先には会津駒がなだらかな曲線を描いて鎮座している。


駒の小屋前のベンチに腰を下ろし大休止。水分補給を怠らない隊長に持参の水分を全部取られて駒の小屋でポカリスエットを購入したが何と400円の高値。荷揚げの苦労を考えたら仕方がない事だと思いつつ、これからは担ぎ上げたビールを500円で売ろうか・・・などと考えたりもする。
木道は草紅葉の中を曲線を描きながら伸びて行く。駒の小屋から会津駒山頂へと続く登山道は階段状に高度を稼ぎ大変きついと同行の清水くんが言う。往復ピストンの我々は側道を抜けて中門岳へと向かう。池塘が点在する草原の中の木道を歩く。尾瀬の象徴である燧ケ岳が間近に見える。青空に鰯雲、秋の真っただ中。
振り返ると日光の山々が連なり頭を覗かせている。一番右に皇海山が特徴ある三角形、プリンの様な奥白根山の隣には男体山や大真名子・小真名子、そして女峰山から帝釈山・田代山。宇都宮市から眺めるのとは全く正反対の景色が面白い。
足元を小さなバッタが跳ねた。よく見ると羽が無いのに気が付いた。草原に入り込んだ闖入者に驚いて跳ねまわっている君たちはこんな素晴らしい場所に暮らしていながらこの雄大なパノラマを見た事は無いのだろうねぇ。
中門岳の標識が立つ大きな池塘を経て先へと進むと木道が周回した終点に辿り着く。我々は別の目的に向かって一時この場から消える。翌日10時25分、再びここに現れる。
 翌日は中門岳の標識前で親子揃って記念撮影。とても親切なオジサンが自ら申し出て我々に向かってシャッターを切ってくれた。とても親切で嬉しい事だったが、一つだけ難を言えばオジサンの親指がレンズに写っている事か・・・。
翌日は中門岳の標識前で親子揃って記念撮影。とても親切なオジサンが自ら申し出て我々に向かってシャッターを切ってくれた。とても親切で嬉しい事だったが、一つだけ難を言えばオジサンの親指がレンズに写っている事か・・・。
中門岳方向から会津駒山頂を目指す。今日はネットで知り合った広島のあーちゃんがこの会津駒の何処かに居る。「帰途の駒の小屋で!」と約束していたが、その時間よりも1時間くらい遅れている。気は焦るが疲れた足が言う事を聞いてくれない。あーちゃんは隊長の顔も知っている筈なので「おまえ先に行ってろよ。」と隊長を先行させる。大した期待も持たずに言った言葉だが隊長はあれよあれよと先に進んで私との距離は開くばかり。いつの間にか隊長に追い越されている自分が情けなくもあり嬉しくもあり。
会津駒山頂は一等三角点が置かれてそれなりの風格だが展望は今一つ。でも2000m超えの山に登った喜びが沸いて来る。今年のぺんぎん登山隊の目標は「登るなら1000m超え」であり2000m級が視野にあるのだから一つの達成感はある。
山頂からの下りは噂通りの階段状。「ここを登らずに良かった!」と素直に思った私である。会津駒と中門岳を日帰りで登る方は余程のドMで無い限りは側道から先に中門岳へ向かい帰途に会津駒に登るコースをお薦め致します。
優しくも隊長は山頂で私を待っていてくれた。まあ山頂での記念写真が欲しかったという本音が見え見えだったが良しとする。二人連れ添い駒の小屋に向かって急ぐ。小屋前のベンチで先を行く隊長に注目している女性に気が付く。その女性が私に向かって大きく手を振ってくれた。


あーちゃんがいた!
広島から単身会津駒に登りに来たあーちゃんと「山で会いましょう!」と約束はしたものの、「会える会えないは時の運」とまで思っていた。第一に私はあーちゃんの顔を知らない。頼よりはあーちゃんにこちらを見つけて貰う事だけなのだ。しかしこういった楽しみがあるから辛い行程も我慢出来るのだろう。山はそして友はいいものだ。
キリンテへ下るというあーちゃんとはここでお別れだ。会えるまでの思いからするとあっという間の出会いだったけれどとても嬉しい出会いだった。「次にもまたどこかで会えるさ。」という期待と予感がこの短い出会いでさえカラッとして別れられる気がする。「じゃあね!気を付けて。」こう声をかけてあーちゃんを見送る。
さて、小屋からは一気に下りだ。会津駒名物の急登は下山時には当然ながら急下降となる。嫌と言うほどの下りの連続に登山口の階段が見えた時には膝が大笑いしていた。

お気楽にご参加下さい
2009年9月21日~22日 福島県会津駒ケ岳 記録者 副隊長
 会津駒ケ岳は福島県南会津郡桧枝岐村にある標高2133mの山で日本百名山の一つ。残雪期に駒の形に見える雪形が現れることが「駒ケ岳」という山名の由来とされている。江戸時代の文献「新編会津風土記」では「駒嶽夏秋ノ間残雪駒ノ形ヲナス処アリ、故に此名アリ」とある。頂上とその稜線は草原になっていて木道が敷設されている。山頂から北北西の中門岳方面への稜線には池塘が多く、高山植物が多い。
会津駒ケ岳は福島県南会津郡桧枝岐村にある標高2133mの山で日本百名山の一つ。残雪期に駒の形に見える雪形が現れることが「駒ケ岳」という山名の由来とされている。江戸時代の文献「新編会津風土記」では「駒嶽夏秋ノ間残雪駒ノ形ヲナス処アリ、故に此名アリ」とある。頂上とその稜線は草原になっていて木道が敷設されている。山頂から北北西の中門岳方面への稜線には池塘が多く、高山植物が多い。まあ、前知識としてはこんなもんで出発。
まだ暗い登山口に到着したが駐車している車の多さにびっくり。私の車は最後の空きスペースに駐車出来たがその後に来た車は林道の下の方までUターンして行った。帰路に知ったのだが登山口まで20分くらい歩くのでは?と思うくらいな場所まで駐車してあった。そしてこれもまた驚きなのだが車の中で夜明けを待つ間に大型のバスが2台やって来て沢山の登山者を下ろして行った。百名山恐るべし!
標準登山時間は滝沢登山口から3時間半とされている。しかし我々ぺんぎん隊には標準などというものは関係無く、ぺんぎん隊時間が適用される。今回は登山以外の目的もあるのでデカザックを背負っている。団体さんのいる登山道は何とも行動しずらくて、抜くのも抜かれるのも時間が掛かる。ぺんぎん隊時間もそっちのけの団体さん時間に翻弄される。
会津駒名物の急登を凌いで何とか水場に到着。
「駒の小屋はまだか?」
「まだだ・・」
これが合言葉のように繰り返される。
森林限界を超えて漸く駒の小屋の姿が望める。木道が延びる先には会津駒がなだらかな曲線を描いて鎮座している。


駒の小屋前のベンチに腰を下ろし大休止。水分補給を怠らない隊長に持参の水分を全部取られて駒の小屋でポカリスエットを購入したが何と400円の高値。荷揚げの苦労を考えたら仕方がない事だと思いつつ、これからは担ぎ上げたビールを500円で売ろうか・・・などと考えたりもする。
木道は草紅葉の中を曲線を描きながら伸びて行く。駒の小屋から会津駒山頂へと続く登山道は階段状に高度を稼ぎ大変きついと同行の清水くんが言う。往復ピストンの我々は側道を抜けて中門岳へと向かう。池塘が点在する草原の中の木道を歩く。尾瀬の象徴である燧ケ岳が間近に見える。青空に鰯雲、秋の真っただ中。
振り返ると日光の山々が連なり頭を覗かせている。一番右に皇海山が特徴ある三角形、プリンの様な奥白根山の隣には男体山や大真名子・小真名子、そして女峰山から帝釈山・田代山。宇都宮市から眺めるのとは全く正反対の景色が面白い。
足元を小さなバッタが跳ねた。よく見ると羽が無いのに気が付いた。草原に入り込んだ闖入者に驚いて跳ねまわっている君たちはこんな素晴らしい場所に暮らしていながらこの雄大なパノラマを見た事は無いのだろうねぇ。
中門岳の標識が立つ大きな池塘を経て先へと進むと木道が周回した終点に辿り着く。我々は別の目的に向かって一時この場から消える。翌日10時25分、再びここに現れる。
 翌日は中門岳の標識前で親子揃って記念撮影。とても親切なオジサンが自ら申し出て我々に向かってシャッターを切ってくれた。とても親切で嬉しい事だったが、一つだけ難を言えばオジサンの親指がレンズに写っている事か・・・。
翌日は中門岳の標識前で親子揃って記念撮影。とても親切なオジサンが自ら申し出て我々に向かってシャッターを切ってくれた。とても親切で嬉しい事だったが、一つだけ難を言えばオジサンの親指がレンズに写っている事か・・・。中門岳方向から会津駒山頂を目指す。今日はネットで知り合った広島のあーちゃんがこの会津駒の何処かに居る。「帰途の駒の小屋で!」と約束していたが、その時間よりも1時間くらい遅れている。気は焦るが疲れた足が言う事を聞いてくれない。あーちゃんは隊長の顔も知っている筈なので「おまえ先に行ってろよ。」と隊長を先行させる。大した期待も持たずに言った言葉だが隊長はあれよあれよと先に進んで私との距離は開くばかり。いつの間にか隊長に追い越されている自分が情けなくもあり嬉しくもあり。
会津駒山頂は一等三角点が置かれてそれなりの風格だが展望は今一つ。でも2000m超えの山に登った喜びが沸いて来る。今年のぺんぎん登山隊の目標は「登るなら1000m超え」であり2000m級が視野にあるのだから一つの達成感はある。
山頂からの下りは噂通りの階段状。「ここを登らずに良かった!」と素直に思った私である。会津駒と中門岳を日帰りで登る方は余程のドMで無い限りは側道から先に中門岳へ向かい帰途に会津駒に登るコースをお薦め致します。
優しくも隊長は山頂で私を待っていてくれた。まあ山頂での記念写真が欲しかったという本音が見え見えだったが良しとする。二人連れ添い駒の小屋に向かって急ぐ。小屋前のベンチで先を行く隊長に注目している女性に気が付く。その女性が私に向かって大きく手を振ってくれた。


あーちゃんがいた!
広島から単身会津駒に登りに来たあーちゃんと「山で会いましょう!」と約束はしたものの、「会える会えないは時の運」とまで思っていた。第一に私はあーちゃんの顔を知らない。頼よりはあーちゃんにこちらを見つけて貰う事だけなのだ。しかしこういった楽しみがあるから辛い行程も我慢出来るのだろう。山はそして友はいいものだ。
キリンテへ下るというあーちゃんとはここでお別れだ。会えるまでの思いからするとあっという間の出会いだったけれどとても嬉しい出会いだった。「次にもまたどこかで会えるさ。」という期待と予感がこの短い出会いでさえカラッとして別れられる気がする。「じゃあね!気を付けて。」こう声をかけてあーちゃんを見送る。
さて、小屋からは一気に下りだ。会津駒名物の急登は下山時には当然ながら急下降となる。嫌と言うほどの下りの連続に登山口の階段が見えた時には膝が大笑いしていた。

お気楽にご参加下さい
タグ :福島