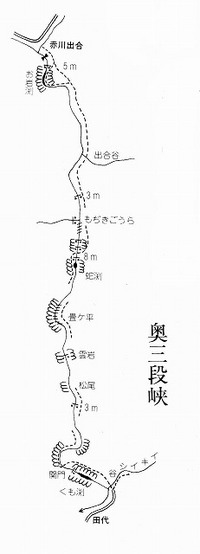2010年06月14日
鋸岳と言う山
鋸岳・コース状況
2010年6月12日(土)~13日(日) 参加者;木偶野呂馬 G3さん 報告者;木偶野呂馬 登り~12日(土)
戸台川・河登 駐車場からしばらく工事用車道を歩いた後に戸台川の河原に入り、ピンクの目印を追って浅い流れを何度か踏み越えたりしながら右岸を進むこと1時間弱で第1の堰堤にかかる。左側につけられた道を通って堰堤を越えると10分足らずで第2の堰堤に到達。階段を昇降して堰堤の上に出ると河原がやや広くなり、砕石が堆積して本流が伏流する上を斜めに横切って徐々に左岸に移動すると、そこからは段丘の樹林と河原を交互する歩道となって20分弱で第1床固と呼ばれる鋼鉄製の堰堤に着く。これを攀じ登って同じような歩道を45分ほど歩くと角兵衛沢の標識に到達する。ここまではただ長いだけの河原歩きであるが、ここで本流を渡らなければならない。流木を利用したり飛び石伝いに渡ることも考えられるが、靴を脱いで渡渉するのが賢明でその覚悟だけは必要。
角兵衛沢の登り口からはすぐに樹林帯の急登となる。途中、25分で右手に水場が、また30分余で横岳分岐の標識があるが、そこから先は何も目印のない急坂が続き、登り始めて2時間40分で大岩下に着く。ここには岩を滴る水がある。
大岩から5分で第2尾根西側のがら場に入る。角兵衛沢の頭から流れ落ちる石の河と言う感じで両手に余るほどのものから小さな岩クズまで、がらがらの岩屑がぎっしり詰まった石の大河を歩くことになる。どの石も1つとして安定したものはなく、踏みしめれば崩れ、次の足を出せばそこがまた崩れ、1歩踏み出しても数cmも進まず、時にはマイナス1歩にもなったりする始末の悪いがら場である。少しでも安定した岩をと求めながら、踏み出して踏み崩した岩屑の上を騙し騙し歩くと言うむなしい繰り返しを何百,何千回,もしかしたら地すべりを誘発してすべての岩屑と一緒になだれ落ちるのではないかと言う恐怖と戦いながら続けることになる。
角兵衛沢の頭は早い段階から窓のようにくっきり切れているのが見えており、そこを目標に登って行く。上部に進むにつれて斜度を増すと共に岩も屑とは言えない大きなものが多くなってくるが、岩が大きくなってもまったく安定せず踏むたびに崩れる歩きにくさは最後まで続く。最後の斜面を中央よりに登り切るとやや平坦になるのだが、石の河の中央部に寄るのが嫌で右手により過ぎて大岩の下に入るとそこから左に戻るためにはがら場を下ることになるので右手に寄り過ぎない方がいい。しかもここからは次の目印が見えず、さらに右手に道らしい踏み跡が見えていてそちらに迷い込むと行き止まりとなって戻らされる羽目になる。
角兵衛沢の頭からはノコギリの歯に当るゴツゴツした岩峰が続き、岩屑の登りで消耗した後にはきつい登りとなる。
コースタイム
12日(土)
戸台川鋸岳駐車場5:58-6:35戸台川河床に入る-6:54第1の堰堤-7:02第2の堰堤7:17-7:35第1床固-8:20角兵衛沢(渡渉点)登山口8:50-9:15水場-9:22横岳分岐-11:28大岩下・大休止12:40-12:45がら場の取り付き-15:26角兵衛沢の頭-16:10鋸岳
13日(日)
テント6:45-6:50下り鎖場7:00-7:02上り鎖場7:12-7:19鹿穴7:42-7:45道迷い・引き返し点-8:01鹿穴下-8:19第2高点上り起点-8:42第2高点9:00-10:07熊穴沢付近10:35-11:10樹林帯入る-12:08戸台川河床-12:20角兵沢・渡渉12:55-13:35第1床固-13:55第2堰堤-14:05第1堰堤-14:20工事用車道14:30-14:43戸台駐車場
降り/13(日)
鋸岳山頂から稜線を南南西方向に下り、5分で鎖場に到達。慎重に下ればどうと言うことはないが、岩が脆くて剥がれやすいので落石を起す危険があり、1人が完全に降り切るまで待つ必要がある。鎖場を降るとすぐに長い鎖場の登りとなる。あまりに長いので腕力に頼りすぎると後半力尽きかねない。鎖場はゆっくり時間をかけたい。
鎖場を登って7~8分で鹿窓に着く。上に向かう道があるがこれは冬期登攀用で、こちらを上がる場合はザイルによる懸垂下降となる。鹿窓も長い鎖場で慎重を要する。鹿窓を降り切って進行方向を見ると道があるが、これも進めば懸垂が必要なルート。ここからはさらに下方にピンクの目印があり、それを追ってい下がりきったところから第2高点への登りが始まる。ここでは少し迷ってルートを見つけるのに35分を費やした。起点から20分あまりで第2高点。
第2高点から前日同様のがら場を一気に下る。角兵衛沢のそれとの違いは、岩が比較的大きくて割と安定していること。安定していると言っても乗っかれば動くが、下りなのでそれに乗って止まる所までずり下がりながら進めることであろうか・・。なので1時間ほどで2000m付近まで降ることが出来る。
熊穴沢付近から30分あまりで樹林帯に入るとはるか下方に沢音が聞こえ始める。岩屑が小さくなって道が次第に登山道らしく歩きやすくなり、約1時間で戸台川に降り立つことが出来る。
右岸を10分あまりで角兵衛沢の渡渉点に到達し再渡渉となる。以下第1床固,第2堰堤,第1堰堤と前日の逆を歩いて1時間50分で駐車場に着き終了。
2010年6月12日(土)~13日(日) 参加者;木偶野呂馬 G3さん 報告者;木偶野呂馬 登り~12日(土)
戸台川・河登 駐車場からしばらく工事用車道を歩いた後に戸台川の河原に入り、ピンクの目印を追って浅い流れを何度か踏み越えたりしながら右岸を進むこと1時間弱で第1の堰堤にかかる。左側につけられた道を通って堰堤を越えると10分足らずで第2の堰堤に到達。階段を昇降して堰堤の上に出ると河原がやや広くなり、砕石が堆積して本流が伏流する上を斜めに横切って徐々に左岸に移動すると、そこからは段丘の樹林と河原を交互する歩道となって20分弱で第1床固と呼ばれる鋼鉄製の堰堤に着く。これを攀じ登って同じような歩道を45分ほど歩くと角兵衛沢の標識に到達する。ここまではただ長いだけの河原歩きであるが、ここで本流を渡らなければならない。流木を利用したり飛び石伝いに渡ることも考えられるが、靴を脱いで渡渉するのが賢明でその覚悟だけは必要。
角兵衛沢の登り口からはすぐに樹林帯の急登となる。途中、25分で右手に水場が、また30分余で横岳分岐の標識があるが、そこから先は何も目印のない急坂が続き、登り始めて2時間40分で大岩下に着く。ここには岩を滴る水がある。
大岩から5分で第2尾根西側のがら場に入る。角兵衛沢の頭から流れ落ちる石の河と言う感じで両手に余るほどのものから小さな岩クズまで、がらがらの岩屑がぎっしり詰まった石の大河を歩くことになる。どの石も1つとして安定したものはなく、踏みしめれば崩れ、次の足を出せばそこがまた崩れ、1歩踏み出しても数cmも進まず、時にはマイナス1歩にもなったりする始末の悪いがら場である。少しでも安定した岩をと求めながら、踏み出して踏み崩した岩屑の上を騙し騙し歩くと言うむなしい繰り返しを何百,何千回,もしかしたら地すべりを誘発してすべての岩屑と一緒になだれ落ちるのではないかと言う恐怖と戦いながら続けることになる。
角兵衛沢の頭は早い段階から窓のようにくっきり切れているのが見えており、そこを目標に登って行く。上部に進むにつれて斜度を増すと共に岩も屑とは言えない大きなものが多くなってくるが、岩が大きくなってもまったく安定せず踏むたびに崩れる歩きにくさは最後まで続く。最後の斜面を中央よりに登り切るとやや平坦になるのだが、石の河の中央部に寄るのが嫌で右手により過ぎて大岩の下に入るとそこから左に戻るためにはがら場を下ることになるので右手に寄り過ぎない方がいい。しかもここからは次の目印が見えず、さらに右手に道らしい踏み跡が見えていてそちらに迷い込むと行き止まりとなって戻らされる羽目になる。
角兵衛沢の頭からはノコギリの歯に当るゴツゴツした岩峰が続き、岩屑の登りで消耗した後にはきつい登りとなる。
コースタイム
12日(土)
戸台川鋸岳駐車場5:58-6:35戸台川河床に入る-6:54第1の堰堤-7:02第2の堰堤7:17-7:35第1床固-8:20角兵衛沢(渡渉点)登山口8:50-9:15水場-9:22横岳分岐-11:28大岩下・大休止12:40-12:45がら場の取り付き-15:26角兵衛沢の頭-16:10鋸岳
13日(日)
テント6:45-6:50下り鎖場7:00-7:02上り鎖場7:12-7:19鹿穴7:42-7:45道迷い・引き返し点-8:01鹿穴下-8:19第2高点上り起点-8:42第2高点9:00-10:07熊穴沢付近10:35-11:10樹林帯入る-12:08戸台川河床-12:20角兵沢・渡渉12:55-13:35第1床固-13:55第2堰堤-14:05第1堰堤-14:20工事用車道14:30-14:43戸台駐車場
降り/13(日)
鋸岳山頂から稜線を南南西方向に下り、5分で鎖場に到達。慎重に下ればどうと言うことはないが、岩が脆くて剥がれやすいので落石を起す危険があり、1人が完全に降り切るまで待つ必要がある。鎖場を降るとすぐに長い鎖場の登りとなる。あまりに長いので腕力に頼りすぎると後半力尽きかねない。鎖場はゆっくり時間をかけたい。
鎖場を登って7~8分で鹿窓に着く。上に向かう道があるがこれは冬期登攀用で、こちらを上がる場合はザイルによる懸垂下降となる。鹿窓も長い鎖場で慎重を要する。鹿窓を降り切って進行方向を見ると道があるが、これも進めば懸垂が必要なルート。ここからはさらに下方にピンクの目印があり、それを追ってい下がりきったところから第2高点への登りが始まる。ここでは少し迷ってルートを見つけるのに35分を費やした。起点から20分あまりで第2高点。
第2高点から前日同様のがら場を一気に下る。角兵衛沢のそれとの違いは、岩が比較的大きくて割と安定していること。安定していると言っても乗っかれば動くが、下りなのでそれに乗って止まる所までずり下がりながら進めることであろうか・・。なので1時間ほどで2000m付近まで降ることが出来る。
熊穴沢付近から30分あまりで樹林帯に入るとはるか下方に沢音が聞こえ始める。岩屑が小さくなって道が次第に登山道らしく歩きやすくなり、約1時間で戸台川に降り立つことが出来る。
右岸を10分あまりで角兵衛沢の渡渉点に到達し再渡渉となる。以下第1床固,第2堰堤,第1堰堤と前日の逆を歩いて1時間50分で駐車場に着き終了。
2010年02月01日
大菩薩嶺
大菩薩嶺
10年1月30日(土) 快晴 参加者:jun1&木偶野呂馬 記録:木偶野呂馬


豊科IC発4:00で6:15頃丸川峠分岐P着。道路は封鎖されておりここから歩く。6:40発。車道を10分で千石平の小屋への橋を渡ってここから登山道となる。2人とも地理不案内の上に計画は全部jun1さんにお任せで地図も持たず、ただ相方についと行くだけ。jun1さんは軽登山靴で快調に飛ばすがこちらは壊れかけたプラブーツで足取り重く、このところ5分くらい後をひたすら追いかけることが多い。


千石平から尾根をひたすら登ること20分で後方に南アルプスと思われる白銀の山なみが紅く染まりながら浮かび上ってくるのを見る。
7:16,第1展望台に着き山の形から山名を特定しようと試みるが、甲斐駒ヶ岳のみそれと分かる他は殆ど分からない。分からないままに甲斐駒の南に雪を頂く山を仙丈ヶ岳,その南を北岳,続いて間ノ岳,農鳥岳,塩見岳~荒川三山であろうと推測する。白く輝いている筈の鳳凰三山を擁する支脈は目立たない黒尾根ですぐにはそれと分からなかった。


10分ほど歩くとブナの若木が現れる。鍋倉山等、北信のブナと違って雪圧を受けず根元からまっすぐ伸びているのが若々しい感じでありまた物足りなくもある。
7:40,第2展望台で休憩中に上がってきた人に山座を聞くとほぼ推測通りだった。北岳をこちら側から見るのは初めてで結構端正な形をしていると思った。


尾根の北側の沢を隔てて大きく迂回していた林道が一旦接近する辺りの道は、登山道によって表土を失った山肌が雨に激しく浸食されて人の背丈,あるいはその倍ほども抉れており、歩けなくなったその道の傍に新しい道が設けられている所が多く、古い道に向かって土砂が崩落したり大木が倒れ込んでいるのが目につく。登山道による山肌の荒れはどこにでもあるがこれほど酷いところは珍しいと思った。


8:25上日川峠,ロッジ長兵衛(冬期無人)着。トイレ(10分)休憩の後出発。林道にほぼ並行する林間の登山道を行く。日陰で凍結しているので時おり滑る。
9:35福ちゃん荘着。事前研究をしていなかったが峠から大菩薩嶺に向かうものと思っていたところ、jun1さんの選択は逆周りの唐松コースだった。どっちでもよかったが大菩薩嶺から丸川峠に下るコースは消えた。


唐松コースは前半こそ緩やかだが唐松林にかかる辺りから斜度を増し、最後の150mはかなりの急登になるのだが下から見上げると草つきの稜線がなだらかに見えるので歩いている実感としては余計にきつい。


だが樹林帯を抜ける辺りから振り返る目に飛び込んでくる雄大な富士の姿がそれを癒してくれる。立ち止まり振り返るごとに富士もまた競りあがり、遮るもののない雄大なその広がりに爽快感がいや増す。


10:32,見上げて目標にしてきた雷岩を標識でそれと知り、追いかけてjun1さんに遅れること5分で大菩薩嶺に到達。展望も何もなく寒いだけのその場では証拠写真を撮る以外に用はなく、すぐに引き返して大菩薩嶺に向かう。


稜線に戻ると北側から若干の風はあるものの雲1つない快晴に八ヶ岳から丹沢山塊辺りまで,100点満点の大展望が広がる。


その景観を楽しみながらルンルンで2000m地点(妙見ノ頭?)を越え、避難小屋まで下って暑いほどの日差しを浴びながら早目の昼食休憩をとる。このところ好天に恵まれている。


11:30発。目の前の丘に立つと眼下に大菩薩峠の小屋が見え10分で介山荘に着く。


山座を記した方向盤で山名を調べるとほぼ真東の方向に大岳山と三頭山の名があった。そうだとすると手前に見えているダムは小河内ダムで下の集落は小菅村と言うことになるのかな・・?
在京時代に五日市や桧原村で仕事をしたり、小菅村や丹波山村を走り回ったことはあるが登山の機会を得ず、いつかこれらの山々を高いところから眺めたいと思っていたが、図らずもそれが叶った。これで奥多摩と大菩連嶺が鳥の目で繋がり、両者を結ぶ縦走ラインを考えてみたりした。


11:45発,殆どが日陰の林道を下る。所によっては道の全面がカチカチに凍ってアイゼンなしには歩けないほどで、一度ならずもんどりうって転倒ししたたか腰を打つ。


勝緑荘,富士見山荘と下って12:21福ちゃん荘,さらに林道を下って12:40ロッジ長兵衛。13:05第2展望台,同17第1展望台を経て13:57帰着。


14:15発,ほったらかしの湯と言うのを探して散々走り回り、露天風呂で大菩薩嶺~大菩薩峠のコースをなぞる。安曇野着は17時頃。
10年1月30日(土) 快晴 参加者:jun1&木偶野呂馬 記録:木偶野呂馬


豊科IC発4:00で6:15頃丸川峠分岐P着。道路は封鎖されておりここから歩く。6:40発。車道を10分で千石平の小屋への橋を渡ってここから登山道となる。2人とも地理不案内の上に計画は全部jun1さんにお任せで地図も持たず、ただ相方についと行くだけ。jun1さんは軽登山靴で快調に飛ばすがこちらは壊れかけたプラブーツで足取り重く、このところ5分くらい後をひたすら追いかけることが多い。


千石平から尾根をひたすら登ること20分で後方に南アルプスと思われる白銀の山なみが紅く染まりながら浮かび上ってくるのを見る。
7:16,第1展望台に着き山の形から山名を特定しようと試みるが、甲斐駒ヶ岳のみそれと分かる他は殆ど分からない。分からないままに甲斐駒の南に雪を頂く山を仙丈ヶ岳,その南を北岳,続いて間ノ岳,農鳥岳,塩見岳~荒川三山であろうと推測する。白く輝いている筈の鳳凰三山を擁する支脈は目立たない黒尾根ですぐにはそれと分からなかった。


10分ほど歩くとブナの若木が現れる。鍋倉山等、北信のブナと違って雪圧を受けず根元からまっすぐ伸びているのが若々しい感じでありまた物足りなくもある。
7:40,第2展望台で休憩中に上がってきた人に山座を聞くとほぼ推測通りだった。北岳をこちら側から見るのは初めてで結構端正な形をしていると思った。


尾根の北側の沢を隔てて大きく迂回していた林道が一旦接近する辺りの道は、登山道によって表土を失った山肌が雨に激しく浸食されて人の背丈,あるいはその倍ほども抉れており、歩けなくなったその道の傍に新しい道が設けられている所が多く、古い道に向かって土砂が崩落したり大木が倒れ込んでいるのが目につく。登山道による山肌の荒れはどこにでもあるがこれほど酷いところは珍しいと思った。


8:25上日川峠,ロッジ長兵衛(冬期無人)着。トイレ(10分)休憩の後出発。林道にほぼ並行する林間の登山道を行く。日陰で凍結しているので時おり滑る。
9:35福ちゃん荘着。事前研究をしていなかったが峠から大菩薩嶺に向かうものと思っていたところ、jun1さんの選択は逆周りの唐松コースだった。どっちでもよかったが大菩薩嶺から丸川峠に下るコースは消えた。


唐松コースは前半こそ緩やかだが唐松林にかかる辺りから斜度を増し、最後の150mはかなりの急登になるのだが下から見上げると草つきの稜線がなだらかに見えるので歩いている実感としては余計にきつい。


だが樹林帯を抜ける辺りから振り返る目に飛び込んでくる雄大な富士の姿がそれを癒してくれる。立ち止まり振り返るごとに富士もまた競りあがり、遮るもののない雄大なその広がりに爽快感がいや増す。


10:32,見上げて目標にしてきた雷岩を標識でそれと知り、追いかけてjun1さんに遅れること5分で大菩薩嶺に到達。展望も何もなく寒いだけのその場では証拠写真を撮る以外に用はなく、すぐに引き返して大菩薩嶺に向かう。


稜線に戻ると北側から若干の風はあるものの雲1つない快晴に八ヶ岳から丹沢山塊辺りまで,100点満点の大展望が広がる。


その景観を楽しみながらルンルンで2000m地点(妙見ノ頭?)を越え、避難小屋まで下って暑いほどの日差しを浴びながら早目の昼食休憩をとる。このところ好天に恵まれている。


11:30発。目の前の丘に立つと眼下に大菩薩峠の小屋が見え10分で介山荘に着く。


山座を記した方向盤で山名を調べるとほぼ真東の方向に大岳山と三頭山の名があった。そうだとすると手前に見えているダムは小河内ダムで下の集落は小菅村と言うことになるのかな・・?
在京時代に五日市や桧原村で仕事をしたり、小菅村や丹波山村を走り回ったことはあるが登山の機会を得ず、いつかこれらの山々を高いところから眺めたいと思っていたが、図らずもそれが叶った。これで奥多摩と大菩連嶺が鳥の目で繋がり、両者を結ぶ縦走ラインを考えてみたりした。


11:45発,殆どが日陰の林道を下る。所によっては道の全面がカチカチに凍ってアイゼンなしには歩けないほどで、一度ならずもんどりうって転倒ししたたか腰を打つ。


勝緑荘,富士見山荘と下って12:21福ちゃん荘,さらに林道を下って12:40ロッジ長兵衛。13:05第2展望台,同17第1展望台を経て13:57帰着。


14:15発,ほったらかしの湯と言うのを探して散々走り回り、露天風呂で大菩薩嶺~大菩薩峠のコースをなぞる。安曇野着は17時頃。
2010年01月11日
ちょいと本沢へ~雪中往復12時間の日帰り入浴
ちょいと本沢へ~雪中往復12時間の日帰り入浴
1月10日(日) 八ヶ岳・渋の湯~本沢温泉往復 参加者2名 記録:木偶野呂馬


前々から本沢温泉に行こう行こうと言いながらなかなか実現しなかったのは、縦走の途中で立ち寄って稲子か松原湖方面に下るのでなければ態々温泉狙いで行ってまた戻ってこなければならないからである。
今回はシーズン最初の足慣らしを兼ねてそれをやろうと言うことになり、天狗岳方面には目もくれずひたすら本沢温泉だけを目指し、また汗をかいて戻ることにした。


中山峠からルートは夏沢峠経由でぐるっと廻るかあるいはその逆かであるが、峠まで来て見ると天狗岳方面の風が強そうなので、あまり深く考えずに行け行けドンドンで峠を越えてみどり池・しらびそ小屋方面に下る。
2人ともそのルートを知らないままに、いきなりの鎖場からほぼ真下に向けて一気に谷底まで下ろされ、さらに急な下りが続くのにびっくりする。200mは下ったかと思う辺りに『中山峠まで40分 みどり池まで40分』と書かれた看板があり、時計を見ると峠から20分かかっていた。その時点では『こんな壁のような急登なんてとても登れたものじゃない~』等と思っていたルートだが、結果的には帰路そこを登る羽目になる。


看板から幾分ゆるくなった道を下る途中で10人あまりのパーティーと数人のパーティー、2人ずれの2組のパーティーを交わし、30分あまりで『みどり池⇔中山峠』の標識を通過,その少し先でみどり池・しらびそ小屋方面と本沢温泉方面の分岐点に到達し、右折して尾根越えの道に入る。中山峠から55分。


道は天狗岳から東に張り出す大きな尾根を越える道で、はじめはほぼ等高線に沿った揺るやかな登りがだらだらと続き、最後にややきつめの登りがあって尾根を乗越す辺りに『本沢温泉へ30分』の標識があり、そこから登った分だけ下るとまもなく稲子小屋方面からの道に合流する。そこで4人のパーティーを追い越して20分弱で本沢温泉に着く。中山峠から2時間17分,渋の湯からは5時間17分。


本館の少し下にある外風呂は本館とは別料金(600円)で男女別になっておらず、混浴もしくは混浴を避けたければ先客優先で空くのを待つ,あるいは待ってもらうと言う仕組みになっている。浴槽が2つあり木の板で覆われているのではじめはかなり熱いが、蓋を取って浸かっているとすぐに丁度いい湯加減になる。蓋を全部取らずに首だけ出していればそれ以上は冷めないのでゆったりと長湯できる。
4~5人は入れるが脱衣場が狭く登山スタイルでの靴や衣類の着脱に手間取るのが難点。野天風呂は登山道を少し登って先の沢にあるが、まったくの野天なので雪の中で入るには脱衣,着衣が大変そう。


しっかり温まり弁当を食べて帰途に就く。予定では夏沢峠から箕冠山,根石岳,東天狗岳と廻ることになるのだが、ナイフリッジで吹雪かれるのは避けたいと言うことで来た道を引き返すことにする。
中山峠直下の登りを考えると気が重いが、お湯に浸かって緩んだ気分での稜線歩きはよろしくないだろう。『逆コースにすればよかった』とjun1さんが悔やむことしきりだが事前研究不足で致し方なし。


中山峠まで3.5時間,渋の湯まで6時間を見込んで11:40に出発。アイゼンをつけたので蹴り足が流れない分だけ歩きやすくなり、みどり池分岐まで1時間半,峠下の看板まで2時間半と順調に来る。途中で女性1名を含む4人の若者のパーティーに先を譲って後を追うも、22~23kgを担いでぐいぐい登って行く若さには追いつきようもなかった。


峠下からの登りでは木の間越しに見えたと思った空が実はその上の雪の壁で、その壁では久々に両手でピッケルを思いっきり打ち込んで体を引き上げる場面もあったが、下った時に思ったほどのしんどさはなく35分で壁を登りきって中山峠に14:45,見込みより30分早く着く。


黒百合ヒュッテ着15:00,気温-9.5℃。朝よりも増えたテントを尻目にすぐに下山。その頃になって日が照り始め、林間がパッと明るくなる。
16:30渋の湯着。本沢温泉から峠まで3時間05分,渋の湯までは5時間50分。


ちょっと温泉へ・・,雪中往復12時間の日帰り入浴やよし!
標高2100mの本沢温泉は本邦最高所温泉とある。昔は白馬鑓温泉が本邦最高所温泉と言われていたが最近はそう言われなくなったし地図にもそうは書いてない。
2.5万図で見ると本沢は2110mの等高線の下,白馬槍はその上に書かれていて白馬鑓の方が高いように見える。ただ野天風呂は2150mと書いてあるので、それを以って最高所としているのかも知れない。
ウイキペディアによると白馬鑓温泉は「以前は『日本最高所の温泉』を名乗っていた時期もあったが、立山のみくりが池温泉や八ヶ岳の本沢温泉などのほうが標高が高く、最近はそのような表示はしていない」とあった。
どちらであろうと大したことではない。※みくりが池温泉は2410m
1月10日(日) 八ヶ岳・渋の湯~本沢温泉往復 参加者2名 記録:木偶野呂馬


前々から本沢温泉に行こう行こうと言いながらなかなか実現しなかったのは、縦走の途中で立ち寄って稲子か松原湖方面に下るのでなければ態々温泉狙いで行ってまた戻ってこなければならないからである。
今回はシーズン最初の足慣らしを兼ねてそれをやろうと言うことになり、天狗岳方面には目もくれずひたすら本沢温泉だけを目指し、また汗をかいて戻ることにした。


中山峠からルートは夏沢峠経由でぐるっと廻るかあるいはその逆かであるが、峠まで来て見ると天狗岳方面の風が強そうなので、あまり深く考えずに行け行けドンドンで峠を越えてみどり池・しらびそ小屋方面に下る。
2人ともそのルートを知らないままに、いきなりの鎖場からほぼ真下に向けて一気に谷底まで下ろされ、さらに急な下りが続くのにびっくりする。200mは下ったかと思う辺りに『中山峠まで40分 みどり池まで40分』と書かれた看板があり、時計を見ると峠から20分かかっていた。その時点では『こんな壁のような急登なんてとても登れたものじゃない~』等と思っていたルートだが、結果的には帰路そこを登る羽目になる。


看板から幾分ゆるくなった道を下る途中で10人あまりのパーティーと数人のパーティー、2人ずれの2組のパーティーを交わし、30分あまりで『みどり池⇔中山峠』の標識を通過,その少し先でみどり池・しらびそ小屋方面と本沢温泉方面の分岐点に到達し、右折して尾根越えの道に入る。中山峠から55分。


道は天狗岳から東に張り出す大きな尾根を越える道で、はじめはほぼ等高線に沿った揺るやかな登りがだらだらと続き、最後にややきつめの登りがあって尾根を乗越す辺りに『本沢温泉へ30分』の標識があり、そこから登った分だけ下るとまもなく稲子小屋方面からの道に合流する。そこで4人のパーティーを追い越して20分弱で本沢温泉に着く。中山峠から2時間17分,渋の湯からは5時間17分。


本館の少し下にある外風呂は本館とは別料金(600円)で男女別になっておらず、混浴もしくは混浴を避けたければ先客優先で空くのを待つ,あるいは待ってもらうと言う仕組みになっている。浴槽が2つあり木の板で覆われているのではじめはかなり熱いが、蓋を取って浸かっているとすぐに丁度いい湯加減になる。蓋を全部取らずに首だけ出していればそれ以上は冷めないのでゆったりと長湯できる。
4~5人は入れるが脱衣場が狭く登山スタイルでの靴や衣類の着脱に手間取るのが難点。野天風呂は登山道を少し登って先の沢にあるが、まったくの野天なので雪の中で入るには脱衣,着衣が大変そう。


しっかり温まり弁当を食べて帰途に就く。予定では夏沢峠から箕冠山,根石岳,東天狗岳と廻ることになるのだが、ナイフリッジで吹雪かれるのは避けたいと言うことで来た道を引き返すことにする。
中山峠直下の登りを考えると気が重いが、お湯に浸かって緩んだ気分での稜線歩きはよろしくないだろう。『逆コースにすればよかった』とjun1さんが悔やむことしきりだが事前研究不足で致し方なし。


中山峠まで3.5時間,渋の湯まで6時間を見込んで11:40に出発。アイゼンをつけたので蹴り足が流れない分だけ歩きやすくなり、みどり池分岐まで1時間半,峠下の看板まで2時間半と順調に来る。途中で女性1名を含む4人の若者のパーティーに先を譲って後を追うも、22~23kgを担いでぐいぐい登って行く若さには追いつきようもなかった。


峠下からの登りでは木の間越しに見えたと思った空が実はその上の雪の壁で、その壁では久々に両手でピッケルを思いっきり打ち込んで体を引き上げる場面もあったが、下った時に思ったほどのしんどさはなく35分で壁を登りきって中山峠に14:45,見込みより30分早く着く。


黒百合ヒュッテ着15:00,気温-9.5℃。朝よりも増えたテントを尻目にすぐに下山。その頃になって日が照り始め、林間がパッと明るくなる。
16:30渋の湯着。本沢温泉から峠まで3時間05分,渋の湯までは5時間50分。


ちょっと温泉へ・・,雪中往復12時間の日帰り入浴やよし!
標高2100mの本沢温泉は本邦最高所温泉とある。昔は白馬鑓温泉が本邦最高所温泉と言われていたが最近はそう言われなくなったし地図にもそうは書いてない。
2.5万図で見ると本沢は2110mの等高線の下,白馬槍はその上に書かれていて白馬鑓の方が高いように見える。ただ野天風呂は2150mと書いてあるので、それを以って最高所としているのかも知れない。
ウイキペディアによると白馬鑓温泉は「以前は『日本最高所の温泉』を名乗っていた時期もあったが、立山のみくりが池温泉や八ヶ岳の本沢温泉などのほうが標高が高く、最近はそのような表示はしていない」とあった。
どちらであろうと大したことではない。※みくりが池温泉は2410m
2009年12月28日
林城&桐原城~山城をめぐるハイキング
長野県史跡・小笠原城跡をめぐるハイキング
09年1月18日(日) 記録者:木偶野呂馬 参加者:里山楽会・境界線10名


里山楽会・境界線の1月山行は『長野県史跡・小笠原城跡めぐり』と称して松本市内の林城と桐原城を訪ねるハイキング。
林城は建武年間(1334~),信濃守護・小笠原貞宗が府中に井川館を設けて以来,小笠原長時が武田晴信に敗れて退去した天文19年(1550)までの約200余年間,厳しい戦国の世に処した小笠原氏の本拠地で、中世における連立式の築城遺構を持つ。城跡は林城の大城,小城および、その前衛をなす桐原城を含めた雄大な要塞として、守護小笠原氏の貫禄を示すものであり、県の代表的な史跡となっている。
美ヶ原を背にした薄川にかかる金華橋のたもとから城址公園の尾根につけられた散策路に入るといきなりの急登となり、ふり返る正面には鹿島槍・爺ヶ岳を見る。尾根を登りきると松林に囲まれた緩やかな道となり、一ノ門跡を経て30分ほどで大着く。


化粧井戸跡
林城等の山城は、平城の城郭の本丸・二の丸に当たる『廓(くるわ)』と称する平坦地を中心に、廓の下側に設けられた『帯廓』・『腰廓』と呼ばれる平坦地,廓の周辺に土を盛り上げてつくる『土塁』,尾根筋からの敵の侵入を防ぐために尾根を切るように設けられた『堀切』,敵の横移動を防ぐために山の斜面に縦方向に設けられた『竪堀』,敵が登りにくいように地面を掘削して急斜面を作り出した『切岸』などからなる。即ち、城は『土から成る』ものであり、それが城と言う字の元(土偏に成)になっていると言える。


石垣と土塁
林大城の廓はかなりの広さで、周辺には土塁が設けられてある。このように廓の周りに土塁を積み上げるのが小笠原氏の山城の特徴なのだそうだ。
大城から下って大嵩先(おおつき)と言う集落に下り、集落を挟んで連立する林小城に向かう。


林大城から西に下って大嵩崎と言う小さな集落を挟み林小城が東に相対して連立式の要塞をなしている。陽だまりに早春の花を咲かせる集落の急坂をを300mほど下って小城の入り口に達し、ここから小城を目指して杉,カラマツ,アカマツの林を登る。その入り口付近に『地獄の釜』と称する底なし沼(?)があった。馬1頭を荷物ごと呑み込んだと言われる沼は今は半ば干上がって2~3坪ばかりの泥場に過ぎないが、試みに棒を突きたてて底を探ってみると確かに深かく、そのような言い伝えが生まれるのも頷けぬことはないかも知れない。
急登20分で林小城の廓を支える石垣が見える場所に着く。廓の一方の端は山の斜面を残して土塁とし、削った土を反対側の端に移動して平面を確保したものと思われる。石垣はその裏側をしっかりと補強するものであるのことがよく分かる。


広澤寺
石垣を廻り込んで廓に入る。廓は大城のそれに比べれば半分ほどであるが周りを囲う土塁や石垣が築城当時の姿をそのまま残していて興味深い。
下って小笠原氏一族の墓がある広澤寺に向かい、お参りさせて頂きたい旨,案内を請うと内部を見学させて頂いた上に、雪を被った庭園を窓越しに見る暖かい部屋で昼食休憩をとらせて頂く。


最後に訪ねた桐原城は、規模こそ小さいが戦国時代の山城の成り立ちを最もよく伝えている点で出色である。
まず第1に桐原城は林城に比べて急峻な山に設けられていて、それ自体が敵の侵入を阻む要塞としての主要素になっていると言う印象を受ける。そのことは廓に登る道自体がまるで竪堀を登っているかのような急坂であり、しかも他に攻める道がないと言うことからも伺える。堀切が設けられているのは言うまでもない。
第2に、仮に他の侵入路から攻めることを試みるとすると、それらはすべて無数に設けられた竪堀につながっていて侵入者が横に移動することを阻み、まっすぐ登れば上から迎え撃たれて容易には落とせない仕組みになっていることを非常にわかり易く提示してくれている。
また、こんもりした小ピークを切り開いて平坦にした感じの一の廓の土塁と土塁を裏側から支える石垣や腰廓の二~四の廓,帯廓等の保存がよく、つくられた過程や山城の成り立ちが一目瞭然である点,絵に描いたように博物館的でわかり易い。


竪堀を下ってみた!
竪堀は少なくとも8本以上あり、中には行き止まりになっているものや畝状に畝ってしかもそれが枝分かれし、どこへ導かれるかわからないままバラバラに分断されて孤立したところを迎え撃たれるようにつくられた(畝状竪堀)ものまである。
帰路はその竪堀の最も大きなものを下ってみたが、実際に上から見下ろしながら下るといかに急傾斜であるかがよく分かる。
まず狭い上に急坂なので攻め手は1人づつ登ることになり、数にものを言わせることが出来ない。横に走ろうにも堀は深いし連絡路もないので竪堀の中を上へ上へと行くしかないが、それは攻めている筈がいつの間にか誘い込まれているに等しい。上には巨岩や槍ふすまが待っていたことであろう・・。
途中から雑兵になったような気分に襲われた。後からは槍で追い立てられ、登れば死が待っていると分かっていながら進むしかなかった雑兵達の恐怖と悲哀に身がすくむ思いがする。


09年1月18日(日) 記録者:木偶野呂馬 参加者:里山楽会・境界線10名


里山楽会・境界線の1月山行は『長野県史跡・小笠原城跡めぐり』と称して松本市内の林城と桐原城を訪ねるハイキング。
林城は建武年間(1334~),信濃守護・小笠原貞宗が府中に井川館を設けて以来,小笠原長時が武田晴信に敗れて退去した天文19年(1550)までの約200余年間,厳しい戦国の世に処した小笠原氏の本拠地で、中世における連立式の築城遺構を持つ。城跡は林城の大城,小城および、その前衛をなす桐原城を含めた雄大な要塞として、守護小笠原氏の貫禄を示すものであり、県の代表的な史跡となっている。
美ヶ原を背にした薄川にかかる金華橋のたもとから城址公園の尾根につけられた散策路に入るといきなりの急登となり、ふり返る正面には鹿島槍・爺ヶ岳を見る。尾根を登りきると松林に囲まれた緩やかな道となり、一ノ門跡を経て30分ほどで大着く。


化粧井戸跡
林城等の山城は、平城の城郭の本丸・二の丸に当たる『廓(くるわ)』と称する平坦地を中心に、廓の下側に設けられた『帯廓』・『腰廓』と呼ばれる平坦地,廓の周辺に土を盛り上げてつくる『土塁』,尾根筋からの敵の侵入を防ぐために尾根を切るように設けられた『堀切』,敵の横移動を防ぐために山の斜面に縦方向に設けられた『竪堀』,敵が登りにくいように地面を掘削して急斜面を作り出した『切岸』などからなる。即ち、城は『土から成る』ものであり、それが城と言う字の元(土偏に成)になっていると言える。


石垣と土塁
林大城の廓はかなりの広さで、周辺には土塁が設けられてある。このように廓の周りに土塁を積み上げるのが小笠原氏の山城の特徴なのだそうだ。
大城から下って大嵩先(おおつき)と言う集落に下り、集落を挟んで連立する林小城に向かう。


林大城から西に下って大嵩崎と言う小さな集落を挟み林小城が東に相対して連立式の要塞をなしている。陽だまりに早春の花を咲かせる集落の急坂をを300mほど下って小城の入り口に達し、ここから小城を目指して杉,カラマツ,アカマツの林を登る。その入り口付近に『地獄の釜』と称する底なし沼(?)があった。馬1頭を荷物ごと呑み込んだと言われる沼は今は半ば干上がって2~3坪ばかりの泥場に過ぎないが、試みに棒を突きたてて底を探ってみると確かに深かく、そのような言い伝えが生まれるのも頷けぬことはないかも知れない。
急登20分で林小城の廓を支える石垣が見える場所に着く。廓の一方の端は山の斜面を残して土塁とし、削った土を反対側の端に移動して平面を確保したものと思われる。石垣はその裏側をしっかりと補強するものであるのことがよく分かる。


広澤寺
石垣を廻り込んで廓に入る。廓は大城のそれに比べれば半分ほどであるが周りを囲う土塁や石垣が築城当時の姿をそのまま残していて興味深い。
下って小笠原氏一族の墓がある広澤寺に向かい、お参りさせて頂きたい旨,案内を請うと内部を見学させて頂いた上に、雪を被った庭園を窓越しに見る暖かい部屋で昼食休憩をとらせて頂く。


最後に訪ねた桐原城は、規模こそ小さいが戦国時代の山城の成り立ちを最もよく伝えている点で出色である。
まず第1に桐原城は林城に比べて急峻な山に設けられていて、それ自体が敵の侵入を阻む要塞としての主要素になっていると言う印象を受ける。そのことは廓に登る道自体がまるで竪堀を登っているかのような急坂であり、しかも他に攻める道がないと言うことからも伺える。堀切が設けられているのは言うまでもない。
第2に、仮に他の侵入路から攻めることを試みるとすると、それらはすべて無数に設けられた竪堀につながっていて侵入者が横に移動することを阻み、まっすぐ登れば上から迎え撃たれて容易には落とせない仕組みになっていることを非常にわかり易く提示してくれている。
また、こんもりした小ピークを切り開いて平坦にした感じの一の廓の土塁と土塁を裏側から支える石垣や腰廓の二~四の廓,帯廓等の保存がよく、つくられた過程や山城の成り立ちが一目瞭然である点,絵に描いたように博物館的でわかり易い。


竪堀を下ってみた!
竪堀は少なくとも8本以上あり、中には行き止まりになっているものや畝状に畝ってしかもそれが枝分かれし、どこへ導かれるかわからないままバラバラに分断されて孤立したところを迎え撃たれるようにつくられた(畝状竪堀)ものまである。
帰路はその竪堀の最も大きなものを下ってみたが、実際に上から見下ろしながら下るといかに急傾斜であるかがよく分かる。
まず狭い上に急坂なので攻め手は1人づつ登ることになり、数にものを言わせることが出来ない。横に走ろうにも堀は深いし連絡路もないので竪堀の中を上へ上へと行くしかないが、それは攻めている筈がいつの間にか誘い込まれているに等しい。上には巨岩や槍ふすまが待っていたことであろう・・。
途中から雑兵になったような気分に襲われた。後からは槍で追い立てられ、登れば死が待っていると分かっていながら進むしかなかった雑兵達の恐怖と悲哀に身がすくむ思いがする。