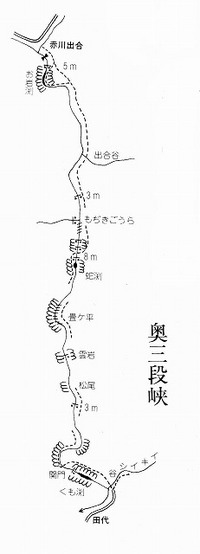2009年12月31日
八紘嶺・山伏(2009.12.22~23)
忘年登山(静岡編)その①
2009年12月22日~23日 静岡県と山梨県の県境 八紘嶺・山伏 記録者 あーちゃん
12月22日。
秋の会津駒ケ岳に登った日に泊まった桧枝岐の民宿で、
たまたま一緒になった山好きのおじさん2人組みに誘われて、忘年登山に静岡まで行ってきました。
こちら広島を朝の5時過ぎにでて、新幹線で一路静岡へ!
10時前に静岡駅に着いて、今回誘っていただいたおじさん2人と合流して、
車で梅ヶ島温泉と言うところへ向かいます。
梅ヶ島温泉の小さな集落を越えたすぐ先に、
この日に登る八紘嶺(はっこうれい)と言う山の登山口がありました。
本当は、もう少し先の別の登山口から行く予定だったらしいのですが、
もう既に、冬季通行止め期間になっていて先にいけなかったので、その場所から、と言うことに。
さて、時間は、11時半前。
準備をして、いざ、出発です。
この前日までは、この静岡でも、かなり冷え込んだ毎日だったようですが、
この日は、気温も持ち直して、かなり、いいお天気の予報。

歩き出してしばらくは、よく手入れされた針葉樹の林の中。
木漏れ日の登山道を歩いていると、冬の最中と言うよりは、春浅い登山道を歩いているような気がしました。

でも、時々、登山道に、霜柱。
歩いていると、さくさくと音がして、その音も心地いい。
歩き出して、約1時間ほどで、安部峠との分岐に到着。
ここから、八紘嶺方面に向かいます。この先は、広葉樹の森。
辺りは、雲ひとつない、見事なまでの青空!!

登山道は、明るくて気持ちがよくって、どんどんと進んでいきました。
他の山でもそうなのですが、目の前に見えてくるピークを見ては、
『この見えているピークが頂上!?』と思うのですが、大抵は違うことが多く、
『また、偽頂上にだまされたねぇ…』なんて笑いながら、登っていきました。
そんなこんなで、どんどん進んでいったのですが、何気に登山道の右側を見ると、
『あーっ、富士山!!!』
白い雪をかぶった美しい姿の富士山が見えていました。
さすが、静岡!!

木の枝が邪魔をして、なかなかきれいな姿が見えないのですが、
青空に映えて、その美しい姿と言ったら!!!
俄然元気が出てきて、またどんどんと進んでいきました。
周辺の景色も、かなりきれいです。
それにしても、見事な青空だ…

木立の間から、木々に邪魔されずに富士山が見えるスポットがあったので、そこからの富士山です。
裾野の美しさや、雪のかぶり具合や、その形そのもの…
ホント、絵になりますねぇ♪
思うに、富士山のある風景って、それだけで絶景になりますね♪
だから、富士山が見える地域に住んでいる方々は、それだけで得されているような気が…(^^
しかし…、つくづく日本人って…、富士山、好きですよね…(^^;
さて、富士山に元気をもらって、またさらにどんどん進みます。
が、そのうち、登山道は、雪で真っ白に…

でも、凍っていないので、普通の登山靴のままで、問題なく歩けました。
木立の間から、真っ白な南アルプスの山並み!!

振り返ってみた、静岡の山並み。
思っていた以上に、深い山並み…
こっち、中国地方とは、全然違う山の景色です。
で、その後、偽ピークにだまされること数回、
もしかして、雪のせいで頂上に気がつかなかったのかも?と、思いはじめていた14時14分。
やっと頂上に到着!!!

頂上からも、南アルプスの山々が、木立の間に白く見えていました。
もちろん、富士山も!!

しばらく、みんなで写真を撮ったり、食べ物を食べたりして、大休止。
ここから、この次の日に登る山や、そのほかにも縦走が出来るそうです。
でも、登山道はしっかり雪に覆われていました。
頂上で休んだ後、元の道をピストン。

頂上付近から。
下りはいつも早いですよね。何度もだまされた偽ピークを越え、ひたすら下っていきます。
下り道に、再び富士山♪
夏には木々が生い茂っていそうなので、これは、冬だから見える富士山かな?

登りの時には気がつかなかった、ベストポジションにて!
年賀状の写真になるねぇってお話しながら、しばし、富士山に見入ってしまいました。
その後、どんどんと下って行きます。
夕方が迫ってきていましたので、ペースも上がっていきます。
さて、時間は、夕方の4時前。
最初に歩いた針葉樹の森に着いた時には、辺りは夕方の雰囲気。
山の陰になるから、お日様が山の向こうに落ちていくのが早いのでしょうね。
この日泊まる梅ヶ島温泉の民宿の人が心配しているねって言いながら、
足を速めて下って行って、元の登山口に着いた時間は、午後4時半前。

登山口の辺りから、梅ヶ島温泉の集落を見る!
さて、この日は、安部の大滝と言う(今回は、行かなかったけど)、
滝までの道の入り口の橋の近くにある民宿にお泊りです。
紅葉シーズンには賑わったらしいのですが、今回は、私たちのみでした。
すぐに、民宿内にあるお風呂へ。
もちろん、温泉♪。
ここの温泉のお湯は、硫黄のにおいのするぬるっとしたお湯。
お肌すべすべ!
気持ちよかったです♪
お風呂のあと、夕食。
3人で楽しく食べた後、もってきてくださった、手製の果実酒等々を飲みながら、
あーだこーだとお話して、夜の11時頃に、お開き。
なんだかんだで、面白かったです
お話していたときも言っていたけど、秋にたまたま同じ民宿に泊まったのですが、
もし、同じ民宿に泊まらなかったら、出会わなかったわけで、
でも、一緒の民宿に泊まっても、たくさん人がいたりしたら、その他大勢にまぎれて、お話もしなかったわけで…
それに、このおじさん方が、こんな陽気な人達でなかったら、やっぱ、きっと、お話もしなかったわけで…
人と人って、何かの縁があって、知り合いになるべくしてなっていのだと思う。
縁…って、面白いなぁ…って思います。
不思議だとも思います。
この方々、二人でいろいろな所に出かけて、いろいろ山に登っているとのこと。
百名山が残す所あとわずかだとのこと。
でも、百名山に登ることばかりを目指しているわけではないと。
私のように、普段は近場の里山にも出かけるんだとか。
百名山は、一つのきっかけにすぎないようで、その登る過程を大事にしている人のような気がしました。
ま、とにかく、陽気なおじさんたちで、今まで登った山のお話や、珍道中(?)のお話をたくさんしてくださいました。
また、ご一緒しましょうって言って下さいました。
よい山友達が出来ました。友達って言うのも失礼かもしれないけど…(^^;
でも、年も住んでいるところも違うけど、そんな仲間が出来るのも、山の持つ魅力かもね(^^
さて、その後は、この日、朝が早かったから、爆睡…
久々に、ゆっくり眠ったような気がしました。
この次の日は、この梅ヶ島温泉から30分くらいの所にある、山伏(やんぶし)に登ります。

民宿の前で。
しっかり日本人。3人ともピース
隠れた顔は、三人とも笑顔(^^v
と、その①は、ここまで。
この続きは、その②に続きます。
2009年12月22日~23日 静岡県と山梨県の県境 八紘嶺・山伏 記録者 あーちゃん
12月22日。
秋の会津駒ケ岳に登った日に泊まった桧枝岐の民宿で、
たまたま一緒になった山好きのおじさん2人組みに誘われて、忘年登山に静岡まで行ってきました。
こちら広島を朝の5時過ぎにでて、新幹線で一路静岡へ!
10時前に静岡駅に着いて、今回誘っていただいたおじさん2人と合流して、
車で梅ヶ島温泉と言うところへ向かいます。
梅ヶ島温泉の小さな集落を越えたすぐ先に、
この日に登る八紘嶺(はっこうれい)と言う山の登山口がありました。
本当は、もう少し先の別の登山口から行く予定だったらしいのですが、
もう既に、冬季通行止め期間になっていて先にいけなかったので、その場所から、と言うことに。
さて、時間は、11時半前。
準備をして、いざ、出発です。
この前日までは、この静岡でも、かなり冷え込んだ毎日だったようですが、
この日は、気温も持ち直して、かなり、いいお天気の予報。
歩き出してしばらくは、よく手入れされた針葉樹の林の中。
木漏れ日の登山道を歩いていると、冬の最中と言うよりは、春浅い登山道を歩いているような気がしました。
でも、時々、登山道に、霜柱。
歩いていると、さくさくと音がして、その音も心地いい。
歩き出して、約1時間ほどで、安部峠との分岐に到着。
ここから、八紘嶺方面に向かいます。この先は、広葉樹の森。
辺りは、雲ひとつない、見事なまでの青空!!
登山道は、明るくて気持ちがよくって、どんどんと進んでいきました。
他の山でもそうなのですが、目の前に見えてくるピークを見ては、
『この見えているピークが頂上!?』と思うのですが、大抵は違うことが多く、
『また、偽頂上にだまされたねぇ…』なんて笑いながら、登っていきました。
そんなこんなで、どんどん進んでいったのですが、何気に登山道の右側を見ると、
『あーっ、富士山!!!』
白い雪をかぶった美しい姿の富士山が見えていました。
さすが、静岡!!
木の枝が邪魔をして、なかなかきれいな姿が見えないのですが、
青空に映えて、その美しい姿と言ったら!!!
俄然元気が出てきて、またどんどんと進んでいきました。
周辺の景色も、かなりきれいです。
それにしても、見事な青空だ…
木立の間から、木々に邪魔されずに富士山が見えるスポットがあったので、そこからの富士山です。
裾野の美しさや、雪のかぶり具合や、その形そのもの…
ホント、絵になりますねぇ♪
思うに、富士山のある風景って、それだけで絶景になりますね♪
だから、富士山が見える地域に住んでいる方々は、それだけで得されているような気が…(^^
しかし…、つくづく日本人って…、富士山、好きですよね…(^^;
さて、富士山に元気をもらって、またさらにどんどん進みます。
が、そのうち、登山道は、雪で真っ白に…
でも、凍っていないので、普通の登山靴のままで、問題なく歩けました。
木立の間から、真っ白な南アルプスの山並み!!
振り返ってみた、静岡の山並み。
思っていた以上に、深い山並み…
こっち、中国地方とは、全然違う山の景色です。
で、その後、偽ピークにだまされること数回、
もしかして、雪のせいで頂上に気がつかなかったのかも?と、思いはじめていた14時14分。
やっと頂上に到着!!!
頂上からも、南アルプスの山々が、木立の間に白く見えていました。
もちろん、富士山も!!
しばらく、みんなで写真を撮ったり、食べ物を食べたりして、大休止。
ここから、この次の日に登る山や、そのほかにも縦走が出来るそうです。
でも、登山道はしっかり雪に覆われていました。
頂上で休んだ後、元の道をピストン。
頂上付近から。
下りはいつも早いですよね。何度もだまされた偽ピークを越え、ひたすら下っていきます。
下り道に、再び富士山♪
夏には木々が生い茂っていそうなので、これは、冬だから見える富士山かな?
登りの時には気がつかなかった、ベストポジションにて!
年賀状の写真になるねぇってお話しながら、しばし、富士山に見入ってしまいました。
その後、どんどんと下って行きます。
夕方が迫ってきていましたので、ペースも上がっていきます。
さて、時間は、夕方の4時前。
最初に歩いた針葉樹の森に着いた時には、辺りは夕方の雰囲気。
山の陰になるから、お日様が山の向こうに落ちていくのが早いのでしょうね。
この日泊まる梅ヶ島温泉の民宿の人が心配しているねって言いながら、
足を速めて下って行って、元の登山口に着いた時間は、午後4時半前。
登山口の辺りから、梅ヶ島温泉の集落を見る!
さて、この日は、安部の大滝と言う(今回は、行かなかったけど)、
滝までの道の入り口の橋の近くにある民宿にお泊りです。
紅葉シーズンには賑わったらしいのですが、今回は、私たちのみでした。
すぐに、民宿内にあるお風呂へ。
もちろん、温泉♪。
ここの温泉のお湯は、硫黄のにおいのするぬるっとしたお湯。
お肌すべすべ!
気持ちよかったです♪
お風呂のあと、夕食。
3人で楽しく食べた後、もってきてくださった、手製の果実酒等々を飲みながら、
あーだこーだとお話して、夜の11時頃に、お開き。
なんだかんだで、面白かったです

お話していたときも言っていたけど、秋にたまたま同じ民宿に泊まったのですが、
もし、同じ民宿に泊まらなかったら、出会わなかったわけで、
でも、一緒の民宿に泊まっても、たくさん人がいたりしたら、その他大勢にまぎれて、お話もしなかったわけで…
それに、このおじさん方が、こんな陽気な人達でなかったら、やっぱ、きっと、お話もしなかったわけで…
人と人って、何かの縁があって、知り合いになるべくしてなっていのだと思う。
縁…って、面白いなぁ…って思います。
不思議だとも思います。
この方々、二人でいろいろな所に出かけて、いろいろ山に登っているとのこと。
百名山が残す所あとわずかだとのこと。
でも、百名山に登ることばかりを目指しているわけではないと。
私のように、普段は近場の里山にも出かけるんだとか。
百名山は、一つのきっかけにすぎないようで、その登る過程を大事にしている人のような気がしました。
ま、とにかく、陽気なおじさんたちで、今まで登った山のお話や、珍道中(?)のお話をたくさんしてくださいました。
また、ご一緒しましょうって言って下さいました。
よい山友達が出来ました。友達って言うのも失礼かもしれないけど…(^^;
でも、年も住んでいるところも違うけど、そんな仲間が出来るのも、山の持つ魅力かもね(^^
さて、その後は、この日、朝が早かったから、爆睡…
久々に、ゆっくり眠ったような気がしました。
この次の日は、この梅ヶ島温泉から30分くらいの所にある、山伏(やんぶし)に登ります。
民宿の前で。
しっかり日本人。3人ともピース

隠れた顔は、三人とも笑顔(^^v
と、その①は、ここまで。
この続きは、その②に続きます。
2009年12月28日
林城&桐原城~山城をめぐるハイキング
長野県史跡・小笠原城跡をめぐるハイキング
09年1月18日(日) 記録者:木偶野呂馬 参加者:里山楽会・境界線10名


里山楽会・境界線の1月山行は『長野県史跡・小笠原城跡めぐり』と称して松本市内の林城と桐原城を訪ねるハイキング。
林城は建武年間(1334~),信濃守護・小笠原貞宗が府中に井川館を設けて以来,小笠原長時が武田晴信に敗れて退去した天文19年(1550)までの約200余年間,厳しい戦国の世に処した小笠原氏の本拠地で、中世における連立式の築城遺構を持つ。城跡は林城の大城,小城および、その前衛をなす桐原城を含めた雄大な要塞として、守護小笠原氏の貫禄を示すものであり、県の代表的な史跡となっている。
美ヶ原を背にした薄川にかかる金華橋のたもとから城址公園の尾根につけられた散策路に入るといきなりの急登となり、ふり返る正面には鹿島槍・爺ヶ岳を見る。尾根を登りきると松林に囲まれた緩やかな道となり、一ノ門跡を経て30分ほどで大着く。


化粧井戸跡
林城等の山城は、平城の城郭の本丸・二の丸に当たる『廓(くるわ)』と称する平坦地を中心に、廓の下側に設けられた『帯廓』・『腰廓』と呼ばれる平坦地,廓の周辺に土を盛り上げてつくる『土塁』,尾根筋からの敵の侵入を防ぐために尾根を切るように設けられた『堀切』,敵の横移動を防ぐために山の斜面に縦方向に設けられた『竪堀』,敵が登りにくいように地面を掘削して急斜面を作り出した『切岸』などからなる。即ち、城は『土から成る』ものであり、それが城と言う字の元(土偏に成)になっていると言える。


石垣と土塁
林大城の廓はかなりの広さで、周辺には土塁が設けられてある。このように廓の周りに土塁を積み上げるのが小笠原氏の山城の特徴なのだそうだ。
大城から下って大嵩先(おおつき)と言う集落に下り、集落を挟んで連立する林小城に向かう。


林大城から西に下って大嵩崎と言う小さな集落を挟み林小城が東に相対して連立式の要塞をなしている。陽だまりに早春の花を咲かせる集落の急坂をを300mほど下って小城の入り口に達し、ここから小城を目指して杉,カラマツ,アカマツの林を登る。その入り口付近に『地獄の釜』と称する底なし沼(?)があった。馬1頭を荷物ごと呑み込んだと言われる沼は今は半ば干上がって2~3坪ばかりの泥場に過ぎないが、試みに棒を突きたてて底を探ってみると確かに深かく、そのような言い伝えが生まれるのも頷けぬことはないかも知れない。
急登20分で林小城の廓を支える石垣が見える場所に着く。廓の一方の端は山の斜面を残して土塁とし、削った土を反対側の端に移動して平面を確保したものと思われる。石垣はその裏側をしっかりと補強するものであるのことがよく分かる。


広澤寺
石垣を廻り込んで廓に入る。廓は大城のそれに比べれば半分ほどであるが周りを囲う土塁や石垣が築城当時の姿をそのまま残していて興味深い。
下って小笠原氏一族の墓がある広澤寺に向かい、お参りさせて頂きたい旨,案内を請うと内部を見学させて頂いた上に、雪を被った庭園を窓越しに見る暖かい部屋で昼食休憩をとらせて頂く。


最後に訪ねた桐原城は、規模こそ小さいが戦国時代の山城の成り立ちを最もよく伝えている点で出色である。
まず第1に桐原城は林城に比べて急峻な山に設けられていて、それ自体が敵の侵入を阻む要塞としての主要素になっていると言う印象を受ける。そのことは廓に登る道自体がまるで竪堀を登っているかのような急坂であり、しかも他に攻める道がないと言うことからも伺える。堀切が設けられているのは言うまでもない。
第2に、仮に他の侵入路から攻めることを試みるとすると、それらはすべて無数に設けられた竪堀につながっていて侵入者が横に移動することを阻み、まっすぐ登れば上から迎え撃たれて容易には落とせない仕組みになっていることを非常にわかり易く提示してくれている。
また、こんもりした小ピークを切り開いて平坦にした感じの一の廓の土塁と土塁を裏側から支える石垣や腰廓の二~四の廓,帯廓等の保存がよく、つくられた過程や山城の成り立ちが一目瞭然である点,絵に描いたように博物館的でわかり易い。


竪堀を下ってみた!
竪堀は少なくとも8本以上あり、中には行き止まりになっているものや畝状に畝ってしかもそれが枝分かれし、どこへ導かれるかわからないままバラバラに分断されて孤立したところを迎え撃たれるようにつくられた(畝状竪堀)ものまである。
帰路はその竪堀の最も大きなものを下ってみたが、実際に上から見下ろしながら下るといかに急傾斜であるかがよく分かる。
まず狭い上に急坂なので攻め手は1人づつ登ることになり、数にものを言わせることが出来ない。横に走ろうにも堀は深いし連絡路もないので竪堀の中を上へ上へと行くしかないが、それは攻めている筈がいつの間にか誘い込まれているに等しい。上には巨岩や槍ふすまが待っていたことであろう・・。
途中から雑兵になったような気分に襲われた。後からは槍で追い立てられ、登れば死が待っていると分かっていながら進むしかなかった雑兵達の恐怖と悲哀に身がすくむ思いがする。


09年1月18日(日) 記録者:木偶野呂馬 参加者:里山楽会・境界線10名


里山楽会・境界線の1月山行は『長野県史跡・小笠原城跡めぐり』と称して松本市内の林城と桐原城を訪ねるハイキング。
林城は建武年間(1334~),信濃守護・小笠原貞宗が府中に井川館を設けて以来,小笠原長時が武田晴信に敗れて退去した天文19年(1550)までの約200余年間,厳しい戦国の世に処した小笠原氏の本拠地で、中世における連立式の築城遺構を持つ。城跡は林城の大城,小城および、その前衛をなす桐原城を含めた雄大な要塞として、守護小笠原氏の貫禄を示すものであり、県の代表的な史跡となっている。
美ヶ原を背にした薄川にかかる金華橋のたもとから城址公園の尾根につけられた散策路に入るといきなりの急登となり、ふり返る正面には鹿島槍・爺ヶ岳を見る。尾根を登りきると松林に囲まれた緩やかな道となり、一ノ門跡を経て30分ほどで大着く。


化粧井戸跡
林城等の山城は、平城の城郭の本丸・二の丸に当たる『廓(くるわ)』と称する平坦地を中心に、廓の下側に設けられた『帯廓』・『腰廓』と呼ばれる平坦地,廓の周辺に土を盛り上げてつくる『土塁』,尾根筋からの敵の侵入を防ぐために尾根を切るように設けられた『堀切』,敵の横移動を防ぐために山の斜面に縦方向に設けられた『竪堀』,敵が登りにくいように地面を掘削して急斜面を作り出した『切岸』などからなる。即ち、城は『土から成る』ものであり、それが城と言う字の元(土偏に成)になっていると言える。


石垣と土塁
林大城の廓はかなりの広さで、周辺には土塁が設けられてある。このように廓の周りに土塁を積み上げるのが小笠原氏の山城の特徴なのだそうだ。
大城から下って大嵩先(おおつき)と言う集落に下り、集落を挟んで連立する林小城に向かう。


林大城から西に下って大嵩崎と言う小さな集落を挟み林小城が東に相対して連立式の要塞をなしている。陽だまりに早春の花を咲かせる集落の急坂をを300mほど下って小城の入り口に達し、ここから小城を目指して杉,カラマツ,アカマツの林を登る。その入り口付近に『地獄の釜』と称する底なし沼(?)があった。馬1頭を荷物ごと呑み込んだと言われる沼は今は半ば干上がって2~3坪ばかりの泥場に過ぎないが、試みに棒を突きたてて底を探ってみると確かに深かく、そのような言い伝えが生まれるのも頷けぬことはないかも知れない。
急登20分で林小城の廓を支える石垣が見える場所に着く。廓の一方の端は山の斜面を残して土塁とし、削った土を反対側の端に移動して平面を確保したものと思われる。石垣はその裏側をしっかりと補強するものであるのことがよく分かる。


広澤寺
石垣を廻り込んで廓に入る。廓は大城のそれに比べれば半分ほどであるが周りを囲う土塁や石垣が築城当時の姿をそのまま残していて興味深い。
下って小笠原氏一族の墓がある広澤寺に向かい、お参りさせて頂きたい旨,案内を請うと内部を見学させて頂いた上に、雪を被った庭園を窓越しに見る暖かい部屋で昼食休憩をとらせて頂く。


最後に訪ねた桐原城は、規模こそ小さいが戦国時代の山城の成り立ちを最もよく伝えている点で出色である。
まず第1に桐原城は林城に比べて急峻な山に設けられていて、それ自体が敵の侵入を阻む要塞としての主要素になっていると言う印象を受ける。そのことは廓に登る道自体がまるで竪堀を登っているかのような急坂であり、しかも他に攻める道がないと言うことからも伺える。堀切が設けられているのは言うまでもない。
第2に、仮に他の侵入路から攻めることを試みるとすると、それらはすべて無数に設けられた竪堀につながっていて侵入者が横に移動することを阻み、まっすぐ登れば上から迎え撃たれて容易には落とせない仕組みになっていることを非常にわかり易く提示してくれている。
また、こんもりした小ピークを切り開いて平坦にした感じの一の廓の土塁と土塁を裏側から支える石垣や腰廓の二~四の廓,帯廓等の保存がよく、つくられた過程や山城の成り立ちが一目瞭然である点,絵に描いたように博物館的でわかり易い。


竪堀を下ってみた!
竪堀は少なくとも8本以上あり、中には行き止まりになっているものや畝状に畝ってしかもそれが枝分かれし、どこへ導かれるかわからないままバラバラに分断されて孤立したところを迎え撃たれるようにつくられた(畝状竪堀)ものまである。
帰路はその竪堀の最も大きなものを下ってみたが、実際に上から見下ろしながら下るといかに急傾斜であるかがよく分かる。
まず狭い上に急坂なので攻め手は1人づつ登ることになり、数にものを言わせることが出来ない。横に走ろうにも堀は深いし連絡路もないので竪堀の中を上へ上へと行くしかないが、それは攻めている筈がいつの間にか誘い込まれているに等しい。上には巨岩や槍ふすまが待っていたことであろう・・。
途中から雑兵になったような気分に襲われた。後からは槍で追い立てられ、登れば死が待っていると分かっていながら進むしかなかった雑兵達の恐怖と悲哀に身がすくむ思いがする。


2009年12月26日
飯山,柄山スノーシューハイク
雪の野山を歩くスノーシュー&歩くスキーハイク
里山楽会・境界線2月山行 参加者:木偶野呂馬,他7名 記録者:木偶野呂馬


09年2月14日(土)
奈良市の友人,M氏が飯山市柄山に古民家を借りており、雪かきをすることを条件に自由に使わせてもらえることになっているので、その古民家を宿舎として、雪の野山を歩くスノーシュー&歩くスキーハイクを企画した。おりしもM氏が彼の友人で近年奈良から安曇野に移住したS氏を伴って柄山に来ており、我が境界線のメンバーと併せて8名の賑やかな山行となった。


例年よりはるかに少ないとは言え雪は軒のすぐ下まであり、1日早く着いたM氏とS氏が前日から頑張ったそうだが、玄関周りも庭もまだまだ大量の雪が・・。
すぐに全員で作業にかかり、人数にものを言わせて奮闘2時間弱で地面が見えるほどになった。M氏も『ここまでになるとは・・』と満足そう。
昼食後,さっそく裏山のブナ林から上の農場方面に向けてスノーシューハイキングに出かける。その案内をM氏に任せて1人残り、夜の宴の準備にかかる。


ハイキングを終えて冷えた身体を地元の温泉で温め、夜は暖かい部屋で合成にブイヤベースを囲んで持ち寄りの地酒を酌み交わしながら交流・・。
自己紹介を兼ねてそれぞれの山への思いをこもごもに語るうちに初対面同士和やかにうちとけて宴たけなわとなり、かくして柄山の夜はふける・・。


2月15日(日)
温井と柄山をつなぐ農道『みゆきのライン』のスノーシェードのある辺りからスノーシュー,スキーに履き替え、広大な農地の雪原を歩いて信越トレイル稜線上の梨平峠を目指す。農地を越えて距離3kmあまりの尾根を登る。
前日の重苦しく暗い空から一転してピーカンの空模様となり、8時過ぎにして早くも陽射しが暑く汗が目に入る。シールのある山スキーならともかく歩くスキーでの登高には無理があり、立ちはだかる斜面に最初からたじろぐ。


歩き始めて30分,鍋倉山を望む丘に出た。そこから目の前の大きなピークに向けての本格的な登りとなり、小気味よく登って行くスノーシュー組からは大きく遅れてしまった。一歩一歩ステップを切って階段登高で行くしかなく、ゆっくり追いかけると腹を決めた。急斜面との格闘20分でピークに這い上がり、ようやく先行するスノーシューを捉える。前方に信越トレイルの稜線が見えてきた。


そこから先に広大な農地が広がっており、緩やかになった斜面を登り詰めて行くと、『この林を切り開いて農地にしました』と見本のようにブナ林が残されている場所に出た。抜けるような青空が広がり、ジリジリと照りつける太陽が眩しくも暑くもあって日陰が欲しい頃合いだったのでそこから林の中に入る。


過密なほどの若いブナの純林を進むうちにそこがまだ開発されていない山林の末端であることが分かる。ひときわ目を引く瘤を抱えた特異な風貌のブナを見る。このような巨大なものは珍しい。
例年の3分の1しか無いと地元の人が言うほど雪の無い冬。豪雪地帯の飯山にしてこの有様で、早くも根回り穴が口を空けている。4月下旬の様相だ。


密林を抜けるとやや疎林となるがどこまでも続くブナ林である。そこから本格的な登りが始まるり、やがて急斜面の連続となる尾根ではスノーシューが抜群の威力を発揮するのに比べて歩くスキーは四苦八苦して一行からは大きく遅れ、奮闘4時間弱でようやく稜線に到達。そこはしかし目指す梨平峠より一山北よりだと言うことが分かり、スキーでその山を越えて梨平峠を目指すのを断念する。一行の中、M氏とS氏の2人が峠まで行って来るのを待って下山する。


歩くスキーでの急斜面の下山は登り以上に難しく、あまりの急斜面ではスキーを脱いでツボ足で下ったり、スキーを流して谷底まで回収に行ったりと散々で、帰りも大幅に遅れを取った。
それでもスノーシューを履く気にはなれないので、次からはどこかでスキーをデポしてワカンで歩くことにする。


里山楽会・境界線2月山行 参加者:木偶野呂馬,他7名 記録者:木偶野呂馬


09年2月14日(土)
奈良市の友人,M氏が飯山市柄山に古民家を借りており、雪かきをすることを条件に自由に使わせてもらえることになっているので、その古民家を宿舎として、雪の野山を歩くスノーシュー&歩くスキーハイクを企画した。おりしもM氏が彼の友人で近年奈良から安曇野に移住したS氏を伴って柄山に来ており、我が境界線のメンバーと併せて8名の賑やかな山行となった。


例年よりはるかに少ないとは言え雪は軒のすぐ下まであり、1日早く着いたM氏とS氏が前日から頑張ったそうだが、玄関周りも庭もまだまだ大量の雪が・・。
すぐに全員で作業にかかり、人数にものを言わせて奮闘2時間弱で地面が見えるほどになった。M氏も『ここまでになるとは・・』と満足そう。
昼食後,さっそく裏山のブナ林から上の農場方面に向けてスノーシューハイキングに出かける。その案内をM氏に任せて1人残り、夜の宴の準備にかかる。


ハイキングを終えて冷えた身体を地元の温泉で温め、夜は暖かい部屋で合成にブイヤベースを囲んで持ち寄りの地酒を酌み交わしながら交流・・。
自己紹介を兼ねてそれぞれの山への思いをこもごもに語るうちに初対面同士和やかにうちとけて宴たけなわとなり、かくして柄山の夜はふける・・。


2月15日(日)
温井と柄山をつなぐ農道『みゆきのライン』のスノーシェードのある辺りからスノーシュー,スキーに履き替え、広大な農地の雪原を歩いて信越トレイル稜線上の梨平峠を目指す。農地を越えて距離3kmあまりの尾根を登る。
前日の重苦しく暗い空から一転してピーカンの空模様となり、8時過ぎにして早くも陽射しが暑く汗が目に入る。シールのある山スキーならともかく歩くスキーでの登高には無理があり、立ちはだかる斜面に最初からたじろぐ。


歩き始めて30分,鍋倉山を望む丘に出た。そこから目の前の大きなピークに向けての本格的な登りとなり、小気味よく登って行くスノーシュー組からは大きく遅れてしまった。一歩一歩ステップを切って階段登高で行くしかなく、ゆっくり追いかけると腹を決めた。急斜面との格闘20分でピークに這い上がり、ようやく先行するスノーシューを捉える。前方に信越トレイルの稜線が見えてきた。


そこから先に広大な農地が広がっており、緩やかになった斜面を登り詰めて行くと、『この林を切り開いて農地にしました』と見本のようにブナ林が残されている場所に出た。抜けるような青空が広がり、ジリジリと照りつける太陽が眩しくも暑くもあって日陰が欲しい頃合いだったのでそこから林の中に入る。


過密なほどの若いブナの純林を進むうちにそこがまだ開発されていない山林の末端であることが分かる。ひときわ目を引く瘤を抱えた特異な風貌のブナを見る。このような巨大なものは珍しい。
例年の3分の1しか無いと地元の人が言うほど雪の無い冬。豪雪地帯の飯山にしてこの有様で、早くも根回り穴が口を空けている。4月下旬の様相だ。


密林を抜けるとやや疎林となるがどこまでも続くブナ林である。そこから本格的な登りが始まるり、やがて急斜面の連続となる尾根ではスノーシューが抜群の威力を発揮するのに比べて歩くスキーは四苦八苦して一行からは大きく遅れ、奮闘4時間弱でようやく稜線に到達。そこはしかし目指す梨平峠より一山北よりだと言うことが分かり、スキーでその山を越えて梨平峠を目指すのを断念する。一行の中、M氏とS氏の2人が峠まで行って来るのを待って下山する。


歩くスキーでの急斜面の下山は登り以上に難しく、あまりの急斜面ではスキーを脱いでツボ足で下ったり、スキーを流して谷底まで回収に行ったりと散々で、帰りも大幅に遅れを取った。
それでもスノーシューを履く気にはなれないので、次からはどこかでスキーをデポしてワカンで歩くことにする。


2009年12月24日
聖山・あがりこ伝説~元日登山・2
聖山・あがりこ伝説~元日登山・2
09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏

元日の朝,虫倉山に登った後,じゅんちゃが『もう1つやろうよ』と言い、聖山に登る。思いがけずそこでブナの『あがりこ』を見る。

いつごろ切られてこうなったのか・・,かつてこの山は何もない平原だったと聞くが、おそらくそれは戦後の皆伐時代の所業なのかもしれない。しかし、こう言う風に胸高の位置から無数の株が立ち上がるのは、普通は意図的に彦生えが出るのをねらったものとしか考えられない。
即ち、薪炭材等として樹木を利用する場合,根元から伐採すると新しく植えなおすか、植栽に寄らず天然更新に期待するしかなく、植栽の場合は30年以上かかるし、ブナの天然更新などは考えられもしない。それが、胸高で伐ってそこから発生する彦生えが成長するのを利用すれば15~20年で再び利用できるのだ。
これを萌芽更新と言い、場所を少しづつ変えて行けば15~20年後にはまた元に戻って彦生えを利用できると言う訳で、古くからコナラやクヌギなどの林は薪炭材や堆肥として利用され、里山はこのように人々が管理することで維持されてきた。


聖山でブナのあがりこが見られるのは意外なことだ。それはブナという木が人々の生活圏の中で共生するコナラやクヌギ等と違って1300m以上の高山でしか見られない木であり、そこは必ずしも里山とは言い難い山であること,また奥山のブナはパルプとして伐られることはあっても薪炭材にするためにわざわざ苦労して1400m余りもの高所に伐り出しに行くとは考えにくいこと等に因る。さらに言えば、萌芽更新の場合は『もやわけ』と言って無数にある萌芽を2~3本だけ残して間引く作業が行われるので、このようにたくさんの彦生えが乱立することはない。
同じようなあがりこが松本市のすぐそばの戸谷峰でも見られたが、戸谷峰に至っては1600mもの高山であることから、さらに理解しがたい。
聖山と戸谷峰に共通するあがりこの不思議・・。両方とも一過性の伐採が行われたのではないか・・,と言う気がするが、何の目的でこのような伐り方がされたのか、これは立ち入って調べて見なくては・・,と思いながらそのままなっていたことである。


それはそれとして聖山のブナを存分に楽しんできた。聖山は高原状の山で、山頂付近は強い風に吹き晒らされる。このような場所では樹木は高く突出することを避け、平均の中に自己を埋没させることで生き延びようとするのでおしなべて丈が低く、細い幹をひょろひょろとくねらせる特徴的な姿を見せる。この点はブナも例外ではないが、それでもブナにはブナの風格がある。

200mほど下がった林道付近は見事なカラマツ林だった。冬は木々が葉を落とし林内のすべてを見渡せるのがいい。そこに雪があればさらに嬉しいではないか!
09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏

元日の朝,虫倉山に登った後,じゅんちゃが『もう1つやろうよ』と言い、聖山に登る。思いがけずそこでブナの『あがりこ』を見る。

いつごろ切られてこうなったのか・・,かつてこの山は何もない平原だったと聞くが、おそらくそれは戦後の皆伐時代の所業なのかもしれない。しかし、こう言う風に胸高の位置から無数の株が立ち上がるのは、普通は意図的に彦生えが出るのをねらったものとしか考えられない。
即ち、薪炭材等として樹木を利用する場合,根元から伐採すると新しく植えなおすか、植栽に寄らず天然更新に期待するしかなく、植栽の場合は30年以上かかるし、ブナの天然更新などは考えられもしない。それが、胸高で伐ってそこから発生する彦生えが成長するのを利用すれば15~20年で再び利用できるのだ。
これを萌芽更新と言い、場所を少しづつ変えて行けば15~20年後にはまた元に戻って彦生えを利用できると言う訳で、古くからコナラやクヌギなどの林は薪炭材や堆肥として利用され、里山はこのように人々が管理することで維持されてきた。


聖山でブナのあがりこが見られるのは意外なことだ。それはブナという木が人々の生活圏の中で共生するコナラやクヌギ等と違って1300m以上の高山でしか見られない木であり、そこは必ずしも里山とは言い難い山であること,また奥山のブナはパルプとして伐られることはあっても薪炭材にするためにわざわざ苦労して1400m余りもの高所に伐り出しに行くとは考えにくいこと等に因る。さらに言えば、萌芽更新の場合は『もやわけ』と言って無数にある萌芽を2~3本だけ残して間引く作業が行われるので、このようにたくさんの彦生えが乱立することはない。
同じようなあがりこが松本市のすぐそばの戸谷峰でも見られたが、戸谷峰に至っては1600mもの高山であることから、さらに理解しがたい。
聖山と戸谷峰に共通するあがりこの不思議・・。両方とも一過性の伐採が行われたのではないか・・,と言う気がするが、何の目的でこのような伐り方がされたのか、これは立ち入って調べて見なくては・・,と思いながらそのままなっていたことである。


それはそれとして聖山のブナを存分に楽しんできた。聖山は高原状の山で、山頂付近は強い風に吹き晒らされる。このような場所では樹木は高く突出することを避け、平均の中に自己を埋没させることで生き延びようとするのでおしなべて丈が低く、細い幹をひょろひょろとくねらせる特徴的な姿を見せる。この点はブナも例外ではないが、それでもブナにはブナの風格がある。

200mほど下がった林道付近は見事なカラマツ林だった。冬は木々が葉を落とし林内のすべてを見渡せるのがいい。そこに雪があればさらに嬉しいではないか!
Posted by okirakutozan at
01:13
│Comments(0)
2009年12月24日
虫倉山
山姥伝説・虫倉山不動滝コース~元日登山・1
09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏


2009年の元日登山は中条村の虫倉山(1378m)。
林道終点に車を止めて5:45発。知らない山なのでリードを相方のじゅんちゃにまかせっきりで暗い道をただついていくだけ。


6:34 木の間越しに東の空が赤く染まるのを見る。肝心な時にはいつも言うことを聞かないカメラをなだめすかしている間に相方から大きく遅れ、山頂に着いたのは日の出の後だった。


着く早々にお屠蘇をふるまわれる。虫倉山には2パーティー,約10名の先客が古典的な新年の宴を張っていた。すなわち60~70年代型の大きなコッヘェルに将棋の駒型の煤けたポリタンク,コンロだけは現代風のガスでつくるのはもちろん雑煮。油を持参してフライパンで揚げてから煮ているパーティーもあって本腰だ。1つは地元中条村,もう1つは信州新町からのパーティーで恒例の新年登山のようだ。


はじめから薄着で登ればよかったものを、バッチリかためて歩き始めたのでいつもより余分に汗をかいてしまった。思い切ってシャツを脱いで乾かす。
天候は悪くはないのだがめまぐるしく動くガスが山頂付近にあり、指呼の間の戸隠山はおろか、妙高・火打方面も白馬・北アルプス方面も展望が利かず、長居は無用と早々に下山する。


登りは5:45発,7:18着,1時間35分。下りは7:45発,8:35着,50分。


09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏


2009年の元日登山は中条村の虫倉山(1378m)。
林道終点に車を止めて5:45発。知らない山なのでリードを相方のじゅんちゃにまかせっきりで暗い道をただついていくだけ。


6:34 木の間越しに東の空が赤く染まるのを見る。肝心な時にはいつも言うことを聞かないカメラをなだめすかしている間に相方から大きく遅れ、山頂に着いたのは日の出の後だった。


着く早々にお屠蘇をふるまわれる。虫倉山には2パーティー,約10名の先客が古典的な新年の宴を張っていた。すなわち60~70年代型の大きなコッヘェルに将棋の駒型の煤けたポリタンク,コンロだけは現代風のガスでつくるのはもちろん雑煮。油を持参してフライパンで揚げてから煮ているパーティーもあって本腰だ。1つは地元中条村,もう1つは信州新町からのパーティーで恒例の新年登山のようだ。


はじめから薄着で登ればよかったものを、バッチリかためて歩き始めたのでいつもより余分に汗をかいてしまった。思い切ってシャツを脱いで乾かす。
天候は悪くはないのだがめまぐるしく動くガスが山頂付近にあり、指呼の間の戸隠山はおろか、妙高・火打方面も白馬・北アルプス方面も展望が利かず、長居は無用と早々に下山する。


登りは5:45発,7:18着,1時間35分。下りは7:45発,8:35着,50分。


2009年12月23日
南沢岳から不動岳・船窪岳~七倉へ
南沢岳から不動岳・船窪岳~七倉へ
北アルプス裏銀座,逆縦走
6月14日(日) 木偶野呂馬&G3氏
1;コース状況/その他周辺情報:

③南沢岳から不動岳に向かう鞍部の手前で大量の雪のため道は分からなくなり、稜線の縁を避けて左に寄るあまり下がり過ぎてしまった。このため南沢岳から不動岳まで2時間半を要して大きな遅れが生じた。不動岳から船窪岳まではアップダウンが激しく、また鞍部付近に悪場がある上にここでも大量の雪で難渋させられ、大幅に時間をロスして船窪小屋着が予定より4時間近く遅れた。
④本来なら1泊では無理な行程であり、船窪小屋に16時過ぎに着いたことをよしとしてここでもう1泊すべきであるしその用意もあったが、夜道に日暮れ無しと言うことで真っ暗闇の中、下山を強行した結果5時間を要した。



2;行動の記録
6月14日(日)
4時になるのを待って起きる。前夜食べなかったアルファ米1袋とレトルトのカレーがあったが、これを湯煎するのもまた用意したアルファ米のリゾットを湯戻しするのも時間がかかるので、お湯を沸かして残った握り飯と簡単スープを流し込む。融かした雪でお茶を作って飲料を確保し、6:00出発。
6:08,南沢岳の三角点を通過。前日,通過したピークは山頂ではなかったようで、標高2625mは今回の縦走最高地点。目の前には不動岳西面の大崩れが見えているが、その間には南沢乗越の深い切れ込みがあってここからは200mあまりの下りとなる。



不動岳西側の高瀬ダム側は、前日最後に渡った濁沢の源頭部に当たっており激しく崩落している。それは乗越を隔てたこちら側の南沢岳も同じで、登山道は稜線の縁である崩落した部分とハイマツ帯の境目を通っているので気が抜けない。
この辺りから残雪が多くなり、雪の急斜面の下降を余儀なくされる場面もしばしばで、その途中でスリップして5mほど滑りハイマツ帯に突っ込む。しばらくの後腕時計がなくなっているのに気づいたが引き返すにはすでに遅すぎた。
そう言う雪で寸断された難しい道であっても、雪が融けた所には春が来て草が芽吹き、花が咲く。
6:45,南沢乗越を通過して大きくガレた不動岳の前ピークの登りに入る。西面は急登だが雪がなく花が豊富で、ユキザサに混じってキヌガサソウやショウジョウバカマが見られるようになる。キヌガサソウの芽だしはユキザサをそのまま太くしたような感じで両者が非常によく似ていることを知る。



ふり返ると先ほど下ってきた南沢岳からの道がよく分かり、またはるか遠方には烏帽子岳の奇怪な山頂を望むことができた。
7:25,前ピークに到達。10分休んで展望を楽しむ。南沢岳からここまでは1時間25分。大幅ではないが予定をややオーバーしているのは雪が多いせいか・・。
7:35分。不動岳まで順調に行けば20分ほどの道であるが、ここから登山道が完全に雪に閉ざされて分からなくなった。右側の様子が分からないので稜線の縁を避けて左側の雪面を斜めに下り、樹林帯を突破しようとしているうちに稜線からかなり離れた位置まで下ってしまった。
道を見失い、遮二無二ブッシュをかき分けて抜けると広くて分厚い雪の斜面に突き当たる。幅40m,下に向かってどこまでも続く大斜面で長さは計り知れない。目印を探したが何もなく、その上悪いことにG氏が潅木に眼鏡を取られて探しに戻るというアクシデントが起きた。
ここは斜面を登って稜線に出る道を探すか、ハイマツ帯を突破するしかないと覚悟を決めて急斜面を登る。
雪の斜面を斜めに横断しながら登りきると道があった。上からハイマツを踏んで下ってくるなら兎も角、下からハイマツ帯を突破して登る等,口では言えてもできるものではない。この道がなかったら稜線に出るのは不可能に近く、樹林帯に迷い込んだ位置まで戻るしかなかったかもしれない。
8:35不動岳着。テン場から2時間35分と夏道の2倍の時間を要し大幅に遅れが出た。倒れた山頂標識を2人で立て直したり、写真を撮ったりしてやや長めの休憩をとる。烏帽子ははるか遠くなり、南沢岳にかけてガスが立ち始めていた。



8:55発。しばらくは不動沢側が大きくガレた稜線の縁を歩く。黒部側がハイマツ帯なので問題はないが、道の所々にひびが入っていてその道もいずれは崩落していくものと思われた。前日の大腿部側方の痛みは跡形もなく消えたが、この日は下りの際の深い屈曲で大腿部前面に痙攣が来ており、一抹の不安を抱えたまま船窪岳への登りにかかる。
目標までに第2ピークを含むまで3つのピークを越えなければならず、船窪小屋までは5時間弱,七倉へはさらに4時間の下降で明るいうちに下山するのは難しい情勢になってきた。



9:38,1つ目のピークにかかる。穏やかな登りでミツバオーレンの花に混じって何故かツルリンドウの赤い実が見られた。
10:07,2341mのピークに到達。目の前に第2ピークへと続く岩稜帯の岩肌を見る。日当たりのいい岩場の縁にコイワカガミが咲き、少し樹林帯に寄った辺りにはショウジョウバカマが見られる。



ロープやワイヤーのある岩場をさらに1時間40分歩き、それとわからぬままに2つ目のピーク(2299m)を越えて11:55船窪第2P(2459m)に着く。不動岳から3時間,この間にいくつものアップダウンがあり、その度に雪渓があって大幅に時間を食い、目標とする時刻より1時間近い遅れが生じていた。
ここから船窪乗越までは夏道で1時間10分,船窪小屋まではさらに1時間10分を要するので14時までに小屋へ着くのは難しいかもしれないが、ビバークの用意はあるので花を見ながら急がずに歩いてきた。



雪に覆われた第2Pからはガスで東半分を隠されて槍のように天を突く唐沢岳や七倉岳方面,最後の稜線歩きとなる船窪CP場への道,また北北東から真北にかけて蓮華岳・針の木岳の大きな山塊を見る。
12:20発。ここから船窪岳までの道は小さなアップダウンにワイヤーと梯子が連続し、足場の定まらない場所もある不安定な道。12:57,小さな鞍部を越えて急登にかかるとそこからシラネアオイの大群落が始まり、感嘆の声を上げながらしばらくは写真に没頭。最後にミネザクラの花を見るが、そこから最も険悪な鞍部への足場の悪い急降下となる。
邪魔なワイヤーを避けながら下りきるとすぐに登り返しとなるが、掴んだ岩が脆くて剥がれ、岩を抱いたまま背中から1mほどずり落ちる。右手(稜線側)の岩が谷側にせり出しているので逆コース(下り=前回)にとってはさらに難しい所だ。13:20に通過。
悪場はさらに続き、壊れた丸太の足場,半ば腐ったロープ場を越えてひと登りでようやく崩れた稜線の縁に出る。10分で船窪岳に着(13:41)き、20分の休憩。



14:00発。下って14:07船窪乗越を通過。前回は針の木谷から登って来てここで烏帽子岳へのコースに合流したのでここから先は未知のルートとなる。
乗越を越えると北葛岳が正面になり、どんどんとそちらに近づいて行く感じになる。船窪・七倉岳への道はそこから大きく右に曲がり、やがて北葛岳が遠のいて正面に七倉岳が見えてくる。
14:34,再び現れたシラネアオイの花を撮る間にG氏が先行。ここまで水の量に不安があり雪を食べながら歩いて来たので水場のあるキャンプ場の位置が気になって仕方がない。



14:54,再び稜線の縁に出て眼下に不動沢最深部の荒々しい岩場を見る。暑くなり渇きを覚え、水場を期待しつつさらに20分歩いて15:14,キャンプ場に着く。水を確保できることで安心する。
だがキャンプ場に期待した水場はなく、あったのは雪田の下部に出来た小さな水溜りだった。水面に小さな虫が浮いてはいるが水は澄んでいるので濁らせないように静かにボトルに詰めてそれを飲み、さらにもう1本のボトルに詰めて船窪からの下りに備えることにする。虫の死骸などもはや気にもならない。
本来の水場は北葛側の谷の方にあったらしいのだが、そちらを探す余裕はなかったのだ。



15:39発。階段を登って右にゆっくり斜上する道を行く。その道は不動岳からずっと見えていた七倉岳の尾根に向かう道であり、船窪小屋はその尾根のラインの向こう側にある。
16:03七倉・北葛岳方面に向かう分岐点を通過。16:08明るいハイマツ帯の中、青い屋根の船窪小屋見る。16:11着。



以下,編集中
北アルプス裏銀座,逆縦走
6月14日(日) 木偶野呂馬&G3氏
1;コース状況/その他周辺情報:

③南沢岳から不動岳に向かう鞍部の手前で大量の雪のため道は分からなくなり、稜線の縁を避けて左に寄るあまり下がり過ぎてしまった。このため南沢岳から不動岳まで2時間半を要して大きな遅れが生じた。不動岳から船窪岳まではアップダウンが激しく、また鞍部付近に悪場がある上にここでも大量の雪で難渋させられ、大幅に時間をロスして船窪小屋着が予定より4時間近く遅れた。
④本来なら1泊では無理な行程であり、船窪小屋に16時過ぎに着いたことをよしとしてここでもう1泊すべきであるしその用意もあったが、夜道に日暮れ無しと言うことで真っ暗闇の中、下山を強行した結果5時間を要した。



2;行動の記録
6月14日(日)
4時になるのを待って起きる。前夜食べなかったアルファ米1袋とレトルトのカレーがあったが、これを湯煎するのもまた用意したアルファ米のリゾットを湯戻しするのも時間がかかるので、お湯を沸かして残った握り飯と簡単スープを流し込む。融かした雪でお茶を作って飲料を確保し、6:00出発。
6:08,南沢岳の三角点を通過。前日,通過したピークは山頂ではなかったようで、標高2625mは今回の縦走最高地点。目の前には不動岳西面の大崩れが見えているが、その間には南沢乗越の深い切れ込みがあってここからは200mあまりの下りとなる。



不動岳西側の高瀬ダム側は、前日最後に渡った濁沢の源頭部に当たっており激しく崩落している。それは乗越を隔てたこちら側の南沢岳も同じで、登山道は稜線の縁である崩落した部分とハイマツ帯の境目を通っているので気が抜けない。
この辺りから残雪が多くなり、雪の急斜面の下降を余儀なくされる場面もしばしばで、その途中でスリップして5mほど滑りハイマツ帯に突っ込む。しばらくの後腕時計がなくなっているのに気づいたが引き返すにはすでに遅すぎた。
そう言う雪で寸断された難しい道であっても、雪が融けた所には春が来て草が芽吹き、花が咲く。
6:45,南沢乗越を通過して大きくガレた不動岳の前ピークの登りに入る。西面は急登だが雪がなく花が豊富で、ユキザサに混じってキヌガサソウやショウジョウバカマが見られるようになる。キヌガサソウの芽だしはユキザサをそのまま太くしたような感じで両者が非常によく似ていることを知る。



ふり返ると先ほど下ってきた南沢岳からの道がよく分かり、またはるか遠方には烏帽子岳の奇怪な山頂を望むことができた。
7:25,前ピークに到達。10分休んで展望を楽しむ。南沢岳からここまでは1時間25分。大幅ではないが予定をややオーバーしているのは雪が多いせいか・・。
7:35分。不動岳まで順調に行けば20分ほどの道であるが、ここから登山道が完全に雪に閉ざされて分からなくなった。右側の様子が分からないので稜線の縁を避けて左側の雪面を斜めに下り、樹林帯を突破しようとしているうちに稜線からかなり離れた位置まで下ってしまった。
道を見失い、遮二無二ブッシュをかき分けて抜けると広くて分厚い雪の斜面に突き当たる。幅40m,下に向かってどこまでも続く大斜面で長さは計り知れない。目印を探したが何もなく、その上悪いことにG氏が潅木に眼鏡を取られて探しに戻るというアクシデントが起きた。
ここは斜面を登って稜線に出る道を探すか、ハイマツ帯を突破するしかないと覚悟を決めて急斜面を登る。
雪の斜面を斜めに横断しながら登りきると道があった。上からハイマツを踏んで下ってくるなら兎も角、下からハイマツ帯を突破して登る等,口では言えてもできるものではない。この道がなかったら稜線に出るのは不可能に近く、樹林帯に迷い込んだ位置まで戻るしかなかったかもしれない。
8:35不動岳着。テン場から2時間35分と夏道の2倍の時間を要し大幅に遅れが出た。倒れた山頂標識を2人で立て直したり、写真を撮ったりしてやや長めの休憩をとる。烏帽子ははるか遠くなり、南沢岳にかけてガスが立ち始めていた。



8:55発。しばらくは不動沢側が大きくガレた稜線の縁を歩く。黒部側がハイマツ帯なので問題はないが、道の所々にひびが入っていてその道もいずれは崩落していくものと思われた。前日の大腿部側方の痛みは跡形もなく消えたが、この日は下りの際の深い屈曲で大腿部前面に痙攣が来ており、一抹の不安を抱えたまま船窪岳への登りにかかる。
目標までに第2ピークを含むまで3つのピークを越えなければならず、船窪小屋までは5時間弱,七倉へはさらに4時間の下降で明るいうちに下山するのは難しい情勢になってきた。



9:38,1つ目のピークにかかる。穏やかな登りでミツバオーレンの花に混じって何故かツルリンドウの赤い実が見られた。
10:07,2341mのピークに到達。目の前に第2ピークへと続く岩稜帯の岩肌を見る。日当たりのいい岩場の縁にコイワカガミが咲き、少し樹林帯に寄った辺りにはショウジョウバカマが見られる。



ロープやワイヤーのある岩場をさらに1時間40分歩き、それとわからぬままに2つ目のピーク(2299m)を越えて11:55船窪第2P(2459m)に着く。不動岳から3時間,この間にいくつものアップダウンがあり、その度に雪渓があって大幅に時間を食い、目標とする時刻より1時間近い遅れが生じていた。
ここから船窪乗越までは夏道で1時間10分,船窪小屋まではさらに1時間10分を要するので14時までに小屋へ着くのは難しいかもしれないが、ビバークの用意はあるので花を見ながら急がずに歩いてきた。



雪に覆われた第2Pからはガスで東半分を隠されて槍のように天を突く唐沢岳や七倉岳方面,最後の稜線歩きとなる船窪CP場への道,また北北東から真北にかけて蓮華岳・針の木岳の大きな山塊を見る。
12:20発。ここから船窪岳までの道は小さなアップダウンにワイヤーと梯子が連続し、足場の定まらない場所もある不安定な道。12:57,小さな鞍部を越えて急登にかかるとそこからシラネアオイの大群落が始まり、感嘆の声を上げながらしばらくは写真に没頭。最後にミネザクラの花を見るが、そこから最も険悪な鞍部への足場の悪い急降下となる。
邪魔なワイヤーを避けながら下りきるとすぐに登り返しとなるが、掴んだ岩が脆くて剥がれ、岩を抱いたまま背中から1mほどずり落ちる。右手(稜線側)の岩が谷側にせり出しているので逆コース(下り=前回)にとってはさらに難しい所だ。13:20に通過。
悪場はさらに続き、壊れた丸太の足場,半ば腐ったロープ場を越えてひと登りでようやく崩れた稜線の縁に出る。10分で船窪岳に着(13:41)き、20分の休憩。



14:00発。下って14:07船窪乗越を通過。前回は針の木谷から登って来てここで烏帽子岳へのコースに合流したのでここから先は未知のルートとなる。
乗越を越えると北葛岳が正面になり、どんどんとそちらに近づいて行く感じになる。船窪・七倉岳への道はそこから大きく右に曲がり、やがて北葛岳が遠のいて正面に七倉岳が見えてくる。
14:34,再び現れたシラネアオイの花を撮る間にG氏が先行。ここまで水の量に不安があり雪を食べながら歩いて来たので水場のあるキャンプ場の位置が気になって仕方がない。



14:54,再び稜線の縁に出て眼下に不動沢最深部の荒々しい岩場を見る。暑くなり渇きを覚え、水場を期待しつつさらに20分歩いて15:14,キャンプ場に着く。水を確保できることで安心する。
だがキャンプ場に期待した水場はなく、あったのは雪田の下部に出来た小さな水溜りだった。水面に小さな虫が浮いてはいるが水は澄んでいるので濁らせないように静かにボトルに詰めてそれを飲み、さらにもう1本のボトルに詰めて船窪からの下りに備えることにする。虫の死骸などもはや気にもならない。
本来の水場は北葛側の谷の方にあったらしいのだが、そちらを探す余裕はなかったのだ。



15:39発。階段を登って右にゆっくり斜上する道を行く。その道は不動岳からずっと見えていた七倉岳の尾根に向かう道であり、船窪小屋はその尾根のラインの向こう側にある。
16:03七倉・北葛岳方面に向かう分岐点を通過。16:08明るいハイマツ帯の中、青い屋根の船窪小屋見る。16:11着。



以下,編集中
2009年12月23日
日本3坂・ブナ立尾根
日本3坂・ブナ立尾根~1日目・七倉ダムから烏帽子・南沢岳へ
北アルプス裏銀座コース・七倉ダム~烏帽子岳,南沢岳
6月13日(土) 1日目 木偶野呂馬&G3氏
1;コース状況/その他周辺情報

①ブナ立尾根は衆知の急登。2208mの三角点付近から雪が現れる。右手に不動岳方面が見える尾根に出て左にカーブし、ダケカンバの大木を見る辺りからシラビソ帯となり大量の雪を抱えた急斜面の登りとなる。右手の斜面をなるべく避けて左よりの樹林との際を進む。急斜面はどこが登山道か分からないが、異形のダケカンバの下に標識№1があり、そこからは登山道を辿って烏帽子小屋まで一息である。
②烏帽子小屋から烏帽子岳,南沢岳方面へは雪があったりなかったりであるが、北進するにつれて雪が多くなる。南沢岳の手前の平原状の場所は二重山稜のようになっており、南側に見える雪のない尾根の方へ行こうとして迷走し、ハイマツ帯を突破できずに元に戻るのに1時間20分を要した。南沢岳の西のピークの下に雪があって風があまり来ないビバーク点があった。



2;行動の記録
6月13日(土)
登山ブログで交流のあるG3氏との間でブナ立尾根を登ってみませんかと言う話しがまとまり、前夜のうちに静岡市から来て仮眠していたG3氏と七倉ダムのゲートで落ち合う。初対面の挨拶もそこそこにそれぞれパッキングして5:35から歩き始める。
高瀬ダムまでの3.7kmを歩いて6:32ダム下休憩。ロックフィルダムに取り付けられたこっちから向こうまで2往復半,1kmの車道を歩くのは馬鹿らしいので大岩を直登して20分で高瀬ダム堰堤に着く(6:55)。
ダム左岸の不動トンネルを抜けて不動沢の長いつり橋を渡ると河川敷に出る。鉄製の梯子道に導かれて濁り沢の吊り橋を渡り、水を補給して7:35から登山道に入るといきなり急登が始まる。『11』と書かれた標識があるが意味不明。長丁場なので休まずゆっくり登り、8:28,『落石注意』と書かれた標識NO『9』の巨岩,通称『権太落とし』で最初の休憩。
8:35出発。直後にパラパラッと雨が来て、雨の多い南アの人らしくG3氏は素早く雨具とザックカバーを着ける。自分は面倒なので様子を見ながら先行。足元にツバメオモトの花,次いでシラネアオイの花を見て『そう言う季節なのだ』と頭が下界とは違う世界に反応し始める。こうして写真を撮りながら徐々に高度を上げるうちに気持ちも体もその世界に順応して行くのだろう・・。
9:05,標識NO『7』を通過。シラネアオイが見事なのでG3氏にはゆっくり写真を撮ってもらう。



9:42,標識NO『6』に着き2度目の休憩の際に雷鳴を聞く。G3氏によると『前線が通過する見込み』だそうだが、1日中雷につきまとわれるのではないかと不安になる。稜線での雷はゴメン蒙りたいものだ。
9:55発。今回の山行には幾つかの不安があった。早くもそれが的中したのか、左脚大腿の外側に痙攣痛を感じる。ごまかしながら歩いていると痙攣は内側に移行し、なおも我慢していると今度は右脚に移行した。
この冬は一度も冬山に登らなかったので体力に自信がない。加えて登山靴を修理に出したままでアップシューズや地下足袋での山行が続いたために足が登山靴の重さに耐え切れず、歩き始めからどうも左右にふらつくのが気になっていた。大腿部の外側と内側の痛みはその影響と思われた。筋肉は8時間動かさない状態が続くと退化を始めると言うから登山靴の重さや踏ん張りに対応する筋力が衰えているのは明らかであるが、それは使うことによって鍛えられ回復するのを待つしかない。



10:06,右手が開けて烏帽子岳,南沢岳の岩峰群や不動岳の大崩れを望める場所があり、ここで立ち止まって行く手の稜線を地図で確認している間に左右の大腿部両側の痛みがうそのように消えた。10:20,雨がやや強くなりG3氏に倣って雨具とカバーを着ける。マーフィーの法則通り着るとすぐに雨が上がり、20分後に雨具を脱ぐ。雷は去った模様。足元に小イワカガミやエンレイソウ,サンカヨウの花を見る10:31標識NO『5』を通過。
10:49,最初の雪渓が現れG3氏はここでアイゼンをつけたが自分はツボ足で通過。道はすぐに雪渓から離れ、10:59に標高2208mの三角点に着く。登山道に入ってからの所要時間は3時間25分。



11:20発。10分でタヌキ岩と言う巨岩を通過。さらに20分あまりで不動岳,船窪岳を望む場所に出る。そこからは尾根に沿って左にカーブしながら進み、右下がえぐれた場所を通過してダケカンバの大木を過ぎた辺りからシラビソ帯となり、12:24頃から大量の雪を抱えた稜線下の急登が始まる。



登山道が分らないので先頭を行くG3氏も見当をつけて遮二無二登って行くが、次第に斜面が傾斜をまして行くのも構わず平然と登っていくG3氏の後を追うのが恐くて左の樹林の際を行く。
最もそれを必要とするこの急斜面でなぜか2人ともアイゼンをつけず、自分はピッケルさえ背中に負ったままで登ってしまっていた。アイゼンやピッケルのことを考えもせずに雪面に入ってしまったのだが、いつの間にかとんでもない斜度になっていたのだ。



樹林の際を行くと雪の解けた場所から登山道が覗いており、異様な形状のダケカンバがあって標識NO『1』と書かれたその場所でしばらく休む。時刻13:16。ここまで、雪と格闘する間にたちまち時間が経過していたようだ。
すでに小屋に迫っているものと思っていたG氏も少し先で休んでいたらしく、歩き始めるとすぐ前を行く姿が見え、やがて主稜線と小屋への道を分ける標識に着くと目の前に烏帽子の小屋が現れる。
13:51着。三角点からは2時間30分で雪のため夏道の倍近くかかっていた。登山道に入ってからは約6時間,七倉のゲートからは8時間16分。



烏帽子小屋の前庭は立山や薬師岳を望む絶好の展望台で、しばらくはベンチに座ってG3氏が広げた地図で山を同定するなどしてくつろぎながら次の行程をどうするかを考える。
西側の目の前に横たわるのは赤牛岳でそこから左手に伸びた稜線の先に水晶岳があり、その稜線と裏銀座の主脈が合流するのが鷲場岳で、その手前が真砂岳,野口五郎岳と言うことになる。
一方,赤牛の背後に重なるのは薬師岳で、視線を北北東に転じた目の前には不動岳,その後に針の木岳が重なり、さらにその陰には鳴沢、赤沢辺りの山が見え隠れする。黒部ダムはその直下を西に越えたところであり、赤牛岳を目の前にするこの位置からは見えない。その西に位置する立山のカールらしきものは認められるが、剣岳は視認できなかった。
また、南側の眼前には唐沢岳が錐のように鋭く天を突き、その後から餓鬼岳の長い稜線が南に伸び、東沢の大だるみを隔てて燕岳の岩峰を望むことができる。そこから先の大天井岳や常念岳の吊り尾根も見えるが、槍・穂高岳方面はガスの中だ。



14:27,時間的にも体力的にも船窪方面への前進は可能との結論を得て烏帽子岳に向かい出発。ゆるやかに左にカーブするハイマツ帯の稜線を行く。この辺りは雪もなく快調。
2605mの前烏帽子から改めて周辺の山々を見る。何と言っても烏帽子岳の天に向かって合掌するかのような鋭い岩峰が圧巻で、柱のようにきれいに並んだ岩が美しい。この岩峰はしかし、進むにつれてそれまでとはまったく違った異様な姿へと変貌する。



15:08,烏帽子岳岩峰への分岐点に到達。時間が押しているので山頂には向かわず通過,一転して雪の斜面となる。南沢岳との鞍部は烏帽子田圃と言う湿原で、この辺りをビバークの候補地とも考えていたが、できればさらに進んでおきたかった。
湿原は凹地であり、一方の縁は烏帽子からの稜線でもう一方に並行する山稜があって二重山陵を形成していた。そのもう一方の小高い山陵に踏み後が見えたのでそこを目指して雪面を突き進んだが、もう少しと言うところで分厚いハイマツ帯に阻まれて進めなくなる。しばらくはあちらこちらと突破口を探したが無理と分り、後退を決めて下ってきた雪面を登り返し、最後はシラビソとハイマツの混じる薮の中を這うようにして突破し、16:29,登山道に戻る。烏帽子分岐から1時間20分のタイムロスとなる。



ここから南沢岳への登りの途中から急に冷たい西風が吹き始めて山頂下では霰が降る。
17:00,南沢岳(2625m)の前ピークに到達。ここをビバーク地点と決めて山頂東側直下の雪面を均しテントを張る。
雪を溶かした水を沸かしてアルファ米を戻し、レトルトのカレーを温めて用意したが、G3氏がつくってくれた梅酒のお湯わりを頂き、行動食を食べているうちに食事が面倒になり、G3氏によると『あぐらのまま鼾をかき始めた』とのことで結局カレーは食べずに横になる。



ひとしきり熟睡し、目が覚めて2時間近くじっと考え事をしながら夜明けを待つ。風に時おり雨音が混じる。
2時を廻ったかと時計を見るとまだ0時前で、それから悶々と時の過ぎるのを待ち、何度かまどろんでようやく4時を迎える。どんなに疲れていても3~4時間熟睡すれば充分で、後は時間をもてあますのが常の幕営である。
6月14日(日)へ続く
北アルプス裏銀座コース・七倉ダム~烏帽子岳,南沢岳
6月13日(土) 1日目 木偶野呂馬&G3氏
1;コース状況/その他周辺情報

①ブナ立尾根は衆知の急登。2208mの三角点付近から雪が現れる。右手に不動岳方面が見える尾根に出て左にカーブし、ダケカンバの大木を見る辺りからシラビソ帯となり大量の雪を抱えた急斜面の登りとなる。右手の斜面をなるべく避けて左よりの樹林との際を進む。急斜面はどこが登山道か分からないが、異形のダケカンバの下に標識№1があり、そこからは登山道を辿って烏帽子小屋まで一息である。
②烏帽子小屋から烏帽子岳,南沢岳方面へは雪があったりなかったりであるが、北進するにつれて雪が多くなる。南沢岳の手前の平原状の場所は二重山稜のようになっており、南側に見える雪のない尾根の方へ行こうとして迷走し、ハイマツ帯を突破できずに元に戻るのに1時間20分を要した。南沢岳の西のピークの下に雪があって風があまり来ないビバーク点があった。



2;行動の記録
6月13日(土)
登山ブログで交流のあるG3氏との間でブナ立尾根を登ってみませんかと言う話しがまとまり、前夜のうちに静岡市から来て仮眠していたG3氏と七倉ダムのゲートで落ち合う。初対面の挨拶もそこそこにそれぞれパッキングして5:35から歩き始める。
高瀬ダムまでの3.7kmを歩いて6:32ダム下休憩。ロックフィルダムに取り付けられたこっちから向こうまで2往復半,1kmの車道を歩くのは馬鹿らしいので大岩を直登して20分で高瀬ダム堰堤に着く(6:55)。
ダム左岸の不動トンネルを抜けて不動沢の長いつり橋を渡ると河川敷に出る。鉄製の梯子道に導かれて濁り沢の吊り橋を渡り、水を補給して7:35から登山道に入るといきなり急登が始まる。『11』と書かれた標識があるが意味不明。長丁場なので休まずゆっくり登り、8:28,『落石注意』と書かれた標識NO『9』の巨岩,通称『権太落とし』で最初の休憩。
8:35出発。直後にパラパラッと雨が来て、雨の多い南アの人らしくG3氏は素早く雨具とザックカバーを着ける。自分は面倒なので様子を見ながら先行。足元にツバメオモトの花,次いでシラネアオイの花を見て『そう言う季節なのだ』と頭が下界とは違う世界に反応し始める。こうして写真を撮りながら徐々に高度を上げるうちに気持ちも体もその世界に順応して行くのだろう・・。
9:05,標識NO『7』を通過。シラネアオイが見事なのでG3氏にはゆっくり写真を撮ってもらう。



9:42,標識NO『6』に着き2度目の休憩の際に雷鳴を聞く。G3氏によると『前線が通過する見込み』だそうだが、1日中雷につきまとわれるのではないかと不安になる。稜線での雷はゴメン蒙りたいものだ。
9:55発。今回の山行には幾つかの不安があった。早くもそれが的中したのか、左脚大腿の外側に痙攣痛を感じる。ごまかしながら歩いていると痙攣は内側に移行し、なおも我慢していると今度は右脚に移行した。
この冬は一度も冬山に登らなかったので体力に自信がない。加えて登山靴を修理に出したままでアップシューズや地下足袋での山行が続いたために足が登山靴の重さに耐え切れず、歩き始めからどうも左右にふらつくのが気になっていた。大腿部の外側と内側の痛みはその影響と思われた。筋肉は8時間動かさない状態が続くと退化を始めると言うから登山靴の重さや踏ん張りに対応する筋力が衰えているのは明らかであるが、それは使うことによって鍛えられ回復するのを待つしかない。



10:06,右手が開けて烏帽子岳,南沢岳の岩峰群や不動岳の大崩れを望める場所があり、ここで立ち止まって行く手の稜線を地図で確認している間に左右の大腿部両側の痛みがうそのように消えた。10:20,雨がやや強くなりG3氏に倣って雨具とカバーを着ける。マーフィーの法則通り着るとすぐに雨が上がり、20分後に雨具を脱ぐ。雷は去った模様。足元に小イワカガミやエンレイソウ,サンカヨウの花を見る10:31標識NO『5』を通過。
10:49,最初の雪渓が現れG3氏はここでアイゼンをつけたが自分はツボ足で通過。道はすぐに雪渓から離れ、10:59に標高2208mの三角点に着く。登山道に入ってからの所要時間は3時間25分。



11:20発。10分でタヌキ岩と言う巨岩を通過。さらに20分あまりで不動岳,船窪岳を望む場所に出る。そこからは尾根に沿って左にカーブしながら進み、右下がえぐれた場所を通過してダケカンバの大木を過ぎた辺りからシラビソ帯となり、12:24頃から大量の雪を抱えた稜線下の急登が始まる。



登山道が分らないので先頭を行くG3氏も見当をつけて遮二無二登って行くが、次第に斜面が傾斜をまして行くのも構わず平然と登っていくG3氏の後を追うのが恐くて左の樹林の際を行く。
最もそれを必要とするこの急斜面でなぜか2人ともアイゼンをつけず、自分はピッケルさえ背中に負ったままで登ってしまっていた。アイゼンやピッケルのことを考えもせずに雪面に入ってしまったのだが、いつの間にかとんでもない斜度になっていたのだ。



樹林の際を行くと雪の解けた場所から登山道が覗いており、異様な形状のダケカンバがあって標識NO『1』と書かれたその場所でしばらく休む。時刻13:16。ここまで、雪と格闘する間にたちまち時間が経過していたようだ。
すでに小屋に迫っているものと思っていたG氏も少し先で休んでいたらしく、歩き始めるとすぐ前を行く姿が見え、やがて主稜線と小屋への道を分ける標識に着くと目の前に烏帽子の小屋が現れる。
13:51着。三角点からは2時間30分で雪のため夏道の倍近くかかっていた。登山道に入ってからは約6時間,七倉のゲートからは8時間16分。



烏帽子小屋の前庭は立山や薬師岳を望む絶好の展望台で、しばらくはベンチに座ってG3氏が広げた地図で山を同定するなどしてくつろぎながら次の行程をどうするかを考える。
西側の目の前に横たわるのは赤牛岳でそこから左手に伸びた稜線の先に水晶岳があり、その稜線と裏銀座の主脈が合流するのが鷲場岳で、その手前が真砂岳,野口五郎岳と言うことになる。
一方,赤牛の背後に重なるのは薬師岳で、視線を北北東に転じた目の前には不動岳,その後に針の木岳が重なり、さらにその陰には鳴沢、赤沢辺りの山が見え隠れする。黒部ダムはその直下を西に越えたところであり、赤牛岳を目の前にするこの位置からは見えない。その西に位置する立山のカールらしきものは認められるが、剣岳は視認できなかった。
また、南側の眼前には唐沢岳が錐のように鋭く天を突き、その後から餓鬼岳の長い稜線が南に伸び、東沢の大だるみを隔てて燕岳の岩峰を望むことができる。そこから先の大天井岳や常念岳の吊り尾根も見えるが、槍・穂高岳方面はガスの中だ。



14:27,時間的にも体力的にも船窪方面への前進は可能との結論を得て烏帽子岳に向かい出発。ゆるやかに左にカーブするハイマツ帯の稜線を行く。この辺りは雪もなく快調。
2605mの前烏帽子から改めて周辺の山々を見る。何と言っても烏帽子岳の天に向かって合掌するかのような鋭い岩峰が圧巻で、柱のようにきれいに並んだ岩が美しい。この岩峰はしかし、進むにつれてそれまでとはまったく違った異様な姿へと変貌する。



15:08,烏帽子岳岩峰への分岐点に到達。時間が押しているので山頂には向かわず通過,一転して雪の斜面となる。南沢岳との鞍部は烏帽子田圃と言う湿原で、この辺りをビバークの候補地とも考えていたが、できればさらに進んでおきたかった。
湿原は凹地であり、一方の縁は烏帽子からの稜線でもう一方に並行する山稜があって二重山陵を形成していた。そのもう一方の小高い山陵に踏み後が見えたのでそこを目指して雪面を突き進んだが、もう少しと言うところで分厚いハイマツ帯に阻まれて進めなくなる。しばらくはあちらこちらと突破口を探したが無理と分り、後退を決めて下ってきた雪面を登り返し、最後はシラビソとハイマツの混じる薮の中を這うようにして突破し、16:29,登山道に戻る。烏帽子分岐から1時間20分のタイムロスとなる。



ここから南沢岳への登りの途中から急に冷たい西風が吹き始めて山頂下では霰が降る。
17:00,南沢岳(2625m)の前ピークに到達。ここをビバーク地点と決めて山頂東側直下の雪面を均しテントを張る。
雪を溶かした水を沸かしてアルファ米を戻し、レトルトのカレーを温めて用意したが、G3氏がつくってくれた梅酒のお湯わりを頂き、行動食を食べているうちに食事が面倒になり、G3氏によると『あぐらのまま鼾をかき始めた』とのことで結局カレーは食べずに横になる。



ひとしきり熟睡し、目が覚めて2時間近くじっと考え事をしながら夜明けを待つ。風に時おり雨音が混じる。
2時を廻ったかと時計を見るとまだ0時前で、それから悶々と時の過ぎるのを待ち、何度かまどろんでようやく4時を迎える。どんなに疲れていても3~4時間熟睡すれば充分で、後は時間をもてあますのが常の幕営である。
6月14日(日)へ続く
2009年12月23日
前白根山(2009.12.20)
前白根山
2009年12月20日 栃木県日光市 前白根山 記録者 あっちゃん
今期初雪山登山してきました。
予定は菅沼から奥白根でしたが
ここ2~3日の大雪で駐車場が埋まってしまい駐車スペースがありません。
入り口に3台止めてあったので奥をのぞいて見ると
テント泊の方が2人いたのでお話を伺って見たところ
前日にきて駐車スペースを確保するのにほぼ一日スコップで雪かきをして疲れたので
一晩ゆっくりして今から登山開始とのこと
良く周りを見渡すと40センチ~60センチぐらい積もっていて
スコップも持参していない自分達はとても太刀打ちできません。
仕方ないので来た道を引き返し日光湯元温泉へ
前白根山を目指すことにしました。
湯元スキー場駐車場には14~5名に団体登山隊が出発の準備をしており
時間的に遅れてきた自分達はその後を追う様に出発


スキー場の脇を歩き暫くして登山道へ
大雪のためほとんど踏跡はなくなりいきなりのハードなラッセル!!
体はキツイのですがなんだか楽しい気持ちになり今季初ラッセルを楽しめました。
団体さんは途中で下山したため
その後はトレース無しの雪道を辛くも楽しいラッセルで踏破し
前白根山のピークに立つことができ
大満足の今期初雪山山行になりました。


天候が荒れ気味でとても寒かったのですが
山頂付近は見事に晴れ渡り360度の素晴らしい眺めを堪能することができました!
今度はどこに行こうかな~


片山さんの富士山での事故はとても残念に思います。
あれだけ場数を踏んできた人たちでさへ自然の猛威に対処し切れないのですから。
「人の振り見て我が振り直せ」
じゃ無いですけど
素人の自分なりに十分に気をつけて今後の山行に臨みたいと思います。
2009年12月20日 栃木県日光市 前白根山 記録者 あっちゃん
今期初雪山登山してきました。
予定は菅沼から奥白根でしたが
ここ2~3日の大雪で駐車場が埋まってしまい駐車スペースがありません。
入り口に3台止めてあったので奥をのぞいて見ると
テント泊の方が2人いたのでお話を伺って見たところ
前日にきて駐車スペースを確保するのにほぼ一日スコップで雪かきをして疲れたので
一晩ゆっくりして今から登山開始とのこと
良く周りを見渡すと40センチ~60センチぐらい積もっていて
スコップも持参していない自分達はとても太刀打ちできません。
仕方ないので来た道を引き返し日光湯元温泉へ
前白根山を目指すことにしました。
湯元スキー場駐車場には14~5名に団体登山隊が出発の準備をしており
時間的に遅れてきた自分達はその後を追う様に出発


スキー場の脇を歩き暫くして登山道へ
大雪のためほとんど踏跡はなくなりいきなりのハードなラッセル!!
体はキツイのですがなんだか楽しい気持ちになり今季初ラッセルを楽しめました。
団体さんは途中で下山したため
その後はトレース無しの雪道を辛くも楽しいラッセルで踏破し
前白根山のピークに立つことができ
大満足の今期初雪山山行になりました。


天候が荒れ気味でとても寒かったのですが
山頂付近は見事に晴れ渡り360度の素晴らしい眺めを堪能することができました!
今度はどこに行こうかな~


片山さんの富士山での事故はとても残念に思います。
あれだけ場数を踏んできた人たちでさへ自然の猛威に対処し切れないのですから。
「人の振り見て我が振り直せ」
じゃ無いですけど
素人の自分なりに十分に気をつけて今後の山行に臨みたいと思います。
タグ :栃木
2009年12月20日
猪倉山・多気山(2009.12.20)
城山巡り
2009年12月20日 栃木県日光宇都宮 小倉山・猪倉山・多気山 記録者 副隊長
今日も家に居るのことに気が引けるくらい天気が良い。隊長は折悪しく部活、それも午前10時から午後3時という誠に中途半端な時間。午前なら午前、午後なら午後とはっきり区切った指導は出来ないものかと顧問の先生に一言申したい気分である。
まあそんな愚痴を言ったところで事態は好転しないので一人で外出の仕度を始める。図書館に本を返しがてら年末年始に読む本を何かを見つくろって来よう。そんな気持ちで車を走らせたのは良いが余りにも山が綺麗に見えて思わずハンドルを切り車は自然と郊外に向かっていた。
特に何処とも決めたわけでもなかったが、ふと先日登った板橋城址城山を思い出し、あの時に目にした猪倉城址というのを見てみようと決めた。もう一つの小倉城址の方はこの間仕事の合間に登って来ていたのでこの場を借りて合わせてご紹介しよう。
小倉城址の城山は例弊紙街道JR日光線文挟駅前から左折し車窓左手に見える城山を目指して車を走らせ5分ほどで案内板が立つ登山口に着く。
植林されたスギ林を登り途中丸太で組んだ階段を上り切ると本丸跡の山頂に着く。スギ林に囲まれ展望は無く、木々の間から板橋城址城山が見えるくらい。
本丸跡の周辺にはお堀の跡らしき溝や見張り用の台地らしきものが見えるが詳しくは分からず周辺を散歩して下山して来た。


さて続いて猪倉城址城山。こちらは県道宇都宮大沢線を走り猪倉山泉福寺の看板をお寺目掛けて進む。登山口はお寺の本堂前左にある階段を上ったところから始まる。うっそうとしたスギ林の中を黙々と登る。九十九折れに登って行く登山道の途中のあちらこちらに小広い平坦な場所が有る。山城の見張り場の様な所なのかも知れず、そこの一つに立ってみたら登って来た登山道は一目瞭然。城山を攻めて来る敵を迎え撃つには格好の構造になっている気がする。まあ、その辺は全然「城山」というものに詳しく無いので勝手な推測。
お寺の境内からものの30分もかからずに「此処に猪倉城ありき」という石碑に到着。その上のピークが猪倉山の山頂である。


この二つを同じ日に回るとして移動時間も含めて2時間もあれば足りそう。先日の板橋城址城山がこの二つの山の中間にあるので3つを合わせて登って半日といったところか・・・。
今日の場合は猪倉山の45分ほどの散歩しか無いのでついでと言ったら申し訳ないが帰りがけに宇都宮大沢線を国道293号で右折して栃木100名山の一つでもある多気山に寄って来た。
多気山も戦国時代の山城として知られ山全体あちらこちらに土塁や空堀の遺構が散見出来ると言われている。まあ私の場合「城山つながり」といった具合で立ち寄ったまでで、その詳細などには全然詳しく無い。
多気不動尊の赤い鳥居をくぐり山道を車で上がる。ものの1~2分でお茶屋前の大きな駐車場に着くのでそこから登山を始める。
スギ林とヒノキ林のだらだらの山道を登る。ところどころにやはり見張り場であろうか平坦な部分が登山道を挟んで設けられている。途中、崩れかけた石段を登り雑木林が見えて来ると山頂も近い。
山頂は本丸跡であろう大きな平坦地になっていて日当たりが良い。平たん部を抜けて雑木林の中を進むと多気山三角点のあるピークに出る。終始展望は余り良く無い。


こんな具合に「城山つながり」で山を歩いてみたが、展望が良いのは以前に紹介した板橋城址のみで他の3つは展望が無い。ただ山城の城址として興味が有る方にはかなり探検心を掻き立てる山だとは思う。登山道をちょっと脇に入ると空堀や石垣・土塁などが見つかるので面白い。
城址を詳しく調べるのは別として紹介した4つの山を登るのは車があれば1日で全部回れる。
2009年12月20日 栃木県日光宇都宮 小倉山・猪倉山・多気山 記録者 副隊長
今日も家に居るのことに気が引けるくらい天気が良い。隊長は折悪しく部活、それも午前10時から午後3時という誠に中途半端な時間。午前なら午前、午後なら午後とはっきり区切った指導は出来ないものかと顧問の先生に一言申したい気分である。
まあそんな愚痴を言ったところで事態は好転しないので一人で外出の仕度を始める。図書館に本を返しがてら年末年始に読む本を何かを見つくろって来よう。そんな気持ちで車を走らせたのは良いが余りにも山が綺麗に見えて思わずハンドルを切り車は自然と郊外に向かっていた。
特に何処とも決めたわけでもなかったが、ふと先日登った板橋城址城山を思い出し、あの時に目にした猪倉城址というのを見てみようと決めた。もう一つの小倉城址の方はこの間仕事の合間に登って来ていたのでこの場を借りて合わせてご紹介しよう。
小倉城址の城山は例弊紙街道JR日光線文挟駅前から左折し車窓左手に見える城山を目指して車を走らせ5分ほどで案内板が立つ登山口に着く。
植林されたスギ林を登り途中丸太で組んだ階段を上り切ると本丸跡の山頂に着く。スギ林に囲まれ展望は無く、木々の間から板橋城址城山が見えるくらい。
本丸跡の周辺にはお堀の跡らしき溝や見張り用の台地らしきものが見えるが詳しくは分からず周辺を散歩して下山して来た。


さて続いて猪倉城址城山。こちらは県道宇都宮大沢線を走り猪倉山泉福寺の看板をお寺目掛けて進む。登山口はお寺の本堂前左にある階段を上ったところから始まる。うっそうとしたスギ林の中を黙々と登る。九十九折れに登って行く登山道の途中のあちらこちらに小広い平坦な場所が有る。山城の見張り場の様な所なのかも知れず、そこの一つに立ってみたら登って来た登山道は一目瞭然。城山を攻めて来る敵を迎え撃つには格好の構造になっている気がする。まあ、その辺は全然「城山」というものに詳しく無いので勝手な推測。
お寺の境内からものの30分もかからずに「此処に猪倉城ありき」という石碑に到着。その上のピークが猪倉山の山頂である。


この二つを同じ日に回るとして移動時間も含めて2時間もあれば足りそう。先日の板橋城址城山がこの二つの山の中間にあるので3つを合わせて登って半日といったところか・・・。
今日の場合は猪倉山の45分ほどの散歩しか無いのでついでと言ったら申し訳ないが帰りがけに宇都宮大沢線を国道293号で右折して栃木100名山の一つでもある多気山に寄って来た。
多気山も戦国時代の山城として知られ山全体あちらこちらに土塁や空堀の遺構が散見出来ると言われている。まあ私の場合「城山つながり」といった具合で立ち寄ったまでで、その詳細などには全然詳しく無い。
多気不動尊の赤い鳥居をくぐり山道を車で上がる。ものの1~2分でお茶屋前の大きな駐車場に着くのでそこから登山を始める。
スギ林とヒノキ林のだらだらの山道を登る。ところどころにやはり見張り場であろうか平坦な部分が登山道を挟んで設けられている。途中、崩れかけた石段を登り雑木林が見えて来ると山頂も近い。
山頂は本丸跡であろう大きな平坦地になっていて日当たりが良い。平たん部を抜けて雑木林の中を進むと多気山三角点のあるピークに出る。終始展望は余り良く無い。


こんな具合に「城山つながり」で山を歩いてみたが、展望が良いのは以前に紹介した板橋城址のみで他の3つは展望が無い。ただ山城の城址として興味が有る方にはかなり探検心を掻き立てる山だとは思う。登山道をちょっと脇に入ると空堀や石垣・土塁などが見つかるので面白い。
城址を詳しく調べるのは別として紹介した4つの山を登るのは車があれば1日で全部回れる。
タグ :栃木
2009年12月16日
社山(2009.12.13)
社山
2009年12月13日 栃木県日光 社山 記録者 はら坊
一週間の疲れが溜まりに溜まって一日中ゴロゴロ寝ていた土曜日の夕方、副隊長からメールが入った。
『明日空いてる?』
『空いてます。』
『近場で何処か行く?』
ってな感じで日光中禅寺湖の畔に在る社山に行く事になった。
その後の会話も色々あったが、長くなるので省略する事にする。
社山{しゃざん}と言うらしい『随分と神々しい名前だな~。シャザンオールスターズ』などとボケてみるものの反応は中禅寺湖の水くらい冷たい。寒さも余計に身にしみる。
神々しい名前に胸が高鳴る・・・じゃなく湖畔の遊歩道でもう心臓がバクバクで高鳴るのは心拍数だ。
 遊歩道から見える社山の頂は、勿論雪。
遊歩道から見える社山の頂は、勿論雪。
尾根ずたいの登山である事は、下から見ても分かる。
何処と無く赤城山の黒檜山を思わせる佇まいである。
途中男体山が湖に映り込み逆さ冨士ならぬ逆さ男体山を見せてくれた。
副隊長も言っていたが、~富士という名が付いていないのが不思議なくらいだ。
やっと登山道入り口に到着。って先週も言っていたが、標高差が無いので全然楽な筈だが疲れが溜まった体には結構こたえる。


第一のピークに立つと榛名山の掃部ヶ岳からの眺めに似ている。
と言っても此方は、かなりのラージ版である。
 尾根ずたいを歩いていると、足尾側には木が無く、中禅寺湖側には木が生えている。副隊長が言うには、銅山の鉛害の傷跡らしい。
尾根ずたいを歩いていると、足尾側には木が無く、中禅寺湖側には木が生えている。副隊長が言うには、銅山の鉛害の傷跡らしい。
この尾根を挟んで足尾側では、鉱夫たちが身を削り働いて居たのであろう。その北側の中禅寺湖側では、名だたるヨーロッパの貴族たちが余暇を満喫していたのであろう。何だか複雑な気分であったが、展望はと言うともう最高であった。関東平野は雲の中だった物の中禅寺湖側は男体山~白根までくっきりと見える。
が、まだ山頂には到着はしていないのだ。
あそこが山頂だ・・・っと三回くらい言った所でやっと山頂に到着した。
神々しい名前とは裏腹に祠も何も無い山頂だった。
山頂から少し先に行くと視界が開けてとても綺麗だった。副隊長と『あれが皇海山で、鋸山、んじゃあれが庚申山かな』などと先週行った山の位置を確認たりして見る。とても楽しいひと時である。
昼食には久し振りの山頂ラーメンとおむすびをたいらげ下山。
隊長と雪合戦をしながら下山したが、隊長の足取りは今年の両神山の雪の下山の時とは比べもんにならない位軽かった。


下山する時は登りとは別の景色が見えるから不思議だ。それを楽しみながら無事に下山し、イタリア大使館別荘を覗き込んで今回の山行も無事フィナーレとなった。
副隊長の日記は【続きを読む】へ
続きを読む
2009年12月13日 栃木県日光 社山 記録者 はら坊
一週間の疲れが溜まりに溜まって一日中ゴロゴロ寝ていた土曜日の夕方、副隊長からメールが入った。
『明日空いてる?』
『空いてます。』
『近場で何処か行く?』
ってな感じで日光中禅寺湖の畔に在る社山に行く事になった。
その後の会話も色々あったが、長くなるので省略する事にする。
社山{しゃざん}と言うらしい『随分と神々しい名前だな~。シャザンオールスターズ』などとボケてみるものの反応は中禅寺湖の水くらい冷たい。寒さも余計に身にしみる。
神々しい名前に胸が高鳴る・・・じゃなく湖畔の遊歩道でもう心臓がバクバクで高鳴るのは心拍数だ。
尾根ずたいの登山である事は、下から見ても分かる。
何処と無く赤城山の黒檜山を思わせる佇まいである。
途中男体山が湖に映り込み逆さ冨士ならぬ逆さ男体山を見せてくれた。
副隊長も言っていたが、~富士という名が付いていないのが不思議なくらいだ。
やっと登山道入り口に到着。って先週も言っていたが、標高差が無いので全然楽な筈だが疲れが溜まった体には結構こたえる。
第一のピークに立つと榛名山の掃部ヶ岳からの眺めに似ている。
と言っても此方は、かなりのラージ版である。
この尾根を挟んで足尾側では、鉱夫たちが身を削り働いて居たのであろう。その北側の中禅寺湖側では、名だたるヨーロッパの貴族たちが余暇を満喫していたのであろう。何だか複雑な気分であったが、展望はと言うともう最高であった。関東平野は雲の中だった物の中禅寺湖側は男体山~白根までくっきりと見える。
が、まだ山頂には到着はしていないのだ。
あそこが山頂だ・・・っと三回くらい言った所でやっと山頂に到着した。
神々しい名前とは裏腹に祠も何も無い山頂だった。
山頂から少し先に行くと視界が開けてとても綺麗だった。副隊長と『あれが皇海山で、鋸山、んじゃあれが庚申山かな』などと先週行った山の位置を確認たりして見る。とても楽しいひと時である。
昼食には久し振りの山頂ラーメンとおむすびをたいらげ下山。
隊長と雪合戦をしながら下山したが、隊長の足取りは今年の両神山の雪の下山の時とは比べもんにならない位軽かった。
下山する時は登りとは別の景色が見えるから不思議だ。それを楽しみながら無事に下山し、イタリア大使館別荘を覗き込んで今回の山行も無事フィナーレとなった。
副隊長の日記は【続きを読む】へ
続きを読む
タグ :栃木
2009年12月13日
満観峰(2009.12.12)
久々にスカッと晴れた土曜日に、家族で焼津市の満観峰(470m)に行ってきました。
他県の方々には“シラスで有名な用宗(もちむね)港”、“断崖絶壁を走るR150で有名な大崩海岸”と言えば、分かる方もいるかもしれません。
満観峰はその海岸線から少し内陸に入った場所にあります。
近くには高草山(501m)、花沢山(450m)、虚空蔵山(126m)などがあり、チョッとハイキングには最適です。
この日、実は“海抜ゼロメートルからのピーク”を目論んでいたのですが、さすがに娘はまだ無理そうです。強要すると今後、一緒に行かなくなってしまう恐れがありますので、鞍掛峠(300m)から歩き始めました。
狙いは山頂でのパスタランチとキレイな富士山と伊豆半島のワイドビュー。
息子2人は放っておいてもスイスイ行ってしまいますので、女房が監視役。
オイラは娘と一緒にマッタリ歩きです。この前教えてあげたキイチゴを頬張る娘と一緒に歩くのは楽しくてしょうがないです、ハイ。
「つかれた、だっこ」
「お父さんをだっこしてよ」
「ダメェ~」
「テッペンでキレイですっごく大きな富士山見ようね」
「ウン!」
とまぁ、だましだまし、1時間半くらい歩きました。
もう最高!

ちなみに山頂は100人以上が楽しそうに食事をしている銀座でしたが、皆さんいい人で、子どもたちも一緒に遊んでもらいました。
アプローチもたくさんあるので、今度は別にルートから行ってみようかな!
他県の方々には“シラスで有名な用宗(もちむね)港”、“断崖絶壁を走るR150で有名な大崩海岸”と言えば、分かる方もいるかもしれません。
満観峰はその海岸線から少し内陸に入った場所にあります。
近くには高草山(501m)、花沢山(450m)、虚空蔵山(126m)などがあり、チョッとハイキングには最適です。
この日、実は“海抜ゼロメートルからのピーク”を目論んでいたのですが、さすがに娘はまだ無理そうです。強要すると今後、一緒に行かなくなってしまう恐れがありますので、鞍掛峠(300m)から歩き始めました。
狙いは山頂でのパスタランチとキレイな富士山と伊豆半島のワイドビュー。
息子2人は放っておいてもスイスイ行ってしまいますので、女房が監視役。
オイラは娘と一緒にマッタリ歩きです。この前教えてあげたキイチゴを頬張る娘と一緒に歩くのは楽しくてしょうがないです、ハイ。
「つかれた、だっこ」
「お父さんをだっこしてよ」
「ダメェ~」
「テッペンでキレイですっごく大きな富士山見ようね」
「ウン!」
とまぁ、だましだまし、1時間半くらい歩きました。
もう最高!
ちなみに山頂は100人以上が楽しそうに食事をしている銀座でしたが、皆さんいい人で、子どもたちも一緒に遊んでもらいました。
アプローチもたくさんあるので、今度は別にルートから行ってみようかな!
2009年12月10日
城山(2009.11.29)
板橋城址「城山」
2009年11月29日 栃木県日光市板橋 城山 記録者 副隊長
思わぬ良い天気に誘われてて一人で里山を歩いている。里山の場所は日光市(旧今市市)の板橋地区。
確か二年ほど前の新聞で地元が登山道整備に力を入れて登山道が開かれたという記事を読んだ。その時に「ああ、山を切り開いてわざわざ登山道を新しく作るのかぁ、そのままじゃだめなのかなぁ・・・」と漠然とながらその功罪を考えたのがこの里山である。
 名前は「城山」(443m)で山頂には「板橋城跡」がある。宇都宮市そのものが城下町であるからなのか、いにしえの武将がこの辺りを戦略上で重要な地形と見定めたのか、宇都宮市近郊には山を城に見立てて砦の建築を施した「山城」というものが数か所ある。ここ「板橋城」もその一つで1504年から1520年にかけて宇都宮氏一族が築城し、小田原北条氏家臣の板橋氏の手を経て徳川一族へと城主が変遷して行ったという記録がある。時は戦国時代という古い歴史だ。(お城だから当たり前か・・・笑)
名前は「城山」(443m)で山頂には「板橋城跡」がある。宇都宮市そのものが城下町であるからなのか、いにしえの武将がこの辺りを戦略上で重要な地形と見定めたのか、宇都宮市近郊には山を城に見立てて砦の建築を施した「山城」というものが数か所ある。ここ「板橋城」もその一つで1504年から1520年にかけて宇都宮氏一族が築城し、小田原北条氏家臣の板橋氏の手を経て徳川一族へと城主が変遷して行ったという記録がある。時は戦国時代という古い歴史だ。(お城だから当たり前か・・・笑)
さて、現在に時間を戻して登山口から歩いて行く。等幅で綺麗に敷き詰められた砕石の小道を進むといきなり轍の跡がある幅広い林道に飛び出す。「???」と首を傾げながらも道標が指す「板橋城跡」を目指して進む。5分も歩くと小広い車止めに到着して本格的な登山道が始まる。
脇に小沢が流れる登山道はスギ林の奥に向かい緩やかな傾斜で一直線に進んで行く。突き当りから右に折れて丸太で組んだ階段が斜面をズンズン登って行く。私の場合この階段というのが登山で一番疲れる。何の事は無い休むタイミングが取りにくいというだけである。(笑)
約150mの標高差を階段8割で登り詰めると山頂直下の「天狗岩」との分岐に出る。山頂を優先に右に折れ斜面を登る。視線の先は青空が大きく開け東屋の屋根がちょこんと見えている。如何にも展望の良さを想像させる景色である。
 頂上に登り詰めると東屋の中に女性が二人座っていて外で男性が威勢よく両手を振り体操をしながら周囲の説明をしている。脇を通りながら軽く挨拶をすると小声で「あっちから登って来たんだねぇ・・・」という声が聞こえる。山頂は広く小さな窪みを挟んで全長50mほどの平坦な地形である。東屋を背に平たん部の先まで行ってみるとそちらにも登山道が有る事がわかった。どうやら彼女たちはこちらから登って来たらしい。
頂上に登り詰めると東屋の中に女性が二人座っていて外で男性が威勢よく両手を振り体操をしながら周囲の説明をしている。脇を通りながら軽く挨拶をすると小声で「あっちから登って来たんだねぇ・・・」という声が聞こえる。山頂は広く小さな窪みを挟んで全長50mほどの平坦な地形である。東屋を背に平たん部の先まで行ってみるとそちらにも登山道が有る事がわかった。どうやら彼女たちはこちらから登って来たらしい。
この山頂、周囲の眺めは良い。開けていないのは北東方面くらいで東に鞍掛山から古賀志山、鹿沼市街の展望を挟んで二股山などの鹿沼市近郊の山々から遠くは県南の山々、転じて男体山から大真名子・小真名子、女峰、赤薙と並び最後は鶏頂山や釈迦ケ岳・高原山が見える。
山頂にある「城山」の案内板には冒頭の歴史説明がもう少し詳細に記されていてその歴史を振り返りながら城主の如く周囲を見渡すのも面白い。
伐採新しい切り株に腰掛けてスケッチブックを開いてお絵かきを始める。隊長が居ない時の暇つぶしに始めたスケッチである。現地で下書きだけ済ませて帰宅後に暇を見て彩色しているが、本当なら現地で全て仕上げてしまえる腕になりたい願望はある。
 そうこうするうちに東屋脇に白杭が立っている事に気が付いた。「あれ?」と思うが早いか「これは三角点表示杭だよなぁ・・・」と気が付き寄り添うように頭だけ出している御影石に気が付く。「おお、これは三角点様、気が付くのが遅れて申し訳ありません!」と頭こそ下げないけれど敬礼をする。
そうこうするうちに東屋脇に白杭が立っている事に気が付いた。「あれ?」と思うが早いか「これは三角点表示杭だよなぁ・・・」と気が付き寄り添うように頭だけ出している御影石に気が付く。「おお、これは三角点様、気が付くのが遅れて申し訳ありません!」と頭こそ下げないけれど敬礼をする。
油断というのかそれこそ鼻から期待もしていなかった三角点の所在に嬉しさ倍増でカメラを構える。帰宅後に「点の記」を調べたら明治34年に選点されている三等三角点だった。
山頂で30分ほどあれこれと動き回り下山にかかる。帰路「天狗岩」なる物に一応興味を抱いて下山路を通り過ぎて南に進む。途中「畳石」という奇岩?を越えて「天狗岩」まで5分ほど。「天狗岩」はいにしえの物語曰く、「城山の危機に日光山の天狗が降り立った岩」との事でありました。(笑)
分岐まで引き返し往路を一気に下山。車止めを過ぎて林道を歩いている時に往路では気付かなかった異様な洞窟を目にして好奇心旺盛な中年オヤジは左手の斜面に取り付く。近くまで行くとその規則正しい四角形の洞穴から「ああ、大谷石の切り出し場かぁ・・・」と察しが付く。しかし大谷石の採石が盛んだった大谷町は古賀志山をは挟んだ向こう側であるから「こんなところまで・・・」と結構意外な思いではあった。
帰宅後、「城山」から「板橋城」というキーワードを得て少し調べてみたら「猪倉城」「小倉城」というのが近くに在る事がわかった。どちらも「板橋城」に並び当時は威勢を誇った様子が垣間見られる。突っ込んだ興味とまでは行かないが、機会が有ればこの二つの城址である里山を歩いてみたいと思う今回の登山だった。


2009年11月29日 栃木県日光市板橋 城山 記録者 副隊長
思わぬ良い天気に誘われてて一人で里山を歩いている。里山の場所は日光市(旧今市市)の板橋地区。
確か二年ほど前の新聞で地元が登山道整備に力を入れて登山道が開かれたという記事を読んだ。その時に「ああ、山を切り開いてわざわざ登山道を新しく作るのかぁ、そのままじゃだめなのかなぁ・・・」と漠然とながらその功罪を考えたのがこの里山である。
さて、現在に時間を戻して登山口から歩いて行く。等幅で綺麗に敷き詰められた砕石の小道を進むといきなり轍の跡がある幅広い林道に飛び出す。「???」と首を傾げながらも道標が指す「板橋城跡」を目指して進む。5分も歩くと小広い車止めに到着して本格的な登山道が始まる。
脇に小沢が流れる登山道はスギ林の奥に向かい緩やかな傾斜で一直線に進んで行く。突き当りから右に折れて丸太で組んだ階段が斜面をズンズン登って行く。私の場合この階段というのが登山で一番疲れる。何の事は無い休むタイミングが取りにくいというだけである。(笑)
約150mの標高差を階段8割で登り詰めると山頂直下の「天狗岩」との分岐に出る。山頂を優先に右に折れ斜面を登る。視線の先は青空が大きく開け東屋の屋根がちょこんと見えている。如何にも展望の良さを想像させる景色である。
この山頂、周囲の眺めは良い。開けていないのは北東方面くらいで東に鞍掛山から古賀志山、鹿沼市街の展望を挟んで二股山などの鹿沼市近郊の山々から遠くは県南の山々、転じて男体山から大真名子・小真名子、女峰、赤薙と並び最後は鶏頂山や釈迦ケ岳・高原山が見える。
山頂にある「城山」の案内板には冒頭の歴史説明がもう少し詳細に記されていてその歴史を振り返りながら城主の如く周囲を見渡すのも面白い。
伐採新しい切り株に腰掛けてスケッチブックを開いてお絵かきを始める。隊長が居ない時の暇つぶしに始めたスケッチである。現地で下書きだけ済ませて帰宅後に暇を見て彩色しているが、本当なら現地で全て仕上げてしまえる腕になりたい願望はある。
油断というのかそれこそ鼻から期待もしていなかった三角点の所在に嬉しさ倍増でカメラを構える。帰宅後に「点の記」を調べたら明治34年に選点されている三等三角点だった。
山頂で30分ほどあれこれと動き回り下山にかかる。帰路「天狗岩」なる物に一応興味を抱いて下山路を通り過ぎて南に進む。途中「畳石」という奇岩?を越えて「天狗岩」まで5分ほど。「天狗岩」はいにしえの物語曰く、「城山の危機に日光山の天狗が降り立った岩」との事でありました。(笑)
分岐まで引き返し往路を一気に下山。車止めを過ぎて林道を歩いている時に往路では気付かなかった異様な洞窟を目にして好奇心旺盛な中年オヤジは左手の斜面に取り付く。近くまで行くとその規則正しい四角形の洞穴から「ああ、大谷石の切り出し場かぁ・・・」と察しが付く。しかし大谷石の採石が盛んだった大谷町は古賀志山をは挟んだ向こう側であるから「こんなところまで・・・」と結構意外な思いではあった。
帰宅後、「城山」から「板橋城」というキーワードを得て少し調べてみたら「猪倉城」「小倉城」というのが近くに在る事がわかった。どちらも「板橋城」に並び当時は威勢を誇った様子が垣間見られる。突っ込んだ興味とまでは行かないが、機会が有ればこの二つの城址である里山を歩いてみたいと思う今回の登山だった。

タグ :栃木
2009年12月08日
庚申山(2009.12.6)
これだから止められない!
2009年12月6日 栃木県足尾 庚申山 記録者 はら坊
『長男の勇輝が休みだから何処か行きましょ。』
そんな軽いのりで始った今回の山歩き。
場所は副隊長に任せた。
ま~何を言っても頼れる兄貴だから任せて置けばダイジだべ・・・
ぺんぎん隊のキャリアで子供を連れて行ける場所と、コースタイム
は十分把握している。
今回は隊長が居ない、部活の大会らしいが少し寂しい。勇輝が野球を始めてから副隊長の気持ちが痛いほど解る。
という事で、場所の候補はいくつか有ったけど、栃木県旧足尾町に登山口がある庚申山に決った。
朝8:00に登山口のある国民宿舎かじか荘に集合。
少し早く到着し車の中で勇輝と朝食を摂る。
『あっ!! さるだ~っ』と勇輝が叫ぶ。
ここは日光、猿・鹿は珍しくは無いが目の前に出てくると何故か興奮する。
程なく副隊長と合流すると、いきなりスパッツを巻きだし準備完了。
先に着いた我々が副隊長を待たせる羽目に。アタフタしながら準備完了でいざ出発。


 ダラダラと車の走れる林道をひたすら歩く。
ダラダラと車の走れる林道をひたすら歩く。
途中天狗の投石という景勝地が有ったり庚申川の流れを見たりで飽きる事は無い。これで登山も十分だと言うくらい林道を歩くと漸く登山口が現れる。ここまでで相当高度も上がったであろう。
その脇には七滝という景勝地があり、ここで初めての休憩を入れる。
写真を数枚撮り再び出発。
ここからやっと登山道らしくなる。
広葉樹の森の木は、まだ若い木が多いいが秋には素晴しい紅葉を見せるであろう事を予感させてくれる。のでこの季節は真っ裸である。
沢を何度か渡り返しながら歩く。所どころ巨岩奇岩があり、看板が立っている。
暫く行くと前日に降ったであろう雪が現れ出した。勇輝は、雪に目を輝かせ雪で遊んでいる。やっぱり子供だな~っと思う瞬間である。
大人二人はと言うと、嫌な思いが脳裏をよぎる。副隊長は口にしなかったが同じ思いであったに違いない。それは今年の1月に登った両神である。
こいつが出てくると危険度が増し、コースタイムが著しく狂わせられるからだ。
 登山道には鹿の足跡が沢山あり鹿の足跡に導かれる様に庚申山荘に到着。
登山道には鹿の足跡が沢山あり鹿の足跡に導かれる様に庚申山荘に到着。
ここで小休止を摂って山頂を目指し出発。
何やらここからコースが二手に別れるらしいが、見当らないので雪に残る先行者の足跡を追う。
所どころ危険な場所をクリアーしていく。ま~雪が無ければ差ほどでは無いだろうが雪が渋い。
途中先行者が下山して来てすれ違いがてら、『山頂が分からなかった。』
と言う。挨拶を交わした後、副隊長と顔を見合わせ『山頂が分からない訳ね~べぇ~』と言いながら山頂を目指す。
彼らの足跡が途切れた辺りが確かに山頂ではないかと思わせるような場所
では有るが、其れらしい物が無いので、我々はもう少し先に行く。
10分ほどで石碑が頭を出しているが山名板が無いのでもう少し先に行くと
突然視界が開け絶景が広がった。ここまで雪を厄介者にしてきたが、ここで初めて雪に感謝する事になった。この季節、色の無い山肌に雪が化粧してくれて空は青く澄んでいる。勇輝でさえ感動の声を上げている。
息子と同じ物に感動できるって素晴しい事ですよね。
これだから止められないや


山頂で昼食を摂り、写真を撮って寒さに耐え切れず退散。
日光白根山にかかる雲を払おうと白根に向って息を吹き掛けている副隊長を見てニヤニヤしていた勇輝の顔が印象的だった。
勇輝に軽アイゼンを装着させて出発。
 帰り道先ほど通った石碑をもう一度何気なしに見たらそこには山名板が有るではないか、『あんなに探したのに~。写真まで撮ってたのに~』
帰り道先ほど通った石碑をもう一度何気なしに見たらそこには山名板が有るではないか、『あんなに探したのに~。写真まで撮ってたのに~』
と苦笑いを浮べながらもこれで始めて庚申山制覇となった。
帰り道もっと怖がって時間がかかると思ったが、詰まらない位スイスイと降りてしまうのでチョット拍子抜けしたが、お陰でコースタイムより少し速いペースで無事下山できた。
帰りには、かじか荘の温泉で汗を流し帰路についた。
久し振りの副隊長との山登り親子共々お世話になりとても楽しい一日を過ごす事が出来ました。
今度は隊長も一緒に・・・榛名山⇒温泉⇒水沢うどん⇒おもちゃと自動車博物館でしたっけ。
また宜しくお願いします。
2009年12月6日 栃木県足尾 庚申山 記録者 はら坊
『長男の勇輝が休みだから何処か行きましょ。』
そんな軽いのりで始った今回の山歩き。
場所は副隊長に任せた。
ま~何を言っても頼れる兄貴だから任せて置けばダイジだべ・・・
ぺんぎん隊のキャリアで子供を連れて行ける場所と、コースタイム
は十分把握している。
今回は隊長が居ない、部活の大会らしいが少し寂しい。勇輝が野球を始めてから副隊長の気持ちが痛いほど解る。
という事で、場所の候補はいくつか有ったけど、栃木県旧足尾町に登山口がある庚申山に決った。
朝8:00に登山口のある国民宿舎かじか荘に集合。
少し早く到着し車の中で勇輝と朝食を摂る。
『あっ!! さるだ~っ』と勇輝が叫ぶ。
ここは日光、猿・鹿は珍しくは無いが目の前に出てくると何故か興奮する。
程なく副隊長と合流すると、いきなりスパッツを巻きだし準備完了。
先に着いた我々が副隊長を待たせる羽目に。アタフタしながら準備完了でいざ出発。


 ダラダラと車の走れる林道をひたすら歩く。
ダラダラと車の走れる林道をひたすら歩く。途中天狗の投石という景勝地が有ったり庚申川の流れを見たりで飽きる事は無い。これで登山も十分だと言うくらい林道を歩くと漸く登山口が現れる。ここまでで相当高度も上がったであろう。
その脇には七滝という景勝地があり、ここで初めての休憩を入れる。
写真を数枚撮り再び出発。
ここからやっと登山道らしくなる。
広葉樹の森の木は、まだ若い木が多いいが秋には素晴しい紅葉を見せるであろう事を予感させてくれる。のでこの季節は真っ裸である。
沢を何度か渡り返しながら歩く。所どころ巨岩奇岩があり、看板が立っている。
暫く行くと前日に降ったであろう雪が現れ出した。勇輝は、雪に目を輝かせ雪で遊んでいる。やっぱり子供だな~っと思う瞬間である。
大人二人はと言うと、嫌な思いが脳裏をよぎる。副隊長は口にしなかったが同じ思いであったに違いない。それは今年の1月に登った両神である。
こいつが出てくると危険度が増し、コースタイムが著しく狂わせられるからだ。
 登山道には鹿の足跡が沢山あり鹿の足跡に導かれる様に庚申山荘に到着。
登山道には鹿の足跡が沢山あり鹿の足跡に導かれる様に庚申山荘に到着。ここで小休止を摂って山頂を目指し出発。
何やらここからコースが二手に別れるらしいが、見当らないので雪に残る先行者の足跡を追う。
所どころ危険な場所をクリアーしていく。ま~雪が無ければ差ほどでは無いだろうが雪が渋い。
途中先行者が下山して来てすれ違いがてら、『山頂が分からなかった。』
と言う。挨拶を交わした後、副隊長と顔を見合わせ『山頂が分からない訳ね~べぇ~』と言いながら山頂を目指す。
彼らの足跡が途切れた辺りが確かに山頂ではないかと思わせるような場所
では有るが、其れらしい物が無いので、我々はもう少し先に行く。
10分ほどで石碑が頭を出しているが山名板が無いのでもう少し先に行くと
突然視界が開け絶景が広がった。ここまで雪を厄介者にしてきたが、ここで初めて雪に感謝する事になった。この季節、色の無い山肌に雪が化粧してくれて空は青く澄んでいる。勇輝でさえ感動の声を上げている。
息子と同じ物に感動できるって素晴しい事ですよね。
これだから止められないや


山頂で昼食を摂り、写真を撮って寒さに耐え切れず退散。
日光白根山にかかる雲を払おうと白根に向って息を吹き掛けている副隊長を見てニヤニヤしていた勇輝の顔が印象的だった。
勇輝に軽アイゼンを装着させて出発。
 帰り道先ほど通った石碑をもう一度何気なしに見たらそこには山名板が有るではないか、『あんなに探したのに~。写真まで撮ってたのに~』
帰り道先ほど通った石碑をもう一度何気なしに見たらそこには山名板が有るではないか、『あんなに探したのに~。写真まで撮ってたのに~』と苦笑いを浮べながらもこれで始めて庚申山制覇となった。
帰り道もっと怖がって時間がかかると思ったが、詰まらない位スイスイと降りてしまうのでチョット拍子抜けしたが、お陰でコースタイムより少し速いペースで無事下山できた。
帰りには、かじか荘の温泉で汗を流し帰路についた。
久し振りの副隊長との山登り親子共々お世話になりとても楽しい一日を過ごす事が出来ました。
今度は隊長も一緒に・・・榛名山⇒温泉⇒水沢うどん⇒おもちゃと自動車博物館でしたっけ。
また宜しくお願いします。
タグ :栃木
2009年12月06日
家族でお姫平
2009.12.06 快晴 藤枝市の小高い山に行って来ました
久々に快晴の日曜日。
オイラの体調もようやく戻ってきました。
フルオフの日曜日にパスタランチの用意をして、5人で出かけました。
父さんの墓参り~和菓子屋さん~蓮華寺池公園~お姫平という、山援隊レギュラーコースです。
道々、キョロキョロしながら・・・
父さんの墓参りでは、急登の石段をのぼり、
和菓子屋さんでは隊長:大福餅、副隊長:焼き饅頭、事務局長:和風パイを頬張り、
蓮華寺池公園では、棒切れを持って、杖代わり・・・
お姫平でパスタを腹一杯食べました。

ハイキングコース、トリムコース、アスレチックとこの辺りでは休みになると人寄せする場所です。
この日も家族連れからカップル、シニアのウォーカーなど、みんな楽しそうな顔をしていましたが、
山援隊もイイ顔していました!
途中、事務局長が小さな流れに落ちてズブ濡れになるアクシデントがありました。
夕方近かったので、風邪をひくかな?と思い、濡れたズボンを脱がせて、
オイラのフリースをズボン代わりにしました。
両袖に両足を入れさせ、ストラップをゴム代わりにして、格好がつきました(笑)
久々に歩き通して、晩酌と晩御飯の手巻寿司が美味しかったです。
久々に快晴の日曜日。
オイラの体調もようやく戻ってきました。
フルオフの日曜日にパスタランチの用意をして、5人で出かけました。
父さんの墓参り~和菓子屋さん~蓮華寺池公園~お姫平という、山援隊レギュラーコースです。
道々、キョロキョロしながら・・・
父さんの墓参りでは、急登の石段をのぼり、
和菓子屋さんでは隊長:大福餅、副隊長:焼き饅頭、事務局長:和風パイを頬張り、
蓮華寺池公園では、棒切れを持って、杖代わり・・・
お姫平でパスタを腹一杯食べました。

ハイキングコース、トリムコース、アスレチックとこの辺りでは休みになると人寄せする場所です。
この日も家族連れからカップル、シニアのウォーカーなど、みんな楽しそうな顔をしていましたが、
山援隊もイイ顔していました!
途中、事務局長が小さな流れに落ちてズブ濡れになるアクシデントがありました。
夕方近かったので、風邪をひくかな?と思い、濡れたズボンを脱がせて、
オイラのフリースをズボン代わりにしました。
両袖に両足を入れさせ、ストラップをゴム代わりにして、格好がつきました(笑)
久々に歩き通して、晩酌と晩御飯の手巻寿司が美味しかったです。
2009年12月04日
上越国境の山々を望む~続・牧峠から梨平峠へ
上越国境の山々を望む~続・牧峠から梨平峠へ
11月29日(日) 参加者;malmal&木偶野呂馬 記録;木偶 天候;曇り
3;リベンジ



13:00,梨平峠着。今年2月15日に境界線メンバーがスノーシューとスキーで羽広山のスノーシェードから登った時には梨平峠手前の小ピークにまでしか到達しなかった。目の前に見える大きな峰を越えた向こう側だと思ったのでやめたのだ。



梨平峠,2月15日
実際に到達した梨平峠はその峰の頂上で、そこまでの距離はわずか150mしかなかった。峠が山のてっぺんにあるとは思っても見なかったので意表をつかれた気がした。
峠と名がつくところは必ずかつて往来があった所で、2.5万図では上越市側には上牧地区や清里地区に下る道がついているが、飯山側には関田峠につながる道しか載っておらず、羽広山の方に下る道はないことになっている。しかし、峠にはトレイルの道と交差して下って行くと思われる道があり、調べて見る必要があると思った。
4;雲海の苗場山



周辺の山を見ていたMalmalさんがほぼ真東方向の雲海の上に横たわる平らな山を指して『苗場山だ』と言った。そうだとすればその北側に見える雪を戴いた山は何だと言うことから周辺の山名を特定しようと試みるが、何分にも初めての場所なので分からない。分からないなりに巻機山や八海山,越後駒辺りではなかろうかとか、あるいは谷川岳や朝日岳などかもしれない等と侃侃諤諤,いや喧々囂々か・・,すったもんだとひとしきり当てずっぽうを述べた後、牧峠へと引き返す。
13:17発。逆方向に歩き始めると苗場や上越国境方面と思われる山々はずっと前から見えていたことに気づき、より条件のいいところでしっかりと見て山名の特定を試みたが結局断定するには至らず、しかし曇天にもかかわらず展望を楽しんで歩けたことを喜びながら帰路を急ぐ。
13:55,標識のある小沼を通過,14:12牧峠着。
11月29日(日) 参加者;malmal&木偶野呂馬 記録;木偶 天候;曇り
3;リベンジ



13:00,梨平峠着。今年2月15日に境界線メンバーがスノーシューとスキーで羽広山のスノーシェードから登った時には梨平峠手前の小ピークにまでしか到達しなかった。目の前に見える大きな峰を越えた向こう側だと思ったのでやめたのだ。



梨平峠,2月15日
実際に到達した梨平峠はその峰の頂上で、そこまでの距離はわずか150mしかなかった。峠が山のてっぺんにあるとは思っても見なかったので意表をつかれた気がした。
峠と名がつくところは必ずかつて往来があった所で、2.5万図では上越市側には上牧地区や清里地区に下る道がついているが、飯山側には関田峠につながる道しか載っておらず、羽広山の方に下る道はないことになっている。しかし、峠にはトレイルの道と交差して下って行くと思われる道があり、調べて見る必要があると思った。
4;雲海の苗場山



周辺の山を見ていたMalmalさんがほぼ真東方向の雲海の上に横たわる平らな山を指して『苗場山だ』と言った。そうだとすればその北側に見える雪を戴いた山は何だと言うことから周辺の山名を特定しようと試みるが、何分にも初めての場所なので分からない。分からないなりに巻機山や八海山,越後駒辺りではなかろうかとか、あるいは谷川岳や朝日岳などかもしれない等と侃侃諤諤,いや喧々囂々か・・,すったもんだとひとしきり当てずっぽうを述べた後、牧峠へと引き返す。
13:17発。逆方向に歩き始めると苗場や上越国境方面と思われる山々はずっと前から見えていたことに気づき、より条件のいいところでしっかりと見て山名の特定を試みたが結局断定するには至らず、しかし曇天にもかかわらず展望を楽しんで歩けたことを喜びながら帰路を急ぐ。
13:55,標識のある小沼を通過,14:12牧峠着。
Posted by okirakutozan at
18:08
│Comments(0)
2009年12月04日
会津駒ケ岳(2009.9.21~22)
やあ、会えたね!
2009年9月21日~22日 福島県会津駒ケ岳 記録者 副隊長
 会津駒ケ岳は福島県南会津郡桧枝岐村にある標高2133mの山で日本百名山の一つ。残雪期に駒の形に見える雪形が現れることが「駒ケ岳」という山名の由来とされている。江戸時代の文献「新編会津風土記」では「駒嶽夏秋ノ間残雪駒ノ形ヲナス処アリ、故に此名アリ」とある。頂上とその稜線は草原になっていて木道が敷設されている。山頂から北北西の中門岳方面への稜線には池塘が多く、高山植物が多い。
会津駒ケ岳は福島県南会津郡桧枝岐村にある標高2133mの山で日本百名山の一つ。残雪期に駒の形に見える雪形が現れることが「駒ケ岳」という山名の由来とされている。江戸時代の文献「新編会津風土記」では「駒嶽夏秋ノ間残雪駒ノ形ヲナス処アリ、故に此名アリ」とある。頂上とその稜線は草原になっていて木道が敷設されている。山頂から北北西の中門岳方面への稜線には池塘が多く、高山植物が多い。
まあ、前知識としてはこんなもんで出発。
まだ暗い登山口に到着したが駐車している車の多さにびっくり。私の車は最後の空きスペースに駐車出来たがその後に来た車は林道の下の方までUターンして行った。帰路に知ったのだが登山口まで20分くらい歩くのでは?と思うくらいな場所まで駐車してあった。そしてこれもまた驚きなのだが車の中で夜明けを待つ間に大型のバスが2台やって来て沢山の登山者を下ろして行った。百名山恐るべし!
標準登山時間は滝沢登山口から3時間半とされている。しかし我々ぺんぎん隊には標準などというものは関係無く、ぺんぎん隊時間が適用される。今回は登山以外の目的もあるのでデカザックを背負っている。団体さんのいる登山道は何とも行動しずらくて、抜くのも抜かれるのも時間が掛かる。ぺんぎん隊時間もそっちのけの団体さん時間に翻弄される。
会津駒名物の急登を凌いで何とか水場に到着。
「駒の小屋はまだか?」
「まだだ・・」
これが合言葉のように繰り返される。
森林限界を超えて漸く駒の小屋の姿が望める。木道が延びる先には会津駒がなだらかな曲線を描いて鎮座している。


駒の小屋前のベンチに腰を下ろし大休止。水分補給を怠らない隊長に持参の水分を全部取られて駒の小屋でポカリスエットを購入したが何と400円の高値。荷揚げの苦労を考えたら仕方がない事だと思いつつ、これからは担ぎ上げたビールを500円で売ろうか・・・などと考えたりもする。
木道は草紅葉の中を曲線を描きながら伸びて行く。駒の小屋から会津駒山頂へと続く登山道は階段状に高度を稼ぎ大変きついと同行の清水くんが言う。往復ピストンの我々は側道を抜けて中門岳へと向かう。池塘が点在する草原の中の木道を歩く。尾瀬の象徴である燧ケ岳が間近に見える。青空に鰯雲、秋の真っただ中。
振り返ると日光の山々が連なり頭を覗かせている。一番右に皇海山が特徴ある三角形、プリンの様な奥白根山の隣には男体山や大真名子・小真名子、そして女峰山から帝釈山・田代山。宇都宮市から眺めるのとは全く正反対の景色が面白い。
足元を小さなバッタが跳ねた。よく見ると羽が無いのに気が付いた。草原に入り込んだ闖入者に驚いて跳ねまわっている君たちはこんな素晴らしい場所に暮らしていながらこの雄大なパノラマを見た事は無いのだろうねぇ。
中門岳の標識が立つ大きな池塘を経て先へと進むと木道が周回した終点に辿り着く。我々は別の目的に向かって一時この場から消える。翌日10時25分、再びここに現れる。
 翌日は中門岳の標識前で親子揃って記念撮影。とても親切なオジサンが自ら申し出て我々に向かってシャッターを切ってくれた。とても親切で嬉しい事だったが、一つだけ難を言えばオジサンの親指がレンズに写っている事か・・・。
翌日は中門岳の標識前で親子揃って記念撮影。とても親切なオジサンが自ら申し出て我々に向かってシャッターを切ってくれた。とても親切で嬉しい事だったが、一つだけ難を言えばオジサンの親指がレンズに写っている事か・・・。
中門岳方向から会津駒山頂を目指す。今日はネットで知り合った広島のあーちゃんがこの会津駒の何処かに居る。「帰途の駒の小屋で!」と約束していたが、その時間よりも1時間くらい遅れている。気は焦るが疲れた足が言う事を聞いてくれない。あーちゃんは隊長の顔も知っている筈なので「おまえ先に行ってろよ。」と隊長を先行させる。大した期待も持たずに言った言葉だが隊長はあれよあれよと先に進んで私との距離は開くばかり。いつの間にか隊長に追い越されている自分が情けなくもあり嬉しくもあり。
会津駒山頂は一等三角点が置かれてそれなりの風格だが展望は今一つ。でも2000m超えの山に登った喜びが沸いて来る。今年のぺんぎん登山隊の目標は「登るなら1000m超え」であり2000m級が視野にあるのだから一つの達成感はある。
山頂からの下りは噂通りの階段状。「ここを登らずに良かった!」と素直に思った私である。会津駒と中門岳を日帰りで登る方は余程のドMで無い限りは側道から先に中門岳へ向かい帰途に会津駒に登るコースをお薦め致します。
優しくも隊長は山頂で私を待っていてくれた。まあ山頂での記念写真が欲しかったという本音が見え見えだったが良しとする。二人連れ添い駒の小屋に向かって急ぐ。小屋前のベンチで先を行く隊長に注目している女性に気が付く。その女性が私に向かって大きく手を振ってくれた。


あーちゃんがいた!
広島から単身会津駒に登りに来たあーちゃんと「山で会いましょう!」と約束はしたものの、「会える会えないは時の運」とまで思っていた。第一に私はあーちゃんの顔を知らない。頼よりはあーちゃんにこちらを見つけて貰う事だけなのだ。しかしこういった楽しみがあるから辛い行程も我慢出来るのだろう。山はそして友はいいものだ。
キリンテへ下るというあーちゃんとはここでお別れだ。会えるまでの思いからするとあっという間の出会いだったけれどとても嬉しい出会いだった。「次にもまたどこかで会えるさ。」という期待と予感がこの短い出会いでさえカラッとして別れられる気がする。「じゃあね!気を付けて。」こう声をかけてあーちゃんを見送る。
さて、小屋からは一気に下りだ。会津駒名物の急登は下山時には当然ながら急下降となる。嫌と言うほどの下りの連続に登山口の階段が見えた時には膝が大笑いしていた。

お気楽にご参加下さい
2009年9月21日~22日 福島県会津駒ケ岳 記録者 副隊長
 会津駒ケ岳は福島県南会津郡桧枝岐村にある標高2133mの山で日本百名山の一つ。残雪期に駒の形に見える雪形が現れることが「駒ケ岳」という山名の由来とされている。江戸時代の文献「新編会津風土記」では「駒嶽夏秋ノ間残雪駒ノ形ヲナス処アリ、故に此名アリ」とある。頂上とその稜線は草原になっていて木道が敷設されている。山頂から北北西の中門岳方面への稜線には池塘が多く、高山植物が多い。
会津駒ケ岳は福島県南会津郡桧枝岐村にある標高2133mの山で日本百名山の一つ。残雪期に駒の形に見える雪形が現れることが「駒ケ岳」という山名の由来とされている。江戸時代の文献「新編会津風土記」では「駒嶽夏秋ノ間残雪駒ノ形ヲナス処アリ、故に此名アリ」とある。頂上とその稜線は草原になっていて木道が敷設されている。山頂から北北西の中門岳方面への稜線には池塘が多く、高山植物が多い。まあ、前知識としてはこんなもんで出発。
まだ暗い登山口に到着したが駐車している車の多さにびっくり。私の車は最後の空きスペースに駐車出来たがその後に来た車は林道の下の方までUターンして行った。帰路に知ったのだが登山口まで20分くらい歩くのでは?と思うくらいな場所まで駐車してあった。そしてこれもまた驚きなのだが車の中で夜明けを待つ間に大型のバスが2台やって来て沢山の登山者を下ろして行った。百名山恐るべし!
標準登山時間は滝沢登山口から3時間半とされている。しかし我々ぺんぎん隊には標準などというものは関係無く、ぺんぎん隊時間が適用される。今回は登山以外の目的もあるのでデカザックを背負っている。団体さんのいる登山道は何とも行動しずらくて、抜くのも抜かれるのも時間が掛かる。ぺんぎん隊時間もそっちのけの団体さん時間に翻弄される。
会津駒名物の急登を凌いで何とか水場に到着。
「駒の小屋はまだか?」
「まだだ・・」
これが合言葉のように繰り返される。
森林限界を超えて漸く駒の小屋の姿が望める。木道が延びる先には会津駒がなだらかな曲線を描いて鎮座している。


駒の小屋前のベンチに腰を下ろし大休止。水分補給を怠らない隊長に持参の水分を全部取られて駒の小屋でポカリスエットを購入したが何と400円の高値。荷揚げの苦労を考えたら仕方がない事だと思いつつ、これからは担ぎ上げたビールを500円で売ろうか・・・などと考えたりもする。
木道は草紅葉の中を曲線を描きながら伸びて行く。駒の小屋から会津駒山頂へと続く登山道は階段状に高度を稼ぎ大変きついと同行の清水くんが言う。往復ピストンの我々は側道を抜けて中門岳へと向かう。池塘が点在する草原の中の木道を歩く。尾瀬の象徴である燧ケ岳が間近に見える。青空に鰯雲、秋の真っただ中。
振り返ると日光の山々が連なり頭を覗かせている。一番右に皇海山が特徴ある三角形、プリンの様な奥白根山の隣には男体山や大真名子・小真名子、そして女峰山から帝釈山・田代山。宇都宮市から眺めるのとは全く正反対の景色が面白い。
足元を小さなバッタが跳ねた。よく見ると羽が無いのに気が付いた。草原に入り込んだ闖入者に驚いて跳ねまわっている君たちはこんな素晴らしい場所に暮らしていながらこの雄大なパノラマを見た事は無いのだろうねぇ。
中門岳の標識が立つ大きな池塘を経て先へと進むと木道が周回した終点に辿り着く。我々は別の目的に向かって一時この場から消える。翌日10時25分、再びここに現れる。
 翌日は中門岳の標識前で親子揃って記念撮影。とても親切なオジサンが自ら申し出て我々に向かってシャッターを切ってくれた。とても親切で嬉しい事だったが、一つだけ難を言えばオジサンの親指がレンズに写っている事か・・・。
翌日は中門岳の標識前で親子揃って記念撮影。とても親切なオジサンが自ら申し出て我々に向かってシャッターを切ってくれた。とても親切で嬉しい事だったが、一つだけ難を言えばオジサンの親指がレンズに写っている事か・・・。中門岳方向から会津駒山頂を目指す。今日はネットで知り合った広島のあーちゃんがこの会津駒の何処かに居る。「帰途の駒の小屋で!」と約束していたが、その時間よりも1時間くらい遅れている。気は焦るが疲れた足が言う事を聞いてくれない。あーちゃんは隊長の顔も知っている筈なので「おまえ先に行ってろよ。」と隊長を先行させる。大した期待も持たずに言った言葉だが隊長はあれよあれよと先に進んで私との距離は開くばかり。いつの間にか隊長に追い越されている自分が情けなくもあり嬉しくもあり。
会津駒山頂は一等三角点が置かれてそれなりの風格だが展望は今一つ。でも2000m超えの山に登った喜びが沸いて来る。今年のぺんぎん登山隊の目標は「登るなら1000m超え」であり2000m級が視野にあるのだから一つの達成感はある。
山頂からの下りは噂通りの階段状。「ここを登らずに良かった!」と素直に思った私である。会津駒と中門岳を日帰りで登る方は余程のドMで無い限りは側道から先に中門岳へ向かい帰途に会津駒に登るコースをお薦め致します。
優しくも隊長は山頂で私を待っていてくれた。まあ山頂での記念写真が欲しかったという本音が見え見えだったが良しとする。二人連れ添い駒の小屋に向かって急ぐ。小屋前のベンチで先を行く隊長に注目している女性に気が付く。その女性が私に向かって大きく手を振ってくれた。


あーちゃんがいた!
広島から単身会津駒に登りに来たあーちゃんと「山で会いましょう!」と約束はしたものの、「会える会えないは時の運」とまで思っていた。第一に私はあーちゃんの顔を知らない。頼よりはあーちゃんにこちらを見つけて貰う事だけなのだ。しかしこういった楽しみがあるから辛い行程も我慢出来るのだろう。山はそして友はいいものだ。
キリンテへ下るというあーちゃんとはここでお別れだ。会えるまでの思いからするとあっという間の出会いだったけれどとても嬉しい出会いだった。「次にもまたどこかで会えるさ。」という期待と予感がこの短い出会いでさえカラッとして別れられる気がする。「じゃあね!気を付けて。」こう声をかけてあーちゃんを見送る。
さて、小屋からは一気に下りだ。会津駒名物の急登は下山時には当然ながら急下降となる。嫌と言うほどの下りの連続に登山口の階段が見えた時には膝が大笑いしていた。

お気楽にご参加下さい
タグ :福島
2009年12月02日
信越トレイル・牧峠~梨平峠偵察
信越トレイル・牧峠~梨平峠偵察・1
11月29日(日) 記録者:木偶野呂馬 参加者:まるまる&木偶 天候:曇り
1;牧峠へ
11月3日・文化の日に新潟のMarumaruさんと関田峠から鍋倉山までを歩く計画で新潟,長野の双方から関田峠を目指したものの、新潟側は上越市の光ヶ原牧場で30cmの積雪、長野側も飯山温井付近の猛吹雪で関田峠まで乗り入れることが出来ず断念。11月29日(日)に再度鍋倉山を目指したが、すでに道路が閉鎖されてこの日も関田峠に近づくことが出来なかった。
そこで情報収集のために鍋倉高原・森の家に寄ったところ、牧峠を通る道は道路閉鎖が無く積雪さえなければ通れると言うことがわかり、その峠方面に車を走らせる。
11時頃牧峠に着くと、それまでブナに覆われた山や尾根を見上げていたのが一変して、一切の壁が取り払われた景観を鳥の目で見下ろすこととなる。 春日山や直江津港方面は霞んでいて写真にならなかったが、その霞が海岸線から立ち上がって米山,黒姫山と続く山なみを墨絵のように背景の空に溶けこませているのが印象的である。


眼下には日本海に向けて急速に高度を下げる関田山脈の山裾の斜面を切り開いた棚田と集落が入り混じった景色が広がり、それは海岸線のすぐ近くまで続いていて、市街地と言える部分は海岸線のごくわずかであることがよく分かる。


海岸線に吸い寄せられた視線が左手(北北西)方向に春日山のある低い丘陵から直江津港の長い突堤をなぞり、さらに右(北北東~北東)に視線を進めるとに三階節に歌われる米山が見えてくる。
米山からさらに東に向かって低いながらもきれいな稜線が連なる中でひと際目立つ秀麗な山をMarumaruさんは『黒姫山』だと言った。その山名が、5月17日に鍋倉山に登った際に途中の黒倉山で新潟からの登山者に聞いた説明とまったく同じであることが、その時見た景観とともにまざまざと甦って来たことにちょっと驚いた。


峠の一隅に『峠越す荷馬の難所も林道に拠りて湯の町信濃は近し』と書かれた歌碑があり、林道に拠って峠を越え信濃の湯の里が近くなったことを素直に喜んでいる様子が伺えた。
新潟県人であるMarumaruさんは『牧峠,梨平峠,関田峠などの地名はすべて新潟側(上越市)の地名に由来している』と言う。牧峠に限らず、関田山脈を越えて越後と信州を結ぶ往来の峠には特に越後の人の思いが込められているのかもしれない。
2;牧峠から梨平峠へ
関田峠を諦めた代わりに思いがけず牧峠から信越トレイルにアクセスすることが出来たので少しだけ歩いてみようと言うことになり、車中で昼食をすませて12:00に梨平峠を目指して歩き始める。
牧峠から梨平峠までは2.4km,関田峠までは4.5kmで、時間的に関田峠までは無理ではないがちょっと厳しいか・・。
峠に何人かの人がいた他に何台かの車もあったが、残雪には靴跡がなくコース前方は無人。初めにややきつい階段があってなまった脚にはこたえるが、すぐに登りきって以後は起伏のゆるやかな道となり少しづつ高度を上げるに伴って雪が増えて来る。


雪面には肉球のある足跡,カモシカのものらしい2本爪の足跡の他,これまでに見たことのない肉球とも爪跡とも判別のつかない連続した足跡が見られた。
道の両脇はすべてブナの林で、比較的大きな木もあるが、稜線のそれらしく丈が低くて上部がひょろひょろと縮んだものも見られる。足元の倒木を覆う苔の緑が美しい。


12:20,標識のある小さな池(牧の小池)のほとりに着く。牧峠から0.9km,関田峠に3.6kmとある。

続く
11月29日(日) 記録者:木偶野呂馬 参加者:まるまる&木偶 天候:曇り

1;牧峠へ
11月3日・文化の日に新潟のMarumaruさんと関田峠から鍋倉山までを歩く計画で新潟,長野の双方から関田峠を目指したものの、新潟側は上越市の光ヶ原牧場で30cmの積雪、長野側も飯山温井付近の猛吹雪で関田峠まで乗り入れることが出来ず断念。11月29日(日)に再度鍋倉山を目指したが、すでに道路が閉鎖されてこの日も関田峠に近づくことが出来なかった。
そこで情報収集のために鍋倉高原・森の家に寄ったところ、牧峠を通る道は道路閉鎖が無く積雪さえなければ通れると言うことがわかり、その峠方面に車を走らせる。
11時頃牧峠に着くと、それまでブナに覆われた山や尾根を見上げていたのが一変して、一切の壁が取り払われた景観を鳥の目で見下ろすこととなる。 春日山や直江津港方面は霞んでいて写真にならなかったが、その霞が海岸線から立ち上がって米山,黒姫山と続く山なみを墨絵のように背景の空に溶けこませているのが印象的である。


眼下には日本海に向けて急速に高度を下げる関田山脈の山裾の斜面を切り開いた棚田と集落が入り混じった景色が広がり、それは海岸線のすぐ近くまで続いていて、市街地と言える部分は海岸線のごくわずかであることがよく分かる。


海岸線に吸い寄せられた視線が左手(北北西)方向に春日山のある低い丘陵から直江津港の長い突堤をなぞり、さらに右(北北東~北東)に視線を進めるとに三階節に歌われる米山が見えてくる。
米山からさらに東に向かって低いながらもきれいな稜線が連なる中でひと際目立つ秀麗な山をMarumaruさんは『黒姫山』だと言った。その山名が、5月17日に鍋倉山に登った際に途中の黒倉山で新潟からの登山者に聞いた説明とまったく同じであることが、その時見た景観とともにまざまざと甦って来たことにちょっと驚いた。


峠の一隅に『峠越す荷馬の難所も林道に拠りて湯の町信濃は近し』と書かれた歌碑があり、林道に拠って峠を越え信濃の湯の里が近くなったことを素直に喜んでいる様子が伺えた。
新潟県人であるMarumaruさんは『牧峠,梨平峠,関田峠などの地名はすべて新潟側(上越市)の地名に由来している』と言う。牧峠に限らず、関田山脈を越えて越後と信州を結ぶ往来の峠には特に越後の人の思いが込められているのかもしれない。
2;牧峠から梨平峠へ
関田峠を諦めた代わりに思いがけず牧峠から信越トレイルにアクセスすることが出来たので少しだけ歩いてみようと言うことになり、車中で昼食をすませて12:00に梨平峠を目指して歩き始める。
牧峠から梨平峠までは2.4km,関田峠までは4.5kmで、時間的に関田峠までは無理ではないがちょっと厳しいか・・。
峠に何人かの人がいた他に何台かの車もあったが、残雪には靴跡がなくコース前方は無人。初めにややきつい階段があってなまった脚にはこたえるが、すぐに登りきって以後は起伏のゆるやかな道となり少しづつ高度を上げるに伴って雪が増えて来る。


雪面には肉球のある足跡,カモシカのものらしい2本爪の足跡の他,これまでに見たことのない肉球とも爪跡とも判別のつかない連続した足跡が見られた。
道の両脇はすべてブナの林で、比較的大きな木もあるが、稜線のそれらしく丈が低くて上部がひょろひょろと縮んだものも見られる。足元の倒木を覆う苔の緑が美しい。


12:20,標識のある小さな池(牧の小池)のほとりに着く。牧峠から0.9km,関田峠に3.6kmとある。

続く
Posted by okirakutozan at
14:11
│Comments(0)
2009年12月01日
両神山(2009.10.31)
あぁ、あの山に再び
2009年10月31日 埼玉県秩父 両神山 記録者 はら坊
10月も終わりの週末、少年野球を始めて以来週末になると練習やら試合やらでなかなか一緒に山に行けなくなった長男の勇輝が急に『日曜日の練習がインフルエンザの子供が多い為中止になったから山登りに行きたい。両神に行きたい。』と言い出した。
もともと一人でも行こうと思っていたので、相棒が出来てラッキーってことで即OKと準備を始めた。
でも両神山と言ったら今年の冬、隊長と副隊長と三人で雪の中を登り結構キツイイメージが有ったので、場所の変更を提案したが勇輝は両神が良いと言っているので両神山に決定した。
当日まだ暗くて寒い中を日向大谷登山口を目指した。途中コンビニで昼食とオヤツを購入して登山口に向う。薄明るくなる頃到着。
天気は晴れ?朝のうちは霧が出てたりでよく分からない天気だが何しろ寒い。
時折色付いた木の葉が朝焼けに映えとても綺麗だ。
明るくなるのを待ち出発それにしても寒い・・・が歩き始めて日が出てきたら今度は暑い。



 これが11月の秩父か???などと思いながら、歩みを進める。会所を過ぎて上りもキツクなっていくが勇輝が泣かない。
これが11月の秩父か???などと思いながら、歩みを進める。会所を過ぎて上りもキツクなっていくが勇輝が泣かない。
それどころか、私を引っ張るようなペースで歩いている。まだ先は長いのに『早く温泉、早く温泉』と呟きながら登って行く。そう言えば隊長もそんな事言って歩いていた事あったっけな~っと思い出した。
「まだ先は長いぞ~っ。」と少し心配になりながら先を急ぐが途中何人かを追い越して行く。
そんなこんなで、清滝小屋に到着。軽く食事をして山頂を目指す。
小屋から産泰尾根までの急登でも勇輝が泣かない。
自分の前を行く勇輝をみて子供の成長の早さを実感しながら、『早く野球辞めろよ』と心の中で呟く私であった。
産泰尾根に出て、鎖場を数箇所突破して奥の院に到着、水分補給をして山頂を目指す。



 40分ほどで山頂に到着。狭い山頂は沢山の人々で賑わっていたので写真を数枚撮って少し下ったベンチで昼食を
40分ほどで山頂に到着。狭い山頂は沢山の人々で賑わっていたので写真を数枚撮って少し下ったベンチで昼食を
摂る。
勇輝は、『お握りの梅干が真中に無い』と母親の作ったお握りにダメだししながらも3個をたいらげて下山。
あっと言う間に奥の院に到着。小屋までもあっと言う間、小屋で水分と糖分を補給して再び下山。ここで今回初めての泣きが入った。
『下りばっかりでヤダ~・・・足が痛い』下りが大好だったはずの勇輝が珍しいなと思いながらも、確かに疲れる降りだ。前回はこれを雪の中下ったったんだな~と思い出しながら降りる。
それでも先ず先ずのペースで車止めに到着。
トータル6時間15分で全工程を終了。久し振りの子供との登山、紅葉も所どころ綺麗で楽しい一日を過す事が出来た。
帰りは、両神温泉薬師の湯で汗を流し帰路についた。
帰る車中『勇輝早く野球なんて辞めちまうんだぞ~』と助手席で眠る息子に心の中で叫んでみた。



2009年10月31日 埼玉県秩父 両神山 記録者 はら坊
10月も終わりの週末、少年野球を始めて以来週末になると練習やら試合やらでなかなか一緒に山に行けなくなった長男の勇輝が急に『日曜日の練習がインフルエンザの子供が多い為中止になったから山登りに行きたい。両神に行きたい。』と言い出した。
もともと一人でも行こうと思っていたので、相棒が出来てラッキーってことで即OKと準備を始めた。
でも両神山と言ったら今年の冬、隊長と副隊長と三人で雪の中を登り結構キツイイメージが有ったので、場所の変更を提案したが勇輝は両神が良いと言っているので両神山に決定した。
当日まだ暗くて寒い中を日向大谷登山口を目指した。途中コンビニで昼食とオヤツを購入して登山口に向う。薄明るくなる頃到着。
天気は晴れ?朝のうちは霧が出てたりでよく分からない天気だが何しろ寒い。
時折色付いた木の葉が朝焼けに映えとても綺麗だ。
明るくなるのを待ち出発それにしても寒い・・・が歩き始めて日が出てきたら今度は暑い。



 これが11月の秩父か???などと思いながら、歩みを進める。会所を過ぎて上りもキツクなっていくが勇輝が泣かない。
これが11月の秩父か???などと思いながら、歩みを進める。会所を過ぎて上りもキツクなっていくが勇輝が泣かない。 それどころか、私を引っ張るようなペースで歩いている。まだ先は長いのに『早く温泉、早く温泉』と呟きながら登って行く。そう言えば隊長もそんな事言って歩いていた事あったっけな~っと思い出した。
「まだ先は長いぞ~っ。」と少し心配になりながら先を急ぐが途中何人かを追い越して行く。
そんなこんなで、清滝小屋に到着。軽く食事をして山頂を目指す。
小屋から産泰尾根までの急登でも勇輝が泣かない。
自分の前を行く勇輝をみて子供の成長の早さを実感しながら、『早く野球辞めろよ』と心の中で呟く私であった。
産泰尾根に出て、鎖場を数箇所突破して奥の院に到着、水分補給をして山頂を目指す。



 40分ほどで山頂に到着。狭い山頂は沢山の人々で賑わっていたので写真を数枚撮って少し下ったベンチで昼食を
40分ほどで山頂に到着。狭い山頂は沢山の人々で賑わっていたので写真を数枚撮って少し下ったベンチで昼食を 摂る。
勇輝は、『お握りの梅干が真中に無い』と母親の作ったお握りにダメだししながらも3個をたいらげて下山。
あっと言う間に奥の院に到着。小屋までもあっと言う間、小屋で水分と糖分を補給して再び下山。ここで今回初めての泣きが入った。
『下りばっかりでヤダ~・・・足が痛い』下りが大好だったはずの勇輝が珍しいなと思いながらも、確かに疲れる降りだ。前回はこれを雪の中下ったったんだな~と思い出しながら降りる。
それでも先ず先ずのペースで車止めに到着。
トータル6時間15分で全工程を終了。久し振りの子供との登山、紅葉も所どころ綺麗で楽しい一日を過す事が出来た。
帰りは、両神温泉薬師の湯で汗を流し帰路についた。
帰る車中『勇輝早く野球なんて辞めちまうんだぞ~』と助手席で眠る息子に心の中で叫んでみた。



タグ :埼玉