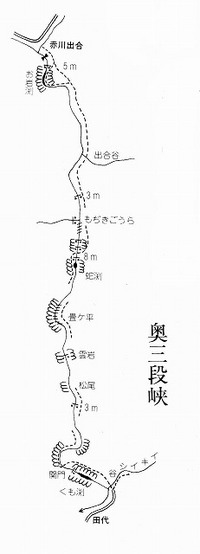2010年08月21日
出羽月山・偵察山行
出羽月山・偵察山行
8月17日(火)
当初の計画は昨16日にやっと栗駒山の登山を果たしただけに終わり、後はただ無目的に帰るだけとなってそれでは余りにも寂しいと言うことになり、せっかくなので今後を見通して山形周辺の山を見ておこうと朝日岳の東の登山口となる朝日鉱泉ナチュラリストの家を訪ねる。その後さらに北上して月山高原8合目・弥陀ヶ原からのコースを偵察することとなる。
月山へは北側の弥陀ヶ原の登山口から入るために態々大回りして羽黒山経由で月山高原ラインを目指したが、湯殿山から羽黒山を経て高原ラインに至る道が分かりづらくて手間取った。
13:50,弥陀ヶ原(8合目)のレストハウス着。前日の栗駒山とほぼ同じ時刻で、上部がスッポリとガスに覆われている点も同じ。違うのは風が強烈なことと、この条件の中を月山に登っている人がかなりあるらしいこと,また遊歩道目的の観光客が多いと言う点である。
14:03,雨具と行動食,水,ヘッドランプをザックにつめ、握り飯を1つ頬張って出発。9合目辺りまで行ければいいと考えている自分と違って今日のjun1さんはやる気満々。
遊歩道の分岐から『月山本営』と書かれた山門をくぐって山頂方面に向かう。ガスの中を次々と降りてくる登山者は、登頂を果たした人だけでなく、あまりの風に途中で引き返した人も混じる。自分もまたどこまでいけるか不安を抱えたまま、とりあえず前進しているだけと言う感じで、たちまちjun1さんにおいて行かれる。
登山道ははじめ石を敷き詰めた遊歩道であったり飛び石状であったりするが、やがて歩きやすい道となる。いくら歩いてもちっとも疲れないのは空身に近いせいで、荷物の重さによってこうも違うものかと半ば呆れる思いで歩いていたが、やがてそうではなくて遊歩道と変わらない緩斜面のおかげと気づく。
登頂目的でなくあくまでも偵察のつもりであるが、途中で何も問題がなければ山頂まで行ってしまう可能性があるので往路は脇目もふらずにひたすら歩き、丁度1時間で佛生池小屋と書かれた9合目の小屋に着く。その少し手前では烈風に吹き晒されてバランスを失いよろめく場面もあって、荷が軽いことが逆に作用すると言うことを体験した。
休まず通過してさらに上を目指す。海側からの風は相変わらず強いが風裏に入るとまったく風が来ない。緩やかな斜面が延々と続き、唯一,行者返しと言う大岩混じりの登りで初めてペースダウンするが、そこを抜けるとまた同じような道で、潅木がなくなって風衝植物群だけの世界となり、風当たりがさらに強くなる。
左手に指導標を見て山頂の近いことを感じるもそこからが意外と長く、緩やかに右に曲がりながらモックラ坂と称する登りの大きな山の塊をいくつか超えて15:45月山神社境内に着く。
門を通って境内に入ると社務所があって参拝料500円を求められる。たまたま1000円札を持っていたので入れたが金を持たない者は山頂に立てないことになる。それならそれを登山口に書いておいて欲しいものだが、どこかに書いてあったかも知れず、事前研究もしないで登る方が悪いと言われそうだ。
境内だからと言われ、お払いだのお清めだのの神事を強いられれば唯々諾々と従う他ないが、『(拝観料は)山の整備や保護に使います』と言い訳めいて言われても『そうですか』と納得はできない。
鳥海山の場合は社務所とは別に山頂標識があって、お払い等を受けるどうかは登山者が選択できる。無宗教の自分には不快感が残るが、信仰の山だからと言われればそれまでで、目くじら立てても仕方がなく通過儀礼とする。
15:50下山開始。山頂まで登ってしまったので後は暗くなろうが雨が降ろうがかまわずゆっくり花を撮りながら下る。
最盛期は過ぎていると思われるが花は豊富で、その1つ1つの名前を確認しながら撮りたいものだが、何も資料を持たず特定できないのがいささか悔しい。なので『〇〇の仲間』としか表せない。
帰路で見かけた花は、ウスユキソウノ仲間,トウウチソウの仲間,以下,『~の仲間』『(?)』『多分』は略して、ハクサンイチゲ,チョウカイアザミ,フウロソウ,ミヤマアキノキリンソウ,ミヤマシシウド,もしくわミヤマトウキ,エゾシオガマ,ウサギギク等々。中でも濃い赤紫のフウロソウが印象的。
16:32佛生池小屋着。ゆっくりしすぎてjun1さんを待たせ、心配させてしまった。後は一目散に駆け下り、途中で山頂手前ですれ違った夫婦を追い越して17:10頃遊歩道に到達。ここから観光客がどっと増える。17:20下山。少しのんびりしすぎて往復3時間は切れなかった。
出発前に予定していなかった山に登ることは、事前研究がまったくなされず地図も持っていない等の点から慎重でなければならないと考えている。今回敢えてその禁を犯したのは前半があまりにみすぼらしい結果に終わり、せっかく交通費と休暇を使ったからには少しでも将来につながるものを得たかったからである。故に登頂したとは言え、これは縦走に向けての下見である。
8月17日(火)
当初の計画は昨16日にやっと栗駒山の登山を果たしただけに終わり、後はただ無目的に帰るだけとなってそれでは余りにも寂しいと言うことになり、せっかくなので今後を見通して山形周辺の山を見ておこうと朝日岳の東の登山口となる朝日鉱泉ナチュラリストの家を訪ねる。その後さらに北上して月山高原8合目・弥陀ヶ原からのコースを偵察することとなる。
月山へは北側の弥陀ヶ原の登山口から入るために態々大回りして羽黒山経由で月山高原ラインを目指したが、湯殿山から羽黒山を経て高原ラインに至る道が分かりづらくて手間取った。
13:50,弥陀ヶ原(8合目)のレストハウス着。前日の栗駒山とほぼ同じ時刻で、上部がスッポリとガスに覆われている点も同じ。違うのは風が強烈なことと、この条件の中を月山に登っている人がかなりあるらしいこと,また遊歩道目的の観光客が多いと言う点である。
14:03,雨具と行動食,水,ヘッドランプをザックにつめ、握り飯を1つ頬張って出発。9合目辺りまで行ければいいと考えている自分と違って今日のjun1さんはやる気満々。
遊歩道の分岐から『月山本営』と書かれた山門をくぐって山頂方面に向かう。ガスの中を次々と降りてくる登山者は、登頂を果たした人だけでなく、あまりの風に途中で引き返した人も混じる。自分もまたどこまでいけるか不安を抱えたまま、とりあえず前進しているだけと言う感じで、たちまちjun1さんにおいて行かれる。
登山道ははじめ石を敷き詰めた遊歩道であったり飛び石状であったりするが、やがて歩きやすい道となる。いくら歩いてもちっとも疲れないのは空身に近いせいで、荷物の重さによってこうも違うものかと半ば呆れる思いで歩いていたが、やがてそうではなくて遊歩道と変わらない緩斜面のおかげと気づく。
登頂目的でなくあくまでも偵察のつもりであるが、途中で何も問題がなければ山頂まで行ってしまう可能性があるので往路は脇目もふらずにひたすら歩き、丁度1時間で佛生池小屋と書かれた9合目の小屋に着く。その少し手前では烈風に吹き晒されてバランスを失いよろめく場面もあって、荷が軽いことが逆に作用すると言うことを体験した。
休まず通過してさらに上を目指す。海側からの風は相変わらず強いが風裏に入るとまったく風が来ない。緩やかな斜面が延々と続き、唯一,行者返しと言う大岩混じりの登りで初めてペースダウンするが、そこを抜けるとまた同じような道で、潅木がなくなって風衝植物群だけの世界となり、風当たりがさらに強くなる。
左手に指導標を見て山頂の近いことを感じるもそこからが意外と長く、緩やかに右に曲がりながらモックラ坂と称する登りの大きな山の塊をいくつか超えて15:45月山神社境内に着く。
門を通って境内に入ると社務所があって参拝料500円を求められる。たまたま1000円札を持っていたので入れたが金を持たない者は山頂に立てないことになる。それならそれを登山口に書いておいて欲しいものだが、どこかに書いてあったかも知れず、事前研究もしないで登る方が悪いと言われそうだ。
境内だからと言われ、お払いだのお清めだのの神事を強いられれば唯々諾々と従う他ないが、『(拝観料は)山の整備や保護に使います』と言い訳めいて言われても『そうですか』と納得はできない。
鳥海山の場合は社務所とは別に山頂標識があって、お払い等を受けるどうかは登山者が選択できる。無宗教の自分には不快感が残るが、信仰の山だからと言われればそれまでで、目くじら立てても仕方がなく通過儀礼とする。
15:50下山開始。山頂まで登ってしまったので後は暗くなろうが雨が降ろうがかまわずゆっくり花を撮りながら下る。
最盛期は過ぎていると思われるが花は豊富で、その1つ1つの名前を確認しながら撮りたいものだが、何も資料を持たず特定できないのがいささか悔しい。なので『〇〇の仲間』としか表せない。
帰路で見かけた花は、ウスユキソウノ仲間,トウウチソウの仲間,以下,『~の仲間』『(?)』『多分』は略して、ハクサンイチゲ,チョウカイアザミ,フウロソウ,ミヤマアキノキリンソウ,ミヤマシシウド,もしくわミヤマトウキ,エゾシオガマ,ウサギギク等々。中でも濃い赤紫のフウロソウが印象的。
16:32佛生池小屋着。ゆっくりしすぎてjun1さんを待たせ、心配させてしまった。後は一目散に駆け下り、途中で山頂手前ですれ違った夫婦を追い越して17:10頃遊歩道に到達。ここから観光客がどっと増える。17:20下山。少しのんびりしすぎて往復3時間は切れなかった。
出発前に予定していなかった山に登ることは、事前研究がまったくなされず地図も持っていない等の点から慎重でなければならないと考えている。今回敢えてその禁を犯したのは前半があまりにみすぼらしい結果に終わり、せっかく交通費と休暇を使ったからには少しでも将来につながるものを得たかったからである。故に登頂したとは言え、これは縦走に向けての下見である。
Posted by okirakutozan at
12:45
│Comments(0)
2010年08月21日
栗駒山
栗駒山
8月13日(金)20:00に安曇野を出発して夜通し走り、早朝阿仁中村に着いて森吉山に登ると言う計画は初っ端から雨で頓挫。翌日,翌々日と降り続く雨に岩手山をも諦めて一度も登山靴を履かないまま16日を迎え、午後からの回復に一縷の望みを託して栗駒山に向かう。
8月16日(月),13:50イワカガミ平に着く。3日間の待機に気勢を削がれあまり意欲がわかないが、このままどこにも登らずに帰ったのではとんだ笑い種なので気持ちを奮い立たせて靴を履く。jun1さんの動きも心なしか鈍い。
頂上まで1時間半,往復2時間半と見て雨具と少量の行動食,水,ヘッドランプのみの空身に近い軽装で14:05発。
広い駐車場の右手から休業中のレストハウスにつながる石畳の道を上に向かい、東栗駒コースを右に見送ってハウスの左脇を抜けるとそこから登山道が始まるのだが、どこまで行ってもコンクリートで固められた石畳の道で登山道と言う気がしない。
視界は200mほどでそこから先はガスに覆われて見えず、どこが山頂なのか分からないまま、丈の低い潅木の間にまっすぐつけられた石畳の道を歩く。道の脇にはミヤマホツツジ,ミヤマアキノキリンソウ,ハクサンオミナエシと思われる黄色い花などが散見され、またホシガラスが食い散らかしたと思われるハイマツの実が随所に落ちているのを見る。
40分ほどでやや視界が広がり、前方にうっすらと山影が見えてくる。山影は右方向に連なって高みを増し、そこから先はガスに隠れて見えないが、そちらが山頂方向であることを示していた。
14:47,『栗駒山・栃ヶ森山森林生態系保護地域』の大看板を通過。石畳はこの手前で終わり、ようやく土の道となる。緩やかながら登り一辺倒だった道が一旦平坦化して右にカーブしながら次の登りに入る辺りでガスの中から子ども達が話す甲高い声が聞こえてくる。入れ違いに年配の男性が降りてきて『子ども(孫?)達は上に行きました。昔はよく登ったけどもう・・』と言い訳しながら下って行った。子ども達の声はその後も常に100mほど先を行き、私達を山頂までリードしてくれた。
足元にはトウウチソウ(白花)やウメバチソウ,イワショウブ,リンドウ,アザミ(ナンブタカネアザミか?)等の花が見られる。いずれも強い南風に晒されて激しく揺れている。
トウウチソウは咲きはじめの花穂の先端に突き出た蘂にわずかな赤みがあるために赤花に見えるものがあるが基調は白花。同様にイワショウブも雌蕊の先端に赤みが混じるので赤く見えるものがある。
道がやや左にカーブしながら傾斜を増し、時折階段が出てくるようになり、子ども達の声がひとしきり大きくなって見覚えのある山頂標識が現れ、15:17登頂。反対側から登ったのは初めてなので一瞬方向感覚が狂って素直に受け入れられない。
山頂には幼児から中学生くらいまで、3人の大人に率いられた6人もの子ども達がいた。ひときわよく響く元気な声で山頂まで引っ張ってくれたのは一番小さな男の子で、『元気だネェ』と言うと『ドスコイっ』とおどけて見せた。
須川温泉まで下るには時間が遅すぎ、風が強く視界もないので山頂には5分いて退散する。来た道を来た時よりも長く感じながらひたすら歩いて16:12下山。
8月13日(金)20:00に安曇野を出発して夜通し走り、早朝阿仁中村に着いて森吉山に登ると言う計画は初っ端から雨で頓挫。翌日,翌々日と降り続く雨に岩手山をも諦めて一度も登山靴を履かないまま16日を迎え、午後からの回復に一縷の望みを託して栗駒山に向かう。
8月16日(月),13:50イワカガミ平に着く。3日間の待機に気勢を削がれあまり意欲がわかないが、このままどこにも登らずに帰ったのではとんだ笑い種なので気持ちを奮い立たせて靴を履く。jun1さんの動きも心なしか鈍い。
頂上まで1時間半,往復2時間半と見て雨具と少量の行動食,水,ヘッドランプのみの空身に近い軽装で14:05発。
広い駐車場の右手から休業中のレストハウスにつながる石畳の道を上に向かい、東栗駒コースを右に見送ってハウスの左脇を抜けるとそこから登山道が始まるのだが、どこまで行ってもコンクリートで固められた石畳の道で登山道と言う気がしない。
視界は200mほどでそこから先はガスに覆われて見えず、どこが山頂なのか分からないまま、丈の低い潅木の間にまっすぐつけられた石畳の道を歩く。道の脇にはミヤマホツツジ,ミヤマアキノキリンソウ,ハクサンオミナエシと思われる黄色い花などが散見され、またホシガラスが食い散らかしたと思われるハイマツの実が随所に落ちているのを見る。
40分ほどでやや視界が広がり、前方にうっすらと山影が見えてくる。山影は右方向に連なって高みを増し、そこから先はガスに隠れて見えないが、そちらが山頂方向であることを示していた。
14:47,『栗駒山・栃ヶ森山森林生態系保護地域』の大看板を通過。石畳はこの手前で終わり、ようやく土の道となる。緩やかながら登り一辺倒だった道が一旦平坦化して右にカーブしながら次の登りに入る辺りでガスの中から子ども達が話す甲高い声が聞こえてくる。入れ違いに年配の男性が降りてきて『子ども(孫?)達は上に行きました。昔はよく登ったけどもう・・』と言い訳しながら下って行った。子ども達の声はその後も常に100mほど先を行き、私達を山頂までリードしてくれた。
足元にはトウウチソウ(白花)やウメバチソウ,イワショウブ,リンドウ,アザミ(ナンブタカネアザミか?)等の花が見られる。いずれも強い南風に晒されて激しく揺れている。
トウウチソウは咲きはじめの花穂の先端に突き出た蘂にわずかな赤みがあるために赤花に見えるものがあるが基調は白花。同様にイワショウブも雌蕊の先端に赤みが混じるので赤く見えるものがある。
道がやや左にカーブしながら傾斜を増し、時折階段が出てくるようになり、子ども達の声がひとしきり大きくなって見覚えのある山頂標識が現れ、15:17登頂。反対側から登ったのは初めてなので一瞬方向感覚が狂って素直に受け入れられない。
山頂には幼児から中学生くらいまで、3人の大人に率いられた6人もの子ども達がいた。ひときわよく響く元気な声で山頂まで引っ張ってくれたのは一番小さな男の子で、『元気だネェ』と言うと『ドスコイっ』とおどけて見せた。
須川温泉まで下るには時間が遅すぎ、風が強く視界もないので山頂には5分いて退散する。来た道を来た時よりも長く感じながらひたすら歩いて16:12下山。
2010年08月15日
モンブラン登頂! by ムトヤン
 7月30日~8月7日の日程で、ヨーロッパ・アルプス最高峰のモンブラン(4810m)にアタック、無事登頂することが出来た。これは某アルパインツアーの企画で決行したが、50歳を期にチャレンジをと思っていた自分のハートにマッチしたためであった。直前まで、灼熱の横浜スタジアムで勤務校の高校野球の応援に全精力を使っていたのだが、残念ながら決勝で敗れ、あまりの悔しさに「絶対、モンブランの山頂で校旗(応援団の黄色い小旗)を掲げるぞ!」と決意して臨んだ(苦笑)。
7月30日~8月7日の日程で、ヨーロッパ・アルプス最高峰のモンブラン(4810m)にアタック、無事登頂することが出来た。これは某アルパインツアーの企画で決行したが、50歳を期にチャレンジをと思っていた自分のハートにマッチしたためであった。直前まで、灼熱の横浜スタジアムで勤務校の高校野球の応援に全精力を使っていたのだが、残念ながら決勝で敗れ、あまりの悔しさに「絶対、モンブランの山頂で校旗(応援団の黄色い小旗)を掲げるぞ!」と決意して臨んだ(苦笑)。さて、往復のフライト3日間(成田からオランダ・アムステルダム空港経由でスイス・ジュネーブ空港。フランス・シャモニーへは車で移動)を除く6日間の内訳は、次の通り。
 (1)足馴らし&高所順応2日
(1)足馴らし&高所順応2日メールドグラス氷河をたどって、グランドジョラスの麓であるクーベルクル小屋(2687m)までの往復。アイゼン歩行と小屋泊まりで高所への順応をはかった。1日の行程は約3~4時間で、本や写真でしか知らなかったグランドジョラスを目の当たりにして感激!初のヨーロッパ・アルプスの洗礼を受けた。
(2)モンブラン登山3日
初日は、シャモニーからバスや登山電車を乗り継いで、テートルース小屋(3167m)まで、約3時間。
2日目は、雪と岩の岩稜帯をグーテ小屋(3782m)まで、約3時間。
3日目は、早朝2時半に出発。約5時間かけてモンブラン山頂へ。朝陽の中で念願の校旗を掲げて記念撮影をする。下りはグーテ小屋まで2時間、更に登山電車の駅ニーデーグル(2386m)まで2時間で下山。その後シャモニーへ下山。
(3)最終日は、シャモニ・フリー。
同行のメンバーで祝杯をあげたり、お土産を買ったりする。また、ガイヤンの岩場など近隣を散策。
 同行のメンバーは5名で、全員登頂ができたことは大変喜ばしいことであった。年齢的には予想外にシルバー隊となり、最高齢は68歳、以下67、62(女性)、55、50(僕)ということで、最年少としては「登らねば!」と若干のプレッシャーも感じた次第。しかし、最高齢の方はマッターホルンを登っていたり、その他の方もキリマンジャロやカラパタールなど、けっこう精力的に海外の山へチャレンジされており、なかなかやるのおという感じであった。ガイドは全て現地ガイドで、日本からの添乗ガイドは一切なし。これは、グーテ小屋など山小屋が全て予約制で、大人数のパーテイーを嫌うための苦肉の策でもあるらしい。主任ガイドは50代のパトリックで、2日間の足馴らしを経て、本番では高齢者2人に個人ガイドを配当し、僕ともう一人はペアでやはりベテランのガイド・アルブと共に登頂した。最高齢の方は、パトリック自らがマンツーマンで山頂へ導いた。
同行のメンバーは5名で、全員登頂ができたことは大変喜ばしいことであった。年齢的には予想外にシルバー隊となり、最高齢は68歳、以下67、62(女性)、55、50(僕)ということで、最年少としては「登らねば!」と若干のプレッシャーも感じた次第。しかし、最高齢の方はマッターホルンを登っていたり、その他の方もキリマンジャロやカラパタールなど、けっこう精力的に海外の山へチャレンジされており、なかなかやるのおという感じであった。ガイドは全て現地ガイドで、日本からの添乗ガイドは一切なし。これは、グーテ小屋など山小屋が全て予約制で、大人数のパーテイーを嫌うための苦肉の策でもあるらしい。主任ガイドは50代のパトリックで、2日間の足馴らしを経て、本番では高齢者2人に個人ガイドを配当し、僕ともう一人はペアでやはりベテランのガイド・アルブと共に登頂した。最高齢の方は、パトリック自らがマンツーマンで山頂へ導いた。 こうした比較的余裕のある日程であれば高所順応もほぼ問題が無く、一定度の雪山経験を積んでいればモンブラン登頂はそう困難ではないと感じた。しかし、問題は天気である。我々も、グーテ小屋に上がる朝には雪が舞っており、回復を待って11時過ぎに出発したし、下山後は2日間の雨で、ちょうどナイス・タイミングで登頂できたことは真にラッキーであったと言う他はない。今後、チャレンジなさる方は、この天気に最大の注意を払って頂きたいと思う。
こうした比較的余裕のある日程であれば高所順応もほぼ問題が無く、一定度の雪山経験を積んでいればモンブラン登頂はそう困難ではないと感じた。しかし、問題は天気である。我々も、グーテ小屋に上がる朝には雪が舞っており、回復を待って11時過ぎに出発したし、下山後は2日間の雨で、ちょうどナイス・タイミングで登頂できたことは真にラッキーであったと言う他はない。今後、チャレンジなさる方は、この天気に最大の注意を払って頂きたいと思う。 更に装備について少しふれると、ピッケルは勿論必要だがストックの方が有用であることや、登山靴は所謂「ガイド靴」と呼ばれているスポルテイバ製のネパール・エボ(日本でもICIやネット通販菊信屋でゲットできる)などが極めて有用である。この靴は、ガイドの約8割が愛用しており、これを履いているとガイド受けが良い。「おまえ、分かってるじゃないか!」という感じである。実際、ウェアや装備を見ていると、アウターからフリース、サロペットなど本場ミレーを始め現地の人間の方が先端を行ってる感じがする。プラブーツはあまり適さない。僕は日本の雪山ではアゾロやコフラックのプラブーツ・オンリーだったが、今回のことで頭を切り換えたいと思うくらいだった。勿論、アイゼンは10本爪以上でビンデイング式でもOKである。ヘルメットはグーテ小屋までの岩稜帯でのみ使用する。何故なら、ここには大クーロワールという岩溝帯があり、雪がついていない時や雪解け時には落石の巣だからである。
更に装備について少しふれると、ピッケルは勿論必要だがストックの方が有用であることや、登山靴は所謂「ガイド靴」と呼ばれているスポルテイバ製のネパール・エボ(日本でもICIやネット通販菊信屋でゲットできる)などが極めて有用である。この靴は、ガイドの約8割が愛用しており、これを履いているとガイド受けが良い。「おまえ、分かってるじゃないか!」という感じである。実際、ウェアや装備を見ていると、アウターからフリース、サロペットなど本場ミレーを始め現地の人間の方が先端を行ってる感じがする。プラブーツはあまり適さない。僕は日本の雪山ではアゾロやコフラックのプラブーツ・オンリーだったが、今回のことで頭を切り換えたいと思うくらいだった。勿論、アイゼンは10本爪以上でビンデイング式でもOKである。ヘルメットはグーテ小屋までの岩稜帯でのみ使用する。何故なら、ここには大クーロワールという岩溝帯があり、雪がついていない時や雪解け時には落石の巣だからである。以上のようなことで、最初のチャレンジでビギナーズ・ラック的に登頂してしまった感もあるが、余裕のある日程と都合3泊の小屋泊まりで順応したことが登頂の重要なキーであるとの実感は、自分の中で確かなものとして残っている。また、事前の準備としてGWの白馬縦走や6月の富士山8合目ビバークなども、一応自分の中では登頂につながるものであったと思いたい。
 というわけで偉そうに書いてしまったが、さすがにヨーロッパ・アルプスは経費が嵩み、約54くらいである。シャモニーでのホテルを一人部屋にしたのでプラス3!先の個人ガイドを頼んだ人はプラス10!であったという。それでも、ヨーロッパ・アルプスの「てっぺん」に立つということは、やはり個人的には素晴らしいことだと思えた。そうそう、シャモニーのホテルで最初の朝に、窓からモンブランがくっきりと見えていた、あの瞬間は忘れることが出来ない。
というわけで偉そうに書いてしまったが、さすがにヨーロッパ・アルプスは経費が嵩み、約54くらいである。シャモニーでのホテルを一人部屋にしたのでプラス3!先の個人ガイドを頼んだ人はプラス10!であったという。それでも、ヨーロッパ・アルプスの「てっぺん」に立つということは、やはり個人的には素晴らしいことだと思えた。そうそう、シャモニーのホテルで最初の朝に、窓からモンブランがくっきりと見えていた、あの瞬間は忘れることが出来ない。最後に、これだけは忠告!くれぐれも、海外の空港で大ザックを待合いのイスに放置しないこと。アムステルダム空港でこれをやり、席を離れてほんの少し買い物をして戻ったらドロンというのが今回最後の「落ち」であった。中には、カメラ道具一式と登山靴、シャモニーで買った土産、校旗などが入っており、さすがにガックリときた。しかし、画像はすべてPCに移したので問題はなかったが。(これらは、現在、保険の請求をしている最中)
 というわけで(なかなか終われないが)、某「お気軽登山隊」のキャンプに参加できそうにないので、ちょっとここで酒の肴的に報告をさせて頂いた次第。えらそうに書いてすいまっしぇん!(映画「植村直己物語」の西田敏行風に)
というわけで(なかなか終われないが)、某「お気軽登山隊」のキャンプに参加できそうにないので、ちょっとここで酒の肴的に報告をさせて頂いた次第。えらそうに書いてすいまっしぇん!(映画「植村直己物語」の西田敏行風に)2010年08月07日
男体山登拝祭 2010.7/31~8/1
男体山登拝祭
2010年7月31日~8月1日 栃木県 日光男体山 記録者 やませみ
登拝祭は、1200年の以上の歴史をもつ、奥日光の霊場と言われる二荒山神社中宮祠の最大の祭りで、男体山の神様を称えまつり諸願成就を祈願する祭典です。 毎年8月1日の午前0時に同神社の登拝門が開けられ7日までの期間中は夜間の男体山登山が解禁となり、山頂で御来光を仰ぐことができます。
 今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。
今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。
7月31日(土) 二荒山神社中宮祠に11時20分に到着。 いつもは社務所で受付けを済ませるのだが、今日はお祭りどうやら勝手が違うみたいだ、入口近くに特設のテントが、ここで登拝料1000円(えっ、通常は500円なのに・・・)を奉納、「御守り」と「登拝之証」をいただき境内へ。溢れんばかりの人混み。初めての夜間登山に一同、自然とテンションが上がる。
 8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。
8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。
登拝者は50~60人ほどの集団に分けられ神主さんの御祓いを受け順次、標高2486mの山頂奥に宮を目指す。しばらくして我々の順番、漆黒の山道へと歩き出す。
山道にはもちろん外灯などなく、真っ暗な道をヘッドランプの明かりを頼りに進む。
だが、しばらく山道を進むとそこは大渋滞。普段なら数分で歩ける道も、人また人で進みようがない。
日頃の運動不足がたたっているのか、息も絶え絶えの登拝者がちらほら。
先ほどまでの厳粛なムードも一掃。山中は一年に一度のお祭りに賑わいを見せ始める。
しばらくして人の波も動き始め、ようやく3合目に時計は既に1時25分をまわっていた。ここからアスファルトの林道を歩くことに。道幅が広がったためか先程までの渋滞に痺れをきらした登拝者が一揆に抜き去って行く。4合目に着く。そこにはいくつもの売店があり飲み物や豚汁を買い求める人たちで賑わっていた。美味しそうな食べ物の香りに誘われついつい覗いてしまう。が、見るだけで何も買わない。
この場所には自衛隊の救護班の方々が待機していた。臨時の仮設トイレも設置してあり女性陣は大助かりである。
一息いれて、石造の鳥居をくぐる。ここから道は少しずつ険しさを増してくる。
がしかし、ここも人・人・人で大渋滞。 暗闇の山道にヘッドランプの明かりが延々と何処までも続いているのが見える。ふと空を見上げれば満天の星空。「こんな綺麗な星をみるの久しぶりだなぁ~」と思いながら滑りやすい山道を慎重に登る。いや、立ち止まっている。
7合目を過ぎ、徐々に気温が下がってくるのが分かる。夜明けが近いのか空が少しずつ白み始めてきた。
 「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。
「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。
ほどなくして夜明けを迎える。なんとまだ7.5合目にいる。なんてことだ・・・
ようやく8合目。前を見ると先を行く3人組が視界から消える。ずいぶんと離されてしまった様だ。東の空をよくみると霧に霞む岩陰にぼんやりとした太陽がすでに昇っていた。
この辺りから女性陣2名のペースが極端に遅くなる。きけば久々の山歩きらしく足が思うように上がらないみたいだ。ひとりの女性がよほど辛かったのか、
「私、ここで待ってる・・・」と言い出す始末。
おいおい、「あとすこしだから頑張ろうよ・・・」
「せっかくここまで登ったんだから・・・」
「山頂まで行こうよ・・・」と宥める私。
その後9合目を過ぎて傾斜は緩やかに、岩場から徐々に崩れやすい砂地状の道に変わってくる。
バテバテ気味の彼女。しばらくの間ペースを合わせ一緒に歩いていたが、気を使わせてしまったのかどうかは解からないが「先に行って・・・」の一言が。(もしかして、もう限界か・・・?)
そこから私は滑りやすい斜面を最後の力を振り絞り、よろけながらも山頂に。
先頭の3人が鳥居の横で私らが登ってくるのを待っていてくれた。先に5人で奥の宮に参拝を済ませ彼女が来るのを待つ。遅れること10分全員が揃い5時40分頂上にようやく辿り着く。「あぁ、疲れた~・・・」
 残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」
残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」
大剣でそれぞれに記念撮影を済ませ、空いてる場所に100均で買ったシートを広げ遅い?朝食にする。
くる途中バナナしか口にしていなかったのでお腹ぺこぺこであった。
おにぎり2個とカップラーメンをぺろりと平らげ残っていたバナナをまた頬張る。冷えた体が徐々に温まりだすのが良くわかる。お腹も満たされじっとして居ると猛烈な睡魔が襲ってくる。
登った山は下りなければならない。当たり前のことだが、意外と忘れなれがちなのが登山は下りの方がきつ いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。
いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。
途中、あの有名な1000回おじさんこと、「田名網忠吉」さんとお会いできメンバー全員が快く握手をしていただく。とても85歳とは思えない握力の強さに一同、驚きであった。
たしかこの日が1175回?目の登頂だったと思う・・・
強烈な下り坂は徐々に我々の足、膝を壊し始める。先を行く彼女が「膝がいた~い!」と言う。
歩くたびにどんどん痛くなってくる。それでも下らなければ帰れない。それが登山なのだ。
「あとどくらいですか・・・?」
ん~「あとすこしかなぁ・・・」
「あとすこしって・・・?」
「だからあともうすこし・・・」
「いま何合目あたりですか・・・?」
「3合目あたりかなぁ・・・」
「ほんとは何合目なの・・・?」
「だから、3合目・・・」 (ほんとうは、まだ6合目あたりであった。(笑))
そんな会話をし、互いを励まし合いながらやっとの想いで登拝門をくぐり抜け、無事下山となった。
時計はあと数分で11時ちょうどになろうとしていた。
帰路、疲れた体を「奥日光湯本温泉」の源泉にゆっくりと浸かり前日来の汗と汚れを洗い流し今回の夜通し2日間に及ぶ山遊びも終わりとなった。「ああ~。ほんまにづがれだ~!」
2010年7月31日~8月1日 栃木県 日光男体山 記録者 やませみ
登拝祭は、1200年の以上の歴史をもつ、奥日光の霊場と言われる二荒山神社中宮祠の最大の祭りで、男体山の神様を称えまつり諸願成就を祈願する祭典です。 毎年8月1日の午前0時に同神社の登拝門が開けられ7日までの期間中は夜間の男体山登山が解禁となり、山頂で御来光を仰ぐことができます。
 今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。
今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。 7月31日(土) 二荒山神社中宮祠に11時20分に到着。 いつもは社務所で受付けを済ませるのだが、今日はお祭りどうやら勝手が違うみたいだ、入口近くに特設のテントが、ここで登拝料1000円(えっ、通常は500円なのに・・・)を奉納、「御守り」と「登拝之証」をいただき境内へ。溢れんばかりの人混み。初めての夜間登山に一同、自然とテンションが上がる。
 8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。
8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。登拝者は50~60人ほどの集団に分けられ神主さんの御祓いを受け順次、標高2486mの山頂奥に宮を目指す。しばらくして我々の順番、漆黒の山道へと歩き出す。
山道にはもちろん外灯などなく、真っ暗な道をヘッドランプの明かりを頼りに進む。
だが、しばらく山道を進むとそこは大渋滞。普段なら数分で歩ける道も、人また人で進みようがない。
日頃の運動不足がたたっているのか、息も絶え絶えの登拝者がちらほら。
先ほどまでの厳粛なムードも一掃。山中は一年に一度のお祭りに賑わいを見せ始める。
しばらくして人の波も動き始め、ようやく3合目に時計は既に1時25分をまわっていた。ここからアスファルトの林道を歩くことに。道幅が広がったためか先程までの渋滞に痺れをきらした登拝者が一揆に抜き去って行く。4合目に着く。そこにはいくつもの売店があり飲み物や豚汁を買い求める人たちで賑わっていた。美味しそうな食べ物の香りに誘われついつい覗いてしまう。が、見るだけで何も買わない。
この場所には自衛隊の救護班の方々が待機していた。臨時の仮設トイレも設置してあり女性陣は大助かりである。
一息いれて、石造の鳥居をくぐる。ここから道は少しずつ険しさを増してくる。
がしかし、ここも人・人・人で大渋滞。 暗闇の山道にヘッドランプの明かりが延々と何処までも続いているのが見える。ふと空を見上げれば満天の星空。「こんな綺麗な星をみるの久しぶりだなぁ~」と思いながら滑りやすい山道を慎重に登る。いや、立ち止まっている。
7合目を過ぎ、徐々に気温が下がってくるのが分かる。夜明けが近いのか空が少しずつ白み始めてきた。
 「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。
「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。ほどなくして夜明けを迎える。なんとまだ7.5合目にいる。なんてことだ・・・
ようやく8合目。前を見ると先を行く3人組が視界から消える。ずいぶんと離されてしまった様だ。東の空をよくみると霧に霞む岩陰にぼんやりとした太陽がすでに昇っていた。
この辺りから女性陣2名のペースが極端に遅くなる。きけば久々の山歩きらしく足が思うように上がらないみたいだ。ひとりの女性がよほど辛かったのか、
「私、ここで待ってる・・・」と言い出す始末。
おいおい、「あとすこしだから頑張ろうよ・・・」
「せっかくここまで登ったんだから・・・」
「山頂まで行こうよ・・・」と宥める私。
その後9合目を過ぎて傾斜は緩やかに、岩場から徐々に崩れやすい砂地状の道に変わってくる。
バテバテ気味の彼女。しばらくの間ペースを合わせ一緒に歩いていたが、気を使わせてしまったのかどうかは解からないが「先に行って・・・」の一言が。(もしかして、もう限界か・・・?)
そこから私は滑りやすい斜面を最後の力を振り絞り、よろけながらも山頂に。
先頭の3人が鳥居の横で私らが登ってくるのを待っていてくれた。先に5人で奥の宮に参拝を済ませ彼女が来るのを待つ。遅れること10分全員が揃い5時40分頂上にようやく辿り着く。「あぁ、疲れた~・・・」
 残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」
残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」大剣でそれぞれに記念撮影を済ませ、空いてる場所に100均で買ったシートを広げ遅い?朝食にする。
くる途中バナナしか口にしていなかったのでお腹ぺこぺこであった。
おにぎり2個とカップラーメンをぺろりと平らげ残っていたバナナをまた頬張る。冷えた体が徐々に温まりだすのが良くわかる。お腹も満たされじっとして居ると猛烈な睡魔が襲ってくる。
登った山は下りなければならない。当たり前のことだが、意外と忘れなれがちなのが登山は下りの方がきつ
 いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。
いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。途中、あの有名な1000回おじさんこと、「田名網忠吉」さんとお会いできメンバー全員が快く握手をしていただく。とても85歳とは思えない握力の強さに一同、驚きであった。
たしかこの日が1175回?目の登頂だったと思う・・・
強烈な下り坂は徐々に我々の足、膝を壊し始める。先を行く彼女が「膝がいた~い!」と言う。
歩くたびにどんどん痛くなってくる。それでも下らなければ帰れない。それが登山なのだ。
「あとどくらいですか・・・?」
ん~「あとすこしかなぁ・・・」
「あとすこしって・・・?」
「だからあともうすこし・・・」
「いま何合目あたりですか・・・?」
「3合目あたりかなぁ・・・」
「ほんとは何合目なの・・・?」
「だから、3合目・・・」 (ほんとうは、まだ6合目あたりであった。(笑))
そんな会話をし、互いを励まし合いながらやっとの想いで登拝門をくぐり抜け、無事下山となった。
時計はあと数分で11時ちょうどになろうとしていた。
帰路、疲れた体を「奥日光湯本温泉」の源泉にゆっくりと浸かり前日来の汗と汚れを洗い流し今回の夜通し2日間に及ぶ山遊びも終わりとなった。「ああ~。ほんまにづがれだ~!」
タグ :栃木
2010年08月01日
尾瀬・2
これが最後か・・,燧ヶ岳
7月24日(土)4
登山口発10:40。木道が終わると大岩混じりの沢状の歩きにくい道となる。しばらくは前方に見えていた3人の姿も遠のいて1人遅れとなる。減量を怠って昨年より3kg以上増えている分だけ体が重く、筋力,持久力が確実に落ちているのを如実に感じながらの登高で、大岩の道が終わって再び木道になるまでの50分間はきつかった。
登山口で休んでいた時、野鳥の声を楽しんでいた軽装の男女の2人連れに『広沢田代まで行ってみようと思うんですが、どれくらいかかりますか?』と聞かれた。『私は荷が重くて遅いので参考にはならないと思いますが、お2人の格好なら地図にある通り1時間程度じゃないでしょうか』と答えると、『別の隊が見晴を4時に出て燧ヶ岳に登っているので出会う所まで行ってみようかと・・』と言って10分ほど先に発って行った。前方にその2人連れの姿が見え、追いついたと思ったのに再び離されてまた1人になる。
ようやく広沢田代の広がりを目の当たりにした時、ベンチで休んでいたのは先の2人連れのみで@ki等3人の姿はなかった。11:46,休まずベンチ脇を通過して先行する3人を追うもすでに次の登りに入ったらしく湿原にその姿はなかった。次の熊沢田代へは目の前にある大きな塊を超えねばならない。
12:00,その登りに差しかかる辺りで10分休んで歩き出そうとした時、上方から大きな集団が賑やかに降りて来て5分あまり待たされる。5分を10分以上に感じさせる悠長さとハラハラさせられるおぼつかない足取りは高年のグループの下りゆえ致し方ないが、出鼻を挫かれて少々焦る。
12:15発。地図通りに広沢田代から50分で熊沢田代まで登るのは無理があり、1986mのピークを超えて湿原の入り口に辿り着くまでに40分あまり,標識のあるベンチまでは55分を要した。広沢のベンチからは70分かかったことになる。
13:10熊沢田代着。そこに@ki嬢が伝令役で残り、絶好調のsarusippoさんには先に頂上まで行ってもらい、新人のmanaさんをuttiさんがリードして今しがた出たところだと言う。彼等は20分前にそこに着いていたそうなので遅かったのは自分1人と言うことのようだ。
13:20発,ワタスゲの坂道を先行するuttiさんと@kiさんの姿がカッコよく、また振り返ると湿原の中の目玉のような池塘が美しい。
すでにバテかけていたので追うのをやめてペースダウンし、山頂付近でのビバーグを考え始めていた時、思いがけず水場に遭遇。天佑とばかり小躍りして3ℓの水を補給する。
14:30,雪渓のある沢を直上,20分かかって沢を抜けると下から見えていた裸地に差しかかり15:00丁度にそこを通過。
さらに40分かかって予定より大幅遅れ(1時間15分)の15:35,俎嵓に到達。柴安嵓登頂は16:07となる。先に着いていたsarusippoさんには随分待たせてしまった。
山頂で記念撮影の後、その後の行動をビバークを含めて検討し下山を決める。見晴着は早くて19時,遅ければ20時か・・。
16:15下山開始。柴安嵓からは急峻と言うほどではないがかなりの勾配を一気に下り、40分ほどで沢筋に到達する。沢筋とは言っても上から見るとそこはまだかなり高い位置にあり、斜度を落としつつ見晴まで延々と樹林帯をの道が続いているのがわかる。ここからが長いのだ。
時刻16:57。後続を待ってmanaさんの表情を伺い、意志を確認してビバークしないことを決める。以後もsappoさんが先行し、manaさんを@kiさん,uttiさんがリードすると言うパターンで自分はsappoさんを追ったが身軽な彼女には追いつけず、切り替えて要所要所で後ろを待ちながらゆっくり歩く。
17:19,石車に乗って激しく転倒したついでに座り込んで休憩。丁度そこに『見晴まで3km』の標識があるのを見る。同24,後ろで話し声と足音が聞こえたので出発。
そこから歩けども歩けども『見晴へ2km』の標識に行き着かず、30分あまり歩いてへたり込む。18:00右手前方に2度目の雷鳴を聞く。まだ遠いがパラパラッと雨が落ち始める。
さらに30分歩いても2kmの標識はなく、後ろとの距離が気になって18:27から大きな木の下で待つ。この間に雨粒が大きくなり雷鳴も近くなってきたのでザックカバーをつけ、雨具を着てヘッドランプを点ける。
待つこと40分あまり,さすがに心配になり、荷を置いて迎えに行こうかと思い始めた時,樹間にランプの光が見えホッとする。先方も同じ思いだったようだ。一度近づいた雷鳴はいつしか遠のき、雨も幾分小降りになる。
19:10,後続を吸収して歩き始めたすぐ先に『見晴へ2km』のポスト。『ええッ』『あんなに歩いたのにぃ~』の声が上がる。
この残り2kmの標識は明らかにおかしい。その証拠にものの15分ほどで尾瀬沼と見晴を結ぶ木道に出てそこには『見晴へ0.6km』とあり、さらに20分でキャンプ場に着いたのだ。標識通りなら『残り3km』から『残り2km』の1kmを70分で歩き、最後の2kmを35分で歩いたことになる。
まっすぐキャンプ場に向かい、テン場を確保。先に着いたsappoさんが受付を済ませてくれており、遅くなったので夕食はつくらず行動食で済ませることとし、希望者は小屋泊まり可とする。
sappoさんが小屋泊を希望し、他はテント泊となるり早々に就寝。直後に激しい雷雨となったらしいが白河夜船で明け方までぐっすり眠る。
かくのごとく今年も雷雨に見舞われたが、一昨年の稜線での激しい雷雨と目の前の岩への落雷,風速?十mの強風に比べれば今年の雷は赤ん坊クラスだ・・。
続く
7月24日(土)4
登山口発10:40。木道が終わると大岩混じりの沢状の歩きにくい道となる。しばらくは前方に見えていた3人の姿も遠のいて1人遅れとなる。減量を怠って昨年より3kg以上増えている分だけ体が重く、筋力,持久力が確実に落ちているのを如実に感じながらの登高で、大岩の道が終わって再び木道になるまでの50分間はきつかった。
登山口で休んでいた時、野鳥の声を楽しんでいた軽装の男女の2人連れに『広沢田代まで行ってみようと思うんですが、どれくらいかかりますか?』と聞かれた。『私は荷が重くて遅いので参考にはならないと思いますが、お2人の格好なら地図にある通り1時間程度じゃないでしょうか』と答えると、『別の隊が見晴を4時に出て燧ヶ岳に登っているので出会う所まで行ってみようかと・・』と言って10分ほど先に発って行った。前方にその2人連れの姿が見え、追いついたと思ったのに再び離されてまた1人になる。
ようやく広沢田代の広がりを目の当たりにした時、ベンチで休んでいたのは先の2人連れのみで@ki等3人の姿はなかった。11:46,休まずベンチ脇を通過して先行する3人を追うもすでに次の登りに入ったらしく湿原にその姿はなかった。次の熊沢田代へは目の前にある大きな塊を超えねばならない。
12:00,その登りに差しかかる辺りで10分休んで歩き出そうとした時、上方から大きな集団が賑やかに降りて来て5分あまり待たされる。5分を10分以上に感じさせる悠長さとハラハラさせられるおぼつかない足取りは高年のグループの下りゆえ致し方ないが、出鼻を挫かれて少々焦る。
12:15発。地図通りに広沢田代から50分で熊沢田代まで登るのは無理があり、1986mのピークを超えて湿原の入り口に辿り着くまでに40分あまり,標識のあるベンチまでは55分を要した。広沢のベンチからは70分かかったことになる。
13:10熊沢田代着。そこに@ki嬢が伝令役で残り、絶好調のsarusippoさんには先に頂上まで行ってもらい、新人のmanaさんをuttiさんがリードして今しがた出たところだと言う。彼等は20分前にそこに着いていたそうなので遅かったのは自分1人と言うことのようだ。
13:20発,ワタスゲの坂道を先行するuttiさんと@kiさんの姿がカッコよく、また振り返ると湿原の中の目玉のような池塘が美しい。
すでにバテかけていたので追うのをやめてペースダウンし、山頂付近でのビバーグを考え始めていた時、思いがけず水場に遭遇。天佑とばかり小躍りして3ℓの水を補給する。
14:30,雪渓のある沢を直上,20分かかって沢を抜けると下から見えていた裸地に差しかかり15:00丁度にそこを通過。
さらに40分かかって予定より大幅遅れ(1時間15分)の15:35,俎嵓に到達。柴安嵓登頂は16:07となる。先に着いていたsarusippoさんには随分待たせてしまった。
山頂で記念撮影の後、その後の行動をビバークを含めて検討し下山を決める。見晴着は早くて19時,遅ければ20時か・・。
16:15下山開始。柴安嵓からは急峻と言うほどではないがかなりの勾配を一気に下り、40分ほどで沢筋に到達する。沢筋とは言っても上から見るとそこはまだかなり高い位置にあり、斜度を落としつつ見晴まで延々と樹林帯をの道が続いているのがわかる。ここからが長いのだ。
時刻16:57。後続を待ってmanaさんの表情を伺い、意志を確認してビバークしないことを決める。以後もsappoさんが先行し、manaさんを@kiさん,uttiさんがリードすると言うパターンで自分はsappoさんを追ったが身軽な彼女には追いつけず、切り替えて要所要所で後ろを待ちながらゆっくり歩く。
17:19,石車に乗って激しく転倒したついでに座り込んで休憩。丁度そこに『見晴まで3km』の標識があるのを見る。同24,後ろで話し声と足音が聞こえたので出発。
そこから歩けども歩けども『見晴へ2km』の標識に行き着かず、30分あまり歩いてへたり込む。18:00右手前方に2度目の雷鳴を聞く。まだ遠いがパラパラッと雨が落ち始める。
さらに30分歩いても2kmの標識はなく、後ろとの距離が気になって18:27から大きな木の下で待つ。この間に雨粒が大きくなり雷鳴も近くなってきたのでザックカバーをつけ、雨具を着てヘッドランプを点ける。
待つこと40分あまり,さすがに心配になり、荷を置いて迎えに行こうかと思い始めた時,樹間にランプの光が見えホッとする。先方も同じ思いだったようだ。一度近づいた雷鳴はいつしか遠のき、雨も幾分小降りになる。
19:10,後続を吸収して歩き始めたすぐ先に『見晴へ2km』のポスト。『ええッ』『あんなに歩いたのにぃ~』の声が上がる。
この残り2kmの標識は明らかにおかしい。その証拠にものの15分ほどで尾瀬沼と見晴を結ぶ木道に出てそこには『見晴へ0.6km』とあり、さらに20分でキャンプ場に着いたのだ。標識通りなら『残り3km』から『残り2km』の1kmを70分で歩き、最後の2kmを35分で歩いたことになる。
まっすぐキャンプ場に向かい、テン場を確保。先に着いたsappoさんが受付を済ませてくれており、遅くなったので夕食はつくらず行動食で済ませることとし、希望者は小屋泊まり可とする。
sappoさんが小屋泊を希望し、他はテント泊となるり早々に就寝。直後に激しい雷雨となったらしいが白河夜船で明け方までぐっすり眠る。
かくのごとく今年も雷雨に見舞われたが、一昨年の稜線での激しい雷雨と目の前の岩への落雷,風速?十mの強風に比べれば今年の雷は赤ん坊クラスだ・・。
続く
2010年08月01日
尾瀬・1
いつも通りの尾瀬入り
7月23日(金)
浦佐駅発13:40のバスで奥只見ダム,ダムから船で尾瀬口,尾瀬口からはバス・・,と乗り継いで16:25に小沢(こぞう)平着。準備を整えて16:33小沢平発,渋沢(しぼっつぁ)温泉小屋に向かう。
初日の歩きは温泉小屋までの1時間あまりのみで、見事なブナ林の中をゆっくり歩いて18:04温泉小屋に着く。
渋沢温泉小屋は馴染みの宿で、山小屋嫌いの自分が泊まる殆ど唯一の山小屋と言える。小屋の主は若い人に代替わりして先代には会えなかったが、翌朝の早発ちに向けて5時半からの朝食をと言う要望を快諾してもらえた。
入浴後の夕食では心づくしの山菜料理を前に新しい出会いに乾杯し、翌日からの健闘を誓い合う。9時消灯。長旅の疲れで一同たちまち深い眠りに落ちた様子。
昨年剣岳を一緒に縦走した@ki嬢が『今年は尾瀬にでも行こうか』との提案に乗ってトントン拍子に話しが進み、広島在住の山のサイトで参加を呼びかけたところ3名の参加があって燧ヶ岳~尾瀬ヶ原~至仏山を幕営・縦走するパーティーが編成された。
広島隊は22日20:10発の夜行バス~上越新幹線を乗り継いで、長野(木偶)からは車と新幹線で浦佐駅に集結。募集の参加者3名と木偶とは初対面。
裏燧林道
7月24日(土)
4時に起きて地下足袋で本流まで行き竿を出す。目印を忘れて糸のたるみが見えず、根がかりして仕掛けを切る。錘をつけようとしたが暗くて小さなガン玉がうまくつけられず、錘なしで餌の川虫を流れに乗せて送り込むもアタリなく、30分ほどで時間切れとなる。
渋沢温泉小屋は代変りして若い人が主となっていたが、早朝の出発に合わせて5:30に朝食を~と言う要望に快く応えてくれ、予定通り,6:27に小屋を発つ。
渋沢温泉親から天神田代へは小屋の前を通り抜けて露天風呂のある河原を上流に向かい、沢を渡って対岸の崖にかけられた階段を上がってから急登の登山道となる。先週白山に登ったのがいい足慣らしになって調子がよい~と言う話をしたらすぐ後ろにいたsarusippoさんも先週白山に登ってきたと言い、偶然の符合に驚く。
白山より西に白山より高い山はないと言うことを知ったばかりだが、燧ケ岳より北にも燧ケ岳より高い山はなく、図らずも1週間を経て東西両端の高峰に登ることになったのだが、それが偶然同じパーティーで2人揃ったと言うのも奇縁であろうか。
sarusippoさんはおそろしく元気がよく、また小柄ながら動きがシャープでフットワークが軽く、最初の休憩後『先に行って好きなように歩湿原を楽しんで下さい』とトップを代わってもらったらたちまち見えなくなってしまい、以後、常に彼女が先導する形となる。
途中で10分弱の休憩を挟んで8:28天神田代着。sarusippoさんは飛んで行ったらしく姿なし。少し長めに休んで行動食を摂り8:50出発。ここからは新人のmanaさんを@kiさんとuttiさんにリードしてもらい、ボッカに専念してラストを行く。珍しく裏燧林道を行き交う人が多い。
しばらく樹林帯が続き、30分ほどで目の前が開けて湿原が広がる。9:20御池へ2.0kmのポスト通過,同:24ヌメリ田代,キンコウカの黄,コバノギボウシの紫,ワタスゲの白が目立つ。
9:35上田代着。sarusippoさんにやっと追いつくも彼女は御池まで行きたいのでとすぐに発つ。ここではヒメシャクナゲやトキソウ,モウセンゴケなどの小さな植物を見る。上田代からは平ヶ岳眺望がよく、また越後駒ヶ岳方面を望むことが出来る。燧ケ岳の山頂方面も少しだけ見える。
9:50遅れて出発。10:02姫田代通過,10:14燧ケ岳登山口着。女性3人とも御池に行っている間,流れの水を補給する。朝から暑くて水の消費量が多い。
10:43登山開始。sarusippoさんが真っ先に飛び出し、次に顔を合わせたのは柴安嵓。次いで@kiさんとuttiさんがmanaさんを引っ張って先を行き、離れてnobouがしんがりと言うパターンが出来上がる。
7月23日(金)
浦佐駅発13:40のバスで奥只見ダム,ダムから船で尾瀬口,尾瀬口からはバス・・,と乗り継いで16:25に小沢(こぞう)平着。準備を整えて16:33小沢平発,渋沢(しぼっつぁ)温泉小屋に向かう。
初日の歩きは温泉小屋までの1時間あまりのみで、見事なブナ林の中をゆっくり歩いて18:04温泉小屋に着く。
渋沢温泉小屋は馴染みの宿で、山小屋嫌いの自分が泊まる殆ど唯一の山小屋と言える。小屋の主は若い人に代替わりして先代には会えなかったが、翌朝の早発ちに向けて5時半からの朝食をと言う要望を快諾してもらえた。
入浴後の夕食では心づくしの山菜料理を前に新しい出会いに乾杯し、翌日からの健闘を誓い合う。9時消灯。長旅の疲れで一同たちまち深い眠りに落ちた様子。
昨年剣岳を一緒に縦走した@ki嬢が『今年は尾瀬にでも行こうか』との提案に乗ってトントン拍子に話しが進み、広島在住の山のサイトで参加を呼びかけたところ3名の参加があって燧ヶ岳~尾瀬ヶ原~至仏山を幕営・縦走するパーティーが編成された。
広島隊は22日20:10発の夜行バス~上越新幹線を乗り継いで、長野(木偶)からは車と新幹線で浦佐駅に集結。募集の参加者3名と木偶とは初対面。
裏燧林道
7月24日(土)
4時に起きて地下足袋で本流まで行き竿を出す。目印を忘れて糸のたるみが見えず、根がかりして仕掛けを切る。錘をつけようとしたが暗くて小さなガン玉がうまくつけられず、錘なしで餌の川虫を流れに乗せて送り込むもアタリなく、30分ほどで時間切れとなる。
渋沢温泉小屋は代変りして若い人が主となっていたが、早朝の出発に合わせて5:30に朝食を~と言う要望に快く応えてくれ、予定通り,6:27に小屋を発つ。
渋沢温泉親から天神田代へは小屋の前を通り抜けて露天風呂のある河原を上流に向かい、沢を渡って対岸の崖にかけられた階段を上がってから急登の登山道となる。先週白山に登ったのがいい足慣らしになって調子がよい~と言う話をしたらすぐ後ろにいたsarusippoさんも先週白山に登ってきたと言い、偶然の符合に驚く。
白山より西に白山より高い山はないと言うことを知ったばかりだが、燧ケ岳より北にも燧ケ岳より高い山はなく、図らずも1週間を経て東西両端の高峰に登ることになったのだが、それが偶然同じパーティーで2人揃ったと言うのも奇縁であろうか。
sarusippoさんはおそろしく元気がよく、また小柄ながら動きがシャープでフットワークが軽く、最初の休憩後『先に行って好きなように歩湿原を楽しんで下さい』とトップを代わってもらったらたちまち見えなくなってしまい、以後、常に彼女が先導する形となる。
途中で10分弱の休憩を挟んで8:28天神田代着。sarusippoさんは飛んで行ったらしく姿なし。少し長めに休んで行動食を摂り8:50出発。ここからは新人のmanaさんを@kiさんとuttiさんにリードしてもらい、ボッカに専念してラストを行く。珍しく裏燧林道を行き交う人が多い。
しばらく樹林帯が続き、30分ほどで目の前が開けて湿原が広がる。9:20御池へ2.0kmのポスト通過,同:24ヌメリ田代,キンコウカの黄,コバノギボウシの紫,ワタスゲの白が目立つ。
9:35上田代着。sarusippoさんにやっと追いつくも彼女は御池まで行きたいのでとすぐに発つ。ここではヒメシャクナゲやトキソウ,モウセンゴケなどの小さな植物を見る。上田代からは平ヶ岳眺望がよく、また越後駒ヶ岳方面を望むことが出来る。燧ケ岳の山頂方面も少しだけ見える。
9:50遅れて出発。10:02姫田代通過,10:14燧ケ岳登山口着。女性3人とも御池に行っている間,流れの水を補給する。朝から暑くて水の消費量が多い。
10:43登山開始。sarusippoさんが真っ先に飛び出し、次に顔を合わせたのは柴安嵓。次いで@kiさんとuttiさんがmanaさんを引っ張って先を行き、離れてnobouがしんがりと言うパターンが出来上がる。
Posted by okirakutozan at
10:23
│Comments(0)