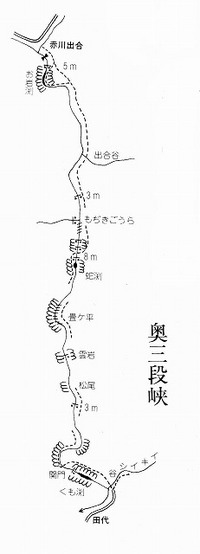2011年01月13日
戸谷峰
前週に続き、足慣らしのため戸谷峰(1929m)に登る。戸谷峰には旧四賀村の保福寺地区から登るコースとR254の三才山(みさやま)トンネル付近の野間沢から登るコースがある他、松本市の稲倉(しなくら)峠から旧四賀村との境界線に沿って縦走するコース,保福寺峠と美ヶ原スカイラインを結ぶ林道の三才トンネルの真上に当たる三才山峠から三才山(1605m),六人坊(1618m),を経て縦走するコースなどがある。
今回は登頂上後、あわよくば六人坊,三才山辺りまでのルート偵察を~,ともくろんでとりつきのいい野間沢コースから登る。
1月8日(土)
標高ほぼ1000mの野間沢橋登山口を7:48発。戸谷峰から東に延びる稜線を100m下った辺りから南に向かって派生する尾根の東斜面を沢に沿って200mほど登る。この沢を遮二無二に登れば主稜線に達することが出来そうだが急斜面の薮漕ぎになるのは必至で、そう言うことをやる馬力と気まぐれは今はない。
なのでここは送電線巡視路でもある登山道の通り右折し(8:21)、右手の1363mピークを大きく廻りこんで東隣の尾根の上に出る。そこから尾根に沿って送電線が上に伸び、次々と現れる3つの鉄塔(No7~73)を追って登る。
右手に進んで東斜面に出ると陽が当たり始め暑くなってきたのでヤッケを脱ぐ(8:47~53)。オーバーズボンも要らないのだが脱ぐのが面倒。カラマツ林の平易な尾根道を歩くこと8分で1360mの№71鉄通過(9:05)。周囲の木の密度が低くなって次第に見通しがよくなり、さらに進むこと20分弱で1450mの№72鉄塔着(9:23)。鉄塔の向こうに戸谷峰の山頂が見え、左手後方に梓川の南に位置する山々がせりあがって来た。
9:40,主稜線上のNo73鉄塔(1510m)着。振り返ると美ヶ原から伸びてくる送電線がよく見える。5分後出発。ここから疎林の主稜線を西に進んで100mほど登り、最後はロープのある急斜面を30mほど登って山頂に到達(10:13)。
雲1つない快晴,まれにみる絶景である。列挙すればキリがない遠近の山々を心行くまで目に焼きつけ堪能し、撮れる限りの写真を撮りまくって山頂を後にする。
10:43,No73鉄塔に戻って昼食を摂り、11:10,荷物を置いて六人坊に向かう。
六人坊は間近に見え、その向こうに保福寺と美ヶ原スカイラインを結ぶ林道が見えていて楽勝と思われたが、目の前の小ピークから50mくらい下がった先にもう1つのピーク(1503m)があり、そこまで行って見通すと先刻以上の下りがあってその鞍部から大きな登り(100m以上)となっているのが分かった。ここまで来て荷物を置いてきたことを悔やんだが後の祭りで、偵察はここまでとして諦めて引き返す。
帰宅して地図を見ると、1503mのピークからは70mの下りの後、120mの登り返しがあるもそこは1562mのピークで、六人坊はそこからさらに60m登っていた。
結局1時間かかって№73鉄塔に戻ることになったが、縦走路の様子があらまし分かっただけでも収穫だった。
12:11下山開始。午後になって陽射しが強くなり暑かったが休まず下って13:08下山。
今回は登頂上後、あわよくば六人坊,三才山辺りまでのルート偵察を~,ともくろんでとりつきのいい野間沢コースから登る。
1月8日(土)
標高ほぼ1000mの野間沢橋登山口を7:48発。戸谷峰から東に延びる稜線を100m下った辺りから南に向かって派生する尾根の東斜面を沢に沿って200mほど登る。この沢を遮二無二に登れば主稜線に達することが出来そうだが急斜面の薮漕ぎになるのは必至で、そう言うことをやる馬力と気まぐれは今はない。
なのでここは送電線巡視路でもある登山道の通り右折し(8:21)、右手の1363mピークを大きく廻りこんで東隣の尾根の上に出る。そこから尾根に沿って送電線が上に伸び、次々と現れる3つの鉄塔(No7~73)を追って登る。
右手に進んで東斜面に出ると陽が当たり始め暑くなってきたのでヤッケを脱ぐ(8:47~53)。オーバーズボンも要らないのだが脱ぐのが面倒。カラマツ林の平易な尾根道を歩くこと8分で1360mの№71鉄通過(9:05)。周囲の木の密度が低くなって次第に見通しがよくなり、さらに進むこと20分弱で1450mの№72鉄塔着(9:23)。鉄塔の向こうに戸谷峰の山頂が見え、左手後方に梓川の南に位置する山々がせりあがって来た。
9:40,主稜線上のNo73鉄塔(1510m)着。振り返ると美ヶ原から伸びてくる送電線がよく見える。5分後出発。ここから疎林の主稜線を西に進んで100mほど登り、最後はロープのある急斜面を30mほど登って山頂に到達(10:13)。
雲1つない快晴,まれにみる絶景である。列挙すればキリがない遠近の山々を心行くまで目に焼きつけ堪能し、撮れる限りの写真を撮りまくって山頂を後にする。
10:43,No73鉄塔に戻って昼食を摂り、11:10,荷物を置いて六人坊に向かう。
六人坊は間近に見え、その向こうに保福寺と美ヶ原スカイラインを結ぶ林道が見えていて楽勝と思われたが、目の前の小ピークから50mくらい下がった先にもう1つのピーク(1503m)があり、そこまで行って見通すと先刻以上の下りがあってその鞍部から大きな登り(100m以上)となっているのが分かった。ここまで来て荷物を置いてきたことを悔やんだが後の祭りで、偵察はここまでとして諦めて引き返す。
帰宅して地図を見ると、1503mのピークからは70mの下りの後、120mの登り返しがあるもそこは1562mのピークで、六人坊はそこからさらに60m登っていた。
結局1時間かかって№73鉄塔に戻ることになったが、縦走路の様子があらまし分かっただけでも収穫だった。
12:11下山開始。午後になって陽射しが強くなり暑かったが休まず下って13:08下山。
2011年01月13日
光城山~長峰山
1月2日(日)
今年の元日登山は茅ヶ岳を予定していたが、年末年始大荒れの予報に怖気づいて計画を中止。西日本や東北は予報通りの荒れ模様だったが、信州はいたって穏やかな年明けで臍を噛んだ。
コタツムリを決め込んで元日の駅伝を見ていたらjun1さんから電話があって『足慣らしに光城山にでも登りますか・・』となる。
と言う訳で8:00に集合し、いつもとは違う北廻りのルートを登る。北廻りルートは光城山の北隣に並ぶほぼ同じ高さの山の尾根を登るルートで、正面のルートが直登に近くてきついのに比して、斜度は変わらないが折り返しの距離が長くとってある分だけゆったりと登れる気がした。
また正面ルートには冬は白鳥型に、春は桜道に沿って電飾が施されたりして手が加えられているのに比してほとんど手が加えられていない分,うるさくなくていい感じである。
山行記録を書く時にはまず写真を取り込み、画像を見て時刻,場所,その場での出来事や状況等,得られる様々な情報を手がかりに書くのが常であり、今回も帰って早速写真をアップすべくメモリーの蓋を開けたところ、そこにあるべきものが入っておらず『ドヒャー!』となって次にガックリした次第。
コンパクトの時は2~3枚撮った時点でカメラが教えてくれるのに対して一眼にはそのような機能は無いらしく、バシャバシャとシャッターが落ちるので全く気がつかなかったノダ・・。
手がかりが無くては書きようが無いとは言わないが、ディティールまでは無理。そんな訳で同じコースを登りなおし、改めて写真を撮ったものを載せることにしたので当日の行動記録は大雑把なものになる。
また登りなおしと言えども動けばそれなりのことはあるので、併せて3日の記録も後に記す。当然ながら写真の時刻は3日午後となる。
2日8:00,光城山登山口集合。jun1さんが『今日はこっちから登って見ようか・・』と谷筋を指し、自分も正面のルートは好きでないので文句無く同意して10分後出発。
光配水地の建物を過ぎて道が2分する。正面ルートに繋がる道を見送って左折し北廻りの登山道に入ると、道は谷を隔てた北隣の山腹を650mの等高線に沿って斜上し始める。
正面ルートが尾根をほぼ真っ直ぐ登っていくのに比べ、こちらは山腹が若干広い分だけゆとりがあってジグザクの距離が長く、ゆったり登っているのと、ケヤキやコナラ,クヌギ等の樹高のある広葉樹が適度の間隔で疎生していて林床が明るく伸びやかなのが特徴であろうか・・。
登山口から山頂まで、標高差300mほどの山なので初めの急登150mを頑張れば20分で中間点標識に着く。そこからは傾斜もゆるくなって、だらだらと歩くこと15分ほどで林道に到達。林道を南に5~6分で光城山の山頂に着く。
せっかくなので光城山から長峰山まで歩こうと言うことになり、林道を北に向かう。10分ほど歩くとかつて『白牧』と言う集落があった場所に到達する。ここには建物の跡はないが、墓や石仏,道祖神等が残っている。ここ(白牧)からは光城山と長峰山の中間を西に下る林道白牧線と言う道がある。そこは未踏査なので帰りはその道を下って見ようなどと話しながら進んで40分あまりで長峰山に到着(9:50頃)。
西山は半分から上が雲の中で常念岳は望めず、10分ほど下界の景観を楽しんでもとの道を戻る。道すがら『長峰荘に下るつもりだったが(下山口が)遠いので止めた』と言う婦人と道連れになり、白牧からも同じ道を下ることになって3人で林道を下る。
林道は復員4m,上部がコンクリート,途中からはアスファルト舗装のしっかりした道で、雪が無ければ車での往来は全く問題ないことが分かった。がしかし、かなりの急勾配で、歩いて下るとつま先を傷めそうで小走りになってしまう。そして思いのほか長い。
白牧に限らず、この地域一帯は急傾斜の地滑り危険地帯であり、地滑り防止対策として『水抜き』の施設が随所に見られる。
途中に炭焼き窯や作業小屋,立ち木を利用して丸太を組んだ足場のようなものがある一画があったり、雑木を伐採して小さな広葉樹を植林した区画があったりと、飽きない程度に見所がある。
約40分で市道に出て更に10分あまり歩き、11:00に駐車場着,散会する。
付
1月3日(月) 登りなおしの記
箱根駅伝を見終わってから再度写真を撮りに出かけたので出発が遅くなってしまった。我が母校はかろうじて10位以内に逃げ込んだが、このところ振るわない。
14:15発。さくら並木への道を見送って北廻り道に入ってすぐの所に標識があったのを昨日は見落としていた。そこから上に道が1本あったのが気になったが、標識に従って真っ直ぐ進む。がしかし、昨日のことなのにその辺りの記憶が全くなく、その道がどんどん北に廻って行く気配なので引き返して標識から上に向かって見た。ひと登りすると右手に正面ルートの尾根から山頂までもがよく見える場所に到達。いい角度で山頂を写すことが出来、ふり向けば蝶ヶ岳をも見ることが出来たのはいいが、『昨日,こんな場面があったっけ・・』と?符が・・。マア、行ける所まで行ってみよう・・,と先に進むもすぐに道が途絶え、引き返す羽目になる。何と言う注意力の欠如かッ!
14:40,戻って北寄りに進むと上から男性が1人,さらに上から3人の女性が降りて来た。正面ルートから登ってこちらへ降りてくると言うパターンがあるようだ。同じ所に降りれるのが魅力なのだろう。
急斜面を20分ほど登ってようやく傾斜が緩くなる辺りに『さくら池・山頂中間点(14:57)』と言う標識があるのだが、さくら池がどこにあるのか、またこの山の山頂それなのか、光城山のそれなのか分からない。
背後の太陽が木々の長い影を登山道に落とし、それを踏んだり跨いだりしながら進む。スックと伸びた影や横たわる影,こんがらがった影もあれば踊っているような影もあって、この時間帯は自分達が『主役だ』と言わんばかりに好き勝手に、自在にふるまっている。
15:09,2つの尾根が平行して光城山がすぐ隣に見える辺り,山頂付近で光るものが見えるのを望遠で撮っている時、降りてきた3人連れが山仲間だったのに驚き、かつ思いがけない再会を喜ぶ。動けばそれなりに何がしかの収穫があることのこれが1つ目。
15:17,林道に到達し、前日同様,光城山の山頂まで行く。15:31,山頂の神社着。ちらほらと登山者があり、そのいずれもが北廻りルートに向かうのと入れ替わって、昨日は姿を見せなかったアルプス~頭だけの常念岳,雪の大天井岳,頭を隠した燕岳・有明山~を眺め、穂高の町を見下ろす。
15:27発,林道を北に向かい15:36白牧着。石仏や道祖神の写真を撮った後、15:40から林道を下る。
前日同様,小走りに下ってカーブを廻った時,突然目の前の林道にカモシカがいるのに出くわす(15:47)。距離は10mあるかなしかで、動かずこちらを見ているのをゆっくり撮ることができた。4~5枚撮ってからそろりと前進すると林道の向こうの斜面に飛び込んで行った。追いかけて覗きこむとすぐ下にいたのが一転して上に走り、林道を駆け渡って右手の斜面の先に消えた。なおも追って行くと30mも先の潅木の中でこっちを見ている。こうして束の間ながらカモシカとの時間を共有したこれが収穫の2つ目。
そこから1kmほど下ると右手に炭焼き窯や小屋のある一画があって中年の男性が作業していた(16:04)。入り込んで話しを聞くと男性はその一帯の森林の所有者で、森林の手入れをしながら炭焼きをしたり、丸太を組んでアスレチックのようなものを作ったりして森との共生を楽しんでいるとのこと。
ちょうどその辺りから山の斜面を伐採してその跡地に小さな広葉樹を植林し、目印にピンクのリボンがつけてあるのが見られたのでそのことを尋ねると、それは公有地を対象とした県と国の事業だそうで、『自分の所もやってくれないか』と聞いてみたが私有地は対象外だと言われたので、今後自分でやっていくつもりだと言うことだった。
大変な作業になると思われるが、そうやって手入れすると言う人は貴重な存在なので補助があってもよさそうなものだと思った。
16:12,炭焼き小屋を辞去。道が大きく右奥に伸びて下がり切ると奥沢と言う沢にぶつかり、ヘアピン状に折り返して高度を下げながら500m進むと今度は左手の白牧沢に行き当たる。2つの沢が合流するところにある堰堤を過ぎると人里は近い。
16:35,市道に出て左折し6分で登山口に着き終了(16:41)。
今年の元日登山は茅ヶ岳を予定していたが、年末年始大荒れの予報に怖気づいて計画を中止。西日本や東北は予報通りの荒れ模様だったが、信州はいたって穏やかな年明けで臍を噛んだ。
コタツムリを決め込んで元日の駅伝を見ていたらjun1さんから電話があって『足慣らしに光城山にでも登りますか・・』となる。
と言う訳で8:00に集合し、いつもとは違う北廻りのルートを登る。北廻りルートは光城山の北隣に並ぶほぼ同じ高さの山の尾根を登るルートで、正面のルートが直登に近くてきついのに比して、斜度は変わらないが折り返しの距離が長くとってある分だけゆったりと登れる気がした。
また正面ルートには冬は白鳥型に、春は桜道に沿って電飾が施されたりして手が加えられているのに比してほとんど手が加えられていない分,うるさくなくていい感じである。
山行記録を書く時にはまず写真を取り込み、画像を見て時刻,場所,その場での出来事や状況等,得られる様々な情報を手がかりに書くのが常であり、今回も帰って早速写真をアップすべくメモリーの蓋を開けたところ、そこにあるべきものが入っておらず『ドヒャー!』となって次にガックリした次第。
コンパクトの時は2~3枚撮った時点でカメラが教えてくれるのに対して一眼にはそのような機能は無いらしく、バシャバシャとシャッターが落ちるので全く気がつかなかったノダ・・。
手がかりが無くては書きようが無いとは言わないが、ディティールまでは無理。そんな訳で同じコースを登りなおし、改めて写真を撮ったものを載せることにしたので当日の行動記録は大雑把なものになる。
また登りなおしと言えども動けばそれなりのことはあるので、併せて3日の記録も後に記す。当然ながら写真の時刻は3日午後となる。
2日8:00,光城山登山口集合。jun1さんが『今日はこっちから登って見ようか・・』と谷筋を指し、自分も正面のルートは好きでないので文句無く同意して10分後出発。
光配水地の建物を過ぎて道が2分する。正面ルートに繋がる道を見送って左折し北廻りの登山道に入ると、道は谷を隔てた北隣の山腹を650mの等高線に沿って斜上し始める。
正面ルートが尾根をほぼ真っ直ぐ登っていくのに比べ、こちらは山腹が若干広い分だけゆとりがあってジグザクの距離が長く、ゆったり登っているのと、ケヤキやコナラ,クヌギ等の樹高のある広葉樹が適度の間隔で疎生していて林床が明るく伸びやかなのが特徴であろうか・・。
登山口から山頂まで、標高差300mほどの山なので初めの急登150mを頑張れば20分で中間点標識に着く。そこからは傾斜もゆるくなって、だらだらと歩くこと15分ほどで林道に到達。林道を南に5~6分で光城山の山頂に着く。
せっかくなので光城山から長峰山まで歩こうと言うことになり、林道を北に向かう。10分ほど歩くとかつて『白牧』と言う集落があった場所に到達する。ここには建物の跡はないが、墓や石仏,道祖神等が残っている。ここ(白牧)からは光城山と長峰山の中間を西に下る林道白牧線と言う道がある。そこは未踏査なので帰りはその道を下って見ようなどと話しながら進んで40分あまりで長峰山に到着(9:50頃)。
西山は半分から上が雲の中で常念岳は望めず、10分ほど下界の景観を楽しんでもとの道を戻る。道すがら『長峰荘に下るつもりだったが(下山口が)遠いので止めた』と言う婦人と道連れになり、白牧からも同じ道を下ることになって3人で林道を下る。
林道は復員4m,上部がコンクリート,途中からはアスファルト舗装のしっかりした道で、雪が無ければ車での往来は全く問題ないことが分かった。がしかし、かなりの急勾配で、歩いて下るとつま先を傷めそうで小走りになってしまう。そして思いのほか長い。
白牧に限らず、この地域一帯は急傾斜の地滑り危険地帯であり、地滑り防止対策として『水抜き』の施設が随所に見られる。
途中に炭焼き窯や作業小屋,立ち木を利用して丸太を組んだ足場のようなものがある一画があったり、雑木を伐採して小さな広葉樹を植林した区画があったりと、飽きない程度に見所がある。
約40分で市道に出て更に10分あまり歩き、11:00に駐車場着,散会する。
付
1月3日(月) 登りなおしの記
箱根駅伝を見終わってから再度写真を撮りに出かけたので出発が遅くなってしまった。我が母校はかろうじて10位以内に逃げ込んだが、このところ振るわない。
14:15発。さくら並木への道を見送って北廻り道に入ってすぐの所に標識があったのを昨日は見落としていた。そこから上に道が1本あったのが気になったが、標識に従って真っ直ぐ進む。がしかし、昨日のことなのにその辺りの記憶が全くなく、その道がどんどん北に廻って行く気配なので引き返して標識から上に向かって見た。ひと登りすると右手に正面ルートの尾根から山頂までもがよく見える場所に到達。いい角度で山頂を写すことが出来、ふり向けば蝶ヶ岳をも見ることが出来たのはいいが、『昨日,こんな場面があったっけ・・』と?符が・・。マア、行ける所まで行ってみよう・・,と先に進むもすぐに道が途絶え、引き返す羽目になる。何と言う注意力の欠如かッ!
14:40,戻って北寄りに進むと上から男性が1人,さらに上から3人の女性が降りて来た。正面ルートから登ってこちらへ降りてくると言うパターンがあるようだ。同じ所に降りれるのが魅力なのだろう。
急斜面を20分ほど登ってようやく傾斜が緩くなる辺りに『さくら池・山頂中間点(14:57)』と言う標識があるのだが、さくら池がどこにあるのか、またこの山の山頂それなのか、光城山のそれなのか分からない。
背後の太陽が木々の長い影を登山道に落とし、それを踏んだり跨いだりしながら進む。スックと伸びた影や横たわる影,こんがらがった影もあれば踊っているような影もあって、この時間帯は自分達が『主役だ』と言わんばかりに好き勝手に、自在にふるまっている。
15:09,2つの尾根が平行して光城山がすぐ隣に見える辺り,山頂付近で光るものが見えるのを望遠で撮っている時、降りてきた3人連れが山仲間だったのに驚き、かつ思いがけない再会を喜ぶ。動けばそれなりに何がしかの収穫があることのこれが1つ目。
15:17,林道に到達し、前日同様,光城山の山頂まで行く。15:31,山頂の神社着。ちらほらと登山者があり、そのいずれもが北廻りルートに向かうのと入れ替わって、昨日は姿を見せなかったアルプス~頭だけの常念岳,雪の大天井岳,頭を隠した燕岳・有明山~を眺め、穂高の町を見下ろす。
15:27発,林道を北に向かい15:36白牧着。石仏や道祖神の写真を撮った後、15:40から林道を下る。
前日同様,小走りに下ってカーブを廻った時,突然目の前の林道にカモシカがいるのに出くわす(15:47)。距離は10mあるかなしかで、動かずこちらを見ているのをゆっくり撮ることができた。4~5枚撮ってからそろりと前進すると林道の向こうの斜面に飛び込んで行った。追いかけて覗きこむとすぐ下にいたのが一転して上に走り、林道を駆け渡って右手の斜面の先に消えた。なおも追って行くと30mも先の潅木の中でこっちを見ている。こうして束の間ながらカモシカとの時間を共有したこれが収穫の2つ目。
そこから1kmほど下ると右手に炭焼き窯や小屋のある一画があって中年の男性が作業していた(16:04)。入り込んで話しを聞くと男性はその一帯の森林の所有者で、森林の手入れをしながら炭焼きをしたり、丸太を組んでアスレチックのようなものを作ったりして森との共生を楽しんでいるとのこと。
ちょうどその辺りから山の斜面を伐採してその跡地に小さな広葉樹を植林し、目印にピンクのリボンがつけてあるのが見られたのでそのことを尋ねると、それは公有地を対象とした県と国の事業だそうで、『自分の所もやってくれないか』と聞いてみたが私有地は対象外だと言われたので、今後自分でやっていくつもりだと言うことだった。
大変な作業になると思われるが、そうやって手入れすると言う人は貴重な存在なので補助があってもよさそうなものだと思った。
16:12,炭焼き小屋を辞去。道が大きく右奥に伸びて下がり切ると奥沢と言う沢にぶつかり、ヘアピン状に折り返して高度を下げながら500m進むと今度は左手の白牧沢に行き当たる。2つの沢が合流するところにある堰堤を過ぎると人里は近い。
16:35,市道に出て左折し6分で登山口に着き終了(16:41)。
2011年01月13日
広島・武田山連峰西部・鈴峯~鬼ヶ城山~己斐峠
幼少期,広島市と五日市町の境界に位置する鈴峯と言う320mほどの低山を真西から見る位置に暮らしていた。
そこは鈴峯が唯一左右対称の端正な姿を見せる場所で目の前に田んぼがあり、春には水が張られた田に映って上下まで対称な山を見ることが出来た。
今はその風情もなくなってしまったが、当時の風景の記憶は今も鮮明である。
腕白時代の遊び場であり、また燃料として枯葉・枯れ枝を拾い集めさせられた生活の場でもあったその山こそは自分にとっての原点の山であり、切っても切れない縁で繋がったかけがえのないふるさとの山である。
その鈴峯から広島市祇園の武田山に至る約17kmの山なみを武田山連峰と言う。かつて『佐伯冒険学校』と言う子ども達の野外活動クラブを立ち上げるに当たって、その記念登山として子ども達と歩いたのがこのコースである。
『武田山~鈴ヶ峰』の全体を武田山連峰と称することには異論があるかもしれないし、正式な名称であるかどうかも調べたこともないが、東の安佐南区祇園の安川と西の佐伯区五日市の八幡川の間に連なる450m~250mの山々をひと続きの山稜、即ち連峰と見て、その連なりの一方の起点であり400mを越える高さの『武田山』を冠することは、あながち不当なものではないと思っている。
もとより勝手に山の名称をつくることは慎まなければならないことであるが、上の見解に加えて、30年以上前の文献にそのような記述があったことに依拠して、ここでは『武田山連峰』と称することをお許し願うこととする。
呼称の問題はさておいて、同コースは途中,道路で分断されると言う問題はあるにしても、南には瀬戸の海と島々が広がり、宮島の瀬戸を隔てて西から経小屋山,のうが高原,極楽寺山,窓が山,向山と続く山々の奥に大峰山や阿弥陀山が望まれ、大広島市を俯瞰しながらゆったりと歩くことが出来ると言う、眺望に恵まれた素晴らしいコースであると言える。
30数年を経て山そのものも周辺の状況も大きく変貌したが、近年,そのコースが整備され、訪れる人が多くなっていると聞く。
是が非でも再度歩きたいと思っていたその機会が突然来た!
12月22日(水)
9:20発,鈴ヶ峰の登山口までは歩いて10分ほど。昔は山際のどこからでも登れたが、今はバリケードがあって勝手な侵入を拒んでいる。昔の記憶を辿って登山口を見つけ、9:34から登り始める。小灌木の茂る道は思いの外整備されていて歩きやすい。10分ほどで正面に鈴ヶ峰山頂が見えるようになり、さらに10分余りで水準点のある最初の鉄塔に着く。その先で南西側から1本の登山道を合わせるが、昔この道を少し下がった辺りに畑を借りていて母と一緒によく通った思い出がある。
さらに進んで10:12,天ヶ峠(あまがたお)と言う峠の手前のピーク(205m)に着く。ここからは五日市の市街地とその向こうに宮島や大野町の経小屋山等,瀬戸の島と沿岸の山々がよく見える。小ピークを下った所が天ヶ峠で、ここから美鈴が丘団地までは10分余りである。
美鈴が丘団地は今でこそ大きな住宅地であるが、昭和30年代は何もないただの山だった。その辺りを百田と言い、そこにも借りた畑があって大八車を引いた父とよく通った。刈った柴を積み上げた大八車に弟が乗り、自分は乗せてもらえないどころか後ろから押して歩かされたのを覚えている。
天ヶ峠には戦時中だか終戦直後に飛行機が落ちたとか、子ども達の間では水晶が出るという噂があって、私たちは棒切れを持ってチャンバラごっこをしながらよく『探検』にも来た。残念ながら水晶が見つかったことはなかったが、ワクワク感があって楽しかった。
当時、峠へは南西側から登るルートがあって、私達はそれを登ったのだが、その道は藪がかぶっていて痕跡を残すのみとなっていた。下部はおそらくゴルフ場に飲み込まれてしまっていることだろう。
峠からは一気に115mを登って10:33鈴ヶ峰(西峰)に着く。ここまで来ると宮島より東に位置する島が見えてくる。多分大奈佐美島や能美島だろう・・。
当時,私たちが遊びに来たのはここまでで、そこから先,東峰の方に足を延ばしたことはなかった。従って大広島市の市街地や沖に浮かぶ似ノ島,江田島等の島々を見ることもなく、そこが私達の『探険』の限界だった。佐伯郡と広島市とが鈴ヶ峰~鬼ヶ城山ラインと言うたった1本の稜線を隔てて背中を合わせていたことを長い間知らずにいた。そんな狭い空間で跳ね回っていた時代の私達にとって広島と言う街は別世界だった。
山頂には3人の中高年のハイカーがいた。1人は美鈴が丘団地に住む人で、長い間手弁当で登山道をコツコツ整備してきたと言う。30年前とは見違えるほど歩きやすい道になっていたのは、そう言う志ある方々の努力の賜物だったのだと感謝!
10分ほど山頂にいて東峰に向かい、11:08東峰着。そこはかなりの広さの裸地で公園になっていた。無風快晴の穏やかな陽だまりの温もりに浸りながら広島市の市街地と瀬戸の島々の展望を楽しんだ後、北側の道を鬼ヶ城山に向かう。
11:14発。急斜面を100mほど下って細い尾根道に入る。そこから左手下の団地に沿って進むと『鈴ヶ峰⇔鬼ヶ城山』の標識があってそこから街に下る道があるが、右手を進めば『道行地蔵』と言う地蔵のある公園があって、そのまま山道を鬼ヶ城山に向かうことが出来る。
昔,この辺りまで遊びに来た餓鬼大将がいて、彼らの間では『地蔵の首がなかった』とか『いや,あった』などと『首』をめぐる噂話がまことしやかに囁かれていたが、自分はそこまで行く度胸はなかったので地蔵の首があったのかなったのかは知らずじまいでだった。
11:40,道行地蔵通過。西広島バイパスに下る道を横切ることなく、その上を通って鬼ヶ城山に向かう。隣接する市街地は美鈴ヶ丘団地から山田新町へと変わり、尾根に沿って北に伸びる送電線が目標になる。
やや急な登りを80mほど登って11:54,山頂手前の八畳岩と言う大岩に着き、20分の昼食・休憩の後、ひと登りして12:20鬼ヶ城山着。大広島市の市街地と瀬戸の海・島の景観を存分に楽しんで次へ向かう。市の東側の山並みもよく見えているのだが、ほとんど名前が分からない。
12:25発。市街地との境界の崖の上をだらだらと下り、12:45,登山路末端の標識に着く。ここで道が二分するのだがどちらに進めばいいのか分からない。30年前の記憶では一旦道路を渡ってすぐに山道に入った覚えがあるのだが、その後開発が進んで宅地が広がっているものと考えて左側の団地に降り、送電線鉄塔をめがけて進む。
迷走の始まり・・,(いつものことじゃ!)
目の前にそこだけ残された感じの小さな丘があり、そこに土台を築いた鉄塔が立っていて、そこまで行けばその先が見通せるかもしれないと思ってそちらに行きかけたが、先ほどの登山路末端の標識を右に下ればバイパスと山田町を結ぶ草津沼田道路にぶつかって、そこから山道に入れるのではないかと言う迷いが生じて引き返す。
引き返して下る右の道はよく踏まれた登山道らしい道でそちらが正解と思われたが、あまりに下り方が急であり、また道路にぶつかる気配がなくそのまま下山してしまうのではないかと言う迷いが再び生じて諦め、送電線沿いの道を発見すべく再度市街地に下って前述の鉄塔のある丘に登る。
けれどそこは孤立した丘でそこから先を見通すことはできず、市街地に戻って草津沼田道路を見つけてそこを横切ると、そこがちょうど佐伯区と西区の境界に当たる場所だったので、境界線の道,もしくわ鉄塔の巡視路があるはずだと考えてその登り口を探す。西区側に100mほど下るとそれはすぐに見つかった。
13:40,巡視路の白い手すりの階段を登って山道に入る。この時点でそこから先は送電線と鉄塔に頼るしかないと言う意識が強く働いていた。同44,それまで巡視路とは思えないしっかりした道だったのが突然2つに分かれ、そこに『←柚木城山』と書かれた小さな看板が木にかけられているのを見る。
本来の縦走路が『柚木城』と言う城跡のある山を通ることを知っていたら、縦走路につながるであろう右の道を選んでいた筈であるが自分はそれを知らず、細くて薮が被り先行き不安なその道でなく巡視路を選んで左の道を進んだ。
13:51,最初の鉄塔(NO54)に到達。主稜線よりかなり低い位置にいる気がしたが、目の前に次の鉄塔が見えており、送電線自体は主稜線に向かってゆっくり右上がりに延びていて、その先に目指す大茶臼山のTV塔が見えていたので『←53』の標識に従って巡視路を進む。
だが、右寄りに高度を上げるだろう~の予想に反して巡視路はどんどんと稜線から遠ざかる方向に急降下し始め、一気に沢まで下ったと思うと再び急登となって前の鉄塔とほぼ同じレベルまでの登り返しとなる。
落ち葉が積もった急斜面の下りはアイゼンが欲しいほどであるし、イノシシのヌタ場となった沢では泥んこになる等して同行者の動きが極端に遅くなり、30分近くを要して14:18,NO53鉄塔に着く。
ここで、これまで目印にしてきた送電線とは別の系統の送電線がほぼ主稜線にそって大茶臼山に向かっており、こちらの送電線と交差していることに気づく。しかもその主稜線を走る送電線の鉄塔(NO17)が、NO53鉄塔から近いところにある。
チャンスとばかりその鉄塔への移動を試みると細々とではあるが踏み跡があり、2~3分でNO17鉄塔に着く。そこからはしっかりした道があったので喜んでその道を歩き始めたが、目標とは逆に遠ざかって行くので途中でやめて引き返し、再びNO53鉄塔に戻る(14:34)。ここから次の鉄塔までは前とまったく同様に沢に向けて下ってまた登る繰り返しとなる。
14:50,NO52鉄塔に着くとその先で2つの系統の送電線が交差しているのが見え、ここでようやく主稜線の登山道に合流する。
その主稜線沿いの送電線鉄塔(NO18)の先が気になって行ってみると反対(西)方向に向かう登山道があった。つまりそれが縦走路だったと言うことだ。ところが、先ほど乗り換えようとしたNO17鉄塔からも西に向かう道しかなかった。両者はどこでどう繋がるのだろうかと言う疑問が生じる・・。
疑問を抱えながら東に進み、いくつかの鉄塔を通過して15:21,己斐峠着。さらに大茶臼まで歩くつもりだったが、相方がギブアップしたので大茶臼への登山口を確認し、TV塔が見えるところまで登って終了(15:43)とする。
帰路は先刻来の疑問を明かすべく、引き返してNO17鉄塔から鬼ヶ城山登山口までの道を歩いてみたかったのだが、相方にはすでにその余力がなく『自分は街の道を歩いて帰るので1人でどうぞ~』等と言う。『では・・,』と言う訳にも行かず、その区間のみ翌日調べることにして15:43発。7kmを歩いて17:50帰着。
帰宅後,2.5万図で調べてみると、鬼ヶ城山の東側登山口から右(南側)の道を下れば草津沼田道路にぶつかり、そこを横切ると『柚木城山』と言う山をと城跡を通って己斐峠に至る登山道があることが分かった。ただ、この道は標高220mから120mまで100m下がってから一気に315mまで登り返さなければならない。
そこで、鬼ヶ城山登山口から高度を下げずに本来の縦走路に繋がる道はないのだろうかと考えるに至って初めて『←柚木城』と書かれたあの小さな標識と薮の被った頼りなさそうな細い道を無視したことを思い出した。地図を見ると境界線のラインが入っていたのでそこに道があるはずだという確信を得て再調査を決める。
12月23日(木)
前日歩いたコースの鬼ヶ城山から山田団地に降りた地点に車を置き、分岐点の標識まで登って(14:39)から南の道を下る。前日は一旦下りかけ、あまりの下り方に不審を抱いて引き返したが、かまわずどんどん下ると10分弱で県道にぶつかる。
県道を渡ると右手に登山口の標識があり(14:51)、そこから急傾斜の階段が立ち上がっていてうんざりするほど上に延びているのを息を切らしながら登ること18分ほどでやっとそれらしい道になる。『西区やまなみハイキングルート』と書かれた標識に続いて『柚木山』を示す案内標識を見る(15:09)。高度はやっと鬼ヶ城山登山口のレベルであろうか・・。
さらに8分歩いて315m峰に着く(15:17)。そこから細い道を北に下って15:23,本来の縦走路に出る。15:31,最初の鉄塔下を通過したすぐ先に『←山田団(霊泉寺)』と書かれた小さな標識を見る。この標識が、前日無視した『←柚木城山』の標識に対応するものであることは間違いないと思われ、帰りにそれを確かめることにして直進する。
鉄塔を1つ越えて15:41標高339.4mの柚木城山着。同51,2つの送電線が交差する地点,NO18鉄塔着。前日歩いた道を次の鉄塔まで行き引き返す(15:56)。
16:19,先刻確認した分岐点まで戻って右折し山田団地に向かう。入り口付近こそ薮が被っていて明瞭でないが、思いのほか広くてしっかりした道である。約100mをぐんぐんと下って16:27『←柚木山』標識に到達。同43,登り口の県道着。あとは前日歩いた市街地を逆に歩いて車に戻り、納得のいく結論を得て調査を終了する。
追記
前日,NO17鉄塔からの道が主稜線のルートにつながらなかったのは、この鉄塔のみ登山道から北に100mほどずれていて、巡視路が引き込み線になっており、本線との分岐・合流点が柚木城山付近であるために西に向かっていたことによると判明, つまり、前日,諦めずにNO17鉄塔から西に進んでいれば柚木山付近で主稜線にぶつかっていたことになる。帰途、その分岐・合流点を確認した。
そこは鈴峯が唯一左右対称の端正な姿を見せる場所で目の前に田んぼがあり、春には水が張られた田に映って上下まで対称な山を見ることが出来た。
今はその風情もなくなってしまったが、当時の風景の記憶は今も鮮明である。
腕白時代の遊び場であり、また燃料として枯葉・枯れ枝を拾い集めさせられた生活の場でもあったその山こそは自分にとっての原点の山であり、切っても切れない縁で繋がったかけがえのないふるさとの山である。
その鈴峯から広島市祇園の武田山に至る約17kmの山なみを武田山連峰と言う。かつて『佐伯冒険学校』と言う子ども達の野外活動クラブを立ち上げるに当たって、その記念登山として子ども達と歩いたのがこのコースである。
『武田山~鈴ヶ峰』の全体を武田山連峰と称することには異論があるかもしれないし、正式な名称であるかどうかも調べたこともないが、東の安佐南区祇園の安川と西の佐伯区五日市の八幡川の間に連なる450m~250mの山々をひと続きの山稜、即ち連峰と見て、その連なりの一方の起点であり400mを越える高さの『武田山』を冠することは、あながち不当なものではないと思っている。
もとより勝手に山の名称をつくることは慎まなければならないことであるが、上の見解に加えて、30年以上前の文献にそのような記述があったことに依拠して、ここでは『武田山連峰』と称することをお許し願うこととする。
呼称の問題はさておいて、同コースは途中,道路で分断されると言う問題はあるにしても、南には瀬戸の海と島々が広がり、宮島の瀬戸を隔てて西から経小屋山,のうが高原,極楽寺山,窓が山,向山と続く山々の奥に大峰山や阿弥陀山が望まれ、大広島市を俯瞰しながらゆったりと歩くことが出来ると言う、眺望に恵まれた素晴らしいコースであると言える。
30数年を経て山そのものも周辺の状況も大きく変貌したが、近年,そのコースが整備され、訪れる人が多くなっていると聞く。
是が非でも再度歩きたいと思っていたその機会が突然来た!
12月22日(水)
9:20発,鈴ヶ峰の登山口までは歩いて10分ほど。昔は山際のどこからでも登れたが、今はバリケードがあって勝手な侵入を拒んでいる。昔の記憶を辿って登山口を見つけ、9:34から登り始める。小灌木の茂る道は思いの外整備されていて歩きやすい。10分ほどで正面に鈴ヶ峰山頂が見えるようになり、さらに10分余りで水準点のある最初の鉄塔に着く。その先で南西側から1本の登山道を合わせるが、昔この道を少し下がった辺りに畑を借りていて母と一緒によく通った思い出がある。
さらに進んで10:12,天ヶ峠(あまがたお)と言う峠の手前のピーク(205m)に着く。ここからは五日市の市街地とその向こうに宮島や大野町の経小屋山等,瀬戸の島と沿岸の山々がよく見える。小ピークを下った所が天ヶ峠で、ここから美鈴が丘団地までは10分余りである。
美鈴が丘団地は今でこそ大きな住宅地であるが、昭和30年代は何もないただの山だった。その辺りを百田と言い、そこにも借りた畑があって大八車を引いた父とよく通った。刈った柴を積み上げた大八車に弟が乗り、自分は乗せてもらえないどころか後ろから押して歩かされたのを覚えている。
天ヶ峠には戦時中だか終戦直後に飛行機が落ちたとか、子ども達の間では水晶が出るという噂があって、私たちは棒切れを持ってチャンバラごっこをしながらよく『探検』にも来た。残念ながら水晶が見つかったことはなかったが、ワクワク感があって楽しかった。
当時、峠へは南西側から登るルートがあって、私達はそれを登ったのだが、その道は藪がかぶっていて痕跡を残すのみとなっていた。下部はおそらくゴルフ場に飲み込まれてしまっていることだろう。
峠からは一気に115mを登って10:33鈴ヶ峰(西峰)に着く。ここまで来ると宮島より東に位置する島が見えてくる。多分大奈佐美島や能美島だろう・・。
当時,私たちが遊びに来たのはここまでで、そこから先,東峰の方に足を延ばしたことはなかった。従って大広島市の市街地や沖に浮かぶ似ノ島,江田島等の島々を見ることもなく、そこが私達の『探険』の限界だった。佐伯郡と広島市とが鈴ヶ峰~鬼ヶ城山ラインと言うたった1本の稜線を隔てて背中を合わせていたことを長い間知らずにいた。そんな狭い空間で跳ね回っていた時代の私達にとって広島と言う街は別世界だった。
山頂には3人の中高年のハイカーがいた。1人は美鈴が丘団地に住む人で、長い間手弁当で登山道をコツコツ整備してきたと言う。30年前とは見違えるほど歩きやすい道になっていたのは、そう言う志ある方々の努力の賜物だったのだと感謝!
10分ほど山頂にいて東峰に向かい、11:08東峰着。そこはかなりの広さの裸地で公園になっていた。無風快晴の穏やかな陽だまりの温もりに浸りながら広島市の市街地と瀬戸の島々の展望を楽しんだ後、北側の道を鬼ヶ城山に向かう。
11:14発。急斜面を100mほど下って細い尾根道に入る。そこから左手下の団地に沿って進むと『鈴ヶ峰⇔鬼ヶ城山』の標識があってそこから街に下る道があるが、右手を進めば『道行地蔵』と言う地蔵のある公園があって、そのまま山道を鬼ヶ城山に向かうことが出来る。
昔,この辺りまで遊びに来た餓鬼大将がいて、彼らの間では『地蔵の首がなかった』とか『いや,あった』などと『首』をめぐる噂話がまことしやかに囁かれていたが、自分はそこまで行く度胸はなかったので地蔵の首があったのかなったのかは知らずじまいでだった。
11:40,道行地蔵通過。西広島バイパスに下る道を横切ることなく、その上を通って鬼ヶ城山に向かう。隣接する市街地は美鈴ヶ丘団地から山田新町へと変わり、尾根に沿って北に伸びる送電線が目標になる。
やや急な登りを80mほど登って11:54,山頂手前の八畳岩と言う大岩に着き、20分の昼食・休憩の後、ひと登りして12:20鬼ヶ城山着。大広島市の市街地と瀬戸の海・島の景観を存分に楽しんで次へ向かう。市の東側の山並みもよく見えているのだが、ほとんど名前が分からない。
12:25発。市街地との境界の崖の上をだらだらと下り、12:45,登山路末端の標識に着く。ここで道が二分するのだがどちらに進めばいいのか分からない。30年前の記憶では一旦道路を渡ってすぐに山道に入った覚えがあるのだが、その後開発が進んで宅地が広がっているものと考えて左側の団地に降り、送電線鉄塔をめがけて進む。
迷走の始まり・・,(いつものことじゃ!)
目の前にそこだけ残された感じの小さな丘があり、そこに土台を築いた鉄塔が立っていて、そこまで行けばその先が見通せるかもしれないと思ってそちらに行きかけたが、先ほどの登山路末端の標識を右に下ればバイパスと山田町を結ぶ草津沼田道路にぶつかって、そこから山道に入れるのではないかと言う迷いが生じて引き返す。
引き返して下る右の道はよく踏まれた登山道らしい道でそちらが正解と思われたが、あまりに下り方が急であり、また道路にぶつかる気配がなくそのまま下山してしまうのではないかと言う迷いが再び生じて諦め、送電線沿いの道を発見すべく再度市街地に下って前述の鉄塔のある丘に登る。
けれどそこは孤立した丘でそこから先を見通すことはできず、市街地に戻って草津沼田道路を見つけてそこを横切ると、そこがちょうど佐伯区と西区の境界に当たる場所だったので、境界線の道,もしくわ鉄塔の巡視路があるはずだと考えてその登り口を探す。西区側に100mほど下るとそれはすぐに見つかった。
13:40,巡視路の白い手すりの階段を登って山道に入る。この時点でそこから先は送電線と鉄塔に頼るしかないと言う意識が強く働いていた。同44,それまで巡視路とは思えないしっかりした道だったのが突然2つに分かれ、そこに『←柚木城山』と書かれた小さな看板が木にかけられているのを見る。
本来の縦走路が『柚木城』と言う城跡のある山を通ることを知っていたら、縦走路につながるであろう右の道を選んでいた筈であるが自分はそれを知らず、細くて薮が被り先行き不安なその道でなく巡視路を選んで左の道を進んだ。
13:51,最初の鉄塔(NO54)に到達。主稜線よりかなり低い位置にいる気がしたが、目の前に次の鉄塔が見えており、送電線自体は主稜線に向かってゆっくり右上がりに延びていて、その先に目指す大茶臼山のTV塔が見えていたので『←53』の標識に従って巡視路を進む。
だが、右寄りに高度を上げるだろう~の予想に反して巡視路はどんどんと稜線から遠ざかる方向に急降下し始め、一気に沢まで下ったと思うと再び急登となって前の鉄塔とほぼ同じレベルまでの登り返しとなる。
落ち葉が積もった急斜面の下りはアイゼンが欲しいほどであるし、イノシシのヌタ場となった沢では泥んこになる等して同行者の動きが極端に遅くなり、30分近くを要して14:18,NO53鉄塔に着く。
ここで、これまで目印にしてきた送電線とは別の系統の送電線がほぼ主稜線にそって大茶臼山に向かっており、こちらの送電線と交差していることに気づく。しかもその主稜線を走る送電線の鉄塔(NO17)が、NO53鉄塔から近いところにある。
チャンスとばかりその鉄塔への移動を試みると細々とではあるが踏み跡があり、2~3分でNO17鉄塔に着く。そこからはしっかりした道があったので喜んでその道を歩き始めたが、目標とは逆に遠ざかって行くので途中でやめて引き返し、再びNO53鉄塔に戻る(14:34)。ここから次の鉄塔までは前とまったく同様に沢に向けて下ってまた登る繰り返しとなる。
14:50,NO52鉄塔に着くとその先で2つの系統の送電線が交差しているのが見え、ここでようやく主稜線の登山道に合流する。
その主稜線沿いの送電線鉄塔(NO18)の先が気になって行ってみると反対(西)方向に向かう登山道があった。つまりそれが縦走路だったと言うことだ。ところが、先ほど乗り換えようとしたNO17鉄塔からも西に向かう道しかなかった。両者はどこでどう繋がるのだろうかと言う疑問が生じる・・。
疑問を抱えながら東に進み、いくつかの鉄塔を通過して15:21,己斐峠着。さらに大茶臼まで歩くつもりだったが、相方がギブアップしたので大茶臼への登山口を確認し、TV塔が見えるところまで登って終了(15:43)とする。
帰路は先刻来の疑問を明かすべく、引き返してNO17鉄塔から鬼ヶ城山登山口までの道を歩いてみたかったのだが、相方にはすでにその余力がなく『自分は街の道を歩いて帰るので1人でどうぞ~』等と言う。『では・・,』と言う訳にも行かず、その区間のみ翌日調べることにして15:43発。7kmを歩いて17:50帰着。
帰宅後,2.5万図で調べてみると、鬼ヶ城山の東側登山口から右(南側)の道を下れば草津沼田道路にぶつかり、そこを横切ると『柚木城山』と言う山をと城跡を通って己斐峠に至る登山道があることが分かった。ただ、この道は標高220mから120mまで100m下がってから一気に315mまで登り返さなければならない。
そこで、鬼ヶ城山登山口から高度を下げずに本来の縦走路に繋がる道はないのだろうかと考えるに至って初めて『←柚木城』と書かれたあの小さな標識と薮の被った頼りなさそうな細い道を無視したことを思い出した。地図を見ると境界線のラインが入っていたのでそこに道があるはずだという確信を得て再調査を決める。
12月23日(木)
前日歩いたコースの鬼ヶ城山から山田団地に降りた地点に車を置き、分岐点の標識まで登って(14:39)から南の道を下る。前日は一旦下りかけ、あまりの下り方に不審を抱いて引き返したが、かまわずどんどん下ると10分弱で県道にぶつかる。
県道を渡ると右手に登山口の標識があり(14:51)、そこから急傾斜の階段が立ち上がっていてうんざりするほど上に延びているのを息を切らしながら登ること18分ほどでやっとそれらしい道になる。『西区やまなみハイキングルート』と書かれた標識に続いて『柚木山』を示す案内標識を見る(15:09)。高度はやっと鬼ヶ城山登山口のレベルであろうか・・。
さらに8分歩いて315m峰に着く(15:17)。そこから細い道を北に下って15:23,本来の縦走路に出る。15:31,最初の鉄塔下を通過したすぐ先に『←山田団(霊泉寺)』と書かれた小さな標識を見る。この標識が、前日無視した『←柚木城山』の標識に対応するものであることは間違いないと思われ、帰りにそれを確かめることにして直進する。
鉄塔を1つ越えて15:41標高339.4mの柚木城山着。同51,2つの送電線が交差する地点,NO18鉄塔着。前日歩いた道を次の鉄塔まで行き引き返す(15:56)。
16:19,先刻確認した分岐点まで戻って右折し山田団地に向かう。入り口付近こそ薮が被っていて明瞭でないが、思いのほか広くてしっかりした道である。約100mをぐんぐんと下って16:27『←柚木山』標識に到達。同43,登り口の県道着。あとは前日歩いた市街地を逆に歩いて車に戻り、納得のいく結論を得て調査を終了する。
追記
前日,NO17鉄塔からの道が主稜線のルートにつながらなかったのは、この鉄塔のみ登山道から北に100mほどずれていて、巡視路が引き込み線になっており、本線との分岐・合流点が柚木城山付近であるために西に向かっていたことによると判明, つまり、前日,諦めずにNO17鉄塔から西に進んでいれば柚木山付近で主稜線にぶつかっていたことになる。帰途、その分岐・合流点を確認した。