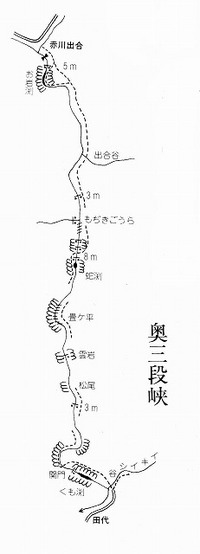2011年01月13日
戸谷峰
前週に続き、足慣らしのため戸谷峰(1929m)に登る。戸谷峰には旧四賀村の保福寺地区から登るコースとR254の三才山(みさやま)トンネル付近の野間沢から登るコースがある他、松本市の稲倉(しなくら)峠から旧四賀村との境界線に沿って縦走するコース,保福寺峠と美ヶ原スカイラインを結ぶ林道の三才トンネルの真上に当たる三才山峠から三才山(1605m),六人坊(1618m),を経て縦走するコースなどがある。
今回は登頂上後、あわよくば六人坊,三才山辺りまでのルート偵察を~,ともくろんでとりつきのいい野間沢コースから登る。
1月8日(土)
標高ほぼ1000mの野間沢橋登山口を7:48発。戸谷峰から東に延びる稜線を100m下った辺りから南に向かって派生する尾根の東斜面を沢に沿って200mほど登る。この沢を遮二無二に登れば主稜線に達することが出来そうだが急斜面の薮漕ぎになるのは必至で、そう言うことをやる馬力と気まぐれは今はない。
なのでここは送電線巡視路でもある登山道の通り右折し(8:21)、右手の1363mピークを大きく廻りこんで東隣の尾根の上に出る。そこから尾根に沿って送電線が上に伸び、次々と現れる3つの鉄塔(No7~73)を追って登る。
右手に進んで東斜面に出ると陽が当たり始め暑くなってきたのでヤッケを脱ぐ(8:47~53)。オーバーズボンも要らないのだが脱ぐのが面倒。カラマツ林の平易な尾根道を歩くこと8分で1360mの№71鉄通過(9:05)。周囲の木の密度が低くなって次第に見通しがよくなり、さらに進むこと20分弱で1450mの№72鉄塔着(9:23)。鉄塔の向こうに戸谷峰の山頂が見え、左手後方に梓川の南に位置する山々がせりあがって来た。
9:40,主稜線上のNo73鉄塔(1510m)着。振り返ると美ヶ原から伸びてくる送電線がよく見える。5分後出発。ここから疎林の主稜線を西に進んで100mほど登り、最後はロープのある急斜面を30mほど登って山頂に到達(10:13)。
雲1つない快晴,まれにみる絶景である。列挙すればキリがない遠近の山々を心行くまで目に焼きつけ堪能し、撮れる限りの写真を撮りまくって山頂を後にする。
10:43,No73鉄塔に戻って昼食を摂り、11:10,荷物を置いて六人坊に向かう。
六人坊は間近に見え、その向こうに保福寺と美ヶ原スカイラインを結ぶ林道が見えていて楽勝と思われたが、目の前の小ピークから50mくらい下がった先にもう1つのピーク(1503m)があり、そこまで行って見通すと先刻以上の下りがあってその鞍部から大きな登り(100m以上)となっているのが分かった。ここまで来て荷物を置いてきたことを悔やんだが後の祭りで、偵察はここまでとして諦めて引き返す。
帰宅して地図を見ると、1503mのピークからは70mの下りの後、120mの登り返しがあるもそこは1562mのピークで、六人坊はそこからさらに60m登っていた。
結局1時間かかって№73鉄塔に戻ることになったが、縦走路の様子があらまし分かっただけでも収穫だった。
12:11下山開始。午後になって陽射しが強くなり暑かったが休まず下って13:08下山。
今回は登頂上後、あわよくば六人坊,三才山辺りまでのルート偵察を~,ともくろんでとりつきのいい野間沢コースから登る。
1月8日(土)
標高ほぼ1000mの野間沢橋登山口を7:48発。戸谷峰から東に延びる稜線を100m下った辺りから南に向かって派生する尾根の東斜面を沢に沿って200mほど登る。この沢を遮二無二に登れば主稜線に達することが出来そうだが急斜面の薮漕ぎになるのは必至で、そう言うことをやる馬力と気まぐれは今はない。
なのでここは送電線巡視路でもある登山道の通り右折し(8:21)、右手の1363mピークを大きく廻りこんで東隣の尾根の上に出る。そこから尾根に沿って送電線が上に伸び、次々と現れる3つの鉄塔(No7~73)を追って登る。
右手に進んで東斜面に出ると陽が当たり始め暑くなってきたのでヤッケを脱ぐ(8:47~53)。オーバーズボンも要らないのだが脱ぐのが面倒。カラマツ林の平易な尾根道を歩くこと8分で1360mの№71鉄通過(9:05)。周囲の木の密度が低くなって次第に見通しがよくなり、さらに進むこと20分弱で1450mの№72鉄塔着(9:23)。鉄塔の向こうに戸谷峰の山頂が見え、左手後方に梓川の南に位置する山々がせりあがって来た。
9:40,主稜線上のNo73鉄塔(1510m)着。振り返ると美ヶ原から伸びてくる送電線がよく見える。5分後出発。ここから疎林の主稜線を西に進んで100mほど登り、最後はロープのある急斜面を30mほど登って山頂に到達(10:13)。
雲1つない快晴,まれにみる絶景である。列挙すればキリがない遠近の山々を心行くまで目に焼きつけ堪能し、撮れる限りの写真を撮りまくって山頂を後にする。
10:43,No73鉄塔に戻って昼食を摂り、11:10,荷物を置いて六人坊に向かう。
六人坊は間近に見え、その向こうに保福寺と美ヶ原スカイラインを結ぶ林道が見えていて楽勝と思われたが、目の前の小ピークから50mくらい下がった先にもう1つのピーク(1503m)があり、そこまで行って見通すと先刻以上の下りがあってその鞍部から大きな登り(100m以上)となっているのが分かった。ここまで来て荷物を置いてきたことを悔やんだが後の祭りで、偵察はここまでとして諦めて引き返す。
帰宅して地図を見ると、1503mのピークからは70mの下りの後、120mの登り返しがあるもそこは1562mのピークで、六人坊はそこからさらに60m登っていた。
結局1時間かかって№73鉄塔に戻ることになったが、縦走路の様子があらまし分かっただけでも収穫だった。
12:11下山開始。午後になって陽射しが強くなり暑かったが休まず下って13:08下山。
2011年01月13日
光城山~長峰山
1月2日(日)
今年の元日登山は茅ヶ岳を予定していたが、年末年始大荒れの予報に怖気づいて計画を中止。西日本や東北は予報通りの荒れ模様だったが、信州はいたって穏やかな年明けで臍を噛んだ。
コタツムリを決め込んで元日の駅伝を見ていたらjun1さんから電話があって『足慣らしに光城山にでも登りますか・・』となる。
と言う訳で8:00に集合し、いつもとは違う北廻りのルートを登る。北廻りルートは光城山の北隣に並ぶほぼ同じ高さの山の尾根を登るルートで、正面のルートが直登に近くてきついのに比して、斜度は変わらないが折り返しの距離が長くとってある分だけゆったりと登れる気がした。
また正面ルートには冬は白鳥型に、春は桜道に沿って電飾が施されたりして手が加えられているのに比してほとんど手が加えられていない分,うるさくなくていい感じである。
山行記録を書く時にはまず写真を取り込み、画像を見て時刻,場所,その場での出来事や状況等,得られる様々な情報を手がかりに書くのが常であり、今回も帰って早速写真をアップすべくメモリーの蓋を開けたところ、そこにあるべきものが入っておらず『ドヒャー!』となって次にガックリした次第。
コンパクトの時は2~3枚撮った時点でカメラが教えてくれるのに対して一眼にはそのような機能は無いらしく、バシャバシャとシャッターが落ちるので全く気がつかなかったノダ・・。
手がかりが無くては書きようが無いとは言わないが、ディティールまでは無理。そんな訳で同じコースを登りなおし、改めて写真を撮ったものを載せることにしたので当日の行動記録は大雑把なものになる。
また登りなおしと言えども動けばそれなりのことはあるので、併せて3日の記録も後に記す。当然ながら写真の時刻は3日午後となる。
2日8:00,光城山登山口集合。jun1さんが『今日はこっちから登って見ようか・・』と谷筋を指し、自分も正面のルートは好きでないので文句無く同意して10分後出発。
光配水地の建物を過ぎて道が2分する。正面ルートに繋がる道を見送って左折し北廻りの登山道に入ると、道は谷を隔てた北隣の山腹を650mの等高線に沿って斜上し始める。
正面ルートが尾根をほぼ真っ直ぐ登っていくのに比べ、こちらは山腹が若干広い分だけゆとりがあってジグザクの距離が長く、ゆったり登っているのと、ケヤキやコナラ,クヌギ等の樹高のある広葉樹が適度の間隔で疎生していて林床が明るく伸びやかなのが特徴であろうか・・。
登山口から山頂まで、標高差300mほどの山なので初めの急登150mを頑張れば20分で中間点標識に着く。そこからは傾斜もゆるくなって、だらだらと歩くこと15分ほどで林道に到達。林道を南に5~6分で光城山の山頂に着く。
せっかくなので光城山から長峰山まで歩こうと言うことになり、林道を北に向かう。10分ほど歩くとかつて『白牧』と言う集落があった場所に到達する。ここには建物の跡はないが、墓や石仏,道祖神等が残っている。ここ(白牧)からは光城山と長峰山の中間を西に下る林道白牧線と言う道がある。そこは未踏査なので帰りはその道を下って見ようなどと話しながら進んで40分あまりで長峰山に到着(9:50頃)。
西山は半分から上が雲の中で常念岳は望めず、10分ほど下界の景観を楽しんでもとの道を戻る。道すがら『長峰荘に下るつもりだったが(下山口が)遠いので止めた』と言う婦人と道連れになり、白牧からも同じ道を下ることになって3人で林道を下る。
林道は復員4m,上部がコンクリート,途中からはアスファルト舗装のしっかりした道で、雪が無ければ車での往来は全く問題ないことが分かった。がしかし、かなりの急勾配で、歩いて下るとつま先を傷めそうで小走りになってしまう。そして思いのほか長い。
白牧に限らず、この地域一帯は急傾斜の地滑り危険地帯であり、地滑り防止対策として『水抜き』の施設が随所に見られる。
途中に炭焼き窯や作業小屋,立ち木を利用して丸太を組んだ足場のようなものがある一画があったり、雑木を伐採して小さな広葉樹を植林した区画があったりと、飽きない程度に見所がある。
約40分で市道に出て更に10分あまり歩き、11:00に駐車場着,散会する。
付
1月3日(月) 登りなおしの記
箱根駅伝を見終わってから再度写真を撮りに出かけたので出発が遅くなってしまった。我が母校はかろうじて10位以内に逃げ込んだが、このところ振るわない。
14:15発。さくら並木への道を見送って北廻り道に入ってすぐの所に標識があったのを昨日は見落としていた。そこから上に道が1本あったのが気になったが、標識に従って真っ直ぐ進む。がしかし、昨日のことなのにその辺りの記憶が全くなく、その道がどんどん北に廻って行く気配なので引き返して標識から上に向かって見た。ひと登りすると右手に正面ルートの尾根から山頂までもがよく見える場所に到達。いい角度で山頂を写すことが出来、ふり向けば蝶ヶ岳をも見ることが出来たのはいいが、『昨日,こんな場面があったっけ・・』と?符が・・。マア、行ける所まで行ってみよう・・,と先に進むもすぐに道が途絶え、引き返す羽目になる。何と言う注意力の欠如かッ!
14:40,戻って北寄りに進むと上から男性が1人,さらに上から3人の女性が降りて来た。正面ルートから登ってこちらへ降りてくると言うパターンがあるようだ。同じ所に降りれるのが魅力なのだろう。
急斜面を20分ほど登ってようやく傾斜が緩くなる辺りに『さくら池・山頂中間点(14:57)』と言う標識があるのだが、さくら池がどこにあるのか、またこの山の山頂それなのか、光城山のそれなのか分からない。
背後の太陽が木々の長い影を登山道に落とし、それを踏んだり跨いだりしながら進む。スックと伸びた影や横たわる影,こんがらがった影もあれば踊っているような影もあって、この時間帯は自分達が『主役だ』と言わんばかりに好き勝手に、自在にふるまっている。
15:09,2つの尾根が平行して光城山がすぐ隣に見える辺り,山頂付近で光るものが見えるのを望遠で撮っている時、降りてきた3人連れが山仲間だったのに驚き、かつ思いがけない再会を喜ぶ。動けばそれなりに何がしかの収穫があることのこれが1つ目。
15:17,林道に到達し、前日同様,光城山の山頂まで行く。15:31,山頂の神社着。ちらほらと登山者があり、そのいずれもが北廻りルートに向かうのと入れ替わって、昨日は姿を見せなかったアルプス~頭だけの常念岳,雪の大天井岳,頭を隠した燕岳・有明山~を眺め、穂高の町を見下ろす。
15:27発,林道を北に向かい15:36白牧着。石仏や道祖神の写真を撮った後、15:40から林道を下る。
前日同様,小走りに下ってカーブを廻った時,突然目の前の林道にカモシカがいるのに出くわす(15:47)。距離は10mあるかなしかで、動かずこちらを見ているのをゆっくり撮ることができた。4~5枚撮ってからそろりと前進すると林道の向こうの斜面に飛び込んで行った。追いかけて覗きこむとすぐ下にいたのが一転して上に走り、林道を駆け渡って右手の斜面の先に消えた。なおも追って行くと30mも先の潅木の中でこっちを見ている。こうして束の間ながらカモシカとの時間を共有したこれが収穫の2つ目。
そこから1kmほど下ると右手に炭焼き窯や小屋のある一画があって中年の男性が作業していた(16:04)。入り込んで話しを聞くと男性はその一帯の森林の所有者で、森林の手入れをしながら炭焼きをしたり、丸太を組んでアスレチックのようなものを作ったりして森との共生を楽しんでいるとのこと。
ちょうどその辺りから山の斜面を伐採してその跡地に小さな広葉樹を植林し、目印にピンクのリボンがつけてあるのが見られたのでそのことを尋ねると、それは公有地を対象とした県と国の事業だそうで、『自分の所もやってくれないか』と聞いてみたが私有地は対象外だと言われたので、今後自分でやっていくつもりだと言うことだった。
大変な作業になると思われるが、そうやって手入れすると言う人は貴重な存在なので補助があってもよさそうなものだと思った。
16:12,炭焼き小屋を辞去。道が大きく右奥に伸びて下がり切ると奥沢と言う沢にぶつかり、ヘアピン状に折り返して高度を下げながら500m進むと今度は左手の白牧沢に行き当たる。2つの沢が合流するところにある堰堤を過ぎると人里は近い。
16:35,市道に出て左折し6分で登山口に着き終了(16:41)。
今年の元日登山は茅ヶ岳を予定していたが、年末年始大荒れの予報に怖気づいて計画を中止。西日本や東北は予報通りの荒れ模様だったが、信州はいたって穏やかな年明けで臍を噛んだ。
コタツムリを決め込んで元日の駅伝を見ていたらjun1さんから電話があって『足慣らしに光城山にでも登りますか・・』となる。
と言う訳で8:00に集合し、いつもとは違う北廻りのルートを登る。北廻りルートは光城山の北隣に並ぶほぼ同じ高さの山の尾根を登るルートで、正面のルートが直登に近くてきついのに比して、斜度は変わらないが折り返しの距離が長くとってある分だけゆったりと登れる気がした。
また正面ルートには冬は白鳥型に、春は桜道に沿って電飾が施されたりして手が加えられているのに比してほとんど手が加えられていない分,うるさくなくていい感じである。
山行記録を書く時にはまず写真を取り込み、画像を見て時刻,場所,その場での出来事や状況等,得られる様々な情報を手がかりに書くのが常であり、今回も帰って早速写真をアップすべくメモリーの蓋を開けたところ、そこにあるべきものが入っておらず『ドヒャー!』となって次にガックリした次第。
コンパクトの時は2~3枚撮った時点でカメラが教えてくれるのに対して一眼にはそのような機能は無いらしく、バシャバシャとシャッターが落ちるので全く気がつかなかったノダ・・。
手がかりが無くては書きようが無いとは言わないが、ディティールまでは無理。そんな訳で同じコースを登りなおし、改めて写真を撮ったものを載せることにしたので当日の行動記録は大雑把なものになる。
また登りなおしと言えども動けばそれなりのことはあるので、併せて3日の記録も後に記す。当然ながら写真の時刻は3日午後となる。
2日8:00,光城山登山口集合。jun1さんが『今日はこっちから登って見ようか・・』と谷筋を指し、自分も正面のルートは好きでないので文句無く同意して10分後出発。
光配水地の建物を過ぎて道が2分する。正面ルートに繋がる道を見送って左折し北廻りの登山道に入ると、道は谷を隔てた北隣の山腹を650mの等高線に沿って斜上し始める。
正面ルートが尾根をほぼ真っ直ぐ登っていくのに比べ、こちらは山腹が若干広い分だけゆとりがあってジグザクの距離が長く、ゆったり登っているのと、ケヤキやコナラ,クヌギ等の樹高のある広葉樹が適度の間隔で疎生していて林床が明るく伸びやかなのが特徴であろうか・・。
登山口から山頂まで、標高差300mほどの山なので初めの急登150mを頑張れば20分で中間点標識に着く。そこからは傾斜もゆるくなって、だらだらと歩くこと15分ほどで林道に到達。林道を南に5~6分で光城山の山頂に着く。
せっかくなので光城山から長峰山まで歩こうと言うことになり、林道を北に向かう。10分ほど歩くとかつて『白牧』と言う集落があった場所に到達する。ここには建物の跡はないが、墓や石仏,道祖神等が残っている。ここ(白牧)からは光城山と長峰山の中間を西に下る林道白牧線と言う道がある。そこは未踏査なので帰りはその道を下って見ようなどと話しながら進んで40分あまりで長峰山に到着(9:50頃)。
西山は半分から上が雲の中で常念岳は望めず、10分ほど下界の景観を楽しんでもとの道を戻る。道すがら『長峰荘に下るつもりだったが(下山口が)遠いので止めた』と言う婦人と道連れになり、白牧からも同じ道を下ることになって3人で林道を下る。
林道は復員4m,上部がコンクリート,途中からはアスファルト舗装のしっかりした道で、雪が無ければ車での往来は全く問題ないことが分かった。がしかし、かなりの急勾配で、歩いて下るとつま先を傷めそうで小走りになってしまう。そして思いのほか長い。
白牧に限らず、この地域一帯は急傾斜の地滑り危険地帯であり、地滑り防止対策として『水抜き』の施設が随所に見られる。
途中に炭焼き窯や作業小屋,立ち木を利用して丸太を組んだ足場のようなものがある一画があったり、雑木を伐採して小さな広葉樹を植林した区画があったりと、飽きない程度に見所がある。
約40分で市道に出て更に10分あまり歩き、11:00に駐車場着,散会する。
付
1月3日(月) 登りなおしの記
箱根駅伝を見終わってから再度写真を撮りに出かけたので出発が遅くなってしまった。我が母校はかろうじて10位以内に逃げ込んだが、このところ振るわない。
14:15発。さくら並木への道を見送って北廻り道に入ってすぐの所に標識があったのを昨日は見落としていた。そこから上に道が1本あったのが気になったが、標識に従って真っ直ぐ進む。がしかし、昨日のことなのにその辺りの記憶が全くなく、その道がどんどん北に廻って行く気配なので引き返して標識から上に向かって見た。ひと登りすると右手に正面ルートの尾根から山頂までもがよく見える場所に到達。いい角度で山頂を写すことが出来、ふり向けば蝶ヶ岳をも見ることが出来たのはいいが、『昨日,こんな場面があったっけ・・』と?符が・・。マア、行ける所まで行ってみよう・・,と先に進むもすぐに道が途絶え、引き返す羽目になる。何と言う注意力の欠如かッ!
14:40,戻って北寄りに進むと上から男性が1人,さらに上から3人の女性が降りて来た。正面ルートから登ってこちらへ降りてくると言うパターンがあるようだ。同じ所に降りれるのが魅力なのだろう。
急斜面を20分ほど登ってようやく傾斜が緩くなる辺りに『さくら池・山頂中間点(14:57)』と言う標識があるのだが、さくら池がどこにあるのか、またこの山の山頂それなのか、光城山のそれなのか分からない。
背後の太陽が木々の長い影を登山道に落とし、それを踏んだり跨いだりしながら進む。スックと伸びた影や横たわる影,こんがらがった影もあれば踊っているような影もあって、この時間帯は自分達が『主役だ』と言わんばかりに好き勝手に、自在にふるまっている。
15:09,2つの尾根が平行して光城山がすぐ隣に見える辺り,山頂付近で光るものが見えるのを望遠で撮っている時、降りてきた3人連れが山仲間だったのに驚き、かつ思いがけない再会を喜ぶ。動けばそれなりに何がしかの収穫があることのこれが1つ目。
15:17,林道に到達し、前日同様,光城山の山頂まで行く。15:31,山頂の神社着。ちらほらと登山者があり、そのいずれもが北廻りルートに向かうのと入れ替わって、昨日は姿を見せなかったアルプス~頭だけの常念岳,雪の大天井岳,頭を隠した燕岳・有明山~を眺め、穂高の町を見下ろす。
15:27発,林道を北に向かい15:36白牧着。石仏や道祖神の写真を撮った後、15:40から林道を下る。
前日同様,小走りに下ってカーブを廻った時,突然目の前の林道にカモシカがいるのに出くわす(15:47)。距離は10mあるかなしかで、動かずこちらを見ているのをゆっくり撮ることができた。4~5枚撮ってからそろりと前進すると林道の向こうの斜面に飛び込んで行った。追いかけて覗きこむとすぐ下にいたのが一転して上に走り、林道を駆け渡って右手の斜面の先に消えた。なおも追って行くと30mも先の潅木の中でこっちを見ている。こうして束の間ながらカモシカとの時間を共有したこれが収穫の2つ目。
そこから1kmほど下ると右手に炭焼き窯や小屋のある一画があって中年の男性が作業していた(16:04)。入り込んで話しを聞くと男性はその一帯の森林の所有者で、森林の手入れをしながら炭焼きをしたり、丸太を組んでアスレチックのようなものを作ったりして森との共生を楽しんでいるとのこと。
ちょうどその辺りから山の斜面を伐採してその跡地に小さな広葉樹を植林し、目印にピンクのリボンがつけてあるのが見られたのでそのことを尋ねると、それは公有地を対象とした県と国の事業だそうで、『自分の所もやってくれないか』と聞いてみたが私有地は対象外だと言われたので、今後自分でやっていくつもりだと言うことだった。
大変な作業になると思われるが、そうやって手入れすると言う人は貴重な存在なので補助があってもよさそうなものだと思った。
16:12,炭焼き小屋を辞去。道が大きく右奥に伸びて下がり切ると奥沢と言う沢にぶつかり、ヘアピン状に折り返して高度を下げながら500m進むと今度は左手の白牧沢に行き当たる。2つの沢が合流するところにある堰堤を過ぎると人里は近い。
16:35,市道に出て左折し6分で登山口に着き終了(16:41)。
2010年03月31日
ワサビと野焼きと早春賦と~安曇野ピースウォーク・後
ワサビと野焼きと早春賦と~安曇野ピースウォーク・後
2010年3月22日(代) 参加者;jun1 木偶野呂馬 記録;木偶野呂馬


安曇野~鋭き屋根寒空を突き 麦の色青し
光城山登山口から早春賦碑までの歩きは時間の関係でスイス村までをカットしてJun1さんの車で移動し、8:35、犀川土手から歩き始める。
堤防道路は猛烈に冷たい川風が吹きつけてくるので堤防の法面を下がって歩く。1kmほど歩くと堤防が低くなり河川敷のニセアカシアの疎林の中に入る。『これが本来の犀川の堤防の高さだ』と生粋の穂高人であるjun1さんが言う。


ワサビ園~桃花紅く 水豊かに流る
この辺りはすでに大王わさび農場の一画で、やがて川床を掘って砂利を敷き詰めた上にワサビの苗をびっしりと植えたワサビ畑が現れてくる。小山のようになっている尾根状の道は、ワサビを植える苗床を掘り上げた土砂を積み上げたもので、すべて人力で築いた山と川なのだそうだ。


早春の賦碑にかかりて咲く花鮮やかに
わさび農場の中をゆっくり歩き、水車や水面に映える逆さの木々を写したりして農場を抜け、9:25,オリンピック道路の信号に到達。ここでjunn1さんが引き返す。ここから万水川を渡り景観保護地区となっている田圃の中の小道を10分ほど歩くと『水色の時』道祖神,更に10分で早春賦碑に到達。時刻9:45。


幾重にも巡る水路に 夥しき虹鱒の群を見る
3度目のコースなのですぐに引き返したが、来た通りの道を引き返さなかったために穂高川の堤防道路を下る羽目になった。穂高川の堤防下には沢山のわさび田と養鱒場があり、それぞれのための水路が無数に走っていて複雑に入り組んでいるので目の前に見えている道路に渡りたくても水路に阻まれて容易には渡れないのだ。
やむなくオリンピック道路のアーチ型の橋の下を潜り抜け、養鱒場の水路にかかる小橋を渡ってアーチ橋に乗る。この辺りから高瀬川の河川敷で大規模な野焼きをやっているのが伺えた。


彼方に見る野焼きの煙 間近に見る炎凄まじ
橋を渡ってゴミ処理場の前まで下り、田圃の道を歩いて10:20に高瀬川にかかるあづみ橋に到達。野焼きの炎と煙を見ながらあづみ橋を渡る。
野焼きはあづみ橋から下流の河川敷のヨシ原を全部焼くつもりらしく、大勢の法被姿の人達が繰り出して火の管理に当っていた。何人かは橋の手前で火を追い返す作業をしており、それは長い棒の先に大きな帯状の厚めの布切れを取りつけたもので火を消す作業で、慣れているらしく手際がよい。


越し方の山々を望みて犀川を渡れば 再び水清く
橋の上からは早朝登った長峰山と光城山がよく見えた。あづみ橋を渡って今度は高瀬川の左岸を犀川との合流点まで歩き、合流点から犀川左岸を下ると程なく犀川橋に到達,時刻10:46。
犀川橋を渡り犀川の右岸を遡る。内側が有名な御宝田の白鳥池である堤防の東側下にはいつも野菜の洗い場に使っている湧水路が走っており、ここにも養鱒場がある。


白鳥の憩う田 傍らに石の神微笑む
水路を越えて更に畑中の道を歩き、11:10頃,R19に出る。そのまま国道を宮本神社まで歩いて長峰荘に向かう。11:33登山口に戻って終了。
500mほど離れた自宅前の田圃に最近よく来るようになったコハクチョウの一群を見つけ、行程中に遭遇したように写真を並べ替える小細工をしたので写真では11:45終了となっている。
2010年3月22日(代) 参加者;jun1 木偶野呂馬 記録;木偶野呂馬


安曇野~鋭き屋根寒空を突き 麦の色青し
光城山登山口から早春賦碑までの歩きは時間の関係でスイス村までをカットしてJun1さんの車で移動し、8:35、犀川土手から歩き始める。
堤防道路は猛烈に冷たい川風が吹きつけてくるので堤防の法面を下がって歩く。1kmほど歩くと堤防が低くなり河川敷のニセアカシアの疎林の中に入る。『これが本来の犀川の堤防の高さだ』と生粋の穂高人であるjun1さんが言う。


ワサビ園~桃花紅く 水豊かに流る
この辺りはすでに大王わさび農場の一画で、やがて川床を掘って砂利を敷き詰めた上にワサビの苗をびっしりと植えたワサビ畑が現れてくる。小山のようになっている尾根状の道は、ワサビを植える苗床を掘り上げた土砂を積み上げたもので、すべて人力で築いた山と川なのだそうだ。


早春の賦碑にかかりて咲く花鮮やかに
わさび農場の中をゆっくり歩き、水車や水面に映える逆さの木々を写したりして農場を抜け、9:25,オリンピック道路の信号に到達。ここでjunn1さんが引き返す。ここから万水川を渡り景観保護地区となっている田圃の中の小道を10分ほど歩くと『水色の時』道祖神,更に10分で早春賦碑に到達。時刻9:45。


幾重にも巡る水路に 夥しき虹鱒の群を見る
3度目のコースなのですぐに引き返したが、来た通りの道を引き返さなかったために穂高川の堤防道路を下る羽目になった。穂高川の堤防下には沢山のわさび田と養鱒場があり、それぞれのための水路が無数に走っていて複雑に入り組んでいるので目の前に見えている道路に渡りたくても水路に阻まれて容易には渡れないのだ。
やむなくオリンピック道路のアーチ型の橋の下を潜り抜け、養鱒場の水路にかかる小橋を渡ってアーチ橋に乗る。この辺りから高瀬川の河川敷で大規模な野焼きをやっているのが伺えた。


彼方に見る野焼きの煙 間近に見る炎凄まじ
橋を渡ってゴミ処理場の前まで下り、田圃の道を歩いて10:20に高瀬川にかかるあづみ橋に到達。野焼きの炎と煙を見ながらあづみ橋を渡る。
野焼きはあづみ橋から下流の河川敷のヨシ原を全部焼くつもりらしく、大勢の法被姿の人達が繰り出して火の管理に当っていた。何人かは橋の手前で火を追い返す作業をしており、それは長い棒の先に大きな帯状の厚めの布切れを取りつけたもので火を消す作業で、慣れているらしく手際がよい。


越し方の山々を望みて犀川を渡れば 再び水清く
橋の上からは早朝登った長峰山と光城山がよく見えた。あづみ橋を渡って今度は高瀬川の左岸を犀川との合流点まで歩き、合流点から犀川左岸を下ると程なく犀川橋に到達,時刻10:46。
犀川橋を渡り犀川の右岸を遡る。内側が有名な御宝田の白鳥池である堤防の東側下にはいつも野菜の洗い場に使っている湧水路が走っており、ここにも養鱒場がある。


白鳥の憩う田 傍らに石の神微笑む
水路を越えて更に畑中の道を歩き、11:10頃,R19に出る。そのまま国道を宮本神社まで歩いて長峰荘に向かう。11:33登山口に戻って終了。
500mほど離れた自宅前の田圃に最近よく来るようになったコハクチョウの一群を見つけ、行程中に遭遇したように写真を並べ替える小細工をしたので写真では11:45終了となっている。
2010年03月31日
Takeruの登山デビュー~安曇野ピースウォーク・前
Takeruの登山デビュー~安曇野ピースウォーク・前
2010年3月22日(代) 参加者;Takeru父子,jun1,木偶 記録者;木偶野呂馬


春分の日は春雷の轟く荒れた天候となり、安曇野ピースウォークは22日に順延した。前日とは打って変わって無風快晴で里山歩きには絶好の天候と思われた。
参加者はnobouの他、冒険学校会員で小学1年生のTakeruとその父の計3名で、Takeruにとっては早朝の長峰山~光城山登山が初めての登山となる。これに光城山でjun1さんが合流することになっている。


5:00,放射冷却の厳しい寒さの中,長峰荘近くの登山口を出発。ヘッドランプを頼りに暗い山道を登り始める。頭上に夏の大三角形を仰ぐ。冷え込みがきつく吸い込む空気の冷たさに喉が痛くなるほどで鼻で呼吸をするようにと指示するが、いきなりの急坂ではこちらも口が開いてしまう。5:30頃,空がしらみ始めランプ不要となる。


武の歩調に合わせて小刻みに何度か休み、1時間で林道に到達,日の出に間に合うようにと急かせて6時04分に登頂。展望台に登って待つこと8分で日の出となる。
腹に何か入れたいが座って食事できる気温ではないので光城山まで行ってから食べることにする。6:30発天平の森通過。


長峰山から光城山までは約1時間の行程だが、早朝から1時間あまりの急登と空腹でいささかつかれ気味のtakeruは『疲れた!』を連発,途中で動けなくなって道に寝転がったりしながらも1時間ほど歩いて7:13光城山着。朝日の当たる場所を選んで朝食を摂る。


Takeruがこの後どの程度歩けるかは本人の体力とやる気次第と言うことになっており、休んで元気を取り戻したかにも見えたが、Takeru父はここまでと判断したようで下山口に母親を呼ぶ電話をかけ、本人は後は下るだけと分かるとケロッとして元気よく歩き始める。子どもの登山なんてこんなものだろう。無理強いして登山嫌いにさせないことだ。


山頂でJun1さんと合流した後、早々に下山して安曇野ピースウォーク前半の早朝登山を終了。武君,早朝から寒い中,よく頑張った。またネッ!
ここから早春賦碑までの歩きは時間の関係でスイス村までをカットしてJun1さんの車で移動し、犀川土手から歩くことにする。
2010年3月22日(代) 参加者;Takeru父子,jun1,木偶 記録者;木偶野呂馬


春分の日は春雷の轟く荒れた天候となり、安曇野ピースウォークは22日に順延した。前日とは打って変わって無風快晴で里山歩きには絶好の天候と思われた。
参加者はnobouの他、冒険学校会員で小学1年生のTakeruとその父の計3名で、Takeruにとっては早朝の長峰山~光城山登山が初めての登山となる。これに光城山でjun1さんが合流することになっている。


5:00,放射冷却の厳しい寒さの中,長峰荘近くの登山口を出発。ヘッドランプを頼りに暗い山道を登り始める。頭上に夏の大三角形を仰ぐ。冷え込みがきつく吸い込む空気の冷たさに喉が痛くなるほどで鼻で呼吸をするようにと指示するが、いきなりの急坂ではこちらも口が開いてしまう。5:30頃,空がしらみ始めランプ不要となる。


武の歩調に合わせて小刻みに何度か休み、1時間で林道に到達,日の出に間に合うようにと急かせて6時04分に登頂。展望台に登って待つこと8分で日の出となる。
腹に何か入れたいが座って食事できる気温ではないので光城山まで行ってから食べることにする。6:30発天平の森通過。


長峰山から光城山までは約1時間の行程だが、早朝から1時間あまりの急登と空腹でいささかつかれ気味のtakeruは『疲れた!』を連発,途中で動けなくなって道に寝転がったりしながらも1時間ほど歩いて7:13光城山着。朝日の当たる場所を選んで朝食を摂る。


Takeruがこの後どの程度歩けるかは本人の体力とやる気次第と言うことになっており、休んで元気を取り戻したかにも見えたが、Takeru父はここまでと判断したようで下山口に母親を呼ぶ電話をかけ、本人は後は下るだけと分かるとケロッとして元気よく歩き始める。子どもの登山なんてこんなものだろう。無理強いして登山嫌いにさせないことだ。


山頂でJun1さんと合流した後、早々に下山して安曇野ピースウォーク前半の早朝登山を終了。武君,早朝から寒い中,よく頑張った。またネッ!
ここから早春賦碑までの歩きは時間の関係でスイス村までをカットしてJun1さんの車で移動し、犀川土手から歩くことにする。
2010年01月20日
上田市・太郎山~虚空蔵山縦走・後
太郎山~虚空蔵山縦走・後
10年1月17日(日) 参加者:じゅんちゃ&木偶野呂馬 記録:木偶野呂馬


北ア蓮華・北葛・唐沢岳方面/雪道を行く
太郎山方虚空蔵山へ
11:00発,階段を登り神社の裏側をすり抜けて太郎山に向かい、5~6分で山頂(1164m)に着くとそこからは雪山だった。神社からの展望に加えて北側の山々,根子岳や四阿山,烏帽子岳,浅間山等が望まれるようになり、また北アルプスの蓮華岳以北の山々もよく見えるようになる。


西峠にて/マップ
大勢の登山者もほとんどが太郎山止まりで、そこから虚空蔵山に向けて縦走する者はいないが踏み跡はある。11:25発,西に向かって伸びる稜線をそのまま下ると程なく境内の展望広場からの道を合わせ、5分ほどで西峠に着く(11:32)。北側からわずかに風があるが陽射しは暖かくルンルンの稜線漫歩となる。


ここでお昼/虚空蔵山かと思った
11:52,1069mのピーク付近で南向きの暖かな草地に腰を下ろして昼食を摂り、12:15出発。しばらく後に木の間越しにそれらしいピークが見え、その間の大きな弛みを下るとその鞍部辺りが大覗きである。そこから市街地に下る道があり虚空蔵山登頂後はそこまで戻って下る予定で12 :20に通過。


最後の登りかと思ったが・・/向こうのピークだった
直下から見上げる件のピークはちょっとした岩峰で、アイゼンのないプラブーツは滑りやすくやや手間取る。12:44にそのピーク(1073m)に到達,だそれは目指す山ではなく、虚空蔵山は目の前の小ピークを越えたさらに先で行くか止めるかちょっとためらう距離にあった。そこに一団の登山者の姿が見えているのを見て前進する。jun1さんはここで軽アイゼンを装着。


虚空蔵山にて/烏帽子岳を望む
13:02,最後のロープ場を登り切って虚空蔵山に着くと、入れ違いに一団のパーティーが太郎山に向けて出発し山頂一帯は急に静かになる。13:12,どこまでも晴れ渡る山々を目に納めて下山開始。ロープ場のすぐ下からの踏み跡を辿って直下降する。


兎峰分岐/ロープ場あり
前世紀の遺物とも言えるプラブーツでの雪のない岩場の下りには最悪である。この靴はくるぶしをスッポリ覆っているので岩場の凹凸を足首で吸収して柔軟に対応することが出来ない。なので思い切って次のステップを踏み出せず歩きのリズムがつくれない。スキー靴を履いて歩くほどではないが、靴によって動きを支配されてしまいおっかなびっくりの腰の引けた歩きになってしまう上に上半身の揺れが大きくなり疲れる。フラットな雪面にフィットしてこそのプラブーツであることがよく分かった。


座摩神社/縁起
13:24,兎峰と言う岩峰に向かう道と、それを迂回する道の分岐で北側をトラバースする峰を選んで滑りやすいロープ場をさらに下り、ようやく緩やかになった辺りで10分の休憩。14:00,送電線鉄塔(№23)を通過,14:06,座摩神社着。そこからは車道があり、大休止の後人家のある平地に下りる(14:34)。


兎峰に登山者が見える/登山口着
14:45,市街地から上田バイパスに出て見上げるとそそり立つ兎峰の岩峰に登山者の姿が認められた。4km歩いて15:40,登山口へ戻り終了。


鹿教温泉文殊堂/氷の灯篭
帰途、久々に鹿教湯温泉に浸かる。文殊堂に向かう道が氷の灯篭でライトアップされて幻想的な雰囲気を醸していた。


付 時代の終焉
90年頃に買ったプラブーツが壊れた。10年間の空白のおかげでかさしたる劣化も見られず未だ使い続けていたのだが、遂に終焉の時は来た。
プラブーツの利点はインナーブーツがあり、それが足に柔らかくフィットして履き心地がよく、また雪山の幕営時、テントから外に出る際にいちいち靴を履かず、インナーだけで出られるので非常に重宝することだ。
一方で突然破壊と言う問題があって90年代には国会でも取り上げられたことがあり、常に不安がつきまとう靴でもあった。実際、壊れたブーツからそのインナーブーツを取り出してみると、プラの本体は底の部分を除くと極めて薄っぺらで決して頑丈とは言えないつくりだったことが分かり、壊れてもおかしくない気がした。
破損部は上部のフックがついた部分が本体から引きちぎれそうになったもので、突然破壊とは言えないが引きちぎれるのは時間の問題となっているので今後の使用には耐えられそうにない。
時代はすでにプラブーツを越えて今では顧みられなくなっている遺物であるが、自分にとっては重宝なだけでなく数々の恩恵を与えてくれた大切な存在だった。


革靴も駄目になって今現在登山靴がないのでたちまちの山行にも支障が出てしまい困ったことになった。リスクの高い稜線では論外だが、単なる雪道ならシュリンゲでぐるぐる巻きにしてでももう1~2回使うつもりではある。
10年1月17日(日) 参加者:じゅんちゃ&木偶野呂馬 記録:木偶野呂馬


北ア蓮華・北葛・唐沢岳方面/雪道を行く
太郎山方虚空蔵山へ
11:00発,階段を登り神社の裏側をすり抜けて太郎山に向かい、5~6分で山頂(1164m)に着くとそこからは雪山だった。神社からの展望に加えて北側の山々,根子岳や四阿山,烏帽子岳,浅間山等が望まれるようになり、また北アルプスの蓮華岳以北の山々もよく見えるようになる。


西峠にて/マップ
大勢の登山者もほとんどが太郎山止まりで、そこから虚空蔵山に向けて縦走する者はいないが踏み跡はある。11:25発,西に向かって伸びる稜線をそのまま下ると程なく境内の展望広場からの道を合わせ、5分ほどで西峠に着く(11:32)。北側からわずかに風があるが陽射しは暖かくルンルンの稜線漫歩となる。


ここでお昼/虚空蔵山かと思った
11:52,1069mのピーク付近で南向きの暖かな草地に腰を下ろして昼食を摂り、12:15出発。しばらく後に木の間越しにそれらしいピークが見え、その間の大きな弛みを下るとその鞍部辺りが大覗きである。そこから市街地に下る道があり虚空蔵山登頂後はそこまで戻って下る予定で12 :20に通過。


最後の登りかと思ったが・・/向こうのピークだった
直下から見上げる件のピークはちょっとした岩峰で、アイゼンのないプラブーツは滑りやすくやや手間取る。12:44にそのピーク(1073m)に到達,だそれは目指す山ではなく、虚空蔵山は目の前の小ピークを越えたさらに先で行くか止めるかちょっとためらう距離にあった。そこに一団の登山者の姿が見えているのを見て前進する。jun1さんはここで軽アイゼンを装着。


虚空蔵山にて/烏帽子岳を望む
13:02,最後のロープ場を登り切って虚空蔵山に着くと、入れ違いに一団のパーティーが太郎山に向けて出発し山頂一帯は急に静かになる。13:12,どこまでも晴れ渡る山々を目に納めて下山開始。ロープ場のすぐ下からの踏み跡を辿って直下降する。


兎峰分岐/ロープ場あり
前世紀の遺物とも言えるプラブーツでの雪のない岩場の下りには最悪である。この靴はくるぶしをスッポリ覆っているので岩場の凹凸を足首で吸収して柔軟に対応することが出来ない。なので思い切って次のステップを踏み出せず歩きのリズムがつくれない。スキー靴を履いて歩くほどではないが、靴によって動きを支配されてしまいおっかなびっくりの腰の引けた歩きになってしまう上に上半身の揺れが大きくなり疲れる。フラットな雪面にフィットしてこそのプラブーツであることがよく分かった。


座摩神社/縁起
13:24,兎峰と言う岩峰に向かう道と、それを迂回する道の分岐で北側をトラバースする峰を選んで滑りやすいロープ場をさらに下り、ようやく緩やかになった辺りで10分の休憩。14:00,送電線鉄塔(№23)を通過,14:06,座摩神社着。そこからは車道があり、大休止の後人家のある平地に下りる(14:34)。


兎峰に登山者が見える/登山口着
14:45,市街地から上田バイパスに出て見上げるとそそり立つ兎峰の岩峰に登山者の姿が認められた。4km歩いて15:40,登山口へ戻り終了。


鹿教温泉文殊堂/氷の灯篭
帰途、久々に鹿教湯温泉に浸かる。文殊堂に向かう道が氷の灯篭でライトアップされて幻想的な雰囲気を醸していた。


付 時代の終焉
90年頃に買ったプラブーツが壊れた。10年間の空白のおかげでかさしたる劣化も見られず未だ使い続けていたのだが、遂に終焉の時は来た。
プラブーツの利点はインナーブーツがあり、それが足に柔らかくフィットして履き心地がよく、また雪山の幕営時、テントから外に出る際にいちいち靴を履かず、インナーだけで出られるので非常に重宝することだ。
一方で突然破壊と言う問題があって90年代には国会でも取り上げられたことがあり、常に不安がつきまとう靴でもあった。実際、壊れたブーツからそのインナーブーツを取り出してみると、プラの本体は底の部分を除くと極めて薄っぺらで決して頑丈とは言えないつくりだったことが分かり、壊れてもおかしくない気がした。
破損部は上部のフックがついた部分が本体から引きちぎれそうになったもので、突然破壊とは言えないが引きちぎれるのは時間の問題となっているので今後の使用には耐えられそうにない。
時代はすでにプラブーツを越えて今では顧みられなくなっている遺物であるが、自分にとっては重宝なだけでなく数々の恩恵を与えてくれた大切な存在だった。


革靴も駄目になって今現在登山靴がないのでたちまちの山行にも支障が出てしまい困ったことになった。リスクの高い稜線では論外だが、単なる雪道ならシュリンゲでぐるぐる巻きにしてでももう1~2回使うつもりではある。
2010年01月19日
上田市・太郎山~虚空蔵山縦走
太郎山~虚空蔵山縦走・前
10年1月17日(日) 参加者:じゅんちゃ&木偶 記録者:木偶野呂馬


左:縦走路からの太郎山 右:上田市街を見下ろす
jnu1さんにお任せで上田市と坂城町の境にある太郎山,虚空蔵山を縦走する。上田近辺の山はまったく未知であるし、当初は近場で雪山ハイキング出来る山を~と言うことだったので完全装備で現地に着いてみたら何と半袖の山だった。
太郎山はこの地方では人気の山で登山口付近の道路には車がズラリと並んでおり、老若男女沢山の登山者がハイキングシューズで次々と登って行く。またすでに下りて来る人もあり、jun1さんは『安曇野で言えば光城山みたいな山らしい』と言う。そんな中での雪山対応のプラブーツはいささか奇異に見えたかもしれないがそれしかなかったのでいたしかたなし。


左:登山口 右:祠あり
9:22発。快晴で陽射しのある所は暖かく地面が緩み始めているが、南東稜を登る登山道は殆どがコナラなどの樹林帯の中で雪が残っており、それが凍って滑りやすく意外と歩きにくい。雪山のつもりだったので軽アイゼンは持っていないし、10本爪を履くわけにもいかないので恐るおそる登る羽目になる。長袖シャツを着て歩き始めたが、直に暑くなり半袖になる。


左:赤門 右:太郎神社
この地方特有の祠や里程標を見ながらゆっくり登って40分で『太郎山神社』と書かれた鳥居を通り、さらに40分で赤い鳥居のある山門の先の石段を登って10:46太郎神社に着く。


左:関東富士見100選碑 右:北ア蓮華岳方面
神社はまったくの日陰で冷蔵庫のような寒さだが、山門に戻って南側に廻るとそこは東~南~西に向けて開けた明るい展望広場で、東の烏帽子岳から浅間の外輪山,秩父山塊,八ヶ岳・蓼科山,南アルプス,霧が峰,美ヶ原,を隔てて西の北アルプスに至る山々が望まれ、また眼下に上田市や青木村の街並みを見下ろすことが出来た。よく晴れていて富士山もスッキリ見えており『関東富士見100選』の1つである。


左:八ヶ岳の裾野と富士 右:蓼科山・八ヶ岳
太郎神社からの展望でアルプスや八ヶ岳,秩父山塊等の遠景の山々以上に興味深かいのは、南南西方向に端正なたたずまいを見せる夫神岳とそれをそのまま持ち上げて南に大きく傾けたような子檀嶺(こまゆみ)岳,そこから始まって十観山,御鷹山,入山,二ツ石峰,保福寺峠,三才山,戸谷峰と連なる山なみや女神岳,独鈷山等,青木村を取り巻く山々である。


左:境界線ラインの右端に子檀嶺(こまゆみ)岳,ラインの左にある端正な山が夫神岳
右:十観山~御鷹山~入山~二ツ石峰~三才山~戸谷峰の境界線ライン
特に保福寺峠から十観山に至る旧四賀村と青木村の境界線の山なみは、これまで冬期縦走を目論みながらも保福寺峠への道が通行不能になるために手を拱いていたのだが、それを逆方向から見ると十観山から保福寺峠まで縦走してピストンするか鹿教湯温泉に下るというコース取りもあり得ると言うことに気づかされ、大いに参考になった。いつもとは違う方向から山を見るのも時に必要なことだと言うことを教えられた気がする。
10年1月17日(日) 参加者:じゅんちゃ&木偶 記録者:木偶野呂馬


左:縦走路からの太郎山 右:上田市街を見下ろす
jnu1さんにお任せで上田市と坂城町の境にある太郎山,虚空蔵山を縦走する。上田近辺の山はまったく未知であるし、当初は近場で雪山ハイキング出来る山を~と言うことだったので完全装備で現地に着いてみたら何と半袖の山だった。
太郎山はこの地方では人気の山で登山口付近の道路には車がズラリと並んでおり、老若男女沢山の登山者がハイキングシューズで次々と登って行く。またすでに下りて来る人もあり、jun1さんは『安曇野で言えば光城山みたいな山らしい』と言う。そんな中での雪山対応のプラブーツはいささか奇異に見えたかもしれないがそれしかなかったのでいたしかたなし。


左:登山口 右:祠あり
9:22発。快晴で陽射しのある所は暖かく地面が緩み始めているが、南東稜を登る登山道は殆どがコナラなどの樹林帯の中で雪が残っており、それが凍って滑りやすく意外と歩きにくい。雪山のつもりだったので軽アイゼンは持っていないし、10本爪を履くわけにもいかないので恐るおそる登る羽目になる。長袖シャツを着て歩き始めたが、直に暑くなり半袖になる。


左:赤門 右:太郎神社
この地方特有の祠や里程標を見ながらゆっくり登って40分で『太郎山神社』と書かれた鳥居を通り、さらに40分で赤い鳥居のある山門の先の石段を登って10:46太郎神社に着く。


左:関東富士見100選碑 右:北ア蓮華岳方面
神社はまったくの日陰で冷蔵庫のような寒さだが、山門に戻って南側に廻るとそこは東~南~西に向けて開けた明るい展望広場で、東の烏帽子岳から浅間の外輪山,秩父山塊,八ヶ岳・蓼科山,南アルプス,霧が峰,美ヶ原,を隔てて西の北アルプスに至る山々が望まれ、また眼下に上田市や青木村の街並みを見下ろすことが出来た。よく晴れていて富士山もスッキリ見えており『関東富士見100選』の1つである。


左:八ヶ岳の裾野と富士 右:蓼科山・八ヶ岳
太郎神社からの展望でアルプスや八ヶ岳,秩父山塊等の遠景の山々以上に興味深かいのは、南南西方向に端正なたたずまいを見せる夫神岳とそれをそのまま持ち上げて南に大きく傾けたような子檀嶺(こまゆみ)岳,そこから始まって十観山,御鷹山,入山,二ツ石峰,保福寺峠,三才山,戸谷峰と連なる山なみや女神岳,独鈷山等,青木村を取り巻く山々である。


左:境界線ラインの右端に子檀嶺(こまゆみ)岳,ラインの左にある端正な山が夫神岳
右:十観山~御鷹山~入山~二ツ石峰~三才山~戸谷峰の境界線ライン
特に保福寺峠から十観山に至る旧四賀村と青木村の境界線の山なみは、これまで冬期縦走を目論みながらも保福寺峠への道が通行不能になるために手を拱いていたのだが、それを逆方向から見ると十観山から保福寺峠まで縦走してピストンするか鹿教湯温泉に下るというコース取りもあり得ると言うことに気づかされ、大いに参考になった。いつもとは違う方向から山を見るのも時に必要なことだと言うことを教えられた気がする。
2009年12月26日
飯山,柄山スノーシューハイク
雪の野山を歩くスノーシュー&歩くスキーハイク
里山楽会・境界線2月山行 参加者:木偶野呂馬,他7名 記録者:木偶野呂馬


09年2月14日(土)
奈良市の友人,M氏が飯山市柄山に古民家を借りており、雪かきをすることを条件に自由に使わせてもらえることになっているので、その古民家を宿舎として、雪の野山を歩くスノーシュー&歩くスキーハイクを企画した。おりしもM氏が彼の友人で近年奈良から安曇野に移住したS氏を伴って柄山に来ており、我が境界線のメンバーと併せて8名の賑やかな山行となった。


例年よりはるかに少ないとは言え雪は軒のすぐ下まであり、1日早く着いたM氏とS氏が前日から頑張ったそうだが、玄関周りも庭もまだまだ大量の雪が・・。
すぐに全員で作業にかかり、人数にものを言わせて奮闘2時間弱で地面が見えるほどになった。M氏も『ここまでになるとは・・』と満足そう。
昼食後,さっそく裏山のブナ林から上の農場方面に向けてスノーシューハイキングに出かける。その案内をM氏に任せて1人残り、夜の宴の準備にかかる。


ハイキングを終えて冷えた身体を地元の温泉で温め、夜は暖かい部屋で合成にブイヤベースを囲んで持ち寄りの地酒を酌み交わしながら交流・・。
自己紹介を兼ねてそれぞれの山への思いをこもごもに語るうちに初対面同士和やかにうちとけて宴たけなわとなり、かくして柄山の夜はふける・・。


2月15日(日)
温井と柄山をつなぐ農道『みゆきのライン』のスノーシェードのある辺りからスノーシュー,スキーに履き替え、広大な農地の雪原を歩いて信越トレイル稜線上の梨平峠を目指す。農地を越えて距離3kmあまりの尾根を登る。
前日の重苦しく暗い空から一転してピーカンの空模様となり、8時過ぎにして早くも陽射しが暑く汗が目に入る。シールのある山スキーならともかく歩くスキーでの登高には無理があり、立ちはだかる斜面に最初からたじろぐ。


歩き始めて30分,鍋倉山を望む丘に出た。そこから目の前の大きなピークに向けての本格的な登りとなり、小気味よく登って行くスノーシュー組からは大きく遅れてしまった。一歩一歩ステップを切って階段登高で行くしかなく、ゆっくり追いかけると腹を決めた。急斜面との格闘20分でピークに這い上がり、ようやく先行するスノーシューを捉える。前方に信越トレイルの稜線が見えてきた。


そこから先に広大な農地が広がっており、緩やかになった斜面を登り詰めて行くと、『この林を切り開いて農地にしました』と見本のようにブナ林が残されている場所に出た。抜けるような青空が広がり、ジリジリと照りつける太陽が眩しくも暑くもあって日陰が欲しい頃合いだったのでそこから林の中に入る。


過密なほどの若いブナの純林を進むうちにそこがまだ開発されていない山林の末端であることが分かる。ひときわ目を引く瘤を抱えた特異な風貌のブナを見る。このような巨大なものは珍しい。
例年の3分の1しか無いと地元の人が言うほど雪の無い冬。豪雪地帯の飯山にしてこの有様で、早くも根回り穴が口を空けている。4月下旬の様相だ。


密林を抜けるとやや疎林となるがどこまでも続くブナ林である。そこから本格的な登りが始まるり、やがて急斜面の連続となる尾根ではスノーシューが抜群の威力を発揮するのに比べて歩くスキーは四苦八苦して一行からは大きく遅れ、奮闘4時間弱でようやく稜線に到達。そこはしかし目指す梨平峠より一山北よりだと言うことが分かり、スキーでその山を越えて梨平峠を目指すのを断念する。一行の中、M氏とS氏の2人が峠まで行って来るのを待って下山する。


歩くスキーでの急斜面の下山は登り以上に難しく、あまりの急斜面ではスキーを脱いでツボ足で下ったり、スキーを流して谷底まで回収に行ったりと散々で、帰りも大幅に遅れを取った。
それでもスノーシューを履く気にはなれないので、次からはどこかでスキーをデポしてワカンで歩くことにする。


里山楽会・境界線2月山行 参加者:木偶野呂馬,他7名 記録者:木偶野呂馬


09年2月14日(土)
奈良市の友人,M氏が飯山市柄山に古民家を借りており、雪かきをすることを条件に自由に使わせてもらえることになっているので、その古民家を宿舎として、雪の野山を歩くスノーシュー&歩くスキーハイクを企画した。おりしもM氏が彼の友人で近年奈良から安曇野に移住したS氏を伴って柄山に来ており、我が境界線のメンバーと併せて8名の賑やかな山行となった。


例年よりはるかに少ないとは言え雪は軒のすぐ下まであり、1日早く着いたM氏とS氏が前日から頑張ったそうだが、玄関周りも庭もまだまだ大量の雪が・・。
すぐに全員で作業にかかり、人数にものを言わせて奮闘2時間弱で地面が見えるほどになった。M氏も『ここまでになるとは・・』と満足そう。
昼食後,さっそく裏山のブナ林から上の農場方面に向けてスノーシューハイキングに出かける。その案内をM氏に任せて1人残り、夜の宴の準備にかかる。


ハイキングを終えて冷えた身体を地元の温泉で温め、夜は暖かい部屋で合成にブイヤベースを囲んで持ち寄りの地酒を酌み交わしながら交流・・。
自己紹介を兼ねてそれぞれの山への思いをこもごもに語るうちに初対面同士和やかにうちとけて宴たけなわとなり、かくして柄山の夜はふける・・。


2月15日(日)
温井と柄山をつなぐ農道『みゆきのライン』のスノーシェードのある辺りからスノーシュー,スキーに履き替え、広大な農地の雪原を歩いて信越トレイル稜線上の梨平峠を目指す。農地を越えて距離3kmあまりの尾根を登る。
前日の重苦しく暗い空から一転してピーカンの空模様となり、8時過ぎにして早くも陽射しが暑く汗が目に入る。シールのある山スキーならともかく歩くスキーでの登高には無理があり、立ちはだかる斜面に最初からたじろぐ。


歩き始めて30分,鍋倉山を望む丘に出た。そこから目の前の大きなピークに向けての本格的な登りとなり、小気味よく登って行くスノーシュー組からは大きく遅れてしまった。一歩一歩ステップを切って階段登高で行くしかなく、ゆっくり追いかけると腹を決めた。急斜面との格闘20分でピークに這い上がり、ようやく先行するスノーシューを捉える。前方に信越トレイルの稜線が見えてきた。


そこから先に広大な農地が広がっており、緩やかになった斜面を登り詰めて行くと、『この林を切り開いて農地にしました』と見本のようにブナ林が残されている場所に出た。抜けるような青空が広がり、ジリジリと照りつける太陽が眩しくも暑くもあって日陰が欲しい頃合いだったのでそこから林の中に入る。


過密なほどの若いブナの純林を進むうちにそこがまだ開発されていない山林の末端であることが分かる。ひときわ目を引く瘤を抱えた特異な風貌のブナを見る。このような巨大なものは珍しい。
例年の3分の1しか無いと地元の人が言うほど雪の無い冬。豪雪地帯の飯山にしてこの有様で、早くも根回り穴が口を空けている。4月下旬の様相だ。


密林を抜けるとやや疎林となるがどこまでも続くブナ林である。そこから本格的な登りが始まるり、やがて急斜面の連続となる尾根ではスノーシューが抜群の威力を発揮するのに比べて歩くスキーは四苦八苦して一行からは大きく遅れ、奮闘4時間弱でようやく稜線に到達。そこはしかし目指す梨平峠より一山北よりだと言うことが分かり、スキーでその山を越えて梨平峠を目指すのを断念する。一行の中、M氏とS氏の2人が峠まで行って来るのを待って下山する。


歩くスキーでの急斜面の下山は登り以上に難しく、あまりの急斜面ではスキーを脱いでツボ足で下ったり、スキーを流して谷底まで回収に行ったりと散々で、帰りも大幅に遅れを取った。
それでもスノーシューを履く気にはなれないので、次からはどこかでスキーをデポしてワカンで歩くことにする。


2009年12月24日
虫倉山
山姥伝説・虫倉山不動滝コース~元日登山・1
09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏


2009年の元日登山は中条村の虫倉山(1378m)。
林道終点に車を止めて5:45発。知らない山なのでリードを相方のじゅんちゃにまかせっきりで暗い道をただついていくだけ。


6:34 木の間越しに東の空が赤く染まるのを見る。肝心な時にはいつも言うことを聞かないカメラをなだめすかしている間に相方から大きく遅れ、山頂に着いたのは日の出の後だった。


着く早々にお屠蘇をふるまわれる。虫倉山には2パーティー,約10名の先客が古典的な新年の宴を張っていた。すなわち60~70年代型の大きなコッヘェルに将棋の駒型の煤けたポリタンク,コンロだけは現代風のガスでつくるのはもちろん雑煮。油を持参してフライパンで揚げてから煮ているパーティーもあって本腰だ。1つは地元中条村,もう1つは信州新町からのパーティーで恒例の新年登山のようだ。


はじめから薄着で登ればよかったものを、バッチリかためて歩き始めたのでいつもより余分に汗をかいてしまった。思い切ってシャツを脱いで乾かす。
天候は悪くはないのだがめまぐるしく動くガスが山頂付近にあり、指呼の間の戸隠山はおろか、妙高・火打方面も白馬・北アルプス方面も展望が利かず、長居は無用と早々に下山する。


登りは5:45発,7:18着,1時間35分。下りは7:45発,8:35着,50分。


09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏


2009年の元日登山は中条村の虫倉山(1378m)。
林道終点に車を止めて5:45発。知らない山なのでリードを相方のじゅんちゃにまかせっきりで暗い道をただついていくだけ。


6:34 木の間越しに東の空が赤く染まるのを見る。肝心な時にはいつも言うことを聞かないカメラをなだめすかしている間に相方から大きく遅れ、山頂に着いたのは日の出の後だった。


着く早々にお屠蘇をふるまわれる。虫倉山には2パーティー,約10名の先客が古典的な新年の宴を張っていた。すなわち60~70年代型の大きなコッヘェルに将棋の駒型の煤けたポリタンク,コンロだけは現代風のガスでつくるのはもちろん雑煮。油を持参してフライパンで揚げてから煮ているパーティーもあって本腰だ。1つは地元中条村,もう1つは信州新町からのパーティーで恒例の新年登山のようだ。


はじめから薄着で登ればよかったものを、バッチリかためて歩き始めたのでいつもより余分に汗をかいてしまった。思い切ってシャツを脱いで乾かす。
天候は悪くはないのだがめまぐるしく動くガスが山頂付近にあり、指呼の間の戸隠山はおろか、妙高・火打方面も白馬・北アルプス方面も展望が利かず、長居は無用と早々に下山する。


登りは5:45発,7:18着,1時間35分。下りは7:45発,8:35着,50分。


2009年12月23日
南沢岳から不動岳・船窪岳~七倉へ
南沢岳から不動岳・船窪岳~七倉へ
北アルプス裏銀座,逆縦走
6月14日(日) 木偶野呂馬&G3氏
1;コース状況/その他周辺情報:

③南沢岳から不動岳に向かう鞍部の手前で大量の雪のため道は分からなくなり、稜線の縁を避けて左に寄るあまり下がり過ぎてしまった。このため南沢岳から不動岳まで2時間半を要して大きな遅れが生じた。不動岳から船窪岳まではアップダウンが激しく、また鞍部付近に悪場がある上にここでも大量の雪で難渋させられ、大幅に時間をロスして船窪小屋着が予定より4時間近く遅れた。
④本来なら1泊では無理な行程であり、船窪小屋に16時過ぎに着いたことをよしとしてここでもう1泊すべきであるしその用意もあったが、夜道に日暮れ無しと言うことで真っ暗闇の中、下山を強行した結果5時間を要した。



2;行動の記録
6月14日(日)
4時になるのを待って起きる。前夜食べなかったアルファ米1袋とレトルトのカレーがあったが、これを湯煎するのもまた用意したアルファ米のリゾットを湯戻しするのも時間がかかるので、お湯を沸かして残った握り飯と簡単スープを流し込む。融かした雪でお茶を作って飲料を確保し、6:00出発。
6:08,南沢岳の三角点を通過。前日,通過したピークは山頂ではなかったようで、標高2625mは今回の縦走最高地点。目の前には不動岳西面の大崩れが見えているが、その間には南沢乗越の深い切れ込みがあってここからは200mあまりの下りとなる。



不動岳西側の高瀬ダム側は、前日最後に渡った濁沢の源頭部に当たっており激しく崩落している。それは乗越を隔てたこちら側の南沢岳も同じで、登山道は稜線の縁である崩落した部分とハイマツ帯の境目を通っているので気が抜けない。
この辺りから残雪が多くなり、雪の急斜面の下降を余儀なくされる場面もしばしばで、その途中でスリップして5mほど滑りハイマツ帯に突っ込む。しばらくの後腕時計がなくなっているのに気づいたが引き返すにはすでに遅すぎた。
そう言う雪で寸断された難しい道であっても、雪が融けた所には春が来て草が芽吹き、花が咲く。
6:45,南沢乗越を通過して大きくガレた不動岳の前ピークの登りに入る。西面は急登だが雪がなく花が豊富で、ユキザサに混じってキヌガサソウやショウジョウバカマが見られるようになる。キヌガサソウの芽だしはユキザサをそのまま太くしたような感じで両者が非常によく似ていることを知る。



ふり返ると先ほど下ってきた南沢岳からの道がよく分かり、またはるか遠方には烏帽子岳の奇怪な山頂を望むことができた。
7:25,前ピークに到達。10分休んで展望を楽しむ。南沢岳からここまでは1時間25分。大幅ではないが予定をややオーバーしているのは雪が多いせいか・・。
7:35分。不動岳まで順調に行けば20分ほどの道であるが、ここから登山道が完全に雪に閉ざされて分からなくなった。右側の様子が分からないので稜線の縁を避けて左側の雪面を斜めに下り、樹林帯を突破しようとしているうちに稜線からかなり離れた位置まで下ってしまった。
道を見失い、遮二無二ブッシュをかき分けて抜けると広くて分厚い雪の斜面に突き当たる。幅40m,下に向かってどこまでも続く大斜面で長さは計り知れない。目印を探したが何もなく、その上悪いことにG氏が潅木に眼鏡を取られて探しに戻るというアクシデントが起きた。
ここは斜面を登って稜線に出る道を探すか、ハイマツ帯を突破するしかないと覚悟を決めて急斜面を登る。
雪の斜面を斜めに横断しながら登りきると道があった。上からハイマツを踏んで下ってくるなら兎も角、下からハイマツ帯を突破して登る等,口では言えてもできるものではない。この道がなかったら稜線に出るのは不可能に近く、樹林帯に迷い込んだ位置まで戻るしかなかったかもしれない。
8:35不動岳着。テン場から2時間35分と夏道の2倍の時間を要し大幅に遅れが出た。倒れた山頂標識を2人で立て直したり、写真を撮ったりしてやや長めの休憩をとる。烏帽子ははるか遠くなり、南沢岳にかけてガスが立ち始めていた。



8:55発。しばらくは不動沢側が大きくガレた稜線の縁を歩く。黒部側がハイマツ帯なので問題はないが、道の所々にひびが入っていてその道もいずれは崩落していくものと思われた。前日の大腿部側方の痛みは跡形もなく消えたが、この日は下りの際の深い屈曲で大腿部前面に痙攣が来ており、一抹の不安を抱えたまま船窪岳への登りにかかる。
目標までに第2ピークを含むまで3つのピークを越えなければならず、船窪小屋までは5時間弱,七倉へはさらに4時間の下降で明るいうちに下山するのは難しい情勢になってきた。



9:38,1つ目のピークにかかる。穏やかな登りでミツバオーレンの花に混じって何故かツルリンドウの赤い実が見られた。
10:07,2341mのピークに到達。目の前に第2ピークへと続く岩稜帯の岩肌を見る。日当たりのいい岩場の縁にコイワカガミが咲き、少し樹林帯に寄った辺りにはショウジョウバカマが見られる。



ロープやワイヤーのある岩場をさらに1時間40分歩き、それとわからぬままに2つ目のピーク(2299m)を越えて11:55船窪第2P(2459m)に着く。不動岳から3時間,この間にいくつものアップダウンがあり、その度に雪渓があって大幅に時間を食い、目標とする時刻より1時間近い遅れが生じていた。
ここから船窪乗越までは夏道で1時間10分,船窪小屋まではさらに1時間10分を要するので14時までに小屋へ着くのは難しいかもしれないが、ビバークの用意はあるので花を見ながら急がずに歩いてきた。



雪に覆われた第2Pからはガスで東半分を隠されて槍のように天を突く唐沢岳や七倉岳方面,最後の稜線歩きとなる船窪CP場への道,また北北東から真北にかけて蓮華岳・針の木岳の大きな山塊を見る。
12:20発。ここから船窪岳までの道は小さなアップダウンにワイヤーと梯子が連続し、足場の定まらない場所もある不安定な道。12:57,小さな鞍部を越えて急登にかかるとそこからシラネアオイの大群落が始まり、感嘆の声を上げながらしばらくは写真に没頭。最後にミネザクラの花を見るが、そこから最も険悪な鞍部への足場の悪い急降下となる。
邪魔なワイヤーを避けながら下りきるとすぐに登り返しとなるが、掴んだ岩が脆くて剥がれ、岩を抱いたまま背中から1mほどずり落ちる。右手(稜線側)の岩が谷側にせり出しているので逆コース(下り=前回)にとってはさらに難しい所だ。13:20に通過。
悪場はさらに続き、壊れた丸太の足場,半ば腐ったロープ場を越えてひと登りでようやく崩れた稜線の縁に出る。10分で船窪岳に着(13:41)き、20分の休憩。



14:00発。下って14:07船窪乗越を通過。前回は針の木谷から登って来てここで烏帽子岳へのコースに合流したのでここから先は未知のルートとなる。
乗越を越えると北葛岳が正面になり、どんどんとそちらに近づいて行く感じになる。船窪・七倉岳への道はそこから大きく右に曲がり、やがて北葛岳が遠のいて正面に七倉岳が見えてくる。
14:34,再び現れたシラネアオイの花を撮る間にG氏が先行。ここまで水の量に不安があり雪を食べながら歩いて来たので水場のあるキャンプ場の位置が気になって仕方がない。



14:54,再び稜線の縁に出て眼下に不動沢最深部の荒々しい岩場を見る。暑くなり渇きを覚え、水場を期待しつつさらに20分歩いて15:14,キャンプ場に着く。水を確保できることで安心する。
だがキャンプ場に期待した水場はなく、あったのは雪田の下部に出来た小さな水溜りだった。水面に小さな虫が浮いてはいるが水は澄んでいるので濁らせないように静かにボトルに詰めてそれを飲み、さらにもう1本のボトルに詰めて船窪からの下りに備えることにする。虫の死骸などもはや気にもならない。
本来の水場は北葛側の谷の方にあったらしいのだが、そちらを探す余裕はなかったのだ。



15:39発。階段を登って右にゆっくり斜上する道を行く。その道は不動岳からずっと見えていた七倉岳の尾根に向かう道であり、船窪小屋はその尾根のラインの向こう側にある。
16:03七倉・北葛岳方面に向かう分岐点を通過。16:08明るいハイマツ帯の中、青い屋根の船窪小屋見る。16:11着。



以下,編集中
北アルプス裏銀座,逆縦走
6月14日(日) 木偶野呂馬&G3氏
1;コース状況/その他周辺情報:

③南沢岳から不動岳に向かう鞍部の手前で大量の雪のため道は分からなくなり、稜線の縁を避けて左に寄るあまり下がり過ぎてしまった。このため南沢岳から不動岳まで2時間半を要して大きな遅れが生じた。不動岳から船窪岳まではアップダウンが激しく、また鞍部付近に悪場がある上にここでも大量の雪で難渋させられ、大幅に時間をロスして船窪小屋着が予定より4時間近く遅れた。
④本来なら1泊では無理な行程であり、船窪小屋に16時過ぎに着いたことをよしとしてここでもう1泊すべきであるしその用意もあったが、夜道に日暮れ無しと言うことで真っ暗闇の中、下山を強行した結果5時間を要した。



2;行動の記録
6月14日(日)
4時になるのを待って起きる。前夜食べなかったアルファ米1袋とレトルトのカレーがあったが、これを湯煎するのもまた用意したアルファ米のリゾットを湯戻しするのも時間がかかるので、お湯を沸かして残った握り飯と簡単スープを流し込む。融かした雪でお茶を作って飲料を確保し、6:00出発。
6:08,南沢岳の三角点を通過。前日,通過したピークは山頂ではなかったようで、標高2625mは今回の縦走最高地点。目の前には不動岳西面の大崩れが見えているが、その間には南沢乗越の深い切れ込みがあってここからは200mあまりの下りとなる。



不動岳西側の高瀬ダム側は、前日最後に渡った濁沢の源頭部に当たっており激しく崩落している。それは乗越を隔てたこちら側の南沢岳も同じで、登山道は稜線の縁である崩落した部分とハイマツ帯の境目を通っているので気が抜けない。
この辺りから残雪が多くなり、雪の急斜面の下降を余儀なくされる場面もしばしばで、その途中でスリップして5mほど滑りハイマツ帯に突っ込む。しばらくの後腕時計がなくなっているのに気づいたが引き返すにはすでに遅すぎた。
そう言う雪で寸断された難しい道であっても、雪が融けた所には春が来て草が芽吹き、花が咲く。
6:45,南沢乗越を通過して大きくガレた不動岳の前ピークの登りに入る。西面は急登だが雪がなく花が豊富で、ユキザサに混じってキヌガサソウやショウジョウバカマが見られるようになる。キヌガサソウの芽だしはユキザサをそのまま太くしたような感じで両者が非常によく似ていることを知る。



ふり返ると先ほど下ってきた南沢岳からの道がよく分かり、またはるか遠方には烏帽子岳の奇怪な山頂を望むことができた。
7:25,前ピークに到達。10分休んで展望を楽しむ。南沢岳からここまでは1時間25分。大幅ではないが予定をややオーバーしているのは雪が多いせいか・・。
7:35分。不動岳まで順調に行けば20分ほどの道であるが、ここから登山道が完全に雪に閉ざされて分からなくなった。右側の様子が分からないので稜線の縁を避けて左側の雪面を斜めに下り、樹林帯を突破しようとしているうちに稜線からかなり離れた位置まで下ってしまった。
道を見失い、遮二無二ブッシュをかき分けて抜けると広くて分厚い雪の斜面に突き当たる。幅40m,下に向かってどこまでも続く大斜面で長さは計り知れない。目印を探したが何もなく、その上悪いことにG氏が潅木に眼鏡を取られて探しに戻るというアクシデントが起きた。
ここは斜面を登って稜線に出る道を探すか、ハイマツ帯を突破するしかないと覚悟を決めて急斜面を登る。
雪の斜面を斜めに横断しながら登りきると道があった。上からハイマツを踏んで下ってくるなら兎も角、下からハイマツ帯を突破して登る等,口では言えてもできるものではない。この道がなかったら稜線に出るのは不可能に近く、樹林帯に迷い込んだ位置まで戻るしかなかったかもしれない。
8:35不動岳着。テン場から2時間35分と夏道の2倍の時間を要し大幅に遅れが出た。倒れた山頂標識を2人で立て直したり、写真を撮ったりしてやや長めの休憩をとる。烏帽子ははるか遠くなり、南沢岳にかけてガスが立ち始めていた。



8:55発。しばらくは不動沢側が大きくガレた稜線の縁を歩く。黒部側がハイマツ帯なので問題はないが、道の所々にひびが入っていてその道もいずれは崩落していくものと思われた。前日の大腿部側方の痛みは跡形もなく消えたが、この日は下りの際の深い屈曲で大腿部前面に痙攣が来ており、一抹の不安を抱えたまま船窪岳への登りにかかる。
目標までに第2ピークを含むまで3つのピークを越えなければならず、船窪小屋までは5時間弱,七倉へはさらに4時間の下降で明るいうちに下山するのは難しい情勢になってきた。



9:38,1つ目のピークにかかる。穏やかな登りでミツバオーレンの花に混じって何故かツルリンドウの赤い実が見られた。
10:07,2341mのピークに到達。目の前に第2ピークへと続く岩稜帯の岩肌を見る。日当たりのいい岩場の縁にコイワカガミが咲き、少し樹林帯に寄った辺りにはショウジョウバカマが見られる。



ロープやワイヤーのある岩場をさらに1時間40分歩き、それとわからぬままに2つ目のピーク(2299m)を越えて11:55船窪第2P(2459m)に着く。不動岳から3時間,この間にいくつものアップダウンがあり、その度に雪渓があって大幅に時間を食い、目標とする時刻より1時間近い遅れが生じていた。
ここから船窪乗越までは夏道で1時間10分,船窪小屋まではさらに1時間10分を要するので14時までに小屋へ着くのは難しいかもしれないが、ビバークの用意はあるので花を見ながら急がずに歩いてきた。



雪に覆われた第2Pからはガスで東半分を隠されて槍のように天を突く唐沢岳や七倉岳方面,最後の稜線歩きとなる船窪CP場への道,また北北東から真北にかけて蓮華岳・針の木岳の大きな山塊を見る。
12:20発。ここから船窪岳までの道は小さなアップダウンにワイヤーと梯子が連続し、足場の定まらない場所もある不安定な道。12:57,小さな鞍部を越えて急登にかかるとそこからシラネアオイの大群落が始まり、感嘆の声を上げながらしばらくは写真に没頭。最後にミネザクラの花を見るが、そこから最も険悪な鞍部への足場の悪い急降下となる。
邪魔なワイヤーを避けながら下りきるとすぐに登り返しとなるが、掴んだ岩が脆くて剥がれ、岩を抱いたまま背中から1mほどずり落ちる。右手(稜線側)の岩が谷側にせり出しているので逆コース(下り=前回)にとってはさらに難しい所だ。13:20に通過。
悪場はさらに続き、壊れた丸太の足場,半ば腐ったロープ場を越えてひと登りでようやく崩れた稜線の縁に出る。10分で船窪岳に着(13:41)き、20分の休憩。



14:00発。下って14:07船窪乗越を通過。前回は針の木谷から登って来てここで烏帽子岳へのコースに合流したのでここから先は未知のルートとなる。
乗越を越えると北葛岳が正面になり、どんどんとそちらに近づいて行く感じになる。船窪・七倉岳への道はそこから大きく右に曲がり、やがて北葛岳が遠のいて正面に七倉岳が見えてくる。
14:34,再び現れたシラネアオイの花を撮る間にG氏が先行。ここまで水の量に不安があり雪を食べながら歩いて来たので水場のあるキャンプ場の位置が気になって仕方がない。



14:54,再び稜線の縁に出て眼下に不動沢最深部の荒々しい岩場を見る。暑くなり渇きを覚え、水場を期待しつつさらに20分歩いて15:14,キャンプ場に着く。水を確保できることで安心する。
だがキャンプ場に期待した水場はなく、あったのは雪田の下部に出来た小さな水溜りだった。水面に小さな虫が浮いてはいるが水は澄んでいるので濁らせないように静かにボトルに詰めてそれを飲み、さらにもう1本のボトルに詰めて船窪からの下りに備えることにする。虫の死骸などもはや気にもならない。
本来の水場は北葛側の谷の方にあったらしいのだが、そちらを探す余裕はなかったのだ。



15:39発。階段を登って右にゆっくり斜上する道を行く。その道は不動岳からずっと見えていた七倉岳の尾根に向かう道であり、船窪小屋はその尾根のラインの向こう側にある。
16:03七倉・北葛岳方面に向かう分岐点を通過。16:08明るいハイマツ帯の中、青い屋根の船窪小屋見る。16:11着。



以下,編集中
2009年12月23日
日本3坂・ブナ立尾根
日本3坂・ブナ立尾根~1日目・七倉ダムから烏帽子・南沢岳へ
北アルプス裏銀座コース・七倉ダム~烏帽子岳,南沢岳
6月13日(土) 1日目 木偶野呂馬&G3氏
1;コース状況/その他周辺情報

①ブナ立尾根は衆知の急登。2208mの三角点付近から雪が現れる。右手に不動岳方面が見える尾根に出て左にカーブし、ダケカンバの大木を見る辺りからシラビソ帯となり大量の雪を抱えた急斜面の登りとなる。右手の斜面をなるべく避けて左よりの樹林との際を進む。急斜面はどこが登山道か分からないが、異形のダケカンバの下に標識№1があり、そこからは登山道を辿って烏帽子小屋まで一息である。
②烏帽子小屋から烏帽子岳,南沢岳方面へは雪があったりなかったりであるが、北進するにつれて雪が多くなる。南沢岳の手前の平原状の場所は二重山稜のようになっており、南側に見える雪のない尾根の方へ行こうとして迷走し、ハイマツ帯を突破できずに元に戻るのに1時間20分を要した。南沢岳の西のピークの下に雪があって風があまり来ないビバーク点があった。



2;行動の記録
6月13日(土)
登山ブログで交流のあるG3氏との間でブナ立尾根を登ってみませんかと言う話しがまとまり、前夜のうちに静岡市から来て仮眠していたG3氏と七倉ダムのゲートで落ち合う。初対面の挨拶もそこそこにそれぞれパッキングして5:35から歩き始める。
高瀬ダムまでの3.7kmを歩いて6:32ダム下休憩。ロックフィルダムに取り付けられたこっちから向こうまで2往復半,1kmの車道を歩くのは馬鹿らしいので大岩を直登して20分で高瀬ダム堰堤に着く(6:55)。
ダム左岸の不動トンネルを抜けて不動沢の長いつり橋を渡ると河川敷に出る。鉄製の梯子道に導かれて濁り沢の吊り橋を渡り、水を補給して7:35から登山道に入るといきなり急登が始まる。『11』と書かれた標識があるが意味不明。長丁場なので休まずゆっくり登り、8:28,『落石注意』と書かれた標識NO『9』の巨岩,通称『権太落とし』で最初の休憩。
8:35出発。直後にパラパラッと雨が来て、雨の多い南アの人らしくG3氏は素早く雨具とザックカバーを着ける。自分は面倒なので様子を見ながら先行。足元にツバメオモトの花,次いでシラネアオイの花を見て『そう言う季節なのだ』と頭が下界とは違う世界に反応し始める。こうして写真を撮りながら徐々に高度を上げるうちに気持ちも体もその世界に順応して行くのだろう・・。
9:05,標識NO『7』を通過。シラネアオイが見事なのでG3氏にはゆっくり写真を撮ってもらう。



9:42,標識NO『6』に着き2度目の休憩の際に雷鳴を聞く。G3氏によると『前線が通過する見込み』だそうだが、1日中雷につきまとわれるのではないかと不安になる。稜線での雷はゴメン蒙りたいものだ。
9:55発。今回の山行には幾つかの不安があった。早くもそれが的中したのか、左脚大腿の外側に痙攣痛を感じる。ごまかしながら歩いていると痙攣は内側に移行し、なおも我慢していると今度は右脚に移行した。
この冬は一度も冬山に登らなかったので体力に自信がない。加えて登山靴を修理に出したままでアップシューズや地下足袋での山行が続いたために足が登山靴の重さに耐え切れず、歩き始めからどうも左右にふらつくのが気になっていた。大腿部の外側と内側の痛みはその影響と思われた。筋肉は8時間動かさない状態が続くと退化を始めると言うから登山靴の重さや踏ん張りに対応する筋力が衰えているのは明らかであるが、それは使うことによって鍛えられ回復するのを待つしかない。



10:06,右手が開けて烏帽子岳,南沢岳の岩峰群や不動岳の大崩れを望める場所があり、ここで立ち止まって行く手の稜線を地図で確認している間に左右の大腿部両側の痛みがうそのように消えた。10:20,雨がやや強くなりG3氏に倣って雨具とカバーを着ける。マーフィーの法則通り着るとすぐに雨が上がり、20分後に雨具を脱ぐ。雷は去った模様。足元に小イワカガミやエンレイソウ,サンカヨウの花を見る10:31標識NO『5』を通過。
10:49,最初の雪渓が現れG3氏はここでアイゼンをつけたが自分はツボ足で通過。道はすぐに雪渓から離れ、10:59に標高2208mの三角点に着く。登山道に入ってからの所要時間は3時間25分。



11:20発。10分でタヌキ岩と言う巨岩を通過。さらに20分あまりで不動岳,船窪岳を望む場所に出る。そこからは尾根に沿って左にカーブしながら進み、右下がえぐれた場所を通過してダケカンバの大木を過ぎた辺りからシラビソ帯となり、12:24頃から大量の雪を抱えた稜線下の急登が始まる。



登山道が分らないので先頭を行くG3氏も見当をつけて遮二無二登って行くが、次第に斜面が傾斜をまして行くのも構わず平然と登っていくG3氏の後を追うのが恐くて左の樹林の際を行く。
最もそれを必要とするこの急斜面でなぜか2人ともアイゼンをつけず、自分はピッケルさえ背中に負ったままで登ってしまっていた。アイゼンやピッケルのことを考えもせずに雪面に入ってしまったのだが、いつの間にかとんでもない斜度になっていたのだ。



樹林の際を行くと雪の解けた場所から登山道が覗いており、異様な形状のダケカンバがあって標識NO『1』と書かれたその場所でしばらく休む。時刻13:16。ここまで、雪と格闘する間にたちまち時間が経過していたようだ。
すでに小屋に迫っているものと思っていたG氏も少し先で休んでいたらしく、歩き始めるとすぐ前を行く姿が見え、やがて主稜線と小屋への道を分ける標識に着くと目の前に烏帽子の小屋が現れる。
13:51着。三角点からは2時間30分で雪のため夏道の倍近くかかっていた。登山道に入ってからは約6時間,七倉のゲートからは8時間16分。



烏帽子小屋の前庭は立山や薬師岳を望む絶好の展望台で、しばらくはベンチに座ってG3氏が広げた地図で山を同定するなどしてくつろぎながら次の行程をどうするかを考える。
西側の目の前に横たわるのは赤牛岳でそこから左手に伸びた稜線の先に水晶岳があり、その稜線と裏銀座の主脈が合流するのが鷲場岳で、その手前が真砂岳,野口五郎岳と言うことになる。
一方,赤牛の背後に重なるのは薬師岳で、視線を北北東に転じた目の前には不動岳,その後に針の木岳が重なり、さらにその陰には鳴沢、赤沢辺りの山が見え隠れする。黒部ダムはその直下を西に越えたところであり、赤牛岳を目の前にするこの位置からは見えない。その西に位置する立山のカールらしきものは認められるが、剣岳は視認できなかった。
また、南側の眼前には唐沢岳が錐のように鋭く天を突き、その後から餓鬼岳の長い稜線が南に伸び、東沢の大だるみを隔てて燕岳の岩峰を望むことができる。そこから先の大天井岳や常念岳の吊り尾根も見えるが、槍・穂高岳方面はガスの中だ。



14:27,時間的にも体力的にも船窪方面への前進は可能との結論を得て烏帽子岳に向かい出発。ゆるやかに左にカーブするハイマツ帯の稜線を行く。この辺りは雪もなく快調。
2605mの前烏帽子から改めて周辺の山々を見る。何と言っても烏帽子岳の天に向かって合掌するかのような鋭い岩峰が圧巻で、柱のようにきれいに並んだ岩が美しい。この岩峰はしかし、進むにつれてそれまでとはまったく違った異様な姿へと変貌する。



15:08,烏帽子岳岩峰への分岐点に到達。時間が押しているので山頂には向かわず通過,一転して雪の斜面となる。南沢岳との鞍部は烏帽子田圃と言う湿原で、この辺りをビバークの候補地とも考えていたが、できればさらに進んでおきたかった。
湿原は凹地であり、一方の縁は烏帽子からの稜線でもう一方に並行する山稜があって二重山陵を形成していた。そのもう一方の小高い山陵に踏み後が見えたのでそこを目指して雪面を突き進んだが、もう少しと言うところで分厚いハイマツ帯に阻まれて進めなくなる。しばらくはあちらこちらと突破口を探したが無理と分り、後退を決めて下ってきた雪面を登り返し、最後はシラビソとハイマツの混じる薮の中を這うようにして突破し、16:29,登山道に戻る。烏帽子分岐から1時間20分のタイムロスとなる。



ここから南沢岳への登りの途中から急に冷たい西風が吹き始めて山頂下では霰が降る。
17:00,南沢岳(2625m)の前ピークに到達。ここをビバーク地点と決めて山頂東側直下の雪面を均しテントを張る。
雪を溶かした水を沸かしてアルファ米を戻し、レトルトのカレーを温めて用意したが、G3氏がつくってくれた梅酒のお湯わりを頂き、行動食を食べているうちに食事が面倒になり、G3氏によると『あぐらのまま鼾をかき始めた』とのことで結局カレーは食べずに横になる。



ひとしきり熟睡し、目が覚めて2時間近くじっと考え事をしながら夜明けを待つ。風に時おり雨音が混じる。
2時を廻ったかと時計を見るとまだ0時前で、それから悶々と時の過ぎるのを待ち、何度かまどろんでようやく4時を迎える。どんなに疲れていても3~4時間熟睡すれば充分で、後は時間をもてあますのが常の幕営である。
6月14日(日)へ続く
北アルプス裏銀座コース・七倉ダム~烏帽子岳,南沢岳
6月13日(土) 1日目 木偶野呂馬&G3氏
1;コース状況/その他周辺情報

①ブナ立尾根は衆知の急登。2208mの三角点付近から雪が現れる。右手に不動岳方面が見える尾根に出て左にカーブし、ダケカンバの大木を見る辺りからシラビソ帯となり大量の雪を抱えた急斜面の登りとなる。右手の斜面をなるべく避けて左よりの樹林との際を進む。急斜面はどこが登山道か分からないが、異形のダケカンバの下に標識№1があり、そこからは登山道を辿って烏帽子小屋まで一息である。
②烏帽子小屋から烏帽子岳,南沢岳方面へは雪があったりなかったりであるが、北進するにつれて雪が多くなる。南沢岳の手前の平原状の場所は二重山稜のようになっており、南側に見える雪のない尾根の方へ行こうとして迷走し、ハイマツ帯を突破できずに元に戻るのに1時間20分を要した。南沢岳の西のピークの下に雪があって風があまり来ないビバーク点があった。



2;行動の記録
6月13日(土)
登山ブログで交流のあるG3氏との間でブナ立尾根を登ってみませんかと言う話しがまとまり、前夜のうちに静岡市から来て仮眠していたG3氏と七倉ダムのゲートで落ち合う。初対面の挨拶もそこそこにそれぞれパッキングして5:35から歩き始める。
高瀬ダムまでの3.7kmを歩いて6:32ダム下休憩。ロックフィルダムに取り付けられたこっちから向こうまで2往復半,1kmの車道を歩くのは馬鹿らしいので大岩を直登して20分で高瀬ダム堰堤に着く(6:55)。
ダム左岸の不動トンネルを抜けて不動沢の長いつり橋を渡ると河川敷に出る。鉄製の梯子道に導かれて濁り沢の吊り橋を渡り、水を補給して7:35から登山道に入るといきなり急登が始まる。『11』と書かれた標識があるが意味不明。長丁場なので休まずゆっくり登り、8:28,『落石注意』と書かれた標識NO『9』の巨岩,通称『権太落とし』で最初の休憩。
8:35出発。直後にパラパラッと雨が来て、雨の多い南アの人らしくG3氏は素早く雨具とザックカバーを着ける。自分は面倒なので様子を見ながら先行。足元にツバメオモトの花,次いでシラネアオイの花を見て『そう言う季節なのだ』と頭が下界とは違う世界に反応し始める。こうして写真を撮りながら徐々に高度を上げるうちに気持ちも体もその世界に順応して行くのだろう・・。
9:05,標識NO『7』を通過。シラネアオイが見事なのでG3氏にはゆっくり写真を撮ってもらう。



9:42,標識NO『6』に着き2度目の休憩の際に雷鳴を聞く。G3氏によると『前線が通過する見込み』だそうだが、1日中雷につきまとわれるのではないかと不安になる。稜線での雷はゴメン蒙りたいものだ。
9:55発。今回の山行には幾つかの不安があった。早くもそれが的中したのか、左脚大腿の外側に痙攣痛を感じる。ごまかしながら歩いていると痙攣は内側に移行し、なおも我慢していると今度は右脚に移行した。
この冬は一度も冬山に登らなかったので体力に自信がない。加えて登山靴を修理に出したままでアップシューズや地下足袋での山行が続いたために足が登山靴の重さに耐え切れず、歩き始めからどうも左右にふらつくのが気になっていた。大腿部の外側と内側の痛みはその影響と思われた。筋肉は8時間動かさない状態が続くと退化を始めると言うから登山靴の重さや踏ん張りに対応する筋力が衰えているのは明らかであるが、それは使うことによって鍛えられ回復するのを待つしかない。



10:06,右手が開けて烏帽子岳,南沢岳の岩峰群や不動岳の大崩れを望める場所があり、ここで立ち止まって行く手の稜線を地図で確認している間に左右の大腿部両側の痛みがうそのように消えた。10:20,雨がやや強くなりG3氏に倣って雨具とカバーを着ける。マーフィーの法則通り着るとすぐに雨が上がり、20分後に雨具を脱ぐ。雷は去った模様。足元に小イワカガミやエンレイソウ,サンカヨウの花を見る10:31標識NO『5』を通過。
10:49,最初の雪渓が現れG3氏はここでアイゼンをつけたが自分はツボ足で通過。道はすぐに雪渓から離れ、10:59に標高2208mの三角点に着く。登山道に入ってからの所要時間は3時間25分。



11:20発。10分でタヌキ岩と言う巨岩を通過。さらに20分あまりで不動岳,船窪岳を望む場所に出る。そこからは尾根に沿って左にカーブしながら進み、右下がえぐれた場所を通過してダケカンバの大木を過ぎた辺りからシラビソ帯となり、12:24頃から大量の雪を抱えた稜線下の急登が始まる。



登山道が分らないので先頭を行くG3氏も見当をつけて遮二無二登って行くが、次第に斜面が傾斜をまして行くのも構わず平然と登っていくG3氏の後を追うのが恐くて左の樹林の際を行く。
最もそれを必要とするこの急斜面でなぜか2人ともアイゼンをつけず、自分はピッケルさえ背中に負ったままで登ってしまっていた。アイゼンやピッケルのことを考えもせずに雪面に入ってしまったのだが、いつの間にかとんでもない斜度になっていたのだ。



樹林の際を行くと雪の解けた場所から登山道が覗いており、異様な形状のダケカンバがあって標識NO『1』と書かれたその場所でしばらく休む。時刻13:16。ここまで、雪と格闘する間にたちまち時間が経過していたようだ。
すでに小屋に迫っているものと思っていたG氏も少し先で休んでいたらしく、歩き始めるとすぐ前を行く姿が見え、やがて主稜線と小屋への道を分ける標識に着くと目の前に烏帽子の小屋が現れる。
13:51着。三角点からは2時間30分で雪のため夏道の倍近くかかっていた。登山道に入ってからは約6時間,七倉のゲートからは8時間16分。



烏帽子小屋の前庭は立山や薬師岳を望む絶好の展望台で、しばらくはベンチに座ってG3氏が広げた地図で山を同定するなどしてくつろぎながら次の行程をどうするかを考える。
西側の目の前に横たわるのは赤牛岳でそこから左手に伸びた稜線の先に水晶岳があり、その稜線と裏銀座の主脈が合流するのが鷲場岳で、その手前が真砂岳,野口五郎岳と言うことになる。
一方,赤牛の背後に重なるのは薬師岳で、視線を北北東に転じた目の前には不動岳,その後に針の木岳が重なり、さらにその陰には鳴沢、赤沢辺りの山が見え隠れする。黒部ダムはその直下を西に越えたところであり、赤牛岳を目の前にするこの位置からは見えない。その西に位置する立山のカールらしきものは認められるが、剣岳は視認できなかった。
また、南側の眼前には唐沢岳が錐のように鋭く天を突き、その後から餓鬼岳の長い稜線が南に伸び、東沢の大だるみを隔てて燕岳の岩峰を望むことができる。そこから先の大天井岳や常念岳の吊り尾根も見えるが、槍・穂高岳方面はガスの中だ。



14:27,時間的にも体力的にも船窪方面への前進は可能との結論を得て烏帽子岳に向かい出発。ゆるやかに左にカーブするハイマツ帯の稜線を行く。この辺りは雪もなく快調。
2605mの前烏帽子から改めて周辺の山々を見る。何と言っても烏帽子岳の天に向かって合掌するかのような鋭い岩峰が圧巻で、柱のようにきれいに並んだ岩が美しい。この岩峰はしかし、進むにつれてそれまでとはまったく違った異様な姿へと変貌する。



15:08,烏帽子岳岩峰への分岐点に到達。時間が押しているので山頂には向かわず通過,一転して雪の斜面となる。南沢岳との鞍部は烏帽子田圃と言う湿原で、この辺りをビバークの候補地とも考えていたが、できればさらに進んでおきたかった。
湿原は凹地であり、一方の縁は烏帽子からの稜線でもう一方に並行する山稜があって二重山陵を形成していた。そのもう一方の小高い山陵に踏み後が見えたのでそこを目指して雪面を突き進んだが、もう少しと言うところで分厚いハイマツ帯に阻まれて進めなくなる。しばらくはあちらこちらと突破口を探したが無理と分り、後退を決めて下ってきた雪面を登り返し、最後はシラビソとハイマツの混じる薮の中を這うようにして突破し、16:29,登山道に戻る。烏帽子分岐から1時間20分のタイムロスとなる。



ここから南沢岳への登りの途中から急に冷たい西風が吹き始めて山頂下では霰が降る。
17:00,南沢岳(2625m)の前ピークに到達。ここをビバーク地点と決めて山頂東側直下の雪面を均しテントを張る。
雪を溶かした水を沸かしてアルファ米を戻し、レトルトのカレーを温めて用意したが、G3氏がつくってくれた梅酒のお湯わりを頂き、行動食を食べているうちに食事が面倒になり、G3氏によると『あぐらのまま鼾をかき始めた』とのことで結局カレーは食べずに横になる。



ひとしきり熟睡し、目が覚めて2時間近くじっと考え事をしながら夜明けを待つ。風に時おり雨音が混じる。
2時を廻ったかと時計を見るとまだ0時前で、それから悶々と時の過ぎるのを待ち、何度かまどろんでようやく4時を迎える。どんなに疲れていても3~4時間熟睡すれば充分で、後は時間をもてあますのが常の幕営である。
6月14日(日)へ続く
2009年11月19日
長峰山,そして四賀村を囲む山々
長峰山,そして四賀村を囲む山々
09年11月19日 長峰山&四賀村境界線 記録者:木偶野呂馬


安曇野市の東側,旧明科町に位置する長峰山は標高933.3mの低山ながら山頂からの眺めが素晴らしく、北は白馬三山から唐松岳,五竜岳,鹿島槍ヶ岳,爺ヶ岳,蓮華岳,餓鬼岳,燕岳,大天井岳,常念岳と続いて蝶ヶ岳,大滝山,鍋冠山に至る後立山連峰のすべてを見渡すことの出来る屈指の展望台である。
http://user.cnet.ne.jp/m/mt-chou/panorama/panorama.html
かつて(昭和45年)作家の川端康成と井上靖,日本画家の東山魁夷の3文化人がここに会して安曇野の心打つ風景と文化を熱く語り、『残したい静けさ、美しさ』と絶賛したことは有名な話しである。
ひとしきりそのアルプスの展望と眼下の明科・穂高の街並みを堪能して目を東側の山なみに転じると・・。

2003年春,松本市に合併する前の旧四賀村に居を構えたばかりの私の目は当然のように自分の住む四賀村とその境界線を追う・・。そしてあることに気づく。
それは、四賀村を取り囲む周辺市町村との境界線の山々のほぼすべてを見渡すことが出来ると言うこと,その境界線は、国道と県道を7ヶ所で横切るが、人家のある地域で他の市町村と接する所は2ヶ所しかなく、殆どすべてが山であること,しかも戸谷峰や入山,御鷹山等,1600mを越える有名,無名の山が6つもあると言うことである。
1つの村がこれほどの山を持つことは驚嘆に値することではないか・・。そこからそのすべての境界線を歩くことを思い立つ。

松本市との境界に位置する戸谷峰(1629m)にはすでに登っていた。戸谷峰から六人坊(1618m),三才山(1605m=みさやま)方面には縦走路がある。三才山から保福寺峠(1320m)までは林道,峠から二ッ石峰(1563m),入山(1626m通称けつだし山),御鷹山(1623m)を経てR143の会吉トンネル(990m)に至る長大な尾根には登山道がある。会吉トンネルからは大洞山(1315m),虚空蔵山(1139m)と登山道のある山が続く。何度か登ったことのある虚空蔵山から花河原峠を経て善光寺街道の立峠(1000m)を越えると明科町との境界,標高1000mから700mのの丘陵地帯になる。登山道は期待できないが境界線はほとんどピークを通っているので探せば道はあるだろう・・,と、大雑把な見通しを立てる。
当面にして一番の問題は長峰山からR143までの四賀村と豊科町との境界線とR143を横切って、善光寺街道の刈谷原峠,東山道の稲倉峠に至るラインの確定である。ここを歩いて踏み跡をつければ後はどうにかなると考え、当時の『あまってら少年団・冒険学校』の活動拠点であった矢の沢に最も近い地点を出発点として調査を開始した。
こうして始まった旧四賀村一周境界線ハイキングは5年がかりで2007年11月に完結した。今年,2年ぶりにその最終行程をアレンジして歩いたのが11月7日のバリエーションルートである。
合併して松本市の一部となり、その名が消えてしまった四賀村であるが、境界線のルートの魅力はいささかも変わらない。即ち、古道と杣道が錯綜する里山の道探し,薮山のルートファインディングの難しさとおもしろさ,地図の読解,急登,痩せ尾根,高山,岩場等々・・。
登山のあらゆる要素を兼ね備えたこのルートの魅力をさらに多くの人々に紹介すべく、新たな展開を企図して行きたいと考えている。

09年11月19日 長峰山&四賀村境界線 記録者:木偶野呂馬


安曇野市の東側,旧明科町に位置する長峰山は標高933.3mの低山ながら山頂からの眺めが素晴らしく、北は白馬三山から唐松岳,五竜岳,鹿島槍ヶ岳,爺ヶ岳,蓮華岳,餓鬼岳,燕岳,大天井岳,常念岳と続いて蝶ヶ岳,大滝山,鍋冠山に至る後立山連峰のすべてを見渡すことの出来る屈指の展望台である。
http://user.cnet.ne.jp/m/mt-chou/panorama/panorama.html
かつて(昭和45年)作家の川端康成と井上靖,日本画家の東山魁夷の3文化人がここに会して安曇野の心打つ風景と文化を熱く語り、『残したい静けさ、美しさ』と絶賛したことは有名な話しである。
ひとしきりそのアルプスの展望と眼下の明科・穂高の街並みを堪能して目を東側の山なみに転じると・・。

2003年春,松本市に合併する前の旧四賀村に居を構えたばかりの私の目は当然のように自分の住む四賀村とその境界線を追う・・。そしてあることに気づく。
それは、四賀村を取り囲む周辺市町村との境界線の山々のほぼすべてを見渡すことが出来ると言うこと,その境界線は、国道と県道を7ヶ所で横切るが、人家のある地域で他の市町村と接する所は2ヶ所しかなく、殆どすべてが山であること,しかも戸谷峰や入山,御鷹山等,1600mを越える有名,無名の山が6つもあると言うことである。
1つの村がこれほどの山を持つことは驚嘆に値することではないか・・。そこからそのすべての境界線を歩くことを思い立つ。

松本市との境界に位置する戸谷峰(1629m)にはすでに登っていた。戸谷峰から六人坊(1618m),三才山(1605m=みさやま)方面には縦走路がある。三才山から保福寺峠(1320m)までは林道,峠から二ッ石峰(1563m),入山(1626m通称けつだし山),御鷹山(1623m)を経てR143の会吉トンネル(990m)に至る長大な尾根には登山道がある。会吉トンネルからは大洞山(1315m),虚空蔵山(1139m)と登山道のある山が続く。何度か登ったことのある虚空蔵山から花河原峠を経て善光寺街道の立峠(1000m)を越えると明科町との境界,標高1000mから700mのの丘陵地帯になる。登山道は期待できないが境界線はほとんどピークを通っているので探せば道はあるだろう・・,と、大雑把な見通しを立てる。
当面にして一番の問題は長峰山からR143までの四賀村と豊科町との境界線とR143を横切って、善光寺街道の刈谷原峠,東山道の稲倉峠に至るラインの確定である。ここを歩いて踏み跡をつければ後はどうにかなると考え、当時の『あまってら少年団・冒険学校』の活動拠点であった矢の沢に最も近い地点を出発点として調査を開始した。
こうして始まった旧四賀村一周境界線ハイキングは5年がかりで2007年11月に完結した。今年,2年ぶりにその最終行程をアレンジして歩いたのが11月7日のバリエーションルートである。
合併して松本市の一部となり、その名が消えてしまった四賀村であるが、境界線のルートの魅力はいささかも変わらない。即ち、古道と杣道が錯綜する里山の道探し,薮山のルートファインディングの難しさとおもしろさ,地図の読解,急登,痩せ尾根,高山,岩場等々・・。
登山のあらゆる要素を兼ね備えたこのルートの魅力をさらに多くの人々に紹介すべく、新たな展開を企図して行きたいと考えている。

2009年11月11日
境界線と古道
境界線と古道~里山尾根道・陽だまりハイキング・2
09年11月7日(土) 快晴 安曇野市東山丘陵
記録者:山のあしおと小学校主宰 木偶野呂馬 参加者:7名(一般募集5名)


戸谷峰・美ヶ原方面/四賀村五常方面
30分ほど見学して出発点に戻り、ストレッチの後出発。出発点からは,松本平,戸谷峰方面や鉢伏山を見る。雲1つない快晴だが、天気がよすぎて稜線が少し眠い感じがする。
コースは旧四賀村と旧明科町の境界線上の尾根を通る道で、当初は境界線を歩くことを目的として見出だしたものだが、道がしっかりしている点と所どころに馬頭観音が見られることから、四賀村北山地区と明科町潮地区天田,および大足地区を結ぶ重要な道であったと考えられる節があり、山歩きと同時に古道を歩くと言う面白さを兼ね備えたコースとして広めて行きたいと考えている。


修復された登山口/荒れてはいるがしっかりした道
山道は中北山林道の終点(起点)から始まるが、その取り付き部分が3年前の水害で崩落したものがつい最近修復されたばかりで、黄色いロープが張られているが構わず入る。
普段歩く人が皆無に近い道は、草木が茂って薮になっていたり道脇の木々の枝が張り出している上に倒木に塞がれている所があって2年前に歩いた時に比べるとすっかり歩きにくくなっている。
道は標高850~860mのラインに沿ってほぼ水平につけられており、所どころに現れる870~880mの小ピークを必ずと言っていいほど巻いていることも、それが人々が行き来した道であることを物語っていると言えよう。


新たに発見した馬頭観音/テングス病の桜
10:45発。最初の小ピークは北側の巻き道を歩き、次の小ピークの上に攀じ登るとそこから眼下の木の間越しに五輪平の家の屋根が見え、北東方向に四阿屋山が、また南東を振り向くとけつだし山の異名をもつ入山や御鷹山が見える。
この小ピークの次のピークを越えた地点で初めて境界線に入るまでは四賀側の道であるが、明科と四賀を結ぶ県道の沢村地区からそこまでの境界線にはまったく道がなく文字通りに薮漕ぎを強いられる難コースなので今回は省略した。
腰に剪定ばさみと鋸を下げ、邪魔な枝や倒木を切ったり取り除きながら進んで11:50にピーク890mに差しかかる。このピークに入る手前が二重山稜になっており中間の窪地の両脇にそれぞれ道と踏み跡があって一方は低い位置を通っているが、南側の踏み跡は細い尾根で片側が崖になっている縁につけられている。このような場所を通過する際に馬が崖から転落して死んだりしたこともあったに違いなく、馬頭観音はそのような歴史を物語るものであると考えられる。


ピーク890mは大きな倒木が折り重なっている北側の巻き道を進み、倒木を越えた先の馬頭観音の位置からピークに攀じ登る。その登りでまた迷ってしまって南側の稜線に出たおかげで常念岳を中心として北の白馬岳から唐松,五竜,鹿島槍,爺,蓮華,餓鬼,燕,大天井と続いて南の蝶ヶ岳,大滝山に至るまでの見事なパノラマを目にすることが出来た。


馴染みの馬頭観音/P890m
12:03ピーク890mに着く。地図によるとここに三角点があることになっているがいくら探しても見つからない。先ほどのパノラマ地点が弁当を食べるにいい場所であったが、生憎馬頭観音にザックを置いて登ってきたのでやむなくザックのある位置まで戻って天田神社に向かう。12:10発,同32,天田神社着。見晴らしがよくないので林道の天田峠に下り路上の涼しいところに陣取って昼食とする。


天田神社/天田峠
09年11月7日(土) 快晴 安曇野市東山丘陵
記録者:山のあしおと小学校主宰 木偶野呂馬 参加者:7名(一般募集5名)


戸谷峰・美ヶ原方面/四賀村五常方面
30分ほど見学して出発点に戻り、ストレッチの後出発。出発点からは,松本平,戸谷峰方面や鉢伏山を見る。雲1つない快晴だが、天気がよすぎて稜線が少し眠い感じがする。
コースは旧四賀村と旧明科町の境界線上の尾根を通る道で、当初は境界線を歩くことを目的として見出だしたものだが、道がしっかりしている点と所どころに馬頭観音が見られることから、四賀村北山地区と明科町潮地区天田,および大足地区を結ぶ重要な道であったと考えられる節があり、山歩きと同時に古道を歩くと言う面白さを兼ね備えたコースとして広めて行きたいと考えている。


修復された登山口/荒れてはいるがしっかりした道
山道は中北山林道の終点(起点)から始まるが、その取り付き部分が3年前の水害で崩落したものがつい最近修復されたばかりで、黄色いロープが張られているが構わず入る。
普段歩く人が皆無に近い道は、草木が茂って薮になっていたり道脇の木々の枝が張り出している上に倒木に塞がれている所があって2年前に歩いた時に比べるとすっかり歩きにくくなっている。
道は標高850~860mのラインに沿ってほぼ水平につけられており、所どころに現れる870~880mの小ピークを必ずと言っていいほど巻いていることも、それが人々が行き来した道であることを物語っていると言えよう。


新たに発見した馬頭観音/テングス病の桜
10:45発。最初の小ピークは北側の巻き道を歩き、次の小ピークの上に攀じ登るとそこから眼下の木の間越しに五輪平の家の屋根が見え、北東方向に四阿屋山が、また南東を振り向くとけつだし山の異名をもつ入山や御鷹山が見える。
この小ピークの次のピークを越えた地点で初めて境界線に入るまでは四賀側の道であるが、明科と四賀を結ぶ県道の沢村地区からそこまでの境界線にはまったく道がなく文字通りに薮漕ぎを強いられる難コースなので今回は省略した。
腰に剪定ばさみと鋸を下げ、邪魔な枝や倒木を切ったり取り除きながら進んで11:50にピーク890mに差しかかる。このピークに入る手前が二重山稜になっており中間の窪地の両脇にそれぞれ道と踏み跡があって一方は低い位置を通っているが、南側の踏み跡は細い尾根で片側が崖になっている縁につけられている。このような場所を通過する際に馬が崖から転落して死んだりしたこともあったに違いなく、馬頭観音はそのような歴史を物語るものであると考えられる。


ピーク890mは大きな倒木が折り重なっている北側の巻き道を進み、倒木を越えた先の馬頭観音の位置からピークに攀じ登る。その登りでまた迷ってしまって南側の稜線に出たおかげで常念岳を中心として北の白馬岳から唐松,五竜,鹿島槍,爺,蓮華,餓鬼,燕,大天井と続いて南の蝶ヶ岳,大滝山に至るまでの見事なパノラマを目にすることが出来た。


馴染みの馬頭観音/P890m
12:03ピーク890mに着く。地図によるとここに三角点があることになっているがいくら探しても見つからない。先ほどのパノラマ地点が弁当を食べるにいい場所であったが、生憎馬頭観音にザックを置いて登ってきたのでやむなくザックのある位置まで戻って天田神社に向かう。12:10発,同32,天田神社着。見晴らしがよくないので林道の天田峠に下り路上の涼しいところに陣取って昼食とする。


天田神社/天田峠
2009年11月11日
五輪平~里山道を歩く・1
五輪平を訪う~里山尾根道陽だまりハイキング・1
09年11月7日(土) 快晴 安曇野市東山丘陵
記録者:山のあしおと小学校主宰 木偶野呂馬 参加者:7名(一般募集5名)


戸谷峰・美ヶ原方面/四賀五常方面
11月7日(土),木偶主宰『山のあしおと小学校』の募集企画。安曇野市の社協が主催した山間僻地に独居するお年寄りを訪問する『散歩会』(10月21,28日)に参加したメンバー5人と、jun1123氏を含む7人の参加となる。
下山口となる大足地区に2台の車を置き、別の2台で出発点の松本市五常北山の五輪平口に移動。山歩きの前に五輪平を訪ねる。


五輪の塔/幼馴染に再会
五輪平
五輪平は標高780mほどの山間に位置し、平地部(標高600m)からは完全に隔絶された隠れ里のような小さな集落でその地名は五輪の塔があることに由来すると言う。3戸の家がありそのうちの2戸は廃屋だが1戸はしっかりした建物である。
2年前に歩いた時、その塔と村の天然記念物のヤマナシを見せてもらおうと案内を乞うた家から出てきたお年よりが奇しくも同行メンバー最高齢のkanさんの幼馴染で、双方ともにお互いをしっかり覚えていて会った瞬間に『アッ』と驚いて絶句,?十年ぶりの再会を喜び合い、『もうこれだけで今日のハイキングは充分意義があったとネ』と他のメンバーも感激したと言う経緯があった。


この家に1人住んでいた/村の天然記念物ヤマナシも枯れて・・
大きな家に1人で住んでいると言うお年よりに『冬なんか大変でしょう・・』と聞くと、『なぁに,雪が降ろうと晴れようと、起きたい時に起きて、コタツにあたってポカポカ転寝していれば極楽極楽。気楽なものよ』と屈託なく笑っていた。息子さんが毎日様子を見に来てくれると言い『今日もこれから来るよ!』と嬉しそうだった。手入れされた庭にはミセバヤの見事な花が咲き、日当たりのいい畑にはお菜(野沢菜)が青々と繁っていた。


青々とお菜/ミセバヤの花もなく
そこだけ緩やかな傾斜地がぽっかりと広がる五輪平は猫の額ほどの小さな集落であるが、3戸の家がつましく暮らすには充分な土地だったのだろう。
2年前までいたその一人暮らしのお年寄りの姿が、先日の下見の時も今回も見当たらず、その家にも生活臭と言うものが感じられなかった。2年後の今も日当たりのいい畑にはお菜やダイコンが植えられて見事に育っているが、主のいない畑でそれが鹿に食べ散らかされているのが痛々しい。あの見事なミセバヤの花はすでになく、村の天然記念物のヤマナシも立ち枯れてしまっているようだ。


鹿の天下/
09年11月7日(土) 快晴 安曇野市東山丘陵
記録者:山のあしおと小学校主宰 木偶野呂馬 参加者:7名(一般募集5名)


戸谷峰・美ヶ原方面/四賀五常方面
11月7日(土),木偶主宰『山のあしおと小学校』の募集企画。安曇野市の社協が主催した山間僻地に独居するお年寄りを訪問する『散歩会』(10月21,28日)に参加したメンバー5人と、jun1123氏を含む7人の参加となる。
下山口となる大足地区に2台の車を置き、別の2台で出発点の松本市五常北山の五輪平口に移動。山歩きの前に五輪平を訪ねる。


五輪の塔/幼馴染に再会
五輪平
五輪平は標高780mほどの山間に位置し、平地部(標高600m)からは完全に隔絶された隠れ里のような小さな集落でその地名は五輪の塔があることに由来すると言う。3戸の家がありそのうちの2戸は廃屋だが1戸はしっかりした建物である。
2年前に歩いた時、その塔と村の天然記念物のヤマナシを見せてもらおうと案内を乞うた家から出てきたお年よりが奇しくも同行メンバー最高齢のkanさんの幼馴染で、双方ともにお互いをしっかり覚えていて会った瞬間に『アッ』と驚いて絶句,?十年ぶりの再会を喜び合い、『もうこれだけで今日のハイキングは充分意義があったとネ』と他のメンバーも感激したと言う経緯があった。


この家に1人住んでいた/村の天然記念物ヤマナシも枯れて・・
大きな家に1人で住んでいると言うお年よりに『冬なんか大変でしょう・・』と聞くと、『なぁに,雪が降ろうと晴れようと、起きたい時に起きて、コタツにあたってポカポカ転寝していれば極楽極楽。気楽なものよ』と屈託なく笑っていた。息子さんが毎日様子を見に来てくれると言い『今日もこれから来るよ!』と嬉しそうだった。手入れされた庭にはミセバヤの見事な花が咲き、日当たりのいい畑にはお菜(野沢菜)が青々と繁っていた。


青々とお菜/ミセバヤの花もなく
そこだけ緩やかな傾斜地がぽっかりと広がる五輪平は猫の額ほどの小さな集落であるが、3戸の家がつましく暮らすには充分な土地だったのだろう。
2年前までいたその一人暮らしのお年寄りの姿が、先日の下見の時も今回も見当たらず、その家にも生活臭と言うものが感じられなかった。2年後の今も日当たりのいい畑にはお菜やダイコンが植えられて見事に育っているが、主のいない畑でそれが鹿に食べ散らかされているのが痛々しい。あの見事なミセバヤの花はすでになく、村の天然記念物のヤマナシも立ち枯れてしまっているようだ。


鹿の天下/
2009年11月02日
西山燃ゆ~ルート調査・3

旧四賀村一周境界線ハイキング・バリエーションルート調査山行・3
~里山道を歩く・・・四賀村五輪平から明科町大足へ~
2009年10月24日(土) 長野県松本市・安曇野市境界山域(無名)
記録者 山のあしおと小学校 木偶野呂馬
前々日のコースを再調査。大足地区の最終民家から5分足らずで到達する稜線が境界線ルートであることを確認するため、前回とは逆に右折して下り始めたが、壊れた祠のある地点から急激に下がり始めたので途中で引き返し、890mのピークに向かう。
 前々日同様、掘平の墓地のあるやや平らな部分で道が分からなくなる。慎重に検討した結果、やはり前回同様に右手の道を行くしかないと判断して右手に進む。
前々日同様、掘平の墓地のあるやや平らな部分で道が分からなくなる。慎重に検討した結果、やはり前回同様に右手の道を行くしかないと判断して右手に進む。前回はその先でP890m峰の中腹を巻くように進んで道を見失ってしまったので、今回は始めからピークを目ざして高い部分をしばらく進むとハッキリした道が見つかり、程なく890mのピークに到達した。前日確認した境界線のルートを下から登った訳で、これによりこの日歩いたコースが境界線のルートであることが確認できたが、たったこれだけのことを確認するのに3日もかかってしまった。
確定したルートを下ってみると、その道は掘平の墓地のある平地を通っておらず、迷うことなくルートを進むことが出来た。そう言えば2年前に歩いた時にも墓地を通った記憶がなかった。
 ここですでに間違っていた。
ここですでに間違っていた。堀平の墓地のある平地を右に見てしばらく進むとやや広い平地に出る。そこまで戻って初めて、間違いはこの地点ですでに始まっていたのだと気づく。即ち堀平の墓地方向に向かわず右寄りに進んでいれば難なくP890mに到達できていたはずであり、2年前には何の迷いもなくそのコースを歩いていたのだ・・。
そう思いながら、だから今度は間違えずまっすぐ下れるぞッ!と勢い込んで右に向かう道を見送って直進したのがまた間違いだった。すぐに気づいて戻り、見送った道の方に向かう。
里山ではわずかな平地や凸地に必ずと言っていいほど複数の踏み跡があり、見通しの効かない林の中では実に迷いやすいと言うことを思い知らされた。
 西山が真っ赤に焼けるのを木の間越しに見ながら標識3号,4号と進み、下山口のマークを見つけた頃にはすっかり暗くなっていた。17:18,出発点の廃屋に戻り終了。
西山が真っ赤に焼けるのを木の間越しに見ながら標識3号,4号と進み、下山口のマークを見つけた頃にはすっかり暗くなっていた。17:18,出発点の廃屋に戻り終了。

旧四賀村の境界線を1周すると言う目的ではじめた企画であるが、途中の道がしっかりした道であること,また馬頭観音があることから別の興味が湧いてきた。
それはこの道が旧四賀村の五常地区と旧明科町の潮地区や大足地区を結ぶ生活道路だったのではないかと言う興味である。大小を問わずすべてのピークにことごとくに迂回路がつけられているのがその証拠で、前日間違えて天田峠に出てしまったのは実は間違いではなく、生活道路であればこそ当然のごとくそちらに導かれた結果だったのであろう。態々境界線を求めたりせず歩きやすい方を歩くのが普通の生活人なのだから・・,である。

さらにまたそれは善光寺街道の支線の1つであったかも知れず、興味は尽きないのだ!
そうであるなら、境界線を忠実に歩く企画はそれとして今回は生活道路としてのルートを歩いてみたいと考えている。そして、そのルートとしては今回歩いた通りに大足地区の最終民家に出て大足に下るか、あるいは前日間違えて天田峠に出た道を歩いて潮地区に下るかのいずれかを選ぶことになる。
どちらを選ぶか、もう少し歴史的なことを調べて結論を出すことにしたい。
2009年10月29日
謎解き~里山道を歩く~ルート調査・2
旧四賀村一周境界線ハイキング・バリエーションルート調査山行・2
~里山道を歩く・・・四賀村五輪平から明科町大足へ~
2009年10月22日(木) 長野県松本市・安曇野市境界山域(無名)
記録者 山のあしおと小学校 木偶野呂馬

五輪平口から名峰戸谷峰を望む
前日,山中で迷ってしまったので改めて調査をやり直すべく、今度はスタート地点になる四賀地区五輪平の入り口から歩く。
県道302号(矢室明科線)五常の藤松屋商店の脇の沢沿いの道を詰める。地図には書かれていないが、この道は林道中北山線の起(終)点につながっており、そこが五輪平の入り口でもある。五輪平は林道を越えて500m(県道からは2km)ほど下がった所に開けた平地で、山中の隔絶された場所ではあるが日当たりがよく、3戸ばかりの家があってそのうちの1戸には今も野菜をつくりながら暮らしている人がいる。
林道起点に車を置いて14:52発。2年前にも2度3度と調査した道であるが、わずかの間に周りの木の枝が繁って張り出したり道に小潅木が生えたり、さらには倒木が道を塞ぐなどしてすっかり歩きづらくなっているのに驚く。
この日の目的は、前日の帰り道で迷った890mのピークまで行って迷った原因を突き止め、林道天田線につながる道を見つけること,それがだめなら境界線の途中から明科大足地区に下る道を見出すことである。
15:24,890mピークの登り口に到達。ここからまっすぐ登れば標識2号と祠のあるピークに達するのだが、迂回する道があるのでそちらを選んで進む。その道はしかし沢山の倒木が折り重なっており,倒れた木を跨いだり下を潜ったりしなければならなかった。
100mほど進んだ所に馬頭観音があり、そこからピークに攀じ登ることもできる。そこまで来て前日の到達点とつながった安心感からピークに登るのを後まわしにして前日迷った地点を先に突き止めようとそのまま道を進む。
その時点ではそれまで西進していた境界線が890mのピークからほぼ直角に左折して南に向かうということ、従って現在歩いているその道は境界線からは離れていくと言うことをすっかり忘れていた。正しく境界線を辿るためにはピークに上がらなければならなかったのだ・・。
それを忘れてどんどんと進むうちに突然舗装された林道に出る。エッと驚いて標識を見るとそこは前日通った林道天田線の天田峠で、そしてそのすぐ上にある天田神社の境内に行き着いて初めて、それが2年前に同じ間違いをして迷い着いた神社であることに気づき、ようやく890mのピークに登って進路を変えなければならなかったこと思い出した。何と言う頭の悪さ・・!

間違えて天田神社に出た
時刻15:40。大急ぎで890mピークに向けて戻り、北西側(天田神社側)からピークに登る(16:02着)。何とその道は前日のピークからの下山の際に、境界線の道だと思って回避した道だった。つまりその道を下っていれば元来た道ではないにしても天田林道に出ることが出来、林道に出ていればそこから1km歩いて車に戻ることが出来たのだ。
前日はその道を境界線の道,即ち南に向かう道だと思い込んでいた。なので大足・天田方面に下るためには右に進路を取って西に向かわなければならないと思ったのだが、実際には180度間違えて東に進んでいたのだ。その途中から下ったために大足・天田とはまったく逆の生竜地区に下ったに違いない。

前日歩いた稜線戸廃屋を望む
これで謎が解けたが、失敗の原因はどのように歩いて890mピークに達したかが解らなかったこと、そのためにピークで方向感覚を失ったことにある。何度も歩いている山でこのような間違いを起すなど断じてあってはならないことなので、もう一度前日の歩きを再現してどう間違えたのかを確かめなくてはならない。
これ以上進むと車に戻る時間がなくなるので一旦戻って大足地区に車を廻し、改めて前日歩いたコースをもう一度確かめることにする。
16:44,出発点に戻り終了
~里山道を歩く・・・四賀村五輪平から明科町大足へ~
2009年10月22日(木) 長野県松本市・安曇野市境界山域(無名)
記録者 山のあしおと小学校 木偶野呂馬

五輪平口から名峰戸谷峰を望む
前日,山中で迷ってしまったので改めて調査をやり直すべく、今度はスタート地点になる四賀地区五輪平の入り口から歩く。
県道302号(矢室明科線)五常の藤松屋商店の脇の沢沿いの道を詰める。地図には書かれていないが、この道は林道中北山線の起(終)点につながっており、そこが五輪平の入り口でもある。五輪平は林道を越えて500m(県道からは2km)ほど下がった所に開けた平地で、山中の隔絶された場所ではあるが日当たりがよく、3戸ばかりの家があってそのうちの1戸には今も野菜をつくりながら暮らしている人がいる。
林道起点に車を置いて14:52発。2年前にも2度3度と調査した道であるが、わずかの間に周りの木の枝が繁って張り出したり道に小潅木が生えたり、さらには倒木が道を塞ぐなどしてすっかり歩きづらくなっているのに驚く。
この日の目的は、前日の帰り道で迷った890mのピークまで行って迷った原因を突き止め、林道天田線につながる道を見つけること,それがだめなら境界線の途中から明科大足地区に下る道を見出すことである。
15:24,890mピークの登り口に到達。ここからまっすぐ登れば標識2号と祠のあるピークに達するのだが、迂回する道があるのでそちらを選んで進む。その道はしかし沢山の倒木が折り重なっており,倒れた木を跨いだり下を潜ったりしなければならなかった。
100mほど進んだ所に馬頭観音があり、そこからピークに攀じ登ることもできる。そこまで来て前日の到達点とつながった安心感からピークに登るのを後まわしにして前日迷った地点を先に突き止めようとそのまま道を進む。
その時点ではそれまで西進していた境界線が890mのピークからほぼ直角に左折して南に向かうということ、従って現在歩いているその道は境界線からは離れていくと言うことをすっかり忘れていた。正しく境界線を辿るためにはピークに上がらなければならなかったのだ・・。
それを忘れてどんどんと進むうちに突然舗装された林道に出る。エッと驚いて標識を見るとそこは前日通った林道天田線の天田峠で、そしてそのすぐ上にある天田神社の境内に行き着いて初めて、それが2年前に同じ間違いをして迷い着いた神社であることに気づき、ようやく890mのピークに登って進路を変えなければならなかったこと思い出した。何と言う頭の悪さ・・!

間違えて天田神社に出た
時刻15:40。大急ぎで890mピークに向けて戻り、北西側(天田神社側)からピークに登る(16:02着)。何とその道は前日のピークからの下山の際に、境界線の道だと思って回避した道だった。つまりその道を下っていれば元来た道ではないにしても天田林道に出ることが出来、林道に出ていればそこから1km歩いて車に戻ることが出来たのだ。
前日はその道を境界線の道,即ち南に向かう道だと思い込んでいた。なので大足・天田方面に下るためには右に進路を取って西に向かわなければならないと思ったのだが、実際には180度間違えて東に進んでいたのだ。その途中から下ったために大足・天田とはまったく逆の生竜地区に下ったに違いない。

前日歩いた稜線戸廃屋を望む
これで謎が解けたが、失敗の原因はどのように歩いて890mピークに達したかが解らなかったこと、そのためにピークで方向感覚を失ったことにある。何度も歩いている山でこのような間違いを起すなど断じてあってはならないことなので、もう一度前日の歩きを再現してどう間違えたのかを確かめなくてはならない。
これ以上進むと車に戻る時間がなくなるので一旦戻って大足地区に車を廻し、改めて前日歩いたコースをもう一度確かめることにする。
16:44,出発点に戻り終了
2009年10月29日
道迷い・山中彷徨・・・つるべ落としの秋の日に
旧四賀村一周境界線ハイキング・バリエーションルート調査山行
~里山道を歩く・・・四賀村五輪平から明科町大足へ~
2009年10月22日(木) 長野県松本市・安曇野市境界山域(無名)
記録者 山のあしおと小学校 木偶野呂馬

2年前の11月18日に歩いた旧四賀村境界線ハイキング第9行程のバリエーションルートを開拓すべく、旧明科街潮の天田地区から境界線を目指して歩く。
林道天田線の終点から境界線までを踏査して境界線沿いに南下し、県道に出る道を見届けて車に戻るつもりが下山道を間違えて生竜と言う地区の林道に出た。
日没寸前のギリギリ時刻に林道に到達して事なきを得たが、車を置いた位置からはとんでもない方向に下りてしまった。
林道天田船の終点の廃屋近く(標高780m)に車を置き15:40出発。廃屋の庭を抜けてかすかな踏み跡を辿るとすぐに別の林道に行き当たる。この道は県道四賀線沿いの大足と言う地区につながる道で、潮地区とはひと山隔てていて天田線とはつながっていない。両者の距離はわずか3~400mほどだが、共に県道からの標高差が230mもある急傾斜地のこの地区には、それぞれに数戸の人家があるだけなので両地区を結ぶ道路が敷設されなかったのだ。その数戸の人家も今は廃屋となって朽ち果てるのを待っていると言う状況ですでにして集落でさえない。
四賀・明科の境界線沿いにはこのような廃屋が無数にあり、境界線を歩く山行はこのような荒れ果てた廃家・廃屋や山深い1軒屋に独居するお年寄りの姿をつぶさに見て歩く山歩きでもあるのだ。
林道を上に向かって歩き始めた時に、右手の廃屋から1台の車が出てきたので戻って乗っていた中年の男性に周辺事情を聞く。今は廃屋のその家から子どもの頃は学校に通ったと言うその男性は、1日おきに畑の管理に来ていると言った。

200mほど歩いて最後の廃屋の前を通り、薮に覆われた踏み跡を辿って尾根に攀じ登る。左折して遮二無二登ること5分で『標柱4号』と言う標識を見る(15:55)。『地すべり防止』の対策を表わすこの手の標識はよく見かけるが、何号かまでは覚えていない。そのまま直進すると6分後に『3号』標識にぶつかる。その先から道が右手の尾根を避けて左寄り進み、16:11 に『掘平』と言う墓地のある三叉路に出る。
左の道は下って行く感じだったので右折して小高い場所を目指し、鹿道を辿って見通しの効く場所に出てみたが期待はずれだったので引き返したものの、その戻り道がわからなくなって探し回るうちに2年前に歩いた境界線ルートの『標識2号』と小さな祠のあるピーク(890m)に出た(16:17)。
境界線上にいることがわかったのでこれを下れば県道に出られるのだが、この日の目的は境界線と林道天田線をつなぐルートの踏査なので、車のある位置へのルートを確定しなければならない。
車があるのは境界線より西寄りであるから2号標識から西に派生する尾根を下らなくてはならないと判断して下り始めたが、途中でつけた目印はおろか掘平の墓地もが見つからない。がしかし自分の頭の中では西~北西寄りに下っている筈だからと踏み跡を辿ってひたすら下る。

ランプを持って来なかったので16:30を過ぎるとちょっと心配になってきた。日没まで1時間弱,明るいうちに人家のある付近まで下らなければと少々焦る。
16:48,やっと廃屋を見つける。家の前を通過して小さな谷にかかる木の橋を渡った少し先に栗林があった。その感じが以前間違えて彷徨った場所に似ている気がした。その場所であれば果樹園を登りきったところに広い道があって、それを下れば左下の林道があるはずだった。左手にもう1つ廃屋が見えていたので、そちらを選ぶ選択肢もあったが、過去の記憶に引きずられ果樹園の急斜面を登りきって出た道は以前のそれとは違う気がした。
道があるにはあったがいくら下っても林道が見えない。だが下るしかない。そのうち道がなくなって沢に下りてしまった。知らぬ沢は地獄・・,ヤバイなと思う反面、滝があるような大きな沢ではないはずなので沢にいる方が確実に里に出られると考えてそのまま下るうちに砂防堰堤にぶつかる。
天田地区に砂防のあるような沢があっただろうか?,あったとしても5つも6つもあるはずはないから里は近い・・,等と考えながら下るうちに第2,第3の堰堤からさらに第4,第5と堰堤が続き、7つ目の堰堤を越えた所でようやく大きな重機のある工事現場に出る。時刻17:18。まだ見える時刻ではあるが10分後にはとっぷりと日が暮れた。
林道を下ると行く手上空に高速道路の巨大な橋が見えて来た。さらに境界線の東にあるはずの送電線鉄塔を西側に見るに至って、自分が境界線の東側に下りた来たことを知り仰天した。天田地区のどこかの沢沿いに下ったと思っていたものがまったく方向違いの旧四賀村に降りていたのだ。どう間違えばこちら側に降りられるのかまったく解らず、キツネにでも化かされた感じだ。そういえば途中でムジナを見たっけ・・。
そんなこんなで2年前に一緒に歩いた小月さんに電話して拾いに来てもらい、天田まで車を回収に行ったと言う次第。
どこでどう間違えたのか、これから再検証に行く。
~里山道を歩く・・・四賀村五輪平から明科町大足へ~
2009年10月22日(木) 長野県松本市・安曇野市境界山域(無名)
記録者 山のあしおと小学校 木偶野呂馬

2年前の11月18日に歩いた旧四賀村境界線ハイキング第9行程のバリエーションルートを開拓すべく、旧明科街潮の天田地区から境界線を目指して歩く。
林道天田線の終点から境界線までを踏査して境界線沿いに南下し、県道に出る道を見届けて車に戻るつもりが下山道を間違えて生竜と言う地区の林道に出た。
日没寸前のギリギリ時刻に林道に到達して事なきを得たが、車を置いた位置からはとんでもない方向に下りてしまった。
林道天田船の終点の廃屋近く(標高780m)に車を置き15:40出発。廃屋の庭を抜けてかすかな踏み跡を辿るとすぐに別の林道に行き当たる。この道は県道四賀線沿いの大足と言う地区につながる道で、潮地区とはひと山隔てていて天田線とはつながっていない。両者の距離はわずか3~400mほどだが、共に県道からの標高差が230mもある急傾斜地のこの地区には、それぞれに数戸の人家があるだけなので両地区を結ぶ道路が敷設されなかったのだ。その数戸の人家も今は廃屋となって朽ち果てるのを待っていると言う状況ですでにして集落でさえない。
四賀・明科の境界線沿いにはこのような廃屋が無数にあり、境界線を歩く山行はこのような荒れ果てた廃家・廃屋や山深い1軒屋に独居するお年寄りの姿をつぶさに見て歩く山歩きでもあるのだ。
林道を上に向かって歩き始めた時に、右手の廃屋から1台の車が出てきたので戻って乗っていた中年の男性に周辺事情を聞く。今は廃屋のその家から子どもの頃は学校に通ったと言うその男性は、1日おきに畑の管理に来ていると言った。

200mほど歩いて最後の廃屋の前を通り、薮に覆われた踏み跡を辿って尾根に攀じ登る。左折して遮二無二登ること5分で『標柱4号』と言う標識を見る(15:55)。『地すべり防止』の対策を表わすこの手の標識はよく見かけるが、何号かまでは覚えていない。そのまま直進すると6分後に『3号』標識にぶつかる。その先から道が右手の尾根を避けて左寄り進み、16:11 に『掘平』と言う墓地のある三叉路に出る。
左の道は下って行く感じだったので右折して小高い場所を目指し、鹿道を辿って見通しの効く場所に出てみたが期待はずれだったので引き返したものの、その戻り道がわからなくなって探し回るうちに2年前に歩いた境界線ルートの『標識2号』と小さな祠のあるピーク(890m)に出た(16:17)。
境界線上にいることがわかったのでこれを下れば県道に出られるのだが、この日の目的は境界線と林道天田線をつなぐルートの踏査なので、車のある位置へのルートを確定しなければならない。
車があるのは境界線より西寄りであるから2号標識から西に派生する尾根を下らなくてはならないと判断して下り始めたが、途中でつけた目印はおろか掘平の墓地もが見つからない。がしかし自分の頭の中では西~北西寄りに下っている筈だからと踏み跡を辿ってひたすら下る。

ランプを持って来なかったので16:30を過ぎるとちょっと心配になってきた。日没まで1時間弱,明るいうちに人家のある付近まで下らなければと少々焦る。
16:48,やっと廃屋を見つける。家の前を通過して小さな谷にかかる木の橋を渡った少し先に栗林があった。その感じが以前間違えて彷徨った場所に似ている気がした。その場所であれば果樹園を登りきったところに広い道があって、それを下れば左下の林道があるはずだった。左手にもう1つ廃屋が見えていたので、そちらを選ぶ選択肢もあったが、過去の記憶に引きずられ果樹園の急斜面を登りきって出た道は以前のそれとは違う気がした。
道があるにはあったがいくら下っても林道が見えない。だが下るしかない。そのうち道がなくなって沢に下りてしまった。知らぬ沢は地獄・・,ヤバイなと思う反面、滝があるような大きな沢ではないはずなので沢にいる方が確実に里に出られると考えてそのまま下るうちに砂防堰堤にぶつかる。
天田地区に砂防のあるような沢があっただろうか?,あったとしても5つも6つもあるはずはないから里は近い・・,等と考えながら下るうちに第2,第3の堰堤からさらに第4,第5と堰堤が続き、7つ目の堰堤を越えた所でようやく大きな重機のある工事現場に出る。時刻17:18。まだ見える時刻ではあるが10分後にはとっぷりと日が暮れた。
林道を下ると行く手上空に高速道路の巨大な橋が見えて来た。さらに境界線の東にあるはずの送電線鉄塔を西側に見るに至って、自分が境界線の東側に下りた来たことを知り仰天した。天田地区のどこかの沢沿いに下ったと思っていたものがまったく方向違いの旧四賀村に降りていたのだ。どう間違えばこちら側に降りられるのかまったく解らず、キツネにでも化かされた感じだ。そういえば途中でムジナを見たっけ・・。
そんなこんなで2年前に一緒に歩いた小月さんに電話して拾いに来てもらい、天田まで車を回収に行ったと言う次第。
どこでどう間違えたのか、これから再検証に行く。