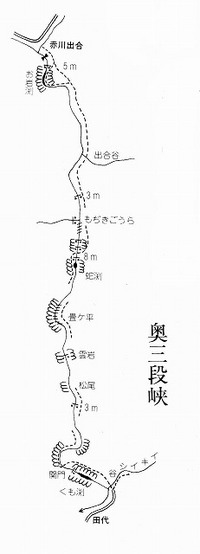2010年02月26日
古賀志山(2010.2.21)
息子と登山♪
2010年2月21日 栃木県宇都宮市 古賀志山 記録者 やませみ
千葉の大学に行ってる次男から20日の朝、突然帰ってくるとのメールが届いたのである。
夕方、いつものように駅まで迎えにその帰り道の車中で私は息子とのある約束を思い出した。
それは一月くらい前にメールで 「●さと、今度お父さんと山、一緒に行くかぁ!」と送ったのです。まぁたぶん返事は「行かないー」だろうと予想してたのですが結果は意外にも「いいよー!!」の快諾でした。
これは息子と山行のチャンス到来!!
うっしーしー。と思う自分がいたのであった。
ほどなくして自宅へ到着、早々母親の歓迎を受け夕食のテーブルへと。 いつになく食卓が賑やかである。明らかに次男が家にいない時と料理の品数が・・・多くねぇ・・。それを見た次男は当然ご満悦であった。
一人でのアパート暮らし普段あまり碌な物は食ってないはずである。
正月以来の一家団欒の時間が始まる。何時になく女房の顔が綻んでいた。未熟児で生まれ人一倍手のかかった次男は特に可愛いみたいである。
ここからは私と次男のやり取り・・
父 「●●と、この間のメールのこと憶えてる?」
次男 「うん。 おぼえてるよぉ」
父 「お父さん明日急きょ休みになったんだよねぇ」
次男 「ふーん。 ・・・んで」
父 「山、いくか?あした」
父 「山頂で食べるラーメンうまいんだよねー」
次男 「何山?いくのぉ」
父 「何処にする?」
次男 「月山、火山なら良いよー」
父 「・・・・・???」
父 「それって山は山でも食物家・・?」 (なんだよぉ、もぉ。)って感じでした。
息子はどうやら山よりも食べ物家の方が好いみたいで、結局その夜は折合いが付かず寝ることに。正直この時点で山行きは半ば諦めていました。
替わって翌朝、朝食を済ませ炬燵でテレビを見ヌクヌクしていると2階から勢いよく次男が私のとなりに繰るなり
「今日、山いくの・・?」・・・しばし無言の私。
すると、「お父さん着るもの貸して。靴はどれ履けばいいのぉ」の声が。
こうなれば話しは早い。速攻出かける準備をする。
近くのコンビニで食料を買い込み家から車で15分で行ける古賀志山へと向かう。赤川ダム下の駐車場に到着。 時間はすでに11時ちょうど。
いつになく車が多く三段下の駐車場にようやく空きスペースを見つけて車を止めやっと出発である。
今日のコースは急だったので特に決めてなく、なんとなく足の向くまま北登山口へ。でもこのまま登るのもつまらいし・・
・・て、ことで東稜の見晴台へ南側から登りはじめることに。
最初は一緒のペースで歩いていたのだが、だんだんと私が遅れをとるようになる。 いやはやなんとも10代の若さが羨ましい。
直登に近い鎖場をなんなく越え見晴し台に着く、案の定昼どきで満杯である。仕方なくそのまま古賀志山頂へと向う。
するとどうでしょう。こちらはがらがらです。 ラッキー!!!
一番南側のテーブルに場所をとりお楽しみの昼食です♪
おにぎりとお気に入りのカップラーメンを頬張りしばしまったりとした親子の時間を過ごしました。おなかも満たされこのまま降るのも芸がないので
御岳山まで足をのばすことになり午後の部開始である。
親子での登山の証しにカメラのシャッターをお願いすべく5人組のご年配の方のひとりに頼み記念撮影。するとメンバーの一人の女性が僕が2人分の荷物を背負ってることに気付き冷かされる始末に。そうなのです、息子はノーザックだったのです。お父さんは甘いのひと言が・・・
でも、もう一人の女性の方が家にも大学生の息子がいるので何となく気持ちは解かりますよとの優しいお声がけ。 そうですか、ありがとうございます。そんな他愛もない会話をしつつメンバー達に別れを告げ登山道へとすすむ。
ところがこの先がほとんど日陰の為、アイスバーン状態ですべるのなんのって。いつもは10分で行ける距離を30分ほどかかりやっとの思いで御岳山頂に着いたのである。ここでも記念の証しを取りそうそうに来た道を恐る恐る戻ったのである。
帰路は残雪のない南登山道を下りることに50分ほどで駐車場に帰ってきました。 この日は天気が良かったのもあり森林公園は家族連れでとても賑わっていました。駐車場が一杯だったのは登山客だけじゃ無かったみたいです。
と言うことで、久々に親子の時間を過ごせた一日でした。
こういう時が「近いうちにまたあれば好いなーと!」・・と願う父である。



2010年2月21日 栃木県宇都宮市 古賀志山 記録者 やませみ
千葉の大学に行ってる次男から20日の朝、突然帰ってくるとのメールが届いたのである。
夕方、いつものように駅まで迎えにその帰り道の車中で私は息子とのある約束を思い出した。
それは一月くらい前にメールで 「●さと、今度お父さんと山、一緒に行くかぁ!」と送ったのです。まぁたぶん返事は「行かないー」だろうと予想してたのですが結果は意外にも「いいよー!!」の快諾でした。
これは息子と山行のチャンス到来!!
うっしーしー。と思う自分がいたのであった。
ほどなくして自宅へ到着、早々母親の歓迎を受け夕食のテーブルへと。 いつになく食卓が賑やかである。明らかに次男が家にいない時と料理の品数が・・・多くねぇ・・。それを見た次男は当然ご満悦であった。
一人でのアパート暮らし普段あまり碌な物は食ってないはずである。
正月以来の一家団欒の時間が始まる。何時になく女房の顔が綻んでいた。未熟児で生まれ人一倍手のかかった次男は特に可愛いみたいである。
ここからは私と次男のやり取り・・
父 「●●と、この間のメールのこと憶えてる?」
次男 「うん。 おぼえてるよぉ」
父 「お父さん明日急きょ休みになったんだよねぇ」
次男 「ふーん。 ・・・んで」
父 「山、いくか?あした」
父 「山頂で食べるラーメンうまいんだよねー」
次男 「何山?いくのぉ」
父 「何処にする?」
次男 「月山、火山なら良いよー」
父 「・・・・・???」
父 「それって山は山でも食物家・・?」 (なんだよぉ、もぉ。)って感じでした。
息子はどうやら山よりも食べ物家の方が好いみたいで、結局その夜は折合いが付かず寝ることに。正直この時点で山行きは半ば諦めていました。
替わって翌朝、朝食を済ませ炬燵でテレビを見ヌクヌクしていると2階から勢いよく次男が私のとなりに繰るなり
「今日、山いくの・・?」・・・しばし無言の私。
すると、「お父さん着るもの貸して。靴はどれ履けばいいのぉ」の声が。
こうなれば話しは早い。速攻出かける準備をする。
近くのコンビニで食料を買い込み家から車で15分で行ける古賀志山へと向かう。赤川ダム下の駐車場に到着。 時間はすでに11時ちょうど。
いつになく車が多く三段下の駐車場にようやく空きスペースを見つけて車を止めやっと出発である。
今日のコースは急だったので特に決めてなく、なんとなく足の向くまま北登山口へ。でもこのまま登るのもつまらいし・・
・・て、ことで東稜の見晴台へ南側から登りはじめることに。
最初は一緒のペースで歩いていたのだが、だんだんと私が遅れをとるようになる。 いやはやなんとも10代の若さが羨ましい。
直登に近い鎖場をなんなく越え見晴し台に着く、案の定昼どきで満杯である。仕方なくそのまま古賀志山頂へと向う。
するとどうでしょう。こちらはがらがらです。 ラッキー!!!
一番南側のテーブルに場所をとりお楽しみの昼食です♪
おにぎりとお気に入りのカップラーメンを頬張りしばしまったりとした親子の時間を過ごしました。おなかも満たされこのまま降るのも芸がないので
御岳山まで足をのばすことになり午後の部開始である。
親子での登山の証しにカメラのシャッターをお願いすべく5人組のご年配の方のひとりに頼み記念撮影。するとメンバーの一人の女性が僕が2人分の荷物を背負ってることに気付き冷かされる始末に。そうなのです、息子はノーザックだったのです。お父さんは甘いのひと言が・・・
でも、もう一人の女性の方が家にも大学生の息子がいるので何となく気持ちは解かりますよとの優しいお声がけ。 そうですか、ありがとうございます。そんな他愛もない会話をしつつメンバー達に別れを告げ登山道へとすすむ。
ところがこの先がほとんど日陰の為、アイスバーン状態ですべるのなんのって。いつもは10分で行ける距離を30分ほどかかりやっとの思いで御岳山頂に着いたのである。ここでも記念の証しを取りそうそうに来た道を恐る恐る戻ったのである。
帰路は残雪のない南登山道を下りることに50分ほどで駐車場に帰ってきました。 この日は天気が良かったのもあり森林公園は家族連れでとても賑わっていました。駐車場が一杯だったのは登山客だけじゃ無かったみたいです。
と言うことで、久々に親子の時間を過ごせた一日でした。
こういう時が「近いうちにまたあれば好いなーと!」・・と願う父である。



タグ :栃木
2010年02月23日
女峰山(2010.2.21)
祝 冬期赤薙山~女峰山ピストン
2010年2月21日 栃木県日光市 赤薙山~女峰山 記録者 あっちゃん
先週の辛い体験と苦い経験の記憶がまだ新しい金曜日
来週は家族に付き合ってお買い物と決めていたのですが、
不意にかみさんから「今回は買い物に行かないから山に行ってくれば~。」と言われ
敗退の悔しさから毎夜自分の体を苛める様に厳しくトレーニングしていたのですが、(当初の目標は28日にトライする予定でした。)その一言でいきなり心に火が灯り心も体も戦闘モードに。
ネットで天候をチッェクしたところ今度の日曜日は気候が安定して絶好の登山日和みたいです。
当日深夜2時に起床
前回同様に総ての支度を前日に夜に済ませ身支度を整え愛車に乗り込みひた走ります。
15分ほど走ったところでメールのチェックと思い携帯電話を探すのですが見当たらず良く良く考えてみたら自分の枕元に忘れてきたようです。
非常時の連絡や下山メールなどに必ず使うし不要な心配を掛けないためにもわざわざ取りに引き返しました。
自宅に着いたとき室内から物音がしてカミサンが携帯を手にして裏口に立って「気を付けてね~。」と一言。
何と無く勇気付けられ「何だか 行けそうな気がする~」と呟きながら最近お気に入りのエルレ ガーデンのCDをガンガンかけて再び車を一路霧降高原へ・・・。
今回は少し早めに歩き出す予定で早起きしたのですが結局前回とあまり変わらない時間に到着。
AM4時15分に駐車場を出発、赤薙山に向けてひた歩きます。
前回の様な疲労感は感じられずとても快調です。
今回はスノーシュウは履かずに初めからアイゼンにしたのが正解だったようでとても歩きやすく
スピードも早いようです。
沢山のトレースがありとても楽チン!!
さすがに人気の山です。
赤薙山到着5時51分
小休止のあとさきを目指します。
ここから先は前回歩いた自分のトレースが所々にあるだけでかなり新鮮味があります。
ラッセルマニアの心を満たすには十分の積雪と不意にはまり込む落とし穴があり息も上がります。



空は白み始め東の方が明るくなりかけたころ急に風が吹き
風速15~20メーターはあろうかと思われる突風が右へ左へ吹き荒れ
足場の危うい尾根や岩場では何度かヒヤリとさせられたのですが1時間ほどで穏やかになり一安心!
奥社跡到着6時45分
オニギリを一つ食べ水分を補給して先を急ぎます。
気持ち良い陽射しの中足取りは快調です。
しかし、長い登りと分かりにくいトレースに少しペースを乱され歩きやすい硬い雪面を探しながら辿り一里ヶ曽根がとても遠く感じられ、なかなか辛いところです。
 一里ヶ曽根到着8時00分
一里ヶ曽根到着8時00分
前回より2時間30分も早い到着どぇっす。
時計を見た時自分もビックリでした。
事前に休憩する場所を決め、その間はゆっくりでも歩き続けることを心がけたのが良かったようです。
ここでまたエネルギーを補給して目の前に聳える女峰山を目指します。
樹林帯を過ぎ山頂が見渡せる尾根に取り付いた時、事前に予定していた通りにザックをデポして空身で山頂へ向かいます。
とは言っても連絡用の携帯、記録用のGPS、コンデジ、ミニ三脚はポケットに詰め込み、片手にはグリベルのピッケルを握り締め今回山行の最大の難所に気合を入れ挑みます。
2箇所、急な岩場の斜面がありおそらくガリガリに凍り付いてかなり危険で在ろうと想像していたのですが、やはりアイゼンのケッツアがやっと食い込むぐらいにカチカチで殆どアイスクライミングに近い登りが30メーターほど滑ったら間違いなく150メーター滑落してしまうであろう急斜面を一気に駆け上がりました。
正に『行きはよいよい帰りは怖い・・」の心境でしたがまずは憧れた女峰山山頂へ
 女峰山登頂10時15分
女峰山登頂10時15分
ついに到着しました。
快晴無風、紺碧の空
轟音を遥か後方に響かせながら通り過ぎるいつもより一回り大きなジェット旅客機
いつもと違うアングルから見渡せる山々
誰もいない山頂はこの一時だけは自分だけのものです。
心地よい疲労感と達成感が心と体に染み渡り何とも言えない満足感が体を包み込み最高の気分です!!
暫く休んで景色を眺め、また来ることを心に誓い山頂を後にしました。
 気持ちよい尾根を下りながらさっき越えてきた岩場の下りが気になります。
気持ちよい尾根を下りながらさっき越えてきた岩場の下りが気になります。
登りより下りの方が恐怖感がありそうで『慎重に行こう!!」と呟きながら暫く下ると程なく切れ落ちた岩場です。
後ろ向きになり足場を確認しながら下るのですが、あまり手がかりも無くピッケルだけが頼りです。
一歩一歩慎重に下り何とか安心できる所まで降りた時「あぁ~、やっと帰れる」と思えたのでした。
後はひたすら歩くのみ、殆ど休まず下山です。
駐車場到着14時29分
思ったよりずいぶん早く下山出来ました。
今回の山行では、丈夫に生んでくれた両親に感謝すると共に、日頃のトレーニングの成果とその内容の見直しが必要かな。
あと、道具も2~3欲しいものが・・・・
あと背中を押してくれたカミサンに感謝です!!
さて、次はどこに行こうかな~。
2010年2月21日 栃木県日光市 赤薙山~女峰山 記録者 あっちゃん
先週の辛い体験と苦い経験の記憶がまだ新しい金曜日
来週は家族に付き合ってお買い物と決めていたのですが、
不意にかみさんから「今回は買い物に行かないから山に行ってくれば~。」と言われ
敗退の悔しさから毎夜自分の体を苛める様に厳しくトレーニングしていたのですが、(当初の目標は28日にトライする予定でした。)その一言でいきなり心に火が灯り心も体も戦闘モードに。
ネットで天候をチッェクしたところ今度の日曜日は気候が安定して絶好の登山日和みたいです。
当日深夜2時に起床
前回同様に総ての支度を前日に夜に済ませ身支度を整え愛車に乗り込みひた走ります。
15分ほど走ったところでメールのチェックと思い携帯電話を探すのですが見当たらず良く良く考えてみたら自分の枕元に忘れてきたようです。
非常時の連絡や下山メールなどに必ず使うし不要な心配を掛けないためにもわざわざ取りに引き返しました。
自宅に着いたとき室内から物音がしてカミサンが携帯を手にして裏口に立って「気を付けてね~。」と一言。
何と無く勇気付けられ「何だか 行けそうな気がする~」と呟きながら最近お気に入りのエルレ ガーデンのCDをガンガンかけて再び車を一路霧降高原へ・・・。
今回は少し早めに歩き出す予定で早起きしたのですが結局前回とあまり変わらない時間に到着。
AM4時15分に駐車場を出発、赤薙山に向けてひた歩きます。
前回の様な疲労感は感じられずとても快調です。
今回はスノーシュウは履かずに初めからアイゼンにしたのが正解だったようでとても歩きやすく
スピードも早いようです。
沢山のトレースがありとても楽チン!!
さすがに人気の山です。
赤薙山到着5時51分
小休止のあとさきを目指します。
ここから先は前回歩いた自分のトレースが所々にあるだけでかなり新鮮味があります。
ラッセルマニアの心を満たすには十分の積雪と不意にはまり込む落とし穴があり息も上がります。



空は白み始め東の方が明るくなりかけたころ急に風が吹き
風速15~20メーターはあろうかと思われる突風が右へ左へ吹き荒れ
足場の危うい尾根や岩場では何度かヒヤリとさせられたのですが1時間ほどで穏やかになり一安心!
奥社跡到着6時45分
オニギリを一つ食べ水分を補給して先を急ぎます。
気持ち良い陽射しの中足取りは快調です。
しかし、長い登りと分かりにくいトレースに少しペースを乱され歩きやすい硬い雪面を探しながら辿り一里ヶ曽根がとても遠く感じられ、なかなか辛いところです。
 一里ヶ曽根到着8時00分
一里ヶ曽根到着8時00分前回より2時間30分も早い到着どぇっす。
時計を見た時自分もビックリでした。
事前に休憩する場所を決め、その間はゆっくりでも歩き続けることを心がけたのが良かったようです。
ここでまたエネルギーを補給して目の前に聳える女峰山を目指します。
樹林帯を過ぎ山頂が見渡せる尾根に取り付いた時、事前に予定していた通りにザックをデポして空身で山頂へ向かいます。
とは言っても連絡用の携帯、記録用のGPS、コンデジ、ミニ三脚はポケットに詰め込み、片手にはグリベルのピッケルを握り締め今回山行の最大の難所に気合を入れ挑みます。
2箇所、急な岩場の斜面がありおそらくガリガリに凍り付いてかなり危険で在ろうと想像していたのですが、やはりアイゼンのケッツアがやっと食い込むぐらいにカチカチで殆どアイスクライミングに近い登りが30メーターほど滑ったら間違いなく150メーター滑落してしまうであろう急斜面を一気に駆け上がりました。
正に『行きはよいよい帰りは怖い・・」の心境でしたがまずは憧れた女峰山山頂へ
 女峰山登頂10時15分
女峰山登頂10時15分ついに到着しました。
快晴無風、紺碧の空
轟音を遥か後方に響かせながら通り過ぎるいつもより一回り大きなジェット旅客機
いつもと違うアングルから見渡せる山々
誰もいない山頂はこの一時だけは自分だけのものです。
心地よい疲労感と達成感が心と体に染み渡り何とも言えない満足感が体を包み込み最高の気分です!!
暫く休んで景色を眺め、また来ることを心に誓い山頂を後にしました。
 気持ちよい尾根を下りながらさっき越えてきた岩場の下りが気になります。
気持ちよい尾根を下りながらさっき越えてきた岩場の下りが気になります。登りより下りの方が恐怖感がありそうで『慎重に行こう!!」と呟きながら暫く下ると程なく切れ落ちた岩場です。
後ろ向きになり足場を確認しながら下るのですが、あまり手がかりも無くピッケルだけが頼りです。
一歩一歩慎重に下り何とか安心できる所まで降りた時「あぁ~、やっと帰れる」と思えたのでした。
後はひたすら歩くのみ、殆ど休まず下山です。
駐車場到着14時29分
思ったよりずいぶん早く下山出来ました。
今回の山行では、丈夫に生んでくれた両親に感謝すると共に、日頃のトレーニングの成果とその内容の見直しが必要かな。
あと、道具も2~3欲しいものが・・・・
あと背中を押してくれたカミサンに感謝です!!
さて、次はどこに行こうかな~。
タグ :栃木
2010年02月17日
女峰山 改 一里ヶ曽根(2010.2.14)
赤薙山~一里ヶ曽根
2010年2月14日 栃木県日光 赤薙山~一里ヶ曽根 記録者 あっちゃん
今回は、霧降高原の駐車場から赤薙山~奥社跡~ヤハズ~一里ヶ曽根~女峰山を日帰りで踏破するべく
深夜3時に起床、
前夜から登山の準備を済ませ、装備を詰め込んだ愛車に乗り込み一路日光へ・・・・。
4時15分駐車場に到着。
まだ真っ暗な中ただ一人黙々と準備を済ませ
ヘッデンの明かりを頼りに歩き始めます。
ゲレンデ跡の急な斜面に息が上がり結構辛く
何と無く今日の体調はあまり良く無い様な気がして少し不安になり
下界の夜景の美しさに勝手に哀愁を感じ感動しつつも
この先の雪の状態が気になります。
ここ数日天気は荒れ模様で今日だけつかの間の晴れ間が期待出来そうとのこと、
予想では、適当な硬さの雪とその上にふんわりと乗っかった新雪の斜面を想像していたのですが
以外に最中状態の雪質で
この後大変な苦労が待って居ようとは思いもせず歩を進めます。
東の空が段々と赤く染まり空の雲の状態が目視出来始めたころ
町の夜景が色あせ、山の形がハッキリしてきます。
直感で「今日の天気が持つのはお昼までだな~。」と感じ行動時間を逆算して
早くも「今回は無理かもな~」と頭の中で自分と違う誰かが囁き
「そうかもね~。」と一人呟く自分がいました。(この時点でまだ赤薙山頂のずいぶん手前でした。)


6時50分赤薙山到着
下からスノーシュウを履いてきたのですがクラストした急斜面では歯が立たず
ズルズルと滑りかなり体力を消耗してしまい結構バテましたが
今年の西暦と同じ標高の2010メートル
今年は登ろうと考えていたので、誰もいない山頂で一人ニヤニヤしながら鳥居をパチリと一枚
小休止の後再び気合を入れ先を目指します。
この先は誰のトレースも無くルートの確認や不安定な足元に悩まされ遅々として距離が伸びず時間ばかりが過ぎて行きかなりテンションが下がります。
アイゼンに履き替えかなり危うい尾根筋を辿り樹林帯を潜り行くと
日向になる部分は表面が硬く比較的歩きやすいのですが
日陰の部分になるとたちまち脆くなり、場所によっては下腹部までもぐり
今まで経験したことの無いラッセルが始まります。
まるで、落とし穴様な雪の斜面はやる気と体力をどんどん自分の体から奪い取ってゆくのでした。
何度落ちたか忘れたころアクシデントが・・・・。
右足が取られた瞬間バランスを崩し、左足のケッツァの部分で自分の右足のフクラハギを蹴り飛ばしてしまい、右足に激痛が・・・。
ここは冷静にと自分に言い聞かせ暫く休んで様子を見たところ外傷も無く段々痛みも和らいできたので
先を目指すことに決め再び歩き始めます。


奥社跡で小休止してヤハズの痩せ尾根を通過
再び樹林帯に入り不規則で予測不能な落とし穴が何度も襲ってきます。
そしてまた同じところを蹴っ飛ばしてしまい思わず「ガッデム!!」「サノバビッチッ!!」と叫ぶ自分でした。
正直この時点でやる気0パーセント
せめて切のよい所で一里ヶ曽根までは行こうと思い
半ば気力だけで何とか辿り着きました。
時間は10時20分
目の前に女峰山が見えるのですが
夏道で約1時間
この状態だと良くて片道2時間半は掛かるだろうと思った時
今回は諦めることにしました。
暫く女峰山を眺めデッカイ声でリベンジを誓い帰路に着きました。


予想はしていたのですが雪山の女峰山は厳しかった!!
帰りは自分のトレースがあるので安心でしたが落とし穴はいたる所にあり
かなり苦労させられました。
次回天候次第でもう一度チャレンジしたいと思います。
今回の山行で実感が掴めたのと、女峰山の頂になんとしても立ってみたい気持ちがさらに高まったのです。
気持ちと体の調子を上げて、来るべき日のためにトレーニングに励みたいと思います。
さ~てと!
頑張るべ~てか~!!
2010年2月14日 栃木県日光 赤薙山~一里ヶ曽根 記録者 あっちゃん
今回は、霧降高原の駐車場から赤薙山~奥社跡~ヤハズ~一里ヶ曽根~女峰山を日帰りで踏破するべく
深夜3時に起床、
前夜から登山の準備を済ませ、装備を詰め込んだ愛車に乗り込み一路日光へ・・・・。
4時15分駐車場に到着。
まだ真っ暗な中ただ一人黙々と準備を済ませ
ヘッデンの明かりを頼りに歩き始めます。
ゲレンデ跡の急な斜面に息が上がり結構辛く
何と無く今日の体調はあまり良く無い様な気がして少し不安になり
下界の夜景の美しさに勝手に哀愁を感じ感動しつつも
この先の雪の状態が気になります。
ここ数日天気は荒れ模様で今日だけつかの間の晴れ間が期待出来そうとのこと、
予想では、適当な硬さの雪とその上にふんわりと乗っかった新雪の斜面を想像していたのですが
以外に最中状態の雪質で
この後大変な苦労が待って居ようとは思いもせず歩を進めます。
東の空が段々と赤く染まり空の雲の状態が目視出来始めたころ
町の夜景が色あせ、山の形がハッキリしてきます。
直感で「今日の天気が持つのはお昼までだな~。」と感じ行動時間を逆算して
早くも「今回は無理かもな~」と頭の中で自分と違う誰かが囁き
「そうかもね~。」と一人呟く自分がいました。(この時点でまだ赤薙山頂のずいぶん手前でした。)


6時50分赤薙山到着
下からスノーシュウを履いてきたのですがクラストした急斜面では歯が立たず
ズルズルと滑りかなり体力を消耗してしまい結構バテましたが
今年の西暦と同じ標高の2010メートル
今年は登ろうと考えていたので、誰もいない山頂で一人ニヤニヤしながら鳥居をパチリと一枚
小休止の後再び気合を入れ先を目指します。
この先は誰のトレースも無くルートの確認や不安定な足元に悩まされ遅々として距離が伸びず時間ばかりが過ぎて行きかなりテンションが下がります。
アイゼンに履き替えかなり危うい尾根筋を辿り樹林帯を潜り行くと
日向になる部分は表面が硬く比較的歩きやすいのですが
日陰の部分になるとたちまち脆くなり、場所によっては下腹部までもぐり
今まで経験したことの無いラッセルが始まります。
まるで、落とし穴様な雪の斜面はやる気と体力をどんどん自分の体から奪い取ってゆくのでした。
何度落ちたか忘れたころアクシデントが・・・・。
右足が取られた瞬間バランスを崩し、左足のケッツァの部分で自分の右足のフクラハギを蹴り飛ばしてしまい、右足に激痛が・・・。
ここは冷静にと自分に言い聞かせ暫く休んで様子を見たところ外傷も無く段々痛みも和らいできたので
先を目指すことに決め再び歩き始めます。


奥社跡で小休止してヤハズの痩せ尾根を通過
再び樹林帯に入り不規則で予測不能な落とし穴が何度も襲ってきます。
そしてまた同じところを蹴っ飛ばしてしまい思わず「ガッデム!!」「サノバビッチッ!!」と叫ぶ自分でした。
正直この時点でやる気0パーセント
せめて切のよい所で一里ヶ曽根までは行こうと思い
半ば気力だけで何とか辿り着きました。
時間は10時20分
目の前に女峰山が見えるのですが
夏道で約1時間
この状態だと良くて片道2時間半は掛かるだろうと思った時
今回は諦めることにしました。
暫く女峰山を眺めデッカイ声でリベンジを誓い帰路に着きました。


予想はしていたのですが雪山の女峰山は厳しかった!!
帰りは自分のトレースがあるので安心でしたが落とし穴はいたる所にあり
かなり苦労させられました。
次回天候次第でもう一度チャレンジしたいと思います。
今回の山行で実感が掴めたのと、女峰山の頂になんとしても立ってみたい気持ちがさらに高まったのです。
気持ちと体の調子を上げて、来るべき日のためにトレーニングに励みたいと思います。
さ~てと!
頑張るべ~てか~!!
タグ :栃木
2010年02月09日
筑波山(2010.2.7)
筑波山
2010年2月7日 茨城県 筑波山 記録者 副隊長
期末テストを控えて息子の部活が休みとなったこの日曜日。女房が顔をしかめるのを見て見ぬ振りを決め込んで息子を伴っての筑波山登山となった。原くんや酒田のじっちゃんとお馴染みの顔に加えて哲ちゃんと大野さんが緊急参加となり賑やかなパーティーでの霊峰筑波山登山である。
霊峰と書いたのには少なからず訳が有る。筑波山は独立峰として見られがちだが実際のところは八溝山脈の南端となる。二つの頂を持つその独特の雄姿で知られ、深田百名山に名を連ねる山である。「峰の上に降り置ける雪し風の共ここに散るらし春にはあれども」など万葉集にいくつも詠われた筑波嶺。その中腹に建つ筑波山神社は関東に人が住むようになった頃からの古社と伝えられ、双耳峰の一方男体山山頂にはイザナギ、もう一方女体山山頂にはイザナミを祀り山全体を御神体と崇めている。ご存じ様にこの二神は日本神話において数々の神々を生んだ親神として知られているがこの神社は縁結び・夫婦円満・家内安全・子授け・子育てにご神徳があるとされている。丁度この日の下山時に神殿で将来を誓い合った若い二人が境内を歩く晴れの姿に出会ったものだ。
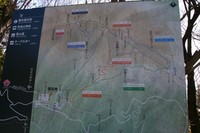


さて、筑波山登山の起点にもなる筑波山神社。この神社から延び二つのルートを今回利用する計画だ。登りは途中いくつもの奇岩を巡りながら歩く「白雲橋コース」。登り始めはスギ林の中を石の階段が続く。喉が痛く感じられる冬の冷たい空気を吸い込む。久しぶりに登る山道に身体がまだ馴染んでいない様で少しだけ足が重い。本調子が出る前に石がゴロゴロする急登に喘がされるが少しの我慢でつつじヶ丘からの登山道を合わせる弁慶茶屋跡に登り着く。ここからはすぐ近くに霞ケ浦がキラキラと輝いて見え足下にはつつじヶ丘が見下ろせる。目の前を通り過ぎるロープウエイに今がチャンスとカメラ向け自分の足で登っている証拠とする。



弁慶茶屋跡を過ぎ「弁慶の七戻り」の巨大岩の下を通り抜ける。いよいよ奇岩巡りが始まる。日本神話で知られる「高天ヶ原」という奇岩に親子でよじ登る。岩の上には立派な祠が有り振り返ると遠く富士山の雄姿が望めた。続いて「母の胎内くぐり」を息子と一緒にくぐる。何か変だけど「まあ、いいか!」。その後も「出船入船」「裏面大黒」「大仏岩」「北斗岩」などがある。表示名を見て「なるほど!」と思うものより「何でだ?」と言う方が多いのはこの手の倣いなのだろう。
さて、そんな奇岩を抜けていよいよ女体山直下の急登。凍り付いた雪に足元を注意しながら一歩一歩登る。老若男女とはよく言ったものでお爺ちゃんやお婆ちゃんが孫を連れて降りて来る姿に出会ったと思えば若いカップルや男同士・女同士の登山者に出会ったりする。よくよく考えれば女体山下にはロープウエイ、男体山下にはケーブルカーと至れり尽くせりの筑波山であるから山頂付近の人口はかなり多いのだ。



さて、手すりに導かれて女体山山頂へ。岩場の手前に一等三角点が埋設されている。御影石マニアとしてはこれをまずカメラに収める。筑波山の標高は従来この三角点の875.9mだったのだが、平成11年11月からは最高点が三角点から少し東寄りの1mほど高い岩盤となり、877mに訂正された。知ってか知らずか哲ちゃんがその岩盤の上に立ち両手を上げているので記念にカメラを向けた。その後で私も息子を伴って最高地点に立ったのは言うまでも無い。



さて、ここで一つ問題が起きた。酒田のじっちゃんが居ないのである。山頂直下を登り始める前に「足が攣った!」とか言っていたので遅れているのだろうと全員でその到着を待ったが一向にその姿は見えない。
まだ来ないとしたら時間的に大そう過ぎているし先に行ったとしたら待っていても離れるばかりと両峰の鞍部に在る「せきれい茶屋」前で思案していると携帯に着信音が響いた。しかし電波状態が悪くて通話に至らずに切れてしまう。相手が酒田のじっちゃんであるのは表示で分かったので生存だけは確認出来た訳である。その後、御幸ヶ原まで出て携帯が繋がり男体山山頂に居ると分かり「救助隊が到着するまで其処を動かないよ~に!」と厳重に注意して一行は男体山へと登り始める。
男体山の山頂はコンクリートで周囲一面を固めた中に大きな祠があり無味乾燥な風景。祠の脇に在る建物の陰に居た酒田のじっちゃんを無事収容。我々が女体山山頂に居る間に男体山を主峰と勘違いして女体山を素通りして来たとの事である。まあ無事に合流出来て一安心。安心したら急に腹が減ったので御幸ヶ原に下り昼食をとることにする。



ラーメン・親子丼・筑波うどん・蕎麦・・・中には○○定食なんてのもある。山の上にこんなにお店が有る所は初めてのぺんぎん隊である。そんな中で定番の山頂ラーメン。登山客(登山者じゃない・・・笑)が「美味しそう!」と言いながら通り過ぎて行く。可愛いお姉さんに「食べますか~?」と言ったら「美味そうだね!」と声を返して来たのはそのお姉さんのオヤジさんらしきおっさんだった。(涙)
腹も膨らんでいよいよ下山。下山のコースはケーブルカーに沿って付けられている「御幸ヶ原コース」を行く。酒田のじっちゃんは女体山山頂を踏んでいないので女体山を登ってからケーブルカーで下って来るという。待ち合わせは駐車場として出発。
ほとんど一直線に筑波山神社へと下るこのコースはそのほとんどが樹林帯で残雪が凍り付きツルツル。一歩一歩滑らない様に慎重に下るのが何ともじれったい。それでも途中ケーブルカーの交換場所でケーブルカーの写真を撮るために小休止を入れながらも40分で神社に到着。丁度ケーブルカーで降りて来た酒田のじっちゃんに出会い、観光客で賑わう筑波山神社の境内を抜けて駐車場に戻った。


 蛇足だが駐車場で着替えを済ませた後、再び温泉街へと戻り立ち寄り湯。今回は「展望露天風呂」という看板に惹かれて「ホテル青木屋」で汗を流した。屋上に作られた展望露天風呂からは関東平野が一望出来る。カラッと晴れた日なら富士山も見えるに違いないが、この日のこの時間帯では霞が出て富士山は見えなかった。
蛇足だが駐車場で着替えを済ませた後、再び温泉街へと戻り立ち寄り湯。今回は「展望露天風呂」という看板に惹かれて「ホテル青木屋」で汗を流した。屋上に作られた展望露天風呂からは関東平野が一望出来る。カラッと晴れた日なら富士山も見えるに違いないが、この日のこの時間帯では霞が出て富士山は見えなかった。
温泉で一日の疲れを洗い流し次回を約して全員解散。「こんな登山も結構面白いなぁ・・」と感じた観光名所の山旅だった。
2010年2月7日 茨城県 筑波山 記録者 副隊長
期末テストを控えて息子の部活が休みとなったこの日曜日。女房が顔をしかめるのを見て見ぬ振りを決め込んで息子を伴っての筑波山登山となった。原くんや酒田のじっちゃんとお馴染みの顔に加えて哲ちゃんと大野さんが緊急参加となり賑やかなパーティーでの霊峰筑波山登山である。
霊峰と書いたのには少なからず訳が有る。筑波山は独立峰として見られがちだが実際のところは八溝山脈の南端となる。二つの頂を持つその独特の雄姿で知られ、深田百名山に名を連ねる山である。「峰の上に降り置ける雪し風の共ここに散るらし春にはあれども」など万葉集にいくつも詠われた筑波嶺。その中腹に建つ筑波山神社は関東に人が住むようになった頃からの古社と伝えられ、双耳峰の一方男体山山頂にはイザナギ、もう一方女体山山頂にはイザナミを祀り山全体を御神体と崇めている。ご存じ様にこの二神は日本神話において数々の神々を生んだ親神として知られているがこの神社は縁結び・夫婦円満・家内安全・子授け・子育てにご神徳があるとされている。丁度この日の下山時に神殿で将来を誓い合った若い二人が境内を歩く晴れの姿に出会ったものだ。
さて、筑波山登山の起点にもなる筑波山神社。この神社から延び二つのルートを今回利用する計画だ。登りは途中いくつもの奇岩を巡りながら歩く「白雲橋コース」。登り始めはスギ林の中を石の階段が続く。喉が痛く感じられる冬の冷たい空気を吸い込む。久しぶりに登る山道に身体がまだ馴染んでいない様で少しだけ足が重い。本調子が出る前に石がゴロゴロする急登に喘がされるが少しの我慢でつつじヶ丘からの登山道を合わせる弁慶茶屋跡に登り着く。ここからはすぐ近くに霞ケ浦がキラキラと輝いて見え足下にはつつじヶ丘が見下ろせる。目の前を通り過ぎるロープウエイに今がチャンスとカメラ向け自分の足で登っている証拠とする。
弁慶茶屋跡を過ぎ「弁慶の七戻り」の巨大岩の下を通り抜ける。いよいよ奇岩巡りが始まる。日本神話で知られる「高天ヶ原」という奇岩に親子でよじ登る。岩の上には立派な祠が有り振り返ると遠く富士山の雄姿が望めた。続いて「母の胎内くぐり」を息子と一緒にくぐる。何か変だけど「まあ、いいか!」。その後も「出船入船」「裏面大黒」「大仏岩」「北斗岩」などがある。表示名を見て「なるほど!」と思うものより「何でだ?」と言う方が多いのはこの手の倣いなのだろう。
さて、そんな奇岩を抜けていよいよ女体山直下の急登。凍り付いた雪に足元を注意しながら一歩一歩登る。老若男女とはよく言ったものでお爺ちゃんやお婆ちゃんが孫を連れて降りて来る姿に出会ったと思えば若いカップルや男同士・女同士の登山者に出会ったりする。よくよく考えれば女体山下にはロープウエイ、男体山下にはケーブルカーと至れり尽くせりの筑波山であるから山頂付近の人口はかなり多いのだ。

さて、手すりに導かれて女体山山頂へ。岩場の手前に一等三角点が埋設されている。御影石マニアとしてはこれをまずカメラに収める。筑波山の標高は従来この三角点の875.9mだったのだが、平成11年11月からは最高点が三角点から少し東寄りの1mほど高い岩盤となり、877mに訂正された。知ってか知らずか哲ちゃんがその岩盤の上に立ち両手を上げているので記念にカメラを向けた。その後で私も息子を伴って最高地点に立ったのは言うまでも無い。

さて、ここで一つ問題が起きた。酒田のじっちゃんが居ないのである。山頂直下を登り始める前に「足が攣った!」とか言っていたので遅れているのだろうと全員でその到着を待ったが一向にその姿は見えない。
まだ来ないとしたら時間的に大そう過ぎているし先に行ったとしたら待っていても離れるばかりと両峰の鞍部に在る「せきれい茶屋」前で思案していると携帯に着信音が響いた。しかし電波状態が悪くて通話に至らずに切れてしまう。相手が酒田のじっちゃんであるのは表示で分かったので生存だけは確認出来た訳である。その後、御幸ヶ原まで出て携帯が繋がり男体山山頂に居ると分かり「救助隊が到着するまで其処を動かないよ~に!」と厳重に注意して一行は男体山へと登り始める。
男体山の山頂はコンクリートで周囲一面を固めた中に大きな祠があり無味乾燥な風景。祠の脇に在る建物の陰に居た酒田のじっちゃんを無事収容。我々が女体山山頂に居る間に男体山を主峰と勘違いして女体山を素通りして来たとの事である。まあ無事に合流出来て一安心。安心したら急に腹が減ったので御幸ヶ原に下り昼食をとることにする。
ラーメン・親子丼・筑波うどん・蕎麦・・・中には○○定食なんてのもある。山の上にこんなにお店が有る所は初めてのぺんぎん隊である。そんな中で定番の山頂ラーメン。登山客(登山者じゃない・・・笑)が「美味しそう!」と言いながら通り過ぎて行く。可愛いお姉さんに「食べますか~?」と言ったら「美味そうだね!」と声を返して来たのはそのお姉さんのオヤジさんらしきおっさんだった。(涙)
腹も膨らんでいよいよ下山。下山のコースはケーブルカーに沿って付けられている「御幸ヶ原コース」を行く。酒田のじっちゃんは女体山山頂を踏んでいないので女体山を登ってからケーブルカーで下って来るという。待ち合わせは駐車場として出発。
ほとんど一直線に筑波山神社へと下るこのコースはそのほとんどが樹林帯で残雪が凍り付きツルツル。一歩一歩滑らない様に慎重に下るのが何ともじれったい。それでも途中ケーブルカーの交換場所でケーブルカーの写真を撮るために小休止を入れながらも40分で神社に到着。丁度ケーブルカーで降りて来た酒田のじっちゃんに出会い、観光客で賑わう筑波山神社の境内を抜けて駐車場に戻った。
温泉で一日の疲れを洗い流し次回を約して全員解散。「こんな登山も結構面白いなぁ・・」と感じた観光名所の山旅だった。
タグ :茨城
2010年02月08日
大霧山(2010.1.30)
大霧山
2010年1月30日 埼玉県東秩父村 大霧山 記録者 たか
比企の名山と言われ、比企三山の一つに数えられる大霧山(766.6m)に登ってきました。
前回までの二つの山は単独でしたが、今回はナカナカさんと私の息子も一緒です。
予定では長瀞の宝登山に行くつもりでしたが、ちょっとしたハプニングで1時間ほど遅れてしまったので、ちょっとだけ近い大霧山に変更です。
車で結構上まで行けるのですが、それだと山頂まで40分ほどで着いてしまうようです。もうちょっと歩きたかったので、橋場バス停から登ることにしました。
橋場バス停には駐車スペースがあり6台くらい車がおけます。
10:42 出発です。
槻川を渡ってしばらくは車道を行きます。知らなかったのですが、この辺りは「ゆず」の産地のようです。
道の傍らにゆずの木がたくさんあり、黄色い実が鈴なりになっています。
庚申塚もありました。
寛政3年(1791年)と彫られています。200年以上も前ですね。この辺りは江戸へ出る道が通っていたようです。



11:33 車道とのp分岐に差し掛かり、やっと長い舗装路歩きも終わります。
ここから車道と分かれて粥仁田峠へと旧道を行きます。
12:04 いったん舗装路に出ますが、すぐに粥仁田峠です。
ここが秩父から江戸へと続く古い道だったようです。
峠の茶屋があるわけでもなく、小さな東屋があるだけのひっそりした峠でした。
ここまで車で来れば歩行時間を大幅に短縮することができます。
この登山口のちょっと下に3台くらい駐車できそうでした。
峠の東屋で一休みしたら、いよいよ大霧山の頂上へと向かって出発です。
登山道に入ったとたん急登です。急斜面が続きます。
この辺りは落葉樹の森で冬場は葉が落ちて陽の光が差し込みます。



12:53 大霧山(766.6m)の頂上に着きました。
素晴らしい青空が広がっています。
ここ大霧山の見晴らしは格別です。



遠くの山々まで見晴らせる素晴らしい展望でした。
真っ白な浅間山も見えました。噴煙が上がっています。
正面のギザギザの山は百名山のひとつ両神山です。
その左に白い山が頭を出しています。これが八ヶ岳(横岳、赤岳)です



大霧山は見晴らしもよく、素晴らしい山でした。舗装路歩きは残念ですが、途中ショートカットする道に入れば登山道っぽく楽しめます。舗装路との分岐を過ぎるとあとは山頂まで山の中を行く道です。
子供を連れての登山には絶好のコースですね。川を挟んで東には比企三山の残り2つ、笠山と堂平山があります。今度はそちらに登って比企三山をコンプリートしたいです。
2010年1月30日 埼玉県東秩父村 大霧山 記録者 たか
比企の名山と言われ、比企三山の一つに数えられる大霧山(766.6m)に登ってきました。
前回までの二つの山は単独でしたが、今回はナカナカさんと私の息子も一緒です。
予定では長瀞の宝登山に行くつもりでしたが、ちょっとしたハプニングで1時間ほど遅れてしまったので、ちょっとだけ近い大霧山に変更です。
車で結構上まで行けるのですが、それだと山頂まで40分ほどで着いてしまうようです。もうちょっと歩きたかったので、橋場バス停から登ることにしました。
橋場バス停には駐車スペースがあり6台くらい車がおけます。
10:42 出発です。
槻川を渡ってしばらくは車道を行きます。知らなかったのですが、この辺りは「ゆず」の産地のようです。
道の傍らにゆずの木がたくさんあり、黄色い実が鈴なりになっています。
庚申塚もありました。
寛政3年(1791年)と彫られています。200年以上も前ですね。この辺りは江戸へ出る道が通っていたようです。



11:33 車道とのp分岐に差し掛かり、やっと長い舗装路歩きも終わります。
ここから車道と分かれて粥仁田峠へと旧道を行きます。
12:04 いったん舗装路に出ますが、すぐに粥仁田峠です。
ここが秩父から江戸へと続く古い道だったようです。
峠の茶屋があるわけでもなく、小さな東屋があるだけのひっそりした峠でした。
ここまで車で来れば歩行時間を大幅に短縮することができます。
この登山口のちょっと下に3台くらい駐車できそうでした。
峠の東屋で一休みしたら、いよいよ大霧山の頂上へと向かって出発です。
登山道に入ったとたん急登です。急斜面が続きます。
この辺りは落葉樹の森で冬場は葉が落ちて陽の光が差し込みます。



12:53 大霧山(766.6m)の頂上に着きました。
素晴らしい青空が広がっています。
ここ大霧山の見晴らしは格別です。



遠くの山々まで見晴らせる素晴らしい展望でした。
真っ白な浅間山も見えました。噴煙が上がっています。
正面のギザギザの山は百名山のひとつ両神山です。
その左に白い山が頭を出しています。これが八ヶ岳(横岳、赤岳)です



大霧山は見晴らしもよく、素晴らしい山でした。舗装路歩きは残念ですが、途中ショートカットする道に入れば登山道っぽく楽しめます。舗装路との分岐を過ぎるとあとは山頂まで山の中を行く道です。
子供を連れての登山には絶好のコースですね。川を挟んで東には比企三山の残り2つ、笠山と堂平山があります。今度はそちらに登って比企三山をコンプリートしたいです。
タグ :埼玉
2010年02月04日
那須縦走 プチ遭難
那須縦走
2010年1月31日 栃木県那須 茶臼岳~南月山~黒尾谷岳 記録者 あっちゃん
今回はクロヤスさんと二人で茶臼岳~南月山~黒尾谷岳と縦走してきました。
大丸温泉駐車場で支度をし、山を眺めながら検討したところ一般の登山道には先行者が多数居る様なので誰も歩いていないスキー場側の斜面を登り茶臼岳方面に登ることに決め真新しいトレースを刻みながら快調に高度を上げていきます。
下から眺めたときは山頂まで近いような気がしていたのですが急登を過ぎた先がだらだらの斜面で結構疲れました。


牛が首付近から茶臼岳を眺めるとなんとそこにはヨーロッパの山並みを思わせるような岩峰が青空に聳え立っており、暫し目を奪われるのでした。
那須にしてはこの時期に珍しい程の快晴美風で何とも心地よいお天気!
気分は最高です!


色んな話をしながら快調に歩を進め
程なく南月山頂へたどり着き木製ベンチに腰掛この後起こる非常事態も予期せぬまま美味しく山頂ラーメンを頂ながら談笑する二人でした。
食事も済んだころ俄かに靄が濃くなりどんどん視界がなくなっていきます。
そそくさと身支度を済ませ先を急ぐことに・・・・・・。
ここに一つの油断がありました。
南月山から黒尾谷岳までのルートを二人とも良く把握しておらず安直に尾根を辿れば辿り着けると思い込み斜面を降りたのですが当てにしていた目印も殆ど無く登山道は雪に埋もれどこなのかハッキリ確認できません。
しかも、靄が段々濃くなり展望が利かなくなり地図も良く確認しないままどんどん下って行ったのが運の尽き完全にロストしてしまい5回6回と行ったり来たりを繰り返し段々ドツボに嵌っていき、何とか黒尾谷岳山頂に辿りついた時はもう辺りは薄暗くなり
ヘッデンを点けての下山となりました。
しかし、ここからも苦難の下山!
まったく登山者がいないようでトレースは見当たらず頼りの目印も殆ど見当たらず何度も登山道からはずれトラバースを何度も繰り返しヘッデンの明かりを頼りに必死の下山を続けやっと、住宅街の明かりがちらほら見え少し安心しつつも苦難は続きます!
下山開始から約2時間半なんとか下山することが出来ました。
事前に良くルートを把握していなかったことが最大の敗因ですがもっと慎重に、そして小まめに現在位置と進むべき方向を確認して行動すべきだったと反省仕切りです!
急な斜面を下るときついつい楽な方へ降りてしまい勝ちですが一つ間違うと命とりになってしまう事もあるのだな~と今回のプチ遭難で思い知らされました。
これからは気持ちを入れ替えより慎重にルートファインデングをして行くように心掛けたいと思いました。
緊急ビバーク用の装備も良く検討していかないと万が一の時運命を左右することも身に染みて感じられ今回は良い反省材料になりました!
次回からはこんなことが無いように気を引き締めて楽しい山行を続けたいと思います!
クロヤスさん辛かったけど良い経験でしたね~!
また、よろぴく!!
さて、次はどこに行こうかな~!


2010年1月31日 栃木県那須 茶臼岳~南月山~黒尾谷岳 記録者 あっちゃん
今回はクロヤスさんと二人で茶臼岳~南月山~黒尾谷岳と縦走してきました。
大丸温泉駐車場で支度をし、山を眺めながら検討したところ一般の登山道には先行者が多数居る様なので誰も歩いていないスキー場側の斜面を登り茶臼岳方面に登ることに決め真新しいトレースを刻みながら快調に高度を上げていきます。
下から眺めたときは山頂まで近いような気がしていたのですが急登を過ぎた先がだらだらの斜面で結構疲れました。


牛が首付近から茶臼岳を眺めるとなんとそこにはヨーロッパの山並みを思わせるような岩峰が青空に聳え立っており、暫し目を奪われるのでした。
那須にしてはこの時期に珍しい程の快晴美風で何とも心地よいお天気!
気分は最高です!


色んな話をしながら快調に歩を進め
程なく南月山頂へたどり着き木製ベンチに腰掛この後起こる非常事態も予期せぬまま美味しく山頂ラーメンを頂ながら談笑する二人でした。
食事も済んだころ俄かに靄が濃くなりどんどん視界がなくなっていきます。
そそくさと身支度を済ませ先を急ぐことに・・・・・・。
ここに一つの油断がありました。
南月山から黒尾谷岳までのルートを二人とも良く把握しておらず安直に尾根を辿れば辿り着けると思い込み斜面を降りたのですが当てにしていた目印も殆ど無く登山道は雪に埋もれどこなのかハッキリ確認できません。
しかも、靄が段々濃くなり展望が利かなくなり地図も良く確認しないままどんどん下って行ったのが運の尽き完全にロストしてしまい5回6回と行ったり来たりを繰り返し段々ドツボに嵌っていき、何とか黒尾谷岳山頂に辿りついた時はもう辺りは薄暗くなり
ヘッデンを点けての下山となりました。
しかし、ここからも苦難の下山!
まったく登山者がいないようでトレースは見当たらず頼りの目印も殆ど見当たらず何度も登山道からはずれトラバースを何度も繰り返しヘッデンの明かりを頼りに必死の下山を続けやっと、住宅街の明かりがちらほら見え少し安心しつつも苦難は続きます!
下山開始から約2時間半なんとか下山することが出来ました。
事前に良くルートを把握していなかったことが最大の敗因ですがもっと慎重に、そして小まめに現在位置と進むべき方向を確認して行動すべきだったと反省仕切りです!
急な斜面を下るときついつい楽な方へ降りてしまい勝ちですが一つ間違うと命とりになってしまう事もあるのだな~と今回のプチ遭難で思い知らされました。
これからは気持ちを入れ替えより慎重にルートファインデングをして行くように心掛けたいと思いました。
緊急ビバーク用の装備も良く検討していかないと万が一の時運命を左右することも身に染みて感じられ今回は良い反省材料になりました!
次回からはこんなことが無いように気を引き締めて楽しい山行を続けたいと思います!
クロヤスさん辛かったけど良い経験でしたね~!
また、よろぴく!!
さて、次はどこに行こうかな~!


タグ :栃木
2010年02月01日
大菩薩嶺
大菩薩嶺
10年1月30日(土) 快晴 参加者:jun1&木偶野呂馬 記録:木偶野呂馬


豊科IC発4:00で6:15頃丸川峠分岐P着。道路は封鎖されておりここから歩く。6:40発。車道を10分で千石平の小屋への橋を渡ってここから登山道となる。2人とも地理不案内の上に計画は全部jun1さんにお任せで地図も持たず、ただ相方についと行くだけ。jun1さんは軽登山靴で快調に飛ばすがこちらは壊れかけたプラブーツで足取り重く、このところ5分くらい後をひたすら追いかけることが多い。


千石平から尾根をひたすら登ること20分で後方に南アルプスと思われる白銀の山なみが紅く染まりながら浮かび上ってくるのを見る。
7:16,第1展望台に着き山の形から山名を特定しようと試みるが、甲斐駒ヶ岳のみそれと分かる他は殆ど分からない。分からないままに甲斐駒の南に雪を頂く山を仙丈ヶ岳,その南を北岳,続いて間ノ岳,農鳥岳,塩見岳~荒川三山であろうと推測する。白く輝いている筈の鳳凰三山を擁する支脈は目立たない黒尾根ですぐにはそれと分からなかった。


10分ほど歩くとブナの若木が現れる。鍋倉山等、北信のブナと違って雪圧を受けず根元からまっすぐ伸びているのが若々しい感じでありまた物足りなくもある。
7:40,第2展望台で休憩中に上がってきた人に山座を聞くとほぼ推測通りだった。北岳をこちら側から見るのは初めてで結構端正な形をしていると思った。


尾根の北側の沢を隔てて大きく迂回していた林道が一旦接近する辺りの道は、登山道によって表土を失った山肌が雨に激しく浸食されて人の背丈,あるいはその倍ほども抉れており、歩けなくなったその道の傍に新しい道が設けられている所が多く、古い道に向かって土砂が崩落したり大木が倒れ込んでいるのが目につく。登山道による山肌の荒れはどこにでもあるがこれほど酷いところは珍しいと思った。


8:25上日川峠,ロッジ長兵衛(冬期無人)着。トイレ(10分)休憩の後出発。林道にほぼ並行する林間の登山道を行く。日陰で凍結しているので時おり滑る。
9:35福ちゃん荘着。事前研究をしていなかったが峠から大菩薩嶺に向かうものと思っていたところ、jun1さんの選択は逆周りの唐松コースだった。どっちでもよかったが大菩薩嶺から丸川峠に下るコースは消えた。


唐松コースは前半こそ緩やかだが唐松林にかかる辺りから斜度を増し、最後の150mはかなりの急登になるのだが下から見上げると草つきの稜線がなだらかに見えるので歩いている実感としては余計にきつい。


だが樹林帯を抜ける辺りから振り返る目に飛び込んでくる雄大な富士の姿がそれを癒してくれる。立ち止まり振り返るごとに富士もまた競りあがり、遮るもののない雄大なその広がりに爽快感がいや増す。


10:32,見上げて目標にしてきた雷岩を標識でそれと知り、追いかけてjun1さんに遅れること5分で大菩薩嶺に到達。展望も何もなく寒いだけのその場では証拠写真を撮る以外に用はなく、すぐに引き返して大菩薩嶺に向かう。


稜線に戻ると北側から若干の風はあるものの雲1つない快晴に八ヶ岳から丹沢山塊辺りまで,100点満点の大展望が広がる。


その景観を楽しみながらルンルンで2000m地点(妙見ノ頭?)を越え、避難小屋まで下って暑いほどの日差しを浴びながら早目の昼食休憩をとる。このところ好天に恵まれている。


11:30発。目の前の丘に立つと眼下に大菩薩峠の小屋が見え10分で介山荘に着く。


山座を記した方向盤で山名を調べるとほぼ真東の方向に大岳山と三頭山の名があった。そうだとすると手前に見えているダムは小河内ダムで下の集落は小菅村と言うことになるのかな・・?
在京時代に五日市や桧原村で仕事をしたり、小菅村や丹波山村を走り回ったことはあるが登山の機会を得ず、いつかこれらの山々を高いところから眺めたいと思っていたが、図らずもそれが叶った。これで奥多摩と大菩連嶺が鳥の目で繋がり、両者を結ぶ縦走ラインを考えてみたりした。


11:45発,殆どが日陰の林道を下る。所によっては道の全面がカチカチに凍ってアイゼンなしには歩けないほどで、一度ならずもんどりうって転倒ししたたか腰を打つ。


勝緑荘,富士見山荘と下って12:21福ちゃん荘,さらに林道を下って12:40ロッジ長兵衛。13:05第2展望台,同17第1展望台を経て13:57帰着。


14:15発,ほったらかしの湯と言うのを探して散々走り回り、露天風呂で大菩薩嶺~大菩薩峠のコースをなぞる。安曇野着は17時頃。
10年1月30日(土) 快晴 参加者:jun1&木偶野呂馬 記録:木偶野呂馬


豊科IC発4:00で6:15頃丸川峠分岐P着。道路は封鎖されておりここから歩く。6:40発。車道を10分で千石平の小屋への橋を渡ってここから登山道となる。2人とも地理不案内の上に計画は全部jun1さんにお任せで地図も持たず、ただ相方についと行くだけ。jun1さんは軽登山靴で快調に飛ばすがこちらは壊れかけたプラブーツで足取り重く、このところ5分くらい後をひたすら追いかけることが多い。


千石平から尾根をひたすら登ること20分で後方に南アルプスと思われる白銀の山なみが紅く染まりながら浮かび上ってくるのを見る。
7:16,第1展望台に着き山の形から山名を特定しようと試みるが、甲斐駒ヶ岳のみそれと分かる他は殆ど分からない。分からないままに甲斐駒の南に雪を頂く山を仙丈ヶ岳,その南を北岳,続いて間ノ岳,農鳥岳,塩見岳~荒川三山であろうと推測する。白く輝いている筈の鳳凰三山を擁する支脈は目立たない黒尾根ですぐにはそれと分からなかった。


10分ほど歩くとブナの若木が現れる。鍋倉山等、北信のブナと違って雪圧を受けず根元からまっすぐ伸びているのが若々しい感じでありまた物足りなくもある。
7:40,第2展望台で休憩中に上がってきた人に山座を聞くとほぼ推測通りだった。北岳をこちら側から見るのは初めてで結構端正な形をしていると思った。


尾根の北側の沢を隔てて大きく迂回していた林道が一旦接近する辺りの道は、登山道によって表土を失った山肌が雨に激しく浸食されて人の背丈,あるいはその倍ほども抉れており、歩けなくなったその道の傍に新しい道が設けられている所が多く、古い道に向かって土砂が崩落したり大木が倒れ込んでいるのが目につく。登山道による山肌の荒れはどこにでもあるがこれほど酷いところは珍しいと思った。


8:25上日川峠,ロッジ長兵衛(冬期無人)着。トイレ(10分)休憩の後出発。林道にほぼ並行する林間の登山道を行く。日陰で凍結しているので時おり滑る。
9:35福ちゃん荘着。事前研究をしていなかったが峠から大菩薩嶺に向かうものと思っていたところ、jun1さんの選択は逆周りの唐松コースだった。どっちでもよかったが大菩薩嶺から丸川峠に下るコースは消えた。


唐松コースは前半こそ緩やかだが唐松林にかかる辺りから斜度を増し、最後の150mはかなりの急登になるのだが下から見上げると草つきの稜線がなだらかに見えるので歩いている実感としては余計にきつい。


だが樹林帯を抜ける辺りから振り返る目に飛び込んでくる雄大な富士の姿がそれを癒してくれる。立ち止まり振り返るごとに富士もまた競りあがり、遮るもののない雄大なその広がりに爽快感がいや増す。


10:32,見上げて目標にしてきた雷岩を標識でそれと知り、追いかけてjun1さんに遅れること5分で大菩薩嶺に到達。展望も何もなく寒いだけのその場では証拠写真を撮る以外に用はなく、すぐに引き返して大菩薩嶺に向かう。


稜線に戻ると北側から若干の風はあるものの雲1つない快晴に八ヶ岳から丹沢山塊辺りまで,100点満点の大展望が広がる。


その景観を楽しみながらルンルンで2000m地点(妙見ノ頭?)を越え、避難小屋まで下って暑いほどの日差しを浴びながら早目の昼食休憩をとる。このところ好天に恵まれている。


11:30発。目の前の丘に立つと眼下に大菩薩峠の小屋が見え10分で介山荘に着く。


山座を記した方向盤で山名を調べるとほぼ真東の方向に大岳山と三頭山の名があった。そうだとすると手前に見えているダムは小河内ダムで下の集落は小菅村と言うことになるのかな・・?
在京時代に五日市や桧原村で仕事をしたり、小菅村や丹波山村を走り回ったことはあるが登山の機会を得ず、いつかこれらの山々を高いところから眺めたいと思っていたが、図らずもそれが叶った。これで奥多摩と大菩連嶺が鳥の目で繋がり、両者を結ぶ縦走ラインを考えてみたりした。


11:45発,殆どが日陰の林道を下る。所によっては道の全面がカチカチに凍ってアイゼンなしには歩けないほどで、一度ならずもんどりうって転倒ししたたか腰を打つ。


勝緑荘,富士見山荘と下って12:21福ちゃん荘,さらに林道を下って12:40ロッジ長兵衛。13:05第2展望台,同17第1展望台を経て13:57帰着。


14:15発,ほったらかしの湯と言うのを探して散々走り回り、露天風呂で大菩薩嶺~大菩薩峠のコースをなぞる。安曇野着は17時頃。