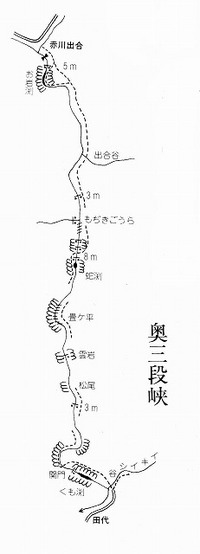2009年12月08日
庚申山(2009.12.6)
これだから止められない!
2009年12月6日 栃木県足尾 庚申山 記録者 はら坊
『長男の勇輝が休みだから何処か行きましょ。』
そんな軽いのりで始った今回の山歩き。
場所は副隊長に任せた。
ま~何を言っても頼れる兄貴だから任せて置けばダイジだべ・・・
ぺんぎん隊のキャリアで子供を連れて行ける場所と、コースタイム
は十分把握している。
今回は隊長が居ない、部活の大会らしいが少し寂しい。勇輝が野球を始めてから副隊長の気持ちが痛いほど解る。
という事で、場所の候補はいくつか有ったけど、栃木県旧足尾町に登山口がある庚申山に決った。
朝8:00に登山口のある国民宿舎かじか荘に集合。
少し早く到着し車の中で勇輝と朝食を摂る。
『あっ!! さるだ~っ』と勇輝が叫ぶ。
ここは日光、猿・鹿は珍しくは無いが目の前に出てくると何故か興奮する。
程なく副隊長と合流すると、いきなりスパッツを巻きだし準備完了。
先に着いた我々が副隊長を待たせる羽目に。アタフタしながら準備完了でいざ出発。


 ダラダラと車の走れる林道をひたすら歩く。
ダラダラと車の走れる林道をひたすら歩く。
途中天狗の投石という景勝地が有ったり庚申川の流れを見たりで飽きる事は無い。これで登山も十分だと言うくらい林道を歩くと漸く登山口が現れる。ここまでで相当高度も上がったであろう。
その脇には七滝という景勝地があり、ここで初めての休憩を入れる。
写真を数枚撮り再び出発。
ここからやっと登山道らしくなる。
広葉樹の森の木は、まだ若い木が多いいが秋には素晴しい紅葉を見せるであろう事を予感させてくれる。のでこの季節は真っ裸である。
沢を何度か渡り返しながら歩く。所どころ巨岩奇岩があり、看板が立っている。
暫く行くと前日に降ったであろう雪が現れ出した。勇輝は、雪に目を輝かせ雪で遊んでいる。やっぱり子供だな~っと思う瞬間である。
大人二人はと言うと、嫌な思いが脳裏をよぎる。副隊長は口にしなかったが同じ思いであったに違いない。それは今年の1月に登った両神である。
こいつが出てくると危険度が増し、コースタイムが著しく狂わせられるからだ。
 登山道には鹿の足跡が沢山あり鹿の足跡に導かれる様に庚申山荘に到着。
登山道には鹿の足跡が沢山あり鹿の足跡に導かれる様に庚申山荘に到着。
ここで小休止を摂って山頂を目指し出発。
何やらここからコースが二手に別れるらしいが、見当らないので雪に残る先行者の足跡を追う。
所どころ危険な場所をクリアーしていく。ま~雪が無ければ差ほどでは無いだろうが雪が渋い。
途中先行者が下山して来てすれ違いがてら、『山頂が分からなかった。』
と言う。挨拶を交わした後、副隊長と顔を見合わせ『山頂が分からない訳ね~べぇ~』と言いながら山頂を目指す。
彼らの足跡が途切れた辺りが確かに山頂ではないかと思わせるような場所
では有るが、其れらしい物が無いので、我々はもう少し先に行く。
10分ほどで石碑が頭を出しているが山名板が無いのでもう少し先に行くと
突然視界が開け絶景が広がった。ここまで雪を厄介者にしてきたが、ここで初めて雪に感謝する事になった。この季節、色の無い山肌に雪が化粧してくれて空は青く澄んでいる。勇輝でさえ感動の声を上げている。
息子と同じ物に感動できるって素晴しい事ですよね。
これだから止められないや


山頂で昼食を摂り、写真を撮って寒さに耐え切れず退散。
日光白根山にかかる雲を払おうと白根に向って息を吹き掛けている副隊長を見てニヤニヤしていた勇輝の顔が印象的だった。
勇輝に軽アイゼンを装着させて出発。
 帰り道先ほど通った石碑をもう一度何気なしに見たらそこには山名板が有るではないか、『あんなに探したのに~。写真まで撮ってたのに~』
帰り道先ほど通った石碑をもう一度何気なしに見たらそこには山名板が有るではないか、『あんなに探したのに~。写真まで撮ってたのに~』
と苦笑いを浮べながらもこれで始めて庚申山制覇となった。
帰り道もっと怖がって時間がかかると思ったが、詰まらない位スイスイと降りてしまうのでチョット拍子抜けしたが、お陰でコースタイムより少し速いペースで無事下山できた。
帰りには、かじか荘の温泉で汗を流し帰路についた。
久し振りの副隊長との山登り親子共々お世話になりとても楽しい一日を過ごす事が出来ました。
今度は隊長も一緒に・・・榛名山⇒温泉⇒水沢うどん⇒おもちゃと自動車博物館でしたっけ。
また宜しくお願いします。
2009年12月6日 栃木県足尾 庚申山 記録者 はら坊
『長男の勇輝が休みだから何処か行きましょ。』
そんな軽いのりで始った今回の山歩き。
場所は副隊長に任せた。
ま~何を言っても頼れる兄貴だから任せて置けばダイジだべ・・・
ぺんぎん隊のキャリアで子供を連れて行ける場所と、コースタイム
は十分把握している。
今回は隊長が居ない、部活の大会らしいが少し寂しい。勇輝が野球を始めてから副隊長の気持ちが痛いほど解る。
という事で、場所の候補はいくつか有ったけど、栃木県旧足尾町に登山口がある庚申山に決った。
朝8:00に登山口のある国民宿舎かじか荘に集合。
少し早く到着し車の中で勇輝と朝食を摂る。
『あっ!! さるだ~っ』と勇輝が叫ぶ。
ここは日光、猿・鹿は珍しくは無いが目の前に出てくると何故か興奮する。
程なく副隊長と合流すると、いきなりスパッツを巻きだし準備完了。
先に着いた我々が副隊長を待たせる羽目に。アタフタしながら準備完了でいざ出発。


 ダラダラと車の走れる林道をひたすら歩く。
ダラダラと車の走れる林道をひたすら歩く。途中天狗の投石という景勝地が有ったり庚申川の流れを見たりで飽きる事は無い。これで登山も十分だと言うくらい林道を歩くと漸く登山口が現れる。ここまでで相当高度も上がったであろう。
その脇には七滝という景勝地があり、ここで初めての休憩を入れる。
写真を数枚撮り再び出発。
ここからやっと登山道らしくなる。
広葉樹の森の木は、まだ若い木が多いいが秋には素晴しい紅葉を見せるであろう事を予感させてくれる。のでこの季節は真っ裸である。
沢を何度か渡り返しながら歩く。所どころ巨岩奇岩があり、看板が立っている。
暫く行くと前日に降ったであろう雪が現れ出した。勇輝は、雪に目を輝かせ雪で遊んでいる。やっぱり子供だな~っと思う瞬間である。
大人二人はと言うと、嫌な思いが脳裏をよぎる。副隊長は口にしなかったが同じ思いであったに違いない。それは今年の1月に登った両神である。
こいつが出てくると危険度が増し、コースタイムが著しく狂わせられるからだ。
 登山道には鹿の足跡が沢山あり鹿の足跡に導かれる様に庚申山荘に到着。
登山道には鹿の足跡が沢山あり鹿の足跡に導かれる様に庚申山荘に到着。ここで小休止を摂って山頂を目指し出発。
何やらここからコースが二手に別れるらしいが、見当らないので雪に残る先行者の足跡を追う。
所どころ危険な場所をクリアーしていく。ま~雪が無ければ差ほどでは無いだろうが雪が渋い。
途中先行者が下山して来てすれ違いがてら、『山頂が分からなかった。』
と言う。挨拶を交わした後、副隊長と顔を見合わせ『山頂が分からない訳ね~べぇ~』と言いながら山頂を目指す。
彼らの足跡が途切れた辺りが確かに山頂ではないかと思わせるような場所
では有るが、其れらしい物が無いので、我々はもう少し先に行く。
10分ほどで石碑が頭を出しているが山名板が無いのでもう少し先に行くと
突然視界が開け絶景が広がった。ここまで雪を厄介者にしてきたが、ここで初めて雪に感謝する事になった。この季節、色の無い山肌に雪が化粧してくれて空は青く澄んでいる。勇輝でさえ感動の声を上げている。
息子と同じ物に感動できるって素晴しい事ですよね。
これだから止められないや


山頂で昼食を摂り、写真を撮って寒さに耐え切れず退散。
日光白根山にかかる雲を払おうと白根に向って息を吹き掛けている副隊長を見てニヤニヤしていた勇輝の顔が印象的だった。
勇輝に軽アイゼンを装着させて出発。
 帰り道先ほど通った石碑をもう一度何気なしに見たらそこには山名板が有るではないか、『あんなに探したのに~。写真まで撮ってたのに~』
帰り道先ほど通った石碑をもう一度何気なしに見たらそこには山名板が有るではないか、『あんなに探したのに~。写真まで撮ってたのに~』と苦笑いを浮べながらもこれで始めて庚申山制覇となった。
帰り道もっと怖がって時間がかかると思ったが、詰まらない位スイスイと降りてしまうのでチョット拍子抜けしたが、お陰でコースタイムより少し速いペースで無事下山できた。
帰りには、かじか荘の温泉で汗を流し帰路についた。
久し振りの副隊長との山登り親子共々お世話になりとても楽しい一日を過ごす事が出来ました。
今度は隊長も一緒に・・・榛名山⇒温泉⇒水沢うどん⇒おもちゃと自動車博物館でしたっけ。
また宜しくお願いします。
タグ :栃木
2009年11月24日
御岳山(2009.11.23)
小春日和に誘われて
2009年11月23日 栃木県宇都宮市郊外 御岳山 記録者 ぺんぎん隊副隊長
昨日の天気が嘘のように晴れ渡る空。ガラス越しに差し込む日差しがポカポカとして暖かい居間にいると何だかこうして家に居るのがもったいない様な気がして来る。「今日なら日光の山々も綺麗に見えているだろうなぁ・・・」そう思うと矢も盾もたまらずそれらの山々を眺めに行きたくなる。山を見るなら山が一番、ということで宇都宮市郊外に在る御岳山に登る事に決めて家を飛び出した。
御岳山は古賀志山と峰続きの岩山でその山頂は北西方向に展望が開けて足尾山塊から日光連山、高原山、那須連山が一望出来る。我が家からはJR宇都宮駅から西に続く「大通り」を一直線、思い立ってから一時間後には山頂に立てる手頃な山である。
 城山西小学校裏手の駐車場に車を止めて登山道に入る。杉の木立に差し込む日差しがキラキラして眩しいくらいだ。滝神社脇の岩壁に取り付くクライマー達の姿を横目に小石がゴロゴロする涸れ沢上の登山道を歩く。ここから稜線までは急登が続くが一気に高度を上げるルートは時間の短縮になる。
城山西小学校裏手の駐車場に車を止めて登山道に入る。杉の木立に差し込む日差しがキラキラして眩しいくらいだ。滝神社脇の岩壁に取り付くクライマー達の姿を横目に小石がゴロゴロする涸れ沢上の登山道を歩く。ここから稜線までは急登が続くが一気に高度を上げるルートは時間の短縮になる。
稜線まで詰めて古賀志山山頂との分岐を左に取れば鉄の梯子を一登りして御岳山山頂に到着する。
残念ながら日光連山の高峰の頭には雲が絡んでいたが、秋の高い青空にポッカリと浮かんだ雲もまた良しと言ったところ。
男体山の左に控える栃木県最高峰である日光白根山が真っ白に雪化粧を施して一連の景色にアクセントを加えてくれている。
御岳山の山頂で日光連山を眺めながらのんびりとスケッチをする。一人でやって来た気楽さから時間を気にせずに陽だまりの中でひと時を過ごす。帰り際にお義理で古賀志山の山頂まで足を延ばしてから往路を下山。足元に生えるを木イチゴを一粒摘まんで渇いたのどを潤す。木イチゴの一粒一粒が日に照らされてキラキラ輝いていたのが印象的だった小春日和の軽登山だった。



是非ご参加下さい
2009年11月23日 栃木県宇都宮市郊外 御岳山 記録者 ぺんぎん隊副隊長
昨日の天気が嘘のように晴れ渡る空。ガラス越しに差し込む日差しがポカポカとして暖かい居間にいると何だかこうして家に居るのがもったいない様な気がして来る。「今日なら日光の山々も綺麗に見えているだろうなぁ・・・」そう思うと矢も盾もたまらずそれらの山々を眺めに行きたくなる。山を見るなら山が一番、ということで宇都宮市郊外に在る御岳山に登る事に決めて家を飛び出した。
御岳山は古賀志山と峰続きの岩山でその山頂は北西方向に展望が開けて足尾山塊から日光連山、高原山、那須連山が一望出来る。我が家からはJR宇都宮駅から西に続く「大通り」を一直線、思い立ってから一時間後には山頂に立てる手頃な山である。
 城山西小学校裏手の駐車場に車を止めて登山道に入る。杉の木立に差し込む日差しがキラキラして眩しいくらいだ。滝神社脇の岩壁に取り付くクライマー達の姿を横目に小石がゴロゴロする涸れ沢上の登山道を歩く。ここから稜線までは急登が続くが一気に高度を上げるルートは時間の短縮になる。
城山西小学校裏手の駐車場に車を止めて登山道に入る。杉の木立に差し込む日差しがキラキラして眩しいくらいだ。滝神社脇の岩壁に取り付くクライマー達の姿を横目に小石がゴロゴロする涸れ沢上の登山道を歩く。ここから稜線までは急登が続くが一気に高度を上げるルートは時間の短縮になる。稜線まで詰めて古賀志山山頂との分岐を左に取れば鉄の梯子を一登りして御岳山山頂に到着する。
残念ながら日光連山の高峰の頭には雲が絡んでいたが、秋の高い青空にポッカリと浮かんだ雲もまた良しと言ったところ。
男体山の左に控える栃木県最高峰である日光白根山が真っ白に雪化粧を施して一連の景色にアクセントを加えてくれている。
御岳山の山頂で日光連山を眺めながらのんびりとスケッチをする。一人でやって来た気楽さから時間を気にせずに陽だまりの中でひと時を過ごす。帰り際にお義理で古賀志山の山頂まで足を延ばしてから往路を下山。足元に生えるを木イチゴを一粒摘まんで渇いたのどを潤す。木イチゴの一粒一粒が日に照らされてキラキラ輝いていたのが印象的だった小春日和の軽登山だった。



是非ご参加下さい
タグ :栃木
2009年11月06日
鳴虫山(2009.11.4)
晩秋から冬へ
2009年11月3日 栃木県日光市 鳴虫山 記録者 ぺんぎん隊副隊長
前日に天気が大きく崩れて雨と風が吹き荒れた。明日の天気は回復し北風は強いが行楽日和との天気予報も「本当かよ?」と思うほど夜半まで雨音は続いていた。
息子の部活が休みとなる明日は私としては登山に行きたいところ。何気なく息子の様子を窺うと彼もまた何処かに出掛けたい様子をしている。しかしそれが何処と言う特定の目的の場所ではないが、かと言って山では無いことも分かっている。こんな具合で何も決める事も無く就寝してしまった。
朝起きると予報通りに薄日が射し始めている。7時少し前の時間で布団の中に居る状況では山に行くと言っても高が知れている訳で頭に思い描いた先は日光の鳴虫山である。何故に鳴虫山かといえば電車を利用して行ける山であり且つその方が都合のよい歩きが出来るからだ。息子は知る人ぞ知る電車好きであり「電車で日光に行くか?」と誘えば「うん!」と言うに決まっている、案の定簡単に鳴虫山登山が決まったのである。
鳴虫山は2004年の9月に一度登っているので息子にしても気が楽な登山と見える。部活で足腰を鍛えているお陰で今では私よりも足が強くなって来ている彼は以前よりも登山そのものに労苦を感じなくなったのだろうか。先日の赤薙山といい今回の鳴虫山といい月に1~2回有るか無しかの折角の部活の休みによく山に付き合ってくれるものだと感心している。
 さて、JR日光駅で降り東武日光駅前を通り抜け日光街道を東照宮方面に少し歩くと左側に日光消防署の建物がある。ここから駐車場を抜けると「鳴虫山登山口」の標識板が見える。標識に従って5分ほど歩けば志度淵川を渡って民家の裏手に回り込み登山口の階段に到着する。登山口に被さるようにして色を変えた紅葉が出迎えてくれた。
さて、JR日光駅で降り東武日光駅前を通り抜け日光街道を東照宮方面に少し歩くと左側に日光消防署の建物がある。ここから駐車場を抜けると「鳴虫山登山口」の標識板が見える。標識に従って5分ほど歩けば志度淵川を渡って民家の裏手に回り込み登山口の階段に到着する。登山口に被さるようにして色を変えた紅葉が出迎えてくれた。
登山道に入り二折れ三折れと登ると右手に石の鳥居と祠がある天王山神社の前に出る。祠の裏側からは女峰山方面に展望があり日光市街地も眼下に広がる。
スギ林の登山道を暫く登り稜線に出ると緩やかな登山道が更に続く。スギ林から雑木林に変わって来ると神ノ主山への分岐に着く。右に進む道は巻き道で標識通りに登れば神ノ主山山頂へと進む。私たちは当然山頂方面に足を向ける。



分岐から山頂までは急な登りが続く。雨に洗われた登山道は木の根が露出して歩き難い。この状態は今回の登山では終始続いた。
神ノ主山(842m)では更に展望が開け男体山から大真名子・小真名子、女峰、赤薙が一望出来る。この日は前日降った雪が山肌をおおって今冬初めての雪化粧だ。見下ろせば大谷川・稲荷川・外山と日光市街地が広がり、緑の森の中に大きな瓦屋根を乗せた赤い社は輪王寺である。
 神ノ主山から鳴虫山に向かう。途中「あそこが頂上か?」と何度も思うほどにいくつかのピークを越える。稜線歩きではあるがあまり視界は良くない。時折上空が雲に覆われて霰を降らせて来るが思いのほか寒くは無い。
神ノ主山から鳴虫山に向かう。途中「あそこが頂上か?」と何度も思うほどにいくつかのピークを越える。稜線歩きではあるがあまり視界は良くない。時折上空が雲に覆われて霰を降らせて来るが思いのほか寒くは無い。
稜線歩きをしていて面白いのは稜線を境にして左側(南側)はスギやヒノキが規則正しく伸びていて、右側(北側)は雑木林になっていて黄色や赤、茶色などに葉の色を変えて賑やかにしている。植林が進んだ斜面と自然のままの斜面を左右に見ながらその境目を歩いているわけである。
木の根が露出する急な登りに掛かる。頭上から何人かの話声が聞こえて来て、登り切ればそこが鳴虫山山頂と分かる。山頂に登り切ると正面に鳴虫山の山頂表示があり、その前に二等三角点の標石がある。右手に女峰山方面には展望台が有るのだが、上り口には登山者がずらっと座って荷物を広げ昼食の準備をしている。相変わらず人気のある山である。
 今日は下山をしてから昼食を摂る予定で来たので山頂には5分も居ないで下山にかかる。急な下りを階段で降り岩や露出した木の根の間を慎重に足を運ぶ。下方から賑やかな声が聞こえて来たと思ったら10人を越えるパーティーが登って来る。
今日は下山をしてから昼食を摂る予定で来たので山頂には5分も居ないで下山にかかる。急な下りを階段で降り岩や露出した木の根の間を慎重に足を運ぶ。下方から賑やかな声が聞こえて来たと思ったら10人を越えるパーティーが登って来る。
下ったと思ったら又も急な登りを強いられ合峰(1084m)へと上がる。そのまま稜線を直進して登り降りを繰り返し独標(925m)に到着。独標からは一気に斜面を下るが雨に洗われた斜面は木の根を露出させ、更に階段の土も洗い流して歩き難い事夥しい。下る際は転倒など十分に注意が必要である。
傾斜が緩やかになると一端林道に飛び出す。林道を100mほど下ると「含満ケ淵」と標識があり左の斜面に登山道が現れるのでそこを下って行くと水路の金網に突き当たる。道なりに進んで日光宇都宮有料道路をくぐれば含満ケ淵の「並び地蔵」の前に出る。このまま沢沿いに下り大谷川の橋を渡って川沿いに下れば日光東照宮前を通り「神橋」に出る。
日光市街で遅い昼食を摂りJR日光駅へと向かい鳴虫山周遊を終えた。







お気楽にご参加下さい
2009年11月3日 栃木県日光市 鳴虫山 記録者 ぺんぎん隊副隊長
前日に天気が大きく崩れて雨と風が吹き荒れた。明日の天気は回復し北風は強いが行楽日和との天気予報も「本当かよ?」と思うほど夜半まで雨音は続いていた。
息子の部活が休みとなる明日は私としては登山に行きたいところ。何気なく息子の様子を窺うと彼もまた何処かに出掛けたい様子をしている。しかしそれが何処と言う特定の目的の場所ではないが、かと言って山では無いことも分かっている。こんな具合で何も決める事も無く就寝してしまった。
朝起きると予報通りに薄日が射し始めている。7時少し前の時間で布団の中に居る状況では山に行くと言っても高が知れている訳で頭に思い描いた先は日光の鳴虫山である。何故に鳴虫山かといえば電車を利用して行ける山であり且つその方が都合のよい歩きが出来るからだ。息子は知る人ぞ知る電車好きであり「電車で日光に行くか?」と誘えば「うん!」と言うに決まっている、案の定簡単に鳴虫山登山が決まったのである。
鳴虫山は2004年の9月に一度登っているので息子にしても気が楽な登山と見える。部活で足腰を鍛えているお陰で今では私よりも足が強くなって来ている彼は以前よりも登山そのものに労苦を感じなくなったのだろうか。先日の赤薙山といい今回の鳴虫山といい月に1~2回有るか無しかの折角の部活の休みによく山に付き合ってくれるものだと感心している。
 さて、JR日光駅で降り東武日光駅前を通り抜け日光街道を東照宮方面に少し歩くと左側に日光消防署の建物がある。ここから駐車場を抜けると「鳴虫山登山口」の標識板が見える。標識に従って5分ほど歩けば志度淵川を渡って民家の裏手に回り込み登山口の階段に到着する。登山口に被さるようにして色を変えた紅葉が出迎えてくれた。
さて、JR日光駅で降り東武日光駅前を通り抜け日光街道を東照宮方面に少し歩くと左側に日光消防署の建物がある。ここから駐車場を抜けると「鳴虫山登山口」の標識板が見える。標識に従って5分ほど歩けば志度淵川を渡って民家の裏手に回り込み登山口の階段に到着する。登山口に被さるようにして色を変えた紅葉が出迎えてくれた。登山道に入り二折れ三折れと登ると右手に石の鳥居と祠がある天王山神社の前に出る。祠の裏側からは女峰山方面に展望があり日光市街地も眼下に広がる。
スギ林の登山道を暫く登り稜線に出ると緩やかな登山道が更に続く。スギ林から雑木林に変わって来ると神ノ主山への分岐に着く。右に進む道は巻き道で標識通りに登れば神ノ主山山頂へと進む。私たちは当然山頂方面に足を向ける。



分岐から山頂までは急な登りが続く。雨に洗われた登山道は木の根が露出して歩き難い。この状態は今回の登山では終始続いた。
神ノ主山(842m)では更に展望が開け男体山から大真名子・小真名子、女峰、赤薙が一望出来る。この日は前日降った雪が山肌をおおって今冬初めての雪化粧だ。見下ろせば大谷川・稲荷川・外山と日光市街地が広がり、緑の森の中に大きな瓦屋根を乗せた赤い社は輪王寺である。
 神ノ主山から鳴虫山に向かう。途中「あそこが頂上か?」と何度も思うほどにいくつかのピークを越える。稜線歩きではあるがあまり視界は良くない。時折上空が雲に覆われて霰を降らせて来るが思いのほか寒くは無い。
神ノ主山から鳴虫山に向かう。途中「あそこが頂上か?」と何度も思うほどにいくつかのピークを越える。稜線歩きではあるがあまり視界は良くない。時折上空が雲に覆われて霰を降らせて来るが思いのほか寒くは無い。稜線歩きをしていて面白いのは稜線を境にして左側(南側)はスギやヒノキが規則正しく伸びていて、右側(北側)は雑木林になっていて黄色や赤、茶色などに葉の色を変えて賑やかにしている。植林が進んだ斜面と自然のままの斜面を左右に見ながらその境目を歩いているわけである。
木の根が露出する急な登りに掛かる。頭上から何人かの話声が聞こえて来て、登り切ればそこが鳴虫山山頂と分かる。山頂に登り切ると正面に鳴虫山の山頂表示があり、その前に二等三角点の標石がある。右手に女峰山方面には展望台が有るのだが、上り口には登山者がずらっと座って荷物を広げ昼食の準備をしている。相変わらず人気のある山である。
 今日は下山をしてから昼食を摂る予定で来たので山頂には5分も居ないで下山にかかる。急な下りを階段で降り岩や露出した木の根の間を慎重に足を運ぶ。下方から賑やかな声が聞こえて来たと思ったら10人を越えるパーティーが登って来る。
今日は下山をしてから昼食を摂る予定で来たので山頂には5分も居ないで下山にかかる。急な下りを階段で降り岩や露出した木の根の間を慎重に足を運ぶ。下方から賑やかな声が聞こえて来たと思ったら10人を越えるパーティーが登って来る。下ったと思ったら又も急な登りを強いられ合峰(1084m)へと上がる。そのまま稜線を直進して登り降りを繰り返し独標(925m)に到着。独標からは一気に斜面を下るが雨に洗われた斜面は木の根を露出させ、更に階段の土も洗い流して歩き難い事夥しい。下る際は転倒など十分に注意が必要である。
傾斜が緩やかになると一端林道に飛び出す。林道を100mほど下ると「含満ケ淵」と標識があり左の斜面に登山道が現れるのでそこを下って行くと水路の金網に突き当たる。道なりに進んで日光宇都宮有料道路をくぐれば含満ケ淵の「並び地蔵」の前に出る。このまま沢沿いに下り大谷川の橋を渡って川沿いに下れば日光東照宮前を通り「神橋」に出る。
日光市街で遅い昼食を摂りJR日光駅へと向かい鳴虫山周遊を終えた。







お気楽にご参加下さい
タグ :栃木
2009年11月03日
学童登山(2009.10.17)
小学生と山登り
2009年10月17日 栃木県宇都宮市 古賀志山 記録者 ぺんぎん隊副隊長
息子との登山をして来たこの10年間で私が感じていた事は今の小学生にとって登山というものは特別な物であるという事だった。特に息子に関しては私や私の友人と行く源流釣りその物がテントを持たないいわゆる野宿という形式で普通の生活では経験しない範疇にありながらそれが当然のように過ごして来た。でも今の小学生にとって山に登る行為それ自体が縁遠い存在であり友達からの遊びの誘いを「山に行くから。」と断る息子の様な存在は不思議人そのものなのだそうだ。
そんな現状に寂しさを感じていた私が宇都宮市の青少年指導員という立場になり地区の育成会事業に関わるようになって計画をしたのが学童登山だった。私が源流釣りで時々立ち寄る山形県の天狗角力取山天狗小屋の小屋番が「毎年大井沢の小学6年生が遠足で来るんだよ。」と宴席の中で漏らした一言がいつも頭に残っていたことも手伝っていた。息子が6年生の時に実現したかったが諸事問題をクリアして実現したのが一年経った今年である。
 小学生を対象に1~3年生はトリムコースでアスレチック、4~6年生は古賀志山登山として募集をかけた。面白いというか予測の範疇ではあったが高学年の申し込みは少なかった。単に「今度のイベントは山登りでしょ?」と言って敬遠されたのだ。
小学生を対象に1~3年生はトリムコースでアスレチック、4~6年生は古賀志山登山として募集をかけた。面白いというか予測の範疇ではあったが高学年の申し込みは少なかった。単に「今度のイベントは山登りでしょ?」と言って敬遠されたのだ。
学校登山そのものが万が一の保障問題で少なくなっている時代であるから一人の青少年指導員が企画する学童登山としては致し方の無い事ではある。それでも女の子を含む10人の小学生が登山に参加してくれた事は次に繋げる意味でも有難い事だった。
古賀志山は宇都宮市の西に位置する。岩で構成される稜線の凹凸が異様であり一目でそれと分かる山である。山頂には円盤型のアンテナが聳えて遠くからでもその位置を確認出来る。市内からも十分にその姿を眺められ身近な山として古くから親しまれている。街の暮らしの中でも「あそこに登ったんだよ。」と指を指してそう言える山である。
高学年児童を従えて宇都宮市森林公園奥の北登山口から登る。古賀志山の一般的な登山コースはこの北登山口ともう一つ山の反対側に位置する城山西小学校奥から登る南登山口がある。北コースは時間が掛かるが割合なだらかな登りで南コースは時間は短縮出来るが急登が続く。今回は森林公園でアスレチックをする低学年との兼ね合いもあり北登山口から登り始める。
 アスファルトの道路から赤川の橋を渡っていよいよ登山道は始まる。辺りはスギ林に囲まれてうす暗く日常と違ういよいよ世界へと冒険する子供たちの顔が引き締まって来る。
アスファルトの道路から赤川の橋を渡っていよいよ登山道は始まる。辺りはスギ林に囲まれてうす暗く日常と違ういよいよ世界へと冒険する子供たちの顔が引き締まって来る。
ほぼ平たんな登山道を約10分歩くと水場に到着。岩の間から顔を出すビニールパイプから水が落ちている。「飲んでも良いですか?!」の問いかけに私が頷くと早速に元気の良い男子が両手を合わせて水を汲み飲む。「美味しい!」の一言で次から次に水を汲み飲み始める。
水場で小休止をして登山を再開。ここから次の休憩地点までの15分くらいはまだまだ緩やかな登りでみんな元気に歩いている。それでも次第に列が間延びして行くのは仕方が無い。若手の育成会役員を先頭に立て、間にも大人を挟んで最後尾を私が歩く。ちなみに息子は中学生ジュニアリーダーとして今回登山の引率を手伝っている。
 最後尾が第二休憩地点である広場に到着した時はもう先行している男子児童は十分に休憩した状態。それでもここからは地面が雨水に洗われて木の根が露出した登山道がしばらく続く。出発前に登山中の注意事項として「登山道は走らない事」「木の根を縦に踏まない事」を特に注意してある。児童たちはその私からの注意事項をこの部分の歩きで身を以て十分に理解してくれた様子である。
最後尾が第二休憩地点である広場に到着した時はもう先行している男子児童は十分に休憩した状態。それでもここからは地面が雨水に洗われて木の根が露出した登山道がしばらく続く。出発前に登山中の注意事項として「登山道は走らない事」「木の根を縦に踏まない事」を特に注意してある。児童たちはその私からの注意事項をこの部分の歩きで身を以て十分に理解してくれた様子である。
木の根も露わな歩きにくい登山道を突き当たると右に折れて稜線へと上がる急登が始まる。見上げれば大きな岩が垂直に切り立つ間をひたすら登って行く。
左手の岩肌10mほど先に丸い物がぶら下がっているのを見つけて子供たちを制止させその場から観察を促す。キイロスズメバチの巣である。ひっ切り無しに出入りしているキイロスズメバチを遠くから眺める子供たちの目は真剣である。町に居ては秋ともなると「遠足中に小学生児童が多数スズメバチに刺されて・・・」なんてニュースを耳にしたこともある彼らにとって、それが何時に無く身近に感じられた時間だっただろう。
稜線に上がると暫くは平たんな尾根歩きが続き最後のクサリ場を迎える。クサリ場と言っても50mほどの急登に補助的なロープが沿って張られているに過ぎない。慌てず急がず登れば良く、強いて言えば下りの時こそ気を付けなければならないと教える。
息を切らせて東稜見晴らしと山頂との中間尾根に飛び出す。まずは「頂上制覇だ!」と右に進み古賀志山山頂に向かう。麓から見えた円盤型のアンテナの横を登り山頂に立つ。東に開けた展望を目の当りにして子供たちは歓声を挙げる。全員の顔に山登りを達成した自信と満足感が溢れている。そんな彼らの顔を記念にと山頂表示の前で記念撮影。
 山頂でのひと時を楽しんだ後、東稜見晴らしに立ち寄り赤川ダムを見下ろす。森林公園の方でアスレチックを終えた何人かがダムの橋上で手を振る姿が見えるのでこちらも負けずに手を振り返す。
山頂でのひと時を楽しんだ後、東稜見晴らしに立ち寄り赤川ダムを見下ろす。森林公園の方でアスレチックを終えた何人かがダムの橋上で手を振る姿が見えるのでこちらも負けずに手を振り返す。
「さて、降りたらバーベキューだ!」
私の声にみんなが「おお!」と歓声を挙げる。
意気揚々と下山に掛る児童たちだった。

2009年10月17日 栃木県宇都宮市 古賀志山 記録者 ぺんぎん隊副隊長
息子との登山をして来たこの10年間で私が感じていた事は今の小学生にとって登山というものは特別な物であるという事だった。特に息子に関しては私や私の友人と行く源流釣りその物がテントを持たないいわゆる野宿という形式で普通の生活では経験しない範疇にありながらそれが当然のように過ごして来た。でも今の小学生にとって山に登る行為それ自体が縁遠い存在であり友達からの遊びの誘いを「山に行くから。」と断る息子の様な存在は不思議人そのものなのだそうだ。
そんな現状に寂しさを感じていた私が宇都宮市の青少年指導員という立場になり地区の育成会事業に関わるようになって計画をしたのが学童登山だった。私が源流釣りで時々立ち寄る山形県の天狗角力取山天狗小屋の小屋番が「毎年大井沢の小学6年生が遠足で来るんだよ。」と宴席の中で漏らした一言がいつも頭に残っていたことも手伝っていた。息子が6年生の時に実現したかったが諸事問題をクリアして実現したのが一年経った今年である。
 小学生を対象に1~3年生はトリムコースでアスレチック、4~6年生は古賀志山登山として募集をかけた。面白いというか予測の範疇ではあったが高学年の申し込みは少なかった。単に「今度のイベントは山登りでしょ?」と言って敬遠されたのだ。
小学生を対象に1~3年生はトリムコースでアスレチック、4~6年生は古賀志山登山として募集をかけた。面白いというか予測の範疇ではあったが高学年の申し込みは少なかった。単に「今度のイベントは山登りでしょ?」と言って敬遠されたのだ。学校登山そのものが万が一の保障問題で少なくなっている時代であるから一人の青少年指導員が企画する学童登山としては致し方の無い事ではある。それでも女の子を含む10人の小学生が登山に参加してくれた事は次に繋げる意味でも有難い事だった。
古賀志山は宇都宮市の西に位置する。岩で構成される稜線の凹凸が異様であり一目でそれと分かる山である。山頂には円盤型のアンテナが聳えて遠くからでもその位置を確認出来る。市内からも十分にその姿を眺められ身近な山として古くから親しまれている。街の暮らしの中でも「あそこに登ったんだよ。」と指を指してそう言える山である。
高学年児童を従えて宇都宮市森林公園奥の北登山口から登る。古賀志山の一般的な登山コースはこの北登山口ともう一つ山の反対側に位置する城山西小学校奥から登る南登山口がある。北コースは時間が掛かるが割合なだらかな登りで南コースは時間は短縮出来るが急登が続く。今回は森林公園でアスレチックをする低学年との兼ね合いもあり北登山口から登り始める。
 アスファルトの道路から赤川の橋を渡っていよいよ登山道は始まる。辺りはスギ林に囲まれてうす暗く日常と違ういよいよ世界へと冒険する子供たちの顔が引き締まって来る。
アスファルトの道路から赤川の橋を渡っていよいよ登山道は始まる。辺りはスギ林に囲まれてうす暗く日常と違ういよいよ世界へと冒険する子供たちの顔が引き締まって来る。ほぼ平たんな登山道を約10分歩くと水場に到着。岩の間から顔を出すビニールパイプから水が落ちている。「飲んでも良いですか?!」の問いかけに私が頷くと早速に元気の良い男子が両手を合わせて水を汲み飲む。「美味しい!」の一言で次から次に水を汲み飲み始める。
水場で小休止をして登山を再開。ここから次の休憩地点までの15分くらいはまだまだ緩やかな登りでみんな元気に歩いている。それでも次第に列が間延びして行くのは仕方が無い。若手の育成会役員を先頭に立て、間にも大人を挟んで最後尾を私が歩く。ちなみに息子は中学生ジュニアリーダーとして今回登山の引率を手伝っている。
 最後尾が第二休憩地点である広場に到着した時はもう先行している男子児童は十分に休憩した状態。それでもここからは地面が雨水に洗われて木の根が露出した登山道がしばらく続く。出発前に登山中の注意事項として「登山道は走らない事」「木の根を縦に踏まない事」を特に注意してある。児童たちはその私からの注意事項をこの部分の歩きで身を以て十分に理解してくれた様子である。
最後尾が第二休憩地点である広場に到着した時はもう先行している男子児童は十分に休憩した状態。それでもここからは地面が雨水に洗われて木の根が露出した登山道がしばらく続く。出発前に登山中の注意事項として「登山道は走らない事」「木の根を縦に踏まない事」を特に注意してある。児童たちはその私からの注意事項をこの部分の歩きで身を以て十分に理解してくれた様子である。木の根も露わな歩きにくい登山道を突き当たると右に折れて稜線へと上がる急登が始まる。見上げれば大きな岩が垂直に切り立つ間をひたすら登って行く。
左手の岩肌10mほど先に丸い物がぶら下がっているのを見つけて子供たちを制止させその場から観察を促す。キイロスズメバチの巣である。ひっ切り無しに出入りしているキイロスズメバチを遠くから眺める子供たちの目は真剣である。町に居ては秋ともなると「遠足中に小学生児童が多数スズメバチに刺されて・・・」なんてニュースを耳にしたこともある彼らにとって、それが何時に無く身近に感じられた時間だっただろう。
稜線に上がると暫くは平たんな尾根歩きが続き最後のクサリ場を迎える。クサリ場と言っても50mほどの急登に補助的なロープが沿って張られているに過ぎない。慌てず急がず登れば良く、強いて言えば下りの時こそ気を付けなければならないと教える。
息を切らせて東稜見晴らしと山頂との中間尾根に飛び出す。まずは「頂上制覇だ!」と右に進み古賀志山山頂に向かう。麓から見えた円盤型のアンテナの横を登り山頂に立つ。東に開けた展望を目の当りにして子供たちは歓声を挙げる。全員の顔に山登りを達成した自信と満足感が溢れている。そんな彼らの顔を記念にと山頂表示の前で記念撮影。
 山頂でのひと時を楽しんだ後、東稜見晴らしに立ち寄り赤川ダムを見下ろす。森林公園の方でアスレチックを終えた何人かがダムの橋上で手を振る姿が見えるのでこちらも負けずに手を振り返す。
山頂でのひと時を楽しんだ後、東稜見晴らしに立ち寄り赤川ダムを見下ろす。森林公園の方でアスレチックを終えた何人かがダムの橋上で手を振る姿が見えるのでこちらも負けずに手を振り返す。「さて、降りたらバーベキューだ!」
私の声にみんなが「おお!」と歓声を挙げる。
意気揚々と下山に掛る児童たちだった。

タグ :栃木
2009年10月24日
赤薙山(2009.10.24)
女峰に行く筈だったのに・・・
2009年10月24日 栃木県日光市 赤薙山 記録者 ぺんぎん隊副隊長
高原ハウス(6:55)~小丸山(7:34)~焼石金剛(7:55)~山頂(8:22)~小丸山(9:24)~高原ハウス(9:56)
赤薙山を越えて女峰山までのピストン山行を計画し埼玉の友人を誘って山行を決めた。日も短くなって来たのでロングアプローチであるこのコースも年内中に安全登山をするにはそろそろ限度になる。多少天気の不安はあったが「降らなければ何とか・・・」くらいのつもりでJR日光駅前を集合地に決め当日を迎えた。
JR日光駅前で4:30合流し一台を日光市立図書館にデポして霧降高原に向かう。高原ハウス駐車場には5:00に到着。夜明けを待ちながら仮眠を取るが6時を過ぎても明るくならない。漸く周囲が明るくなり出したのが7時近くなっていたが、それと同時にその理由も判明した。駐車場から第3リフト終着点である小丸山を見上げるとリフト小屋から上は雲の中である。

リフトゲレンデの横に位置する登山道を登り始める。登山道の中央部分は水の通り道になるらしく大きく削られて歩きにくい。こんな登山道はそれを避けるために両脇にどんどん踏み跡が増えて広く広くなって行ってしまうに違いない。
二回ほど急登をこなすと第三リフト終点から来る道が鹿避けネット外で合流して小丸山に着く。
小丸山から上は予想通りに雲の中で100mの視界が精一杯。
 丸山に向かう登山道を右に分けて稜線を真っ直ぐに登る。背の低い笹原を登る間、左側の谷間から雲が競り上がり寒風がヤッケを揺らしている。徐々に溶岩質の岩が目立ち始める。尾根幅20m一面が岩だらけで縦横に踏み跡が走る。確かにどこをどう歩いても尾根さえ外さなければ良い感じだ。
丸山に向かう登山道を右に分けて稜線を真っ直ぐに登る。背の低い笹原を登る間、左側の谷間から雲が競り上がり寒風がヤッケを揺らしている。徐々に溶岩質の岩が目立ち始める。尾根幅20m一面が岩だらけで縦横に踏み跡が走る。確かにどこをどう歩いても尾根さえ外さなければ良い感じだ。
霧の中に「焼石金剛」の表示板を見て自分の位置を知る。
焼石金剛からは笹を踏み分けた馬の背尾根を行く。晴れたらずいぶんと眺めが良かろうかと思うが天候はここに来て霧雨となる。馬の背を過ぎ赤薙山頂直下の急登に入る。木の根に掴まりながらよじ登る様な場面もあり息が切れて来る。
漸く傾斜も弱まり平たんになると鳥居と祠が据えられた赤薙山山頂だ。
 赤薙山山頂で三等三角点標石を従えて記念撮影。
赤薙山山頂で三等三角点標石を従えて記念撮影。
実はこの三等三角点には悔しい思い出がある。
今年の春、まだ雪が残る赤薙山に登った。私は登頂した記念に三角点標石とその周囲の風景を必ず写真に収めて来る。その時もそのつもりで登って来た。しかし雪が積もる山頂に三角点標石を探し当てる事が出来なかった。「ここか!あそこか!」とストックを雪に刺しては標石を探っていたがついに見つからずに諦めてラーメンを作って食べた正にそのお尻の下に標石は埋まっていたのだ。
今回はそんな悔しい思い出のある標石をカメラに収める事が出来て少なからず満足した。
天候は悪くなる一方で霧雨からしっかりとした雨脚に変わっている。本当なら祠の裏側に見える女峰山だが、今はその山肌さえも眺める事が出来ない。
「今日は勘弁してやるか!」
友人と相談して女峰山を目指す事は次回延期と決めて下山。
その横で息子の顔がほころんだのを見逃さない私でありました。(笑)

2009年10月24日 栃木県日光市 赤薙山 記録者 ぺんぎん隊副隊長
高原ハウス(6:55)~小丸山(7:34)~焼石金剛(7:55)~山頂(8:22)~小丸山(9:24)~高原ハウス(9:56)
赤薙山を越えて女峰山までのピストン山行を計画し埼玉の友人を誘って山行を決めた。日も短くなって来たのでロングアプローチであるこのコースも年内中に安全登山をするにはそろそろ限度になる。多少天気の不安はあったが「降らなければ何とか・・・」くらいのつもりでJR日光駅前を集合地に決め当日を迎えた。
JR日光駅前で4:30合流し一台を日光市立図書館にデポして霧降高原に向かう。高原ハウス駐車場には5:00に到着。夜明けを待ちながら仮眠を取るが6時を過ぎても明るくならない。漸く周囲が明るくなり出したのが7時近くなっていたが、それと同時にその理由も判明した。駐車場から第3リフト終着点である小丸山を見上げるとリフト小屋から上は雲の中である。

リフトゲレンデの横に位置する登山道を登り始める。登山道の中央部分は水の通り道になるらしく大きく削られて歩きにくい。こんな登山道はそれを避けるために両脇にどんどん踏み跡が増えて広く広くなって行ってしまうに違いない。
二回ほど急登をこなすと第三リフト終点から来る道が鹿避けネット外で合流して小丸山に着く。
小丸山から上は予想通りに雲の中で100mの視界が精一杯。
 丸山に向かう登山道を右に分けて稜線を真っ直ぐに登る。背の低い笹原を登る間、左側の谷間から雲が競り上がり寒風がヤッケを揺らしている。徐々に溶岩質の岩が目立ち始める。尾根幅20m一面が岩だらけで縦横に踏み跡が走る。確かにどこをどう歩いても尾根さえ外さなければ良い感じだ。
丸山に向かう登山道を右に分けて稜線を真っ直ぐに登る。背の低い笹原を登る間、左側の谷間から雲が競り上がり寒風がヤッケを揺らしている。徐々に溶岩質の岩が目立ち始める。尾根幅20m一面が岩だらけで縦横に踏み跡が走る。確かにどこをどう歩いても尾根さえ外さなければ良い感じだ。霧の中に「焼石金剛」の表示板を見て自分の位置を知る。
焼石金剛からは笹を踏み分けた馬の背尾根を行く。晴れたらずいぶんと眺めが良かろうかと思うが天候はここに来て霧雨となる。馬の背を過ぎ赤薙山頂直下の急登に入る。木の根に掴まりながらよじ登る様な場面もあり息が切れて来る。
漸く傾斜も弱まり平たんになると鳥居と祠が据えられた赤薙山山頂だ。
 赤薙山山頂で三等三角点標石を従えて記念撮影。
赤薙山山頂で三等三角点標石を従えて記念撮影。実はこの三等三角点には悔しい思い出がある。
今年の春、まだ雪が残る赤薙山に登った。私は登頂した記念に三角点標石とその周囲の風景を必ず写真に収めて来る。その時もそのつもりで登って来た。しかし雪が積もる山頂に三角点標石を探し当てる事が出来なかった。「ここか!あそこか!」とストックを雪に刺しては標石を探っていたがついに見つからずに諦めてラーメンを作って食べた正にそのお尻の下に標石は埋まっていたのだ。
今回はそんな悔しい思い出のある標石をカメラに収める事が出来て少なからず満足した。
天候は悪くなる一方で霧雨からしっかりとした雨脚に変わっている。本当なら祠の裏側に見える女峰山だが、今はその山肌さえも眺める事が出来ない。
「今日は勘弁してやるか!」
友人と相談して女峰山を目指す事は次回延期と決めて下山。
その横で息子の顔がほころんだのを見逃さない私でありました。(笑)

タグ :栃木