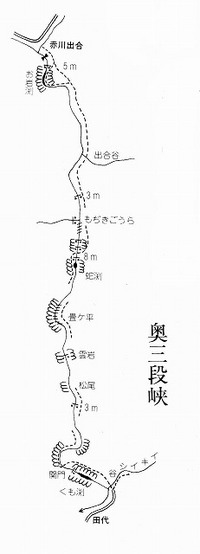2010年06月03日
石裂山(2010.06.01)
石裂山
2010年6月1日 栃木県 石裂山 記録者 副隊長
サラリーマンにとって休日は貴重な一日だとつくづく思う。少し前までは半自営業的な生活だったので自由な時間は自分で作り出せたが、サラリーマンともなると無駄な時間でさえ賃金で拘束され自由が利かない身となるのを10数年ぶりに体感している。
そんな身であるが数年来の山渓遊びを通じて休日の配分にも結構利口になった私である。身体を休める休日と心を休める休日を上手く使い分ける事が出来るようになったのも趣味と言う範疇ではあるけれど自然と触れ合う楽しさを教えて貰えた貴重な体験の積み重ねがあったからこそである。
朝、目を覚ますとまだ隣で佑次郎が寝息を立てている。今日は火曜日、平日の朝だから佑次郎は起き出すと共にそそくさと中学校へと行ってしまう。布団の中から佑次郎を送り出した後しばらく本を読んでいた私だがトイレに立った際に自室に差し込む明るい陽射しが妙に心を捉えて落ち着かなくなった。
「う~ん、今日は天気が良いんだなぁ、山でも歩いて来ようかなぁ・・・。」
こんな考えが浮かんだ途端にもう壁に掛かっていたザックを引き下ろしていた。
 特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。
特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。
荒井川沿いの道を登山口に続く林道を探しながら走ったが、何処をどうしたものか登山口が見つからないままに加蘇山神社の社務所前まで来てしまった。加蘇山神社と言えば石裂山(おざくさん)の登山口に当たる場所である。「これも何かの縁か・・・」と急きょ石裂山登山に切り替える事にした。
社務所に在る石裂山回遊コース案内を眺めると大体4時間くらいの様子だ。現在9:30であるから13:30下山でも14:00過ぎには帰宅出来る目算である。
荒井川源流部に当たる沢沿いの登山道を軽い気分で歩き出す。沢音を聞きながらの登山は釣り屋の私にとって何よりも快適である。あちらこちらに「禁漁区」と赤字で書かれた札を目にするが沢の流れを覗き込んでみても一向に魚影は無い。登山道が横を走る里川の延長でしかない川だから最初から期待はしていないが、ついつい魚影を求めては儚い夢を追いかけてしまう。あざ笑う様に大きなヒキガエルが泳いでいるのが見えて苦笑してしまう。
 周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。
周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。
東屋がある中ノ宮に登り付く。「奥の宮・東剣ノ峰」の標識の先の岩場に長い鎖が下ろされているのが見える。
「そう言えば石裂山は鎖場と梯子の山だった・・・」
 気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。
気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。
この鎖場、「行者返しの岩場」と呼ばれている。私は行者では無いので帰らずに済んだ。でも雨後や雨天時なら無理は禁物と思わされる岩場である。登ってしまったら降りるのに首を傾げる程度の岩場と表現しておく。
さらに脇道にステンレス製の階段が伸びる「奥の宮」を参拝してから登山道に戻り尾根に取り付く。岩場を木の根を掴みながら登る。「一部にはハイキングコースと案内されていますが、ここは登山道です。」と書かれていた案内板の注意文を思い浮かべる。
鎖場・階段を越え「東剣ノ峰」に到着。樹木に遮られて大した展望も無い。「西剣ノ峰」へと進む鞍部に下る。これが長いステンレス製の階段の下り。何の気なしに降り始めたが、その長さに途中で「そう言えば俺って高所恐怖症じゃなかった?!」と気が付いてそれからの長かった事・・・。
鞍部に辿り着くもすぐに西剣ノ峰への登り返し。九十九折れの急登と途中で振り返ると、東剣ノ峰から下る崖に取り付けられた階段が見える。「あんなとこ降りて来たの・・・?!」と改めて驚く。
西剣ノ峰に登り付くと生い茂る樹木の間から鋭い岩肌を見せる石裂山が目の前に見える。正直「あそこに登るの・・・?」と思ったものだが、実際に登ってみるともう核心部は越えていた様で呆気ない思いで山頂に立つ。
山頂から見える展望は地理不案内にてコメント無し。(笑)
 本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。
本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。
月山からの下りも時折鎖場や梯子を介して結構急な下りで一気に標高を下げて来る。スギ林に入る頃には次第に沢音も大きくなって来る。「音はすれども水が見えないなぁ・・・。」と思っていたら突然岩の間から水が流れ出して沢を作り始める。伏流水が顔を出した瞬間である。この流れも荒井川の源流域の一筋となっていくわけである。
もう充分に沢と呼べる流れを渡ると登路と合流して周回を終える。ここからは往路を逆に辿るだけである。緊張の中にも心を癒された一人旅が無事に終わった。
 釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。
釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。
家に帰り御帰還ビールで一杯やっていると佑次郎が帰って来た。「今日ねぇ、山に行って来たんだ。」こう話し掛けると「何処の?」と御愛想が返って来た。それでも山の様子を写真を見せながら詳しく話してやる。「お父さんが“山に行った”って聞くとお前も行きたくなるだろ?」こう問い掛けた私にニヤリと笑いを返して来る。満更でもない表情に安心しながら残りのビールを美味しく飲んだ。「佑、今度は一緒に行こうな・・・」
2010年6月1日 栃木県 石裂山 記録者 副隊長
サラリーマンにとって休日は貴重な一日だとつくづく思う。少し前までは半自営業的な生活だったので自由な時間は自分で作り出せたが、サラリーマンともなると無駄な時間でさえ賃金で拘束され自由が利かない身となるのを10数年ぶりに体感している。
そんな身であるが数年来の山渓遊びを通じて休日の配分にも結構利口になった私である。身体を休める休日と心を休める休日を上手く使い分ける事が出来るようになったのも趣味と言う範疇ではあるけれど自然と触れ合う楽しさを教えて貰えた貴重な体験の積み重ねがあったからこそである。
朝、目を覚ますとまだ隣で佑次郎が寝息を立てている。今日は火曜日、平日の朝だから佑次郎は起き出すと共にそそくさと中学校へと行ってしまう。布団の中から佑次郎を送り出した後しばらく本を読んでいた私だがトイレに立った際に自室に差し込む明るい陽射しが妙に心を捉えて落ち着かなくなった。
「う~ん、今日は天気が良いんだなぁ、山でも歩いて来ようかなぁ・・・。」
こんな考えが浮かんだ途端にもう壁に掛かっていたザックを引き下ろしていた。
 特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。
特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。荒井川沿いの道を登山口に続く林道を探しながら走ったが、何処をどうしたものか登山口が見つからないままに加蘇山神社の社務所前まで来てしまった。加蘇山神社と言えば石裂山(おざくさん)の登山口に当たる場所である。「これも何かの縁か・・・」と急きょ石裂山登山に切り替える事にした。
社務所に在る石裂山回遊コース案内を眺めると大体4時間くらいの様子だ。現在9:30であるから13:30下山でも14:00過ぎには帰宅出来る目算である。
荒井川源流部に当たる沢沿いの登山道を軽い気分で歩き出す。沢音を聞きながらの登山は釣り屋の私にとって何よりも快適である。あちらこちらに「禁漁区」と赤字で書かれた札を目にするが沢の流れを覗き込んでみても一向に魚影は無い。登山道が横を走る里川の延長でしかない川だから最初から期待はしていないが、ついつい魚影を求めては儚い夢を追いかけてしまう。あざ笑う様に大きなヒキガエルが泳いでいるのが見えて苦笑してしまう。
 周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。
周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。東屋がある中ノ宮に登り付く。「奥の宮・東剣ノ峰」の標識の先の岩場に長い鎖が下ろされているのが見える。
「そう言えば石裂山は鎖場と梯子の山だった・・・」
 気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。
気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。この鎖場、「行者返しの岩場」と呼ばれている。私は行者では無いので帰らずに済んだ。でも雨後や雨天時なら無理は禁物と思わされる岩場である。登ってしまったら降りるのに首を傾げる程度の岩場と表現しておく。
さらに脇道にステンレス製の階段が伸びる「奥の宮」を参拝してから登山道に戻り尾根に取り付く。岩場を木の根を掴みながら登る。「一部にはハイキングコースと案内されていますが、ここは登山道です。」と書かれていた案内板の注意文を思い浮かべる。
鎖場・階段を越え「東剣ノ峰」に到着。樹木に遮られて大した展望も無い。「西剣ノ峰」へと進む鞍部に下る。これが長いステンレス製の階段の下り。何の気なしに降り始めたが、その長さに途中で「そう言えば俺って高所恐怖症じゃなかった?!」と気が付いてそれからの長かった事・・・。
鞍部に辿り着くもすぐに西剣ノ峰への登り返し。九十九折れの急登と途中で振り返ると、東剣ノ峰から下る崖に取り付けられた階段が見える。「あんなとこ降りて来たの・・・?!」と改めて驚く。
西剣ノ峰に登り付くと生い茂る樹木の間から鋭い岩肌を見せる石裂山が目の前に見える。正直「あそこに登るの・・・?」と思ったものだが、実際に登ってみるともう核心部は越えていた様で呆気ない思いで山頂に立つ。
山頂から見える展望は地理不案内にてコメント無し。(笑)
 本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。
本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。月山からの下りも時折鎖場や梯子を介して結構急な下りで一気に標高を下げて来る。スギ林に入る頃には次第に沢音も大きくなって来る。「音はすれども水が見えないなぁ・・・。」と思っていたら突然岩の間から水が流れ出して沢を作り始める。伏流水が顔を出した瞬間である。この流れも荒井川の源流域の一筋となっていくわけである。
もう充分に沢と呼べる流れを渡ると登路と合流して周回を終える。ここからは往路を逆に辿るだけである。緊張の中にも心を癒された一人旅が無事に終わった。
 釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。
釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。家に帰り御帰還ビールで一杯やっていると佑次郎が帰って来た。「今日ねぇ、山に行って来たんだ。」こう話し掛けると「何処の?」と御愛想が返って来た。それでも山の様子を写真を見せながら詳しく話してやる。「お父さんが“山に行った”って聞くとお前も行きたくなるだろ?」こう問い掛けた私にニヤリと笑いを返して来る。満更でもない表情に安心しながら残りのビールを美味しく飲んだ。「佑、今度は一緒に行こうな・・・」
Posted by okirakutozan at 15:06│Comments(0)
│栃木
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。